カテゴリー:特集
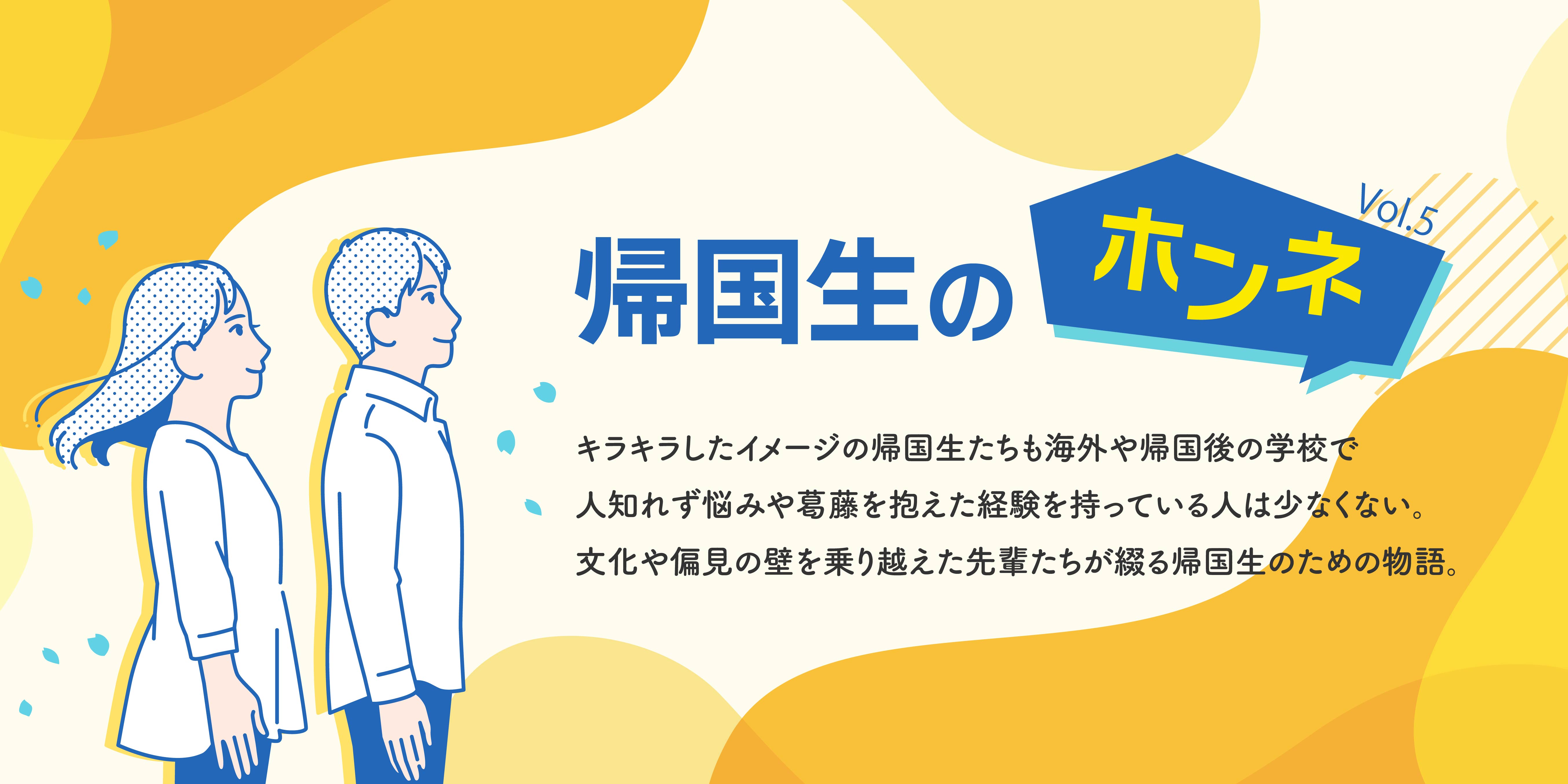
帰国後も自分らしく歩んでいくことが必ず誰かの力になる!
アメリカ・イリノイ州シカゴ近郊で生まれ育った川勝慶成さんは、小学校3年生のとき、初めて日本に帰国し、公立小学校に通い始めた。しかし、スピードの速い日本語や「みんな同じ」を強制されるような雰囲気により、次第に劣等感を感じるようになる。学校で目立つことを避けるようになってしまった小・中学校時代を経て、川勝さんは高校時代にやっと自分の居場所を見つける。それは、困難を抱える若者を支援する活動。アメリカで多様性の中で暮らし、帰国後は勉強が苦手で疎外感を味わった経験が、困っている人に寄り添う活動と共鳴した。
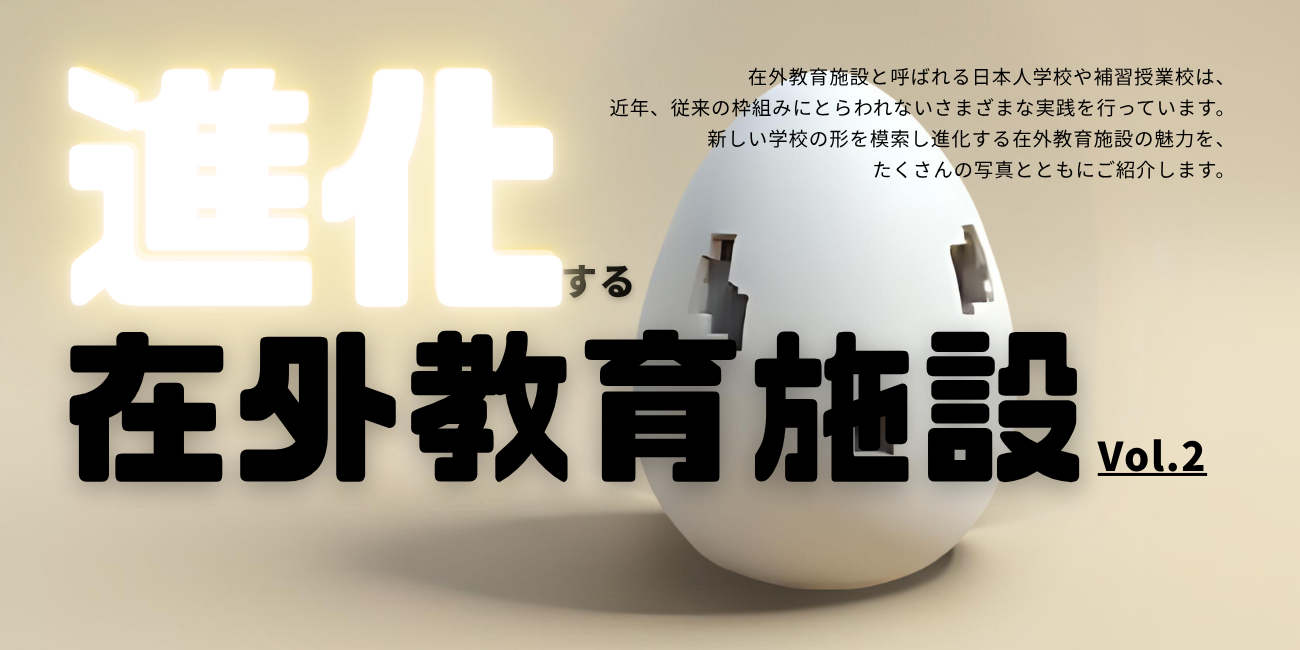
日本人学校幼稚部に宮城教育大学の学生がやってきた! ~グアムにおける海洋教育に関する実証研究(宮城教育大学)~
「進化する在外教育施設」シリーズ第2弾
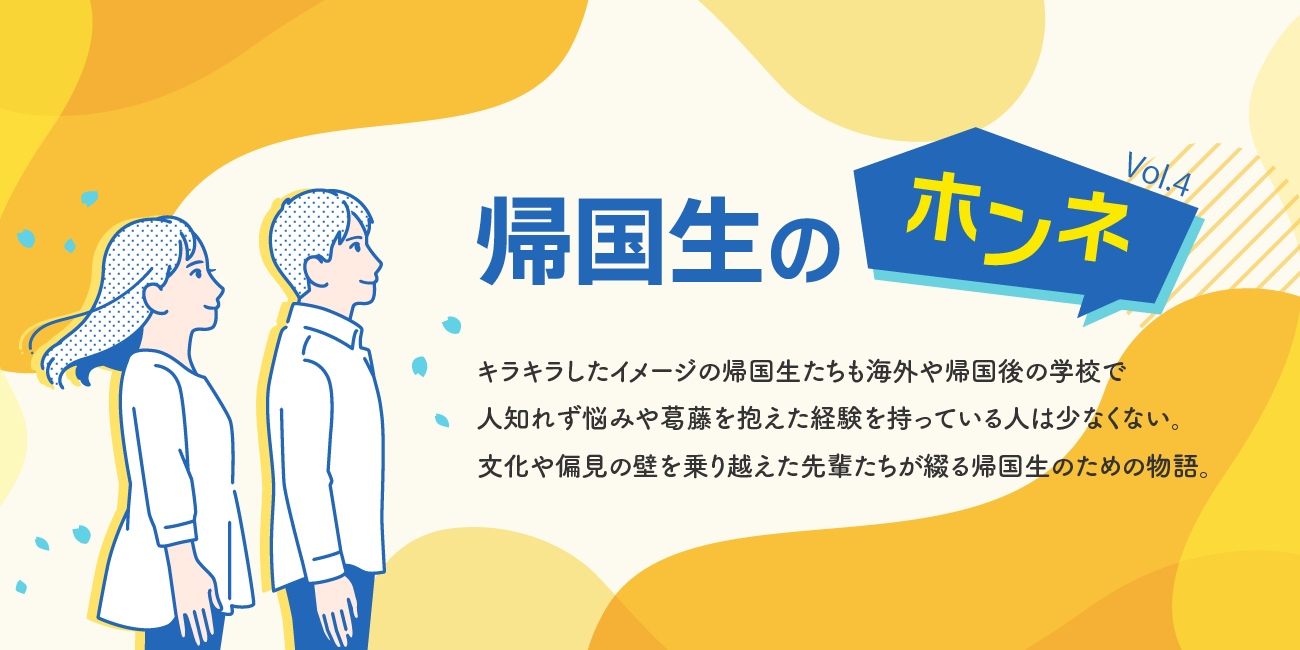
“違和感”の先で掴んだ「世界のどこでも働ける自分」
現在、外資系企業で働く下村友里さんは、幼少期からシンガポール、マレーシア、台湾で計7年間学んだ経験を持つ。社会人になってから自ら貯めた資金でMBA留学も経験し、ヨーロッパで学んだ経験もここに加わった。「世界のどこででも働ける自分でありたい」と語る下村さん。しかし、海外生活はいつも順風満帆だったわけではない。ときにカルチャーギャップに困惑しながら、手探りでキャリアを切り拓いてきた。下村さんが歩んだ道のりを振り返っていこう。

異文化のなかで育った少年が、世界の最前線でリーダーになるまで ―次世代を担う後輩たちへのメッセージ―
ソニーのV字回復をけん引した元最高経営責任者(CEO)であり、現在は一般社団法人プロジェクト希望の代表理事を務める平井一夫氏は、まだ「帰国子女」が珍しかった1960~70 年代に、アメリカ・ニューヨークで小学1年から4年生まで、カナダ・トロントで中学時代を過ごした元帰国子女。当時の異文化体験は、その後の人生や考え方に大きな影響を与えているという。 このたび、公益財団法人海外子女教育振興財団理事長の綿引宏行がホストとなり、「異文化で育つとはどういうことなのか」について、お話を伺った。

海外に住んでみて びっくりしたこと
<シリーズ:海外生活エピソード> 海外に住んでみて びっくりしたことについて、JOES「帰国子女のための外国語保持教室」の生徒や保護者の方を中心に聞いてみました!

昭和を知る・昭和に学ぶミュージアム
毎年夏の恒例企画、「地球はどこでもミュージアム!」、今回のテーマは「過去」。 「じゃあ、歴史?」「化石? 恐竜?」「古い蒸気機関とか?」「土器?」「古文書?」 「そもそも博物館って、昔のものばかり置いてあるよね」 たしかにその通り。でも、もう少し身近な過去である「昭和」に注目してみよう。 レトロブームで人気の昭和、そのデザインはたしかに魅力的。 でも、第二次世界大戦があり、高度経済成長があり、バブル景気があった昭和という複雑な時代のこと、私たちはどれだけ知っているのだろう? 「レトロ」「カワイイ」だけでない、多様で深い昭和の暮らしを垣

海外に住んでいる子どもの夏休み
海外に住んでいる子どもたちは、どんな風に夏休みを過ごしている?読者からの投稿を紹介します。
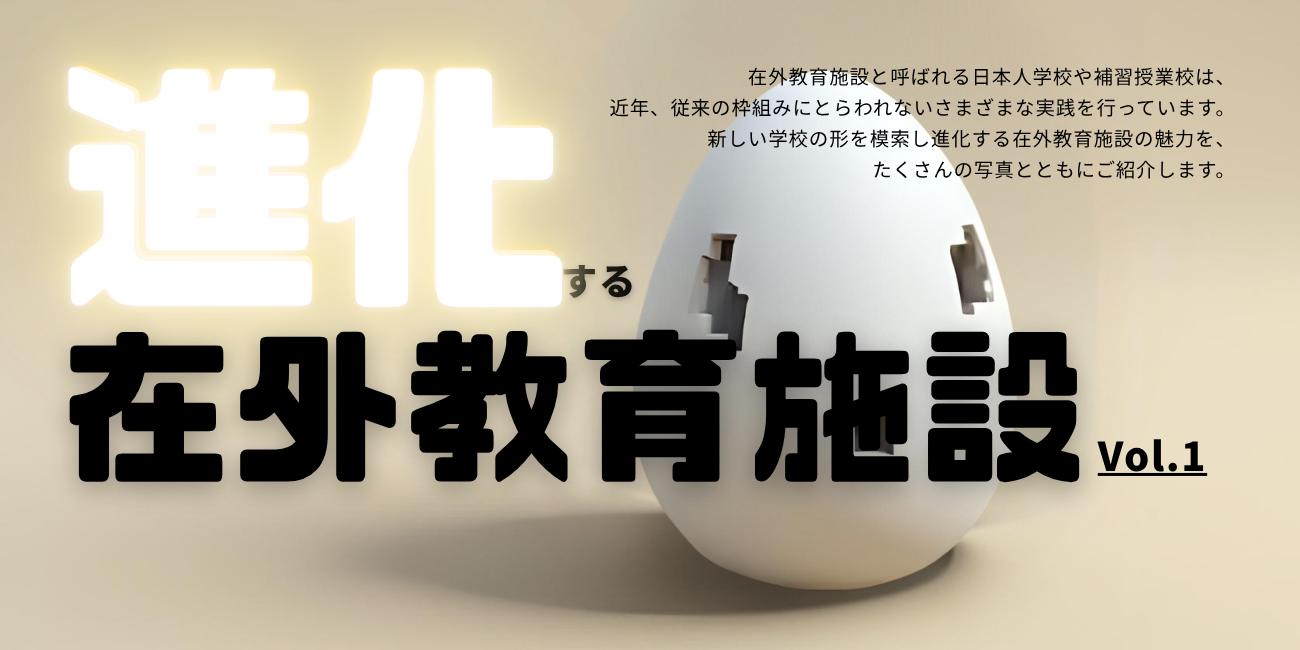
英語で世界を学ぶ ~プノンペンのCLIL授業~ プノンペン日本人学校
「進化する在外教育施設」シリーズ第1弾

海外生活の失敗談 <後編>
<後編>読者から寄せられた海外生活の失敗談

海外生活の失敗談 <前編>
<前編>読者から寄せられた海外生活の失敗談
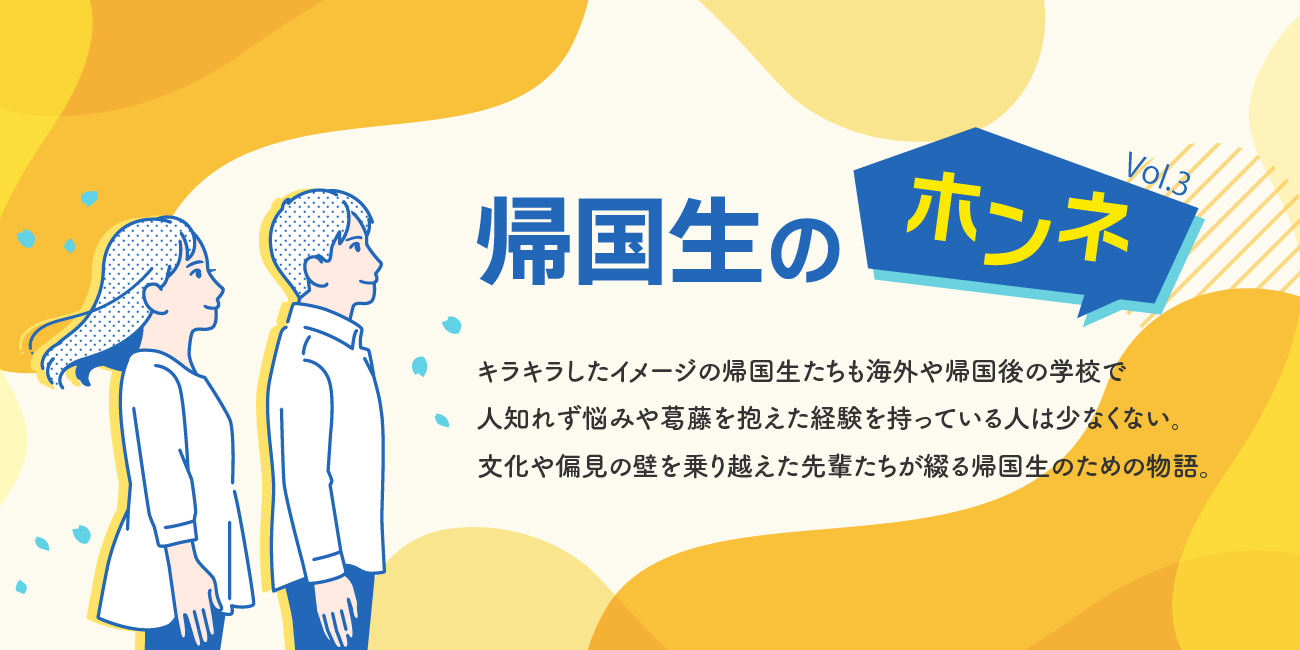
4年間のアメリカ生活が私にくれたもの
東京都に住む宮崎珠実さんは、小学校5年生の夏から中学校3年生の夏までの約4年間をアメリカ・カリフォルニア州で過ごした。英語の環境に憧れ、現地校での生活を選んだ宮崎さんだったが、ネイティブスピーカーの世界に順応するのは、想像以上に難しかった。そんな彼女は、帰国から5年以上が過ぎた今、所属する大学で留学生のサポートをする活動を通して、英語でコミュニケーションをする楽しさを実感している。思春期に経験したアメリカ生活で、宮崎さんは何を学び、何を得たのか……。その答えが、少しずつクリアになり始めている。
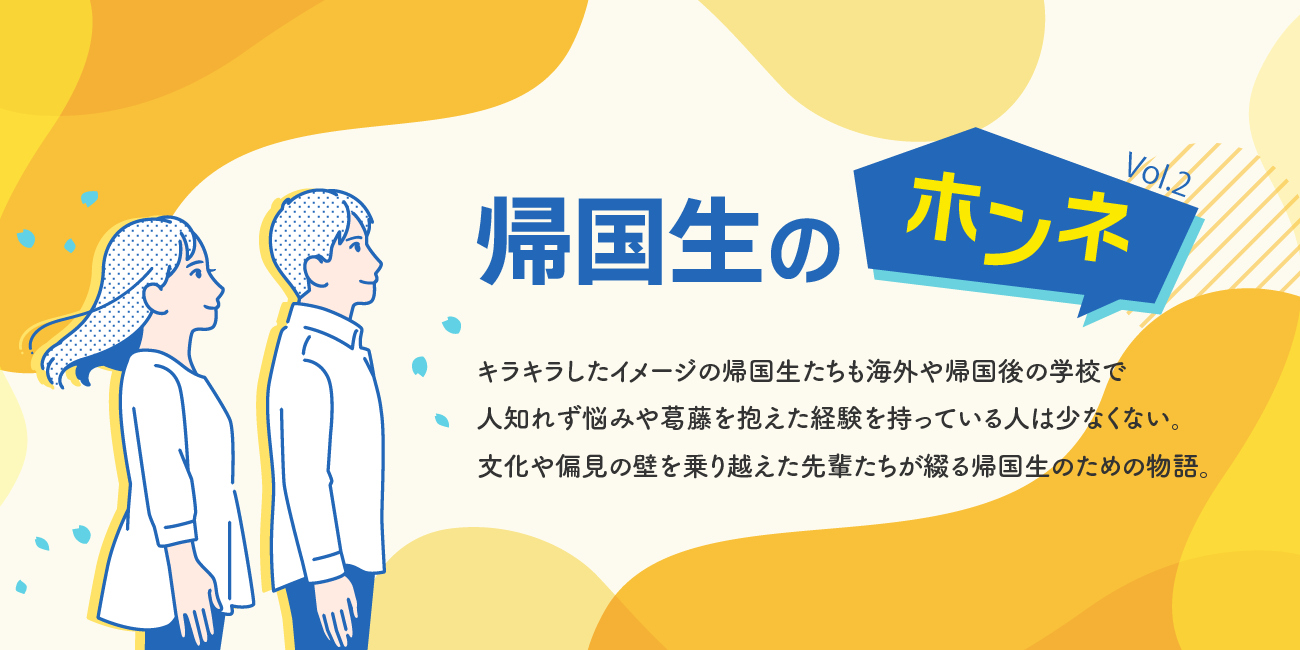
日本・アメリカ・ドイツの“間”にあるもの
小学校4年生から中学3年生までをアメリカ・ロサンゼルスで過ごした坂本鈴音さんは、現在、ドイツのケルンで暮らしている。多様な背景を持つ人々が暮らすドイツでの暮らしは、日本で暮らしていたときの閉塞感を忘れさせてくれるという。坂本さんは今、現地でドイツ語を学びながら、アメリカと日本の教育の違いについて考えている。アメリカの現地校で自分は何を身につけたのか、そして、この先のキャリアをどこで築いていくべきか——。その答えを新天地のドイツで見つけつつある。