カテゴリー:顔

上智大学初のドラフト指名。 自分を信じて切り開いたプロへの道
上智大学硬式野球部に所属する正木悠馬(まさきゆうま)投手。コーチ不在の環境で独学による試行錯誤を重ね、投球は最速153キロに到達。2025年のプロ野球ドラフト会議で埼玉西武ライオンズから育成6位指名を受けた。幼少期や中高時代をアメリカで過ごし、さまざまなスポーツに親しみながら培った自主性と柔軟な発想が、プロへの扉を開いた。その歩みを、海外経験とともに振り返る。
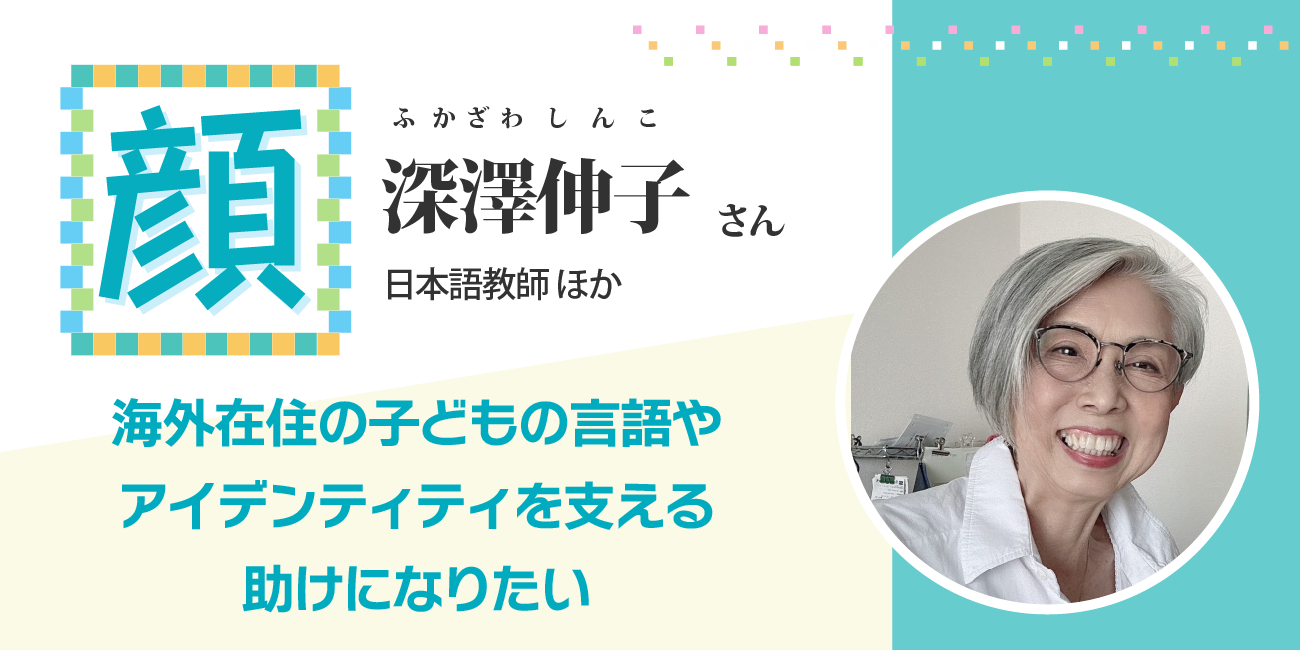
海外在住の子どもの言語やアイデンティティを支える助けになりたい 深澤伸子さん
1982年に帯同家族としてタイを訪れて以来、大学や大学院で日本語教師をしたり、日本語教員養成プログラムを担当したりと、タイにおける日本語教育に黎明期より携わってきた深澤伸子先生。日本語を学ぶタイの学生がバンコク在住の日本人家庭にホームステイするプログラム「ルアムジャイ(心をひとつに)」を立ち上げたり、「バイリンガルの子どものための日本語同好会」の世話役、「タイにおける母語・継承語としての日本語教育研究会」の代表を務めたりと、言語や教育に関わる幅広い活動を続けられています。今回はそんな深澤先生に、タイで暮らす日本にルーツをもつ子どもたちが抱える問題や今後の課題について、話を聞きました。

無限の可能性~唯一無二の作品を創り出す ―発達障害を可能性に変えたアーティスト パリ日本学校卒業生 轟 修杜さん
生まれ育ったパリを拠点に活躍する27歳のアーティスト、轟 修杜さん。「アール・ブリュット」(専門的な美術教育を受けていない人が湧き上がる衝動に従い、自分のために制作するアート)の作品が日仏で高く評価されている。発達障害を個性に、独創的な世界観を発信し続ける力はどこから生まれてくるのか。母親の都さんに話を伺った。

アメリカでの経験を活かして、日本でインクルーシブ教育を実現したい!一般社団法人UNIVA理事 野口晃菜さん
インクルーシブ教育の研究者である野口晃菜さんは現在、一般社団法人UNIVA理事、中央教育審議会委員、戸田市インクルーシブ教育戦略官として、「多様な子どもたちが安心して過ごせる学校づくり」に取り組んでいる。この活動の原点は、小学校6年次に編入したアメリカの現地校で、車いすの子や脳性麻痺の子が当たり前にクラスで一緒に学ぶ姿を見た経験や、自身のはじめてマイノリティ経験があった。日本の学校をアップデートする野口さんの活動について詳しく聞いた。

予想がつかない方に身を投じてみると、思わぬ形で役立つ 歌舞伎俳優 尾上音蔵さん
7代目尾上菊五郎に入門し一般家庭から歌舞伎俳優となった尾上音蔵(おのえおとぞう)さん。彼のルーツは、生後半年から5歳まで暮らしていた南アフリカ共和国・ヨハネスブルグにあった。一見つながりを感じさせない南アフリカでの日々が、歌舞伎俳優として音蔵さんの今に意外な部分でつながっていると話す。これまでの海外経験や言語習得によって培われた力について話を聞いた。

「みんなが自由に表現できる世界をつくりたい!」Belonging Beyond Borders創設者・代表 小池夏子さん
生後2カ月の頃からフィリピンで育ち、中学2年間を日本で暮らした経験を持つ小池夏子(こいけなつこ)さん。現在は、インターナショナルスクール・マニラに通いながら、サードカルチャーキッズやグローバルユースに向けたコミュニティ「Belonging Beyond Borders」の代表を務め、多文化な環境で育った自身と同じ境遇や悩みを持つ若者たちをつなぐ活動に力を注いでいる。BBBを立ち上げたきっかけや活動への思いを聞いた。

ハズムはハズム、僕は僕が大好き! ウィーン少年合唱団 下田弾さん
来日70周年、ウィーン少年合唱団が来日! 団員の下田弾さんにインタビュー オーストリアのユネスコ無形文化遺産にも登録されているウィーン少年合唱団、美しいボーイソプラノ「天使の歌声」で世界中の多くの人々を魅了し続けている。合唱団の歴史は古く、発祥は1498年のローマ帝国に遡る。 国籍を問わない小学校4年生から中学校3年生までの100名の子どもたちがアウガルテン宮殿で寮生活を送りながら、「ハイドン組」「モーツァルト組」「シューベルト組」「ブルックナー組」の4グループに分かれて活動している。毎週日曜日、ウィーンの王宮礼拝堂で行われるミサでミサ曲を歌うほか、さまざまな音楽祭やメディアに登場したり、世界各地でコンサートを開催したりと、その活躍は幅広い。 この5月、来日したのは「モーツァルト組」。今回ご紹介するのは、そのメンバーのひとり、下田弾(しもだはずむ)さん。日本人の母とドイツ人の父を持ち、ドイツ・フランクフルトで生まれ育った14歳、サッカーをしたり、甘いお菓子を食べたりするのが大好きという中学校3年生だ。 合唱団に入るまでは、ドイツのフランクフルトに住み、補習授業校に通っていた。小学部5年生だった時には、海外子女教育振興財団が主催する海外子女文芸作品コンクールの詩部門に応募し、ウィーン少年合唱団のオーディションを受けた時のことを書いた『天使の一員』で、「特選」を受賞している(『天使の一員』は本記事の最後で紹介します)。 憧れだったウィーン少年合唱団の一員となり、今回、来日を果たした下田弾さんに、東京でのコンサート終了後にインタビューした。

「しくじり帰国子女」だから見える 日本のグローバル教育の課題と展望 国際教育評論家 村田学さん
Webメディア「The International School Times」編集長として、日本国内のインターナショナルスクールやIB(国際バカロレア)導入校の取材を続ける国際教育評論家の村田学さん。海外駐在員の家庭に生まれ、幼少期をロサンゼルスで過ごした原体験が帰国後も忘れられず、日本の学校で居場所を探した経験が、現在の国内インターナショナルスクールを支援する仕事の原動力になっているという。自称「しくじり帰国子女」の村田さんに、日本のグローバル教育が抱える課題と今後の展望について聞いた。

間に合ったから、行って撮りまくる 山形豪さん
アフリカの大地で躍動する野生動物たち。ダイナミックで、時には牙をむく自然の中で繰り広げられる生命のやりとり。写真や動物ドキュメンタリーの中で見るそんな世界に、都会に住む私たちは魅了される。 その光景を撮り続けてきた動物写真家の山形豪さん。単に「動物が好き」「カメラが好き」だけでは続かない厳しい世界。被写体を探して無駄足を踏んだり、シャッターチャンスを何時間も待ち続けたりすることもある。アフリカのサバンナは日本からあまりに遠く、時間的・経済的・身体的な負担も大きい。 それでも山形さんは30年以上ひたすら通い続けてきた。 「もちろん、アフリカや動物が好きだからです。同時に、今自分がここで撮っておかないという危機感があるんです」と言う山形さんに話を聞いた。

アメリカで実践する日英バイリンガル教育の現在形 金城直美さん
カリフォルニア州グレンデールにあるダンズモア小学校で教員をしている金城直美先生は、現在、英語・日本語のデュアル・イマージョン教育プログラムを担当している。自らも日本語と英語が家庭内で混在する環境で育った金城先生は、アメリカ・日本での幅広い学びを経て、最終的にバイリンガル教育で子どもたちを指導する道を選んだ。金城先生が目指すのは、誰もが多様な言語で、等しく教育を受けられる環境の実現。バイリンガル教育の現場で見えてきた課題や現在の仕事で実現したい夢について聞いた。

「ケセラセラ」の精神で世界への挑戦を続ける ジュエリーデザイナー 中村穣さん
スイス公文学園への入学を皮切りに、アメリカの大学、オランダの大学院と、約10年間を海外で過ごした中村穣さん。大学と大学院では、プロダクトデザインについて学び、日本に帰国後、2012年に自身のジュエリーブランドを立ち上げた。2016年に開かれた「伊勢志摩G7サミット」では、各国の首脳が身につけたラペルピンを手掛けるなど、国内だけでなく世界へとブランドのデザインを発信する。そんな中村さんに、これまで過ごした3カ国での経験やデザインのこだわりについて話を聞いた。

世界に広がる「駐夫」という選択肢 ジャーナリスト、「世界に広がる駐夫・主夫友の会」代表 小西一禎さん
共同通信社の政治部記者として、毎日深夜まで働いていた小西一禎さんは、2017年に会社の制度を使って休職し、妻の海外赴任に同行する形で渡米する。肩書きがなくなり、5歳の娘と3歳の息子を育てる父・夫としてスタートしたニューヨーク・マンハッタンの対岸、ニュージャージー州での新生活。ここで、小西さんは、自ら「駐夫(ちゅうおっと)」を名乗り、同じ境遇にいる日本人男性にメッセージを発信した。代表を務める「世界に広がる駐夫・主夫友の会」の活動から見えてきた「駐夫」の現状と今後の課題とは?