カテゴリー:特集
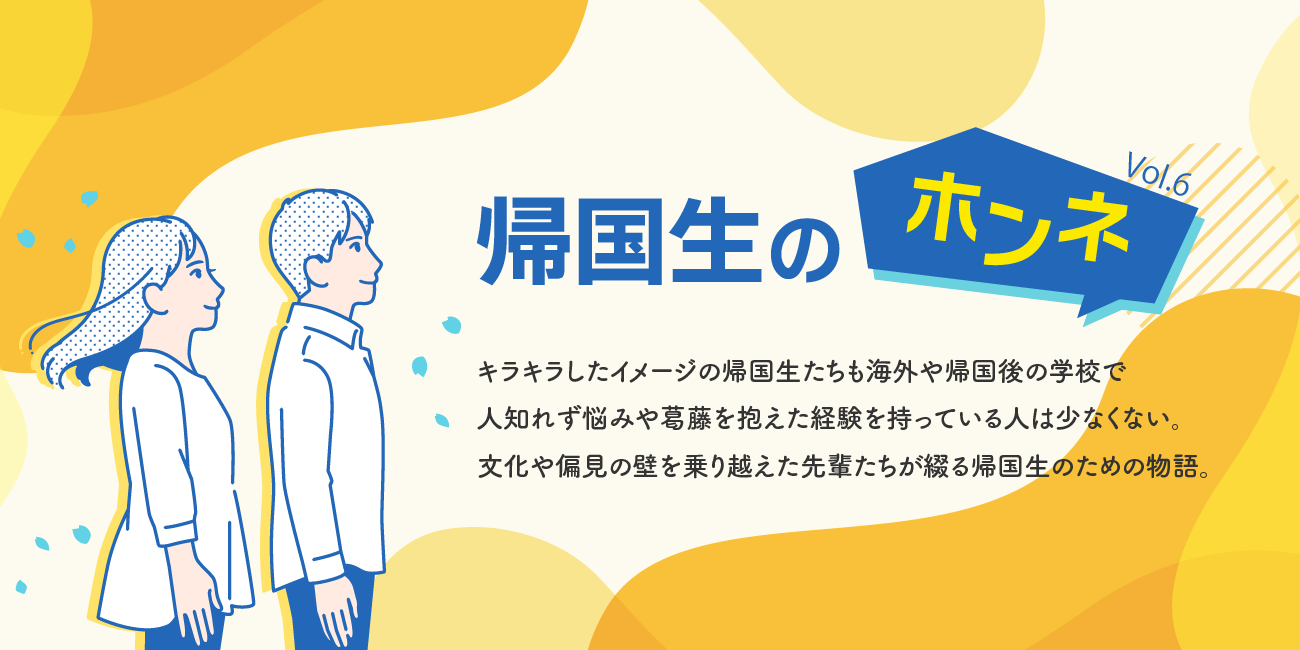
アメリカで学んだ「自由」と日本で学んだ「協調」の間で
アメリカ、ニュージャージー州で生まれた美帆さん(仮名)は、8歳になるまで現地校で英語オンリーの環境で学んだ。その後、小学校2年生で帰国し、持ち物もやることも「みんなと同じ」を強いられる日本の学校に通い始める。違和感を覚えながらも過度な順応をして、仲間をつくった中学校時代を経て、美帆さんは高校時代に2年間、再びアメリカの現地校で学び、日本の大学に進学する。多感な時期に2つの文化を往き来しながら学んだ経験は、美帆さんをどこに導いたのか——。「自分らしく生きる強さ」を手に入れるまでの道のりを語ってもらった。
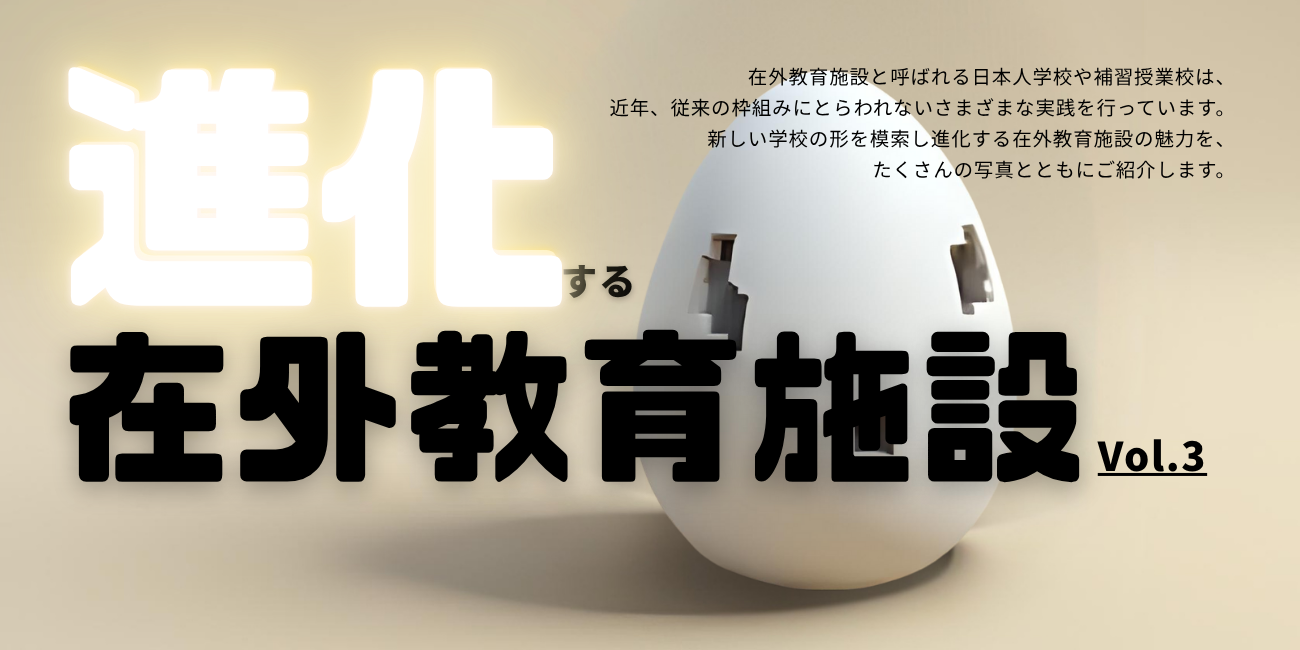
グアム国際日本人学校のビヨンドスクール構想 ~「日本語会話・文化コース」「親子教室『たんぽぽ』」~
「進化する在外教育施設」シリーズ第3弾

カプセルトイが世界中で大ブームのバンダイ「ガシャポン®」に迫る 帰国子女の先輩にもお話を聞きました!
日本の街中や商業施設内などでよく目にするカプセルトイ専門店。次々と入れ替わる商品は、最近だと子どもだけでなく、大人にも拡大し、全世代がターゲットになっていると言います。さらには、日本人だけでなく、訪日観光客からも「手軽に持ち帰られる日本土産」として人気を博しているそう。あらゆる世代や国の人たちに刺さる商品はどのように誕生しているのか。進化するカプセルトイの商品開発について、バンダイのガシャポン®企画開発担当桑野さんにお話を伺いました。帰国子女である桑野さんには、最後にご自身の海外経験や普段のお仕事についても聞きました。

第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(作文その1)
第46回海外子女文芸作品コンクール審査結果発表(作文その1)

第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(作文その2)
第45回海外子女文芸作品コンクール審査結果発表(作文その2)

第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(作文その3)
第46回海外子女文芸作品コンクール審査結果発表(作文その3)

第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(作文その4)
第46回海外子女文芸作品コンクール審査結果発表(作文その4)

第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(詩その1)
第46回海外子女文芸作品コンクール審査結果発表(詩その1)

第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(詩その2)
第46回海外子女文芸作品コンクール審査結果発表(詩その2)

第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(詩その3)
第46回海外子女文芸作品コンクール審査結果発表(詩その3)

第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(詩その4)
第46回海外子女文芸作品コンクール審査結果発表(詩その4)

第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(俳句)
第46回海外子女文芸作品コンクール審査結果発表(俳句)