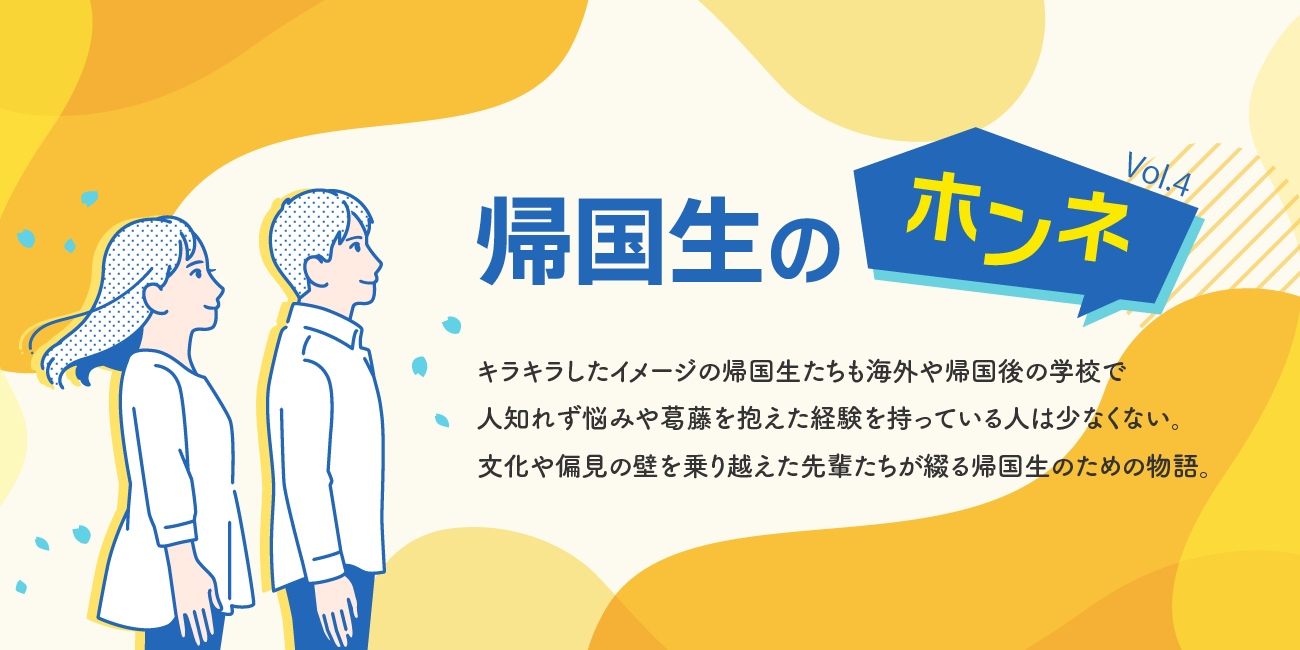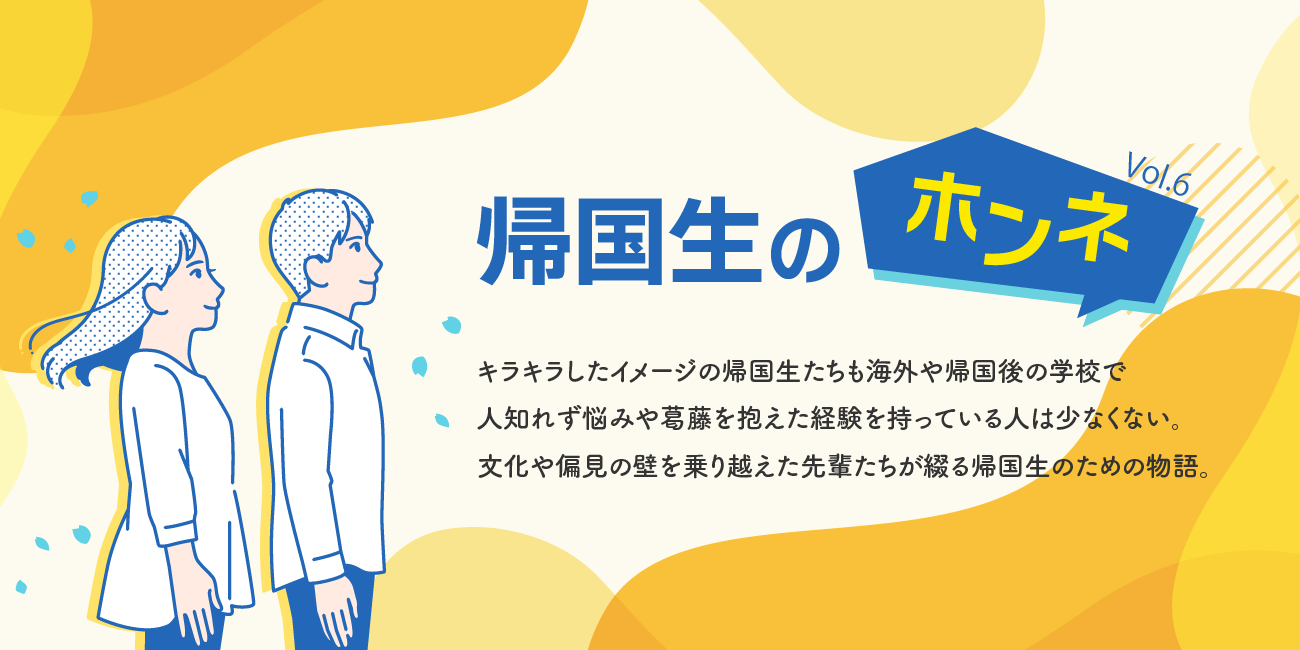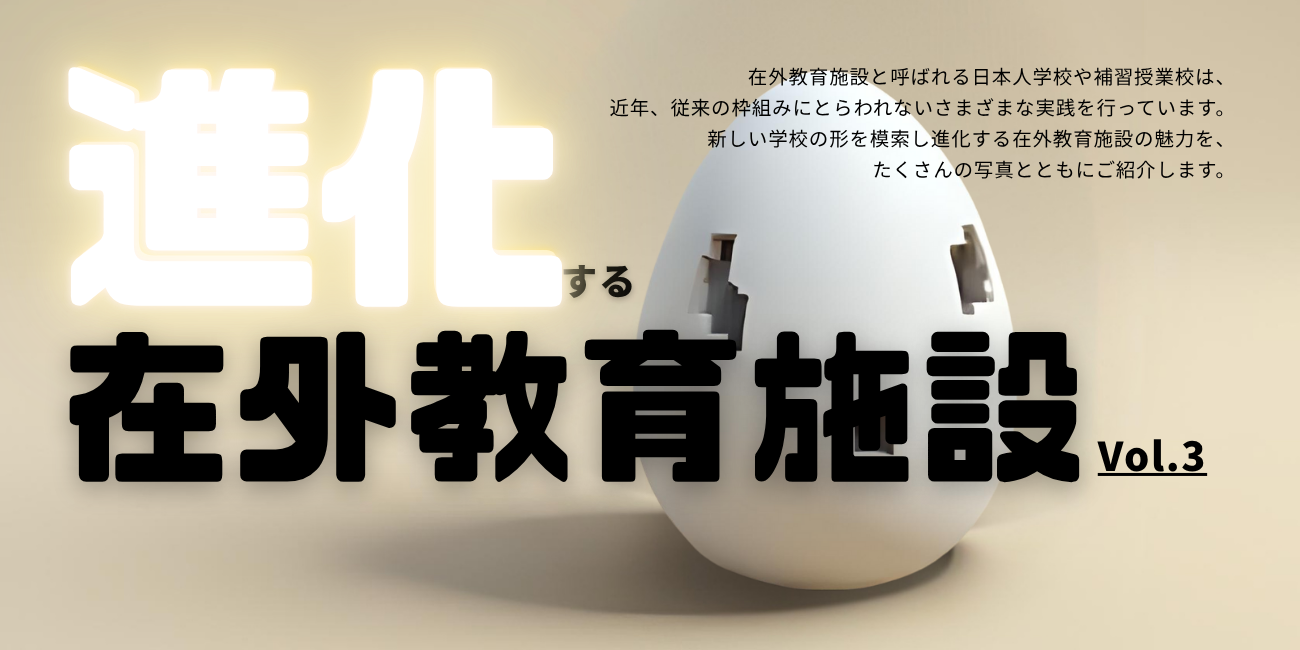現在、外資系企業で働く下村友里さんは、幼少期からシンガポール、マレーシア、台湾で計7年間学んだ経験を持つ。社会人になってから自ら貯めた資金でMBA留学も経験し、ヨーロッパで学んだ経験もここに加わった。「世界のどこででも働ける自分でありたい」と語る下村さん。しかし、海外生活はいつも順風満帆だったわけではない。ときにカルチャーギャップに困惑しながら、手探りでキャリアを切り拓いてきた。下村さんが歩んだ道のりを振り返っていこう。
(取材・執筆:Minimal 丸茂健一)
日本人学校で過ごしたシンガポールの小学生時代
兵庫県で生まれた下村さんが、最初に海外生活を経験したのは、シンガポール。小学校1年生から3年生まで、現地の日本人学校に通った。そこは、1学年4~5クラスあるような大型の学校で、シンガポールの文化を学びながら、ほぼ日本国内と同じような環境だったという。

「最初に通った小学校がここだったので、特に違和感なく通っていました。当時シンガポールで住んでいた家が、プール付きのコンドミニアムだったので、かなり快適だったのを覚えています。今思い出してもいい生活でしたね(笑)」
シンガポール生活を楽しんだ下村さんは、小学校4年次に日本に帰国し、神奈川県の公立小学校に通い始めた。もともと日本人学校に通っていたので、大きなギャップもなく授業に馴染めるようになった。しかし、小学生だった下村さんは、やっとここで海外での生活が貴重なものだったことに気づく。
きっかけは、イギリスから帰国した同級生がいたこと。ネイティブスピーカーのように英語を話す彼の姿を見て、「私もシンガポールでもっと英語を勉強すればよかった!」と強烈に意識するようになった。そんな私を見て母はネイティブスピーカーの英語教室や英検受験など継続的に英語を学べる環境を作ってくれた。また、帰国子女が多く集う親子サークルにも連れて行ってくれ、欧米圏から帰国した子どもたちも数多く通うその環境で刺激を受け、「自分も英語をもっと話したい!」というモチベーションが上がったという。
マレーシアでは、自ら望んでインターナショナルスクールへ
再び海外で生活することになったと両親から聞かされたのは、小学校6年生に上がるタイミングだった。行き先はマレーシアのクアラルンプール。下村さんは自ら希望して、現地のインターナショナルスクールに通う選択をする。
「日本の小学校で仲よくなった友達と別れるのはさみしかったのですが、また海外で学べることはポジティブに受け止めていました。ワクワクしながら、英語の環境に飛び込みました」
現地で通ったのは、イギリス系のインターナショナルスクール。日本で英語力を鍛えて臨んだものの、ハードルは高く、最初はEAL(English as an Additional Language)クラスからのスタートとなった。通っていたのは、中国人、韓国人を中心としたアジア系の子どもたちがメイン。イギリス系のインターナショナルスクールながら、欧米系の子どもたちは少数派だった。アジア系のほか中東系の子どもたちも多く、70カ国以上の文化背景を持つ子どもたちが通う国際色豊かな環境で、新たな生活がスタートした。
小学生なのに日本人代表
最初こそ苦労したものの英語力の蓄積もあったことから、半年ほどで、英語で授業を行う通常クラスに編入することができた。しかし、英語の成績はクラスで最下位レベル……。それまで勉強に対して苦手意識がなかっただけに、ショックを受けることもあった。さらに、英語がままならない状態なのに、授業では、数少ない日本人として意見を求められることもあった。
「第二次世界大戦で、日本がやったことを知っているか?と質問を受け、困惑しました。まだ小学生で日本の近代史のことをよく知らない状態で、日本人代表として意見を求められたわけです。さらに、日本の教科書を見せると『戦争の記述が2ページしかない』と指摘を受けました。もちろん、先生やクラスメイトに悪意はなく、世界のなかの日本というものを初めて意識した瞬間でしたね」
いつも仲よく遊んでいた韓国や中国の子どもたちが、自国のことを熱心に話す姿を見て、自分は日本人なんだとアイデンティティのようなものを感じる一方、自分が日本のことをほとんど知らないことを自覚した。まだ小学校高学年だった下村さんにとって、これは大きな発見だった。
「私の前でビーフを食べないで!」
授業以外でもカルチャーショックを受けることがあった。仲よくなったインド系の友達と現地のマクドナルドを訪れた際、「私の前でビーフを食べないで!」と真顔で怒られた。ヒンドゥー教徒がマジョリティを占めるインドでは、聖なる動物である牛を食べることは、多くの場合タブー視されていた。また、何気ないゼスチャーを「インドではありえない」と指摘を受け、宗教や文化に対して無知なばかりに友達を傷つけてしまう可能性があることを知った。
「マレーシアのインターナショナルスクールで印象に残っているのは、欧米の教育現場では、発言をしないと価値を示すことができないということ。成績表を見ると『授業は理解しているが、シャイで発言が少ない』といつも書かれていて、そう見られていることに私自身も驚きました。日本では、そういうタイプではなかったので……。ただ、多様な価値観、文化を受け入れながら、しっかり自分の意見を言えるようなメンタリティの基礎がここで形成されたと思っています」
台湾の日本人学校を経て、日本の高校に進学
小学校6年生から中学校2年生までをマレーシアのインターナショナルスクールで過ごした下村さんは、父親の仕事の都合で、中学3年生から台湾で暮らすことになる。高校の進路を決める重要なタイミング。検討の末、下村さんは日本での高校進学を視野に入れ、台北の日本人学校で通う決断をした。
「台北では、日本人学校に通いながら、日本人専用の塾で受験勉強に集中しました。学校の授業で中国語も学び、言語に対する興味も深めました。台湾での滞在は1年間と短かったものの、中国語の基礎を身につけられたのは大きな収穫でしたね」

高校受験では、ICUHS(国際基督教大学高等学校)をはじめとする私立の大学附属校を検討し、最終的に帰国子女枠で慶應SFC(慶應義塾湘南藤沢高等部)に合格し、進学することにした。帰国子女が数多く通う自由な校風が自分に合っていると思ったという。
実際、小学校高学年から中学校にかけての多感な時期に欧米系インターナショナルスクールで教育を受けた生徒が、日本の公立校でカルチャーギャップに苦しむケースは多い。下村さんもそのあたりはしっかりと調査して、学校も見学した上で進学先を選んだという。
「中高一貫校のSFCに高校から入学する生徒は、特に帰国生が多く、そのメンバーの中では、私の英語力は『中程度』という感じでした。それでも英語の授業は、クラス分けの一番上に配属され、ネイティブの先生から現地校のような指導を受けることができました。この環境は、SFCならではだと思います」
学校の代表として「女性の社会進出」についての論文を発表
高校時代は、「模擬国連」のアクティビティにも力を入れた。これは、生徒が国連の会議を模して各国の代表となり、国際問題について議論・交渉・決議を行う教育プログラム。下村さんもランダムに割り振られた国の代表として、政策を考え、英語で議論した。ここで、マレーシアのインターナショナルスクール時代の経験が活かされたのは間違いない。
また、高校3年次には、SFC独自の教育スタイルである卒業論文を制作。1年かけて資料を集め、指導教員と議論を重ねながら、「女性の社会進出」についての論文を仕上げた。この論文は、学校の代表に選ばれ、学外での発表も経験したという。
「帰国してから、高校生ながら日本は女性の社会進出が遅れていることを課題として感じていました。自分は社会の第一線で働きたいと思っていたので、少しでも社会を変えられるような提案をしました。海外で活躍する女性たちを現場で見た経験、人前で発表することを繰り返してきた経験が複合的に活かされた成果だったと思います」
慣れない文化に戸惑った大学時代の部活動経験
そんな順風満帆な高校生活を経て、下村さんは慶應義塾大学経済学部に進学する。高校時代にできなかったことのひとつに部活動があった。海外生活が長かっただけに、日本の体育会系の部活動に憧れもあった。そこで、大学時代は運動部のマネージャーになるべく入部をした。しかし、実際に活動を始めてみると、これまでの環境とは異なる価値観や習慣に触れることになった。
「上下関係を大切にし、チームワークを重んじる日本ならではの部活動の文化に触れ、多くのことを学びました。一方で、自分にとっては少し新鮮で、馴染むまでに時間がかかる部分もあったり、『自分は少し異なる感覚を持っているのかもしれない』と感じるようになりました。結果として1年で退部しましたが、多様な考え方や文化の違いを深く理解するきっかけになったと思います」
実力主義で自分のキャリアを築ける環境へ
大学時代に打ち込む目標を見失った下村さんだったが、振り返れば、異文化の壁に立ち向かった経験は初めてではない。すぐに気を取り直し、1年次の春休みには、3カ月の台湾留学を経験し、中国語の習得に力を入れた。ここで、「やはり自分には海外が合う」という手応えを得た下村さんは、2年次以降はアルバイトで貯めたお金で、バックパッカーの旅に出るなど、新たな経験を積んでいく。1カ月でヨーロッパを10カ国以上回ったり、インドを旅したり……まだまだ自分が知らない国や文化があることを知り、将来は国際的に活躍できる仕事をしたいという気持ちが強くなっていった。そこで、在学中は、外資系企業でのインターンシップなどにも挑戦した。
「バックパックを背負ってヨーロッパを旅していたとき、ユースホステルなどで旅行者と英語でやりとりしているときに、やっぱりこれが自分の強みなんだと再確認しました。また、当時はまだ下積みや転勤のある働き方が主流であった日系企業は自分に合わないと感じていたので、実力主義で自分のキャリアを築ける環境を求めました。そこで、就職活動では、外資系企業を中心に面接を受け、最終的に外資系投資銀行への就職を決めました」
社会人9年目に自費でのMBA留学を決意
就職先の投資銀行では、「オペレーション部門」と呼ばれるバックオフィス業務を専門として担う部署を選択した。フロントではないものの、海外とのやりとりが多く、外国人社員も多い環境だった。また、女性が長期的に働ける職場だったため、仕事を楽しむことができたという。そして、約9年間勤務したタイミングで、下村さんは次のステップに向けて大きな決断をする。
「働き始めてからずっとMBA留学をしたいという思いがありました。大学時代に長期留学ができなかったこともあり、いつか自分の意志で海外で学びたいと思っていたのです。ただ、仕事と進学準備の両立、資金の準備などに時間がかかってしまい……丸8年勤務したときに決断して、フランスのビジネススクール『INSEAD(インシアード)』に進学しました」

INSEADでは、シンガポールとフランスの両方のキャンパスで計1年間学ぶという充実した留学生活を送った。The Business School for the Worldを掲げるINSEADには、まさに世界中から学生たちが集まっていた。下村さんが、そこで得たものは、同世代の熱い想いを持つ仲間たち。ケーススタディのグループワークでは、激しい議論になることも少なくなかった。
「同じグループにロシア人とウクライナ人がいたり、イスラエル人とレバノン人がいたり……みんなそれぞれの思想や文化を持っていて、それをぶつけ合う環境がありました。もちろん、私も日本人代表として意見を求められます。それはマレーシアのインター以来のことで、“自分ごと”として世界と向き合う姿勢を思い出すいい機会になりました」
INSEADでMBAを取得し、現在は外資系IT企業で新たなキャリアをスタートしている。今回の仕事は「営業企画」。プログラムマネージャーとして、200人を超える営業部隊の戦略を考える立場にある。IT企業のビジネススピードは速い。それでも外資系企業には、性別も人種も超えて、優れた意見はフェアに尊重されるカルチャーがある。それが心地いいという。
「世界のどこでも働ける自分でありたい」
下村さんには、いつか海外で働きたいという夢がある。現在、勤務する会社には、空いたポジションの募集があれば、全世界から応募できるシステムもある。アメリカにもヨーロッパにもアジアにも広がるMBAの同級生ネットワークもある。
「世界のどこでも働ける自分でありたい」
その言葉は、国内外でさまざまな経験をして、自分の世界を広げてきた彼女のキャリアをそのまま表している。 幼少期からシンガポール、マレーシア、台湾で計7年間学び、現在は外資系企業で活躍する下村さん。最後に「海外子女」の先輩から現役生たちに向けてアドバイスをもらった。
「海外生活は辛いこともあるけど、総じていい経験だったと思います。実際、子どもの頃に海外で暮らす経験なんて、誰にでもできることではありません。どんなことがあっても『これも貴重な経験』とポジティブに捉えることが大切です。私も海外で学んだ経験が、人生の選択に影響を与えているのは間違いありません。海外生活をいい経験にできるかどうかは自分次第。ぜひいろいろなことに挑戦して、できる限り視野を広げてください」