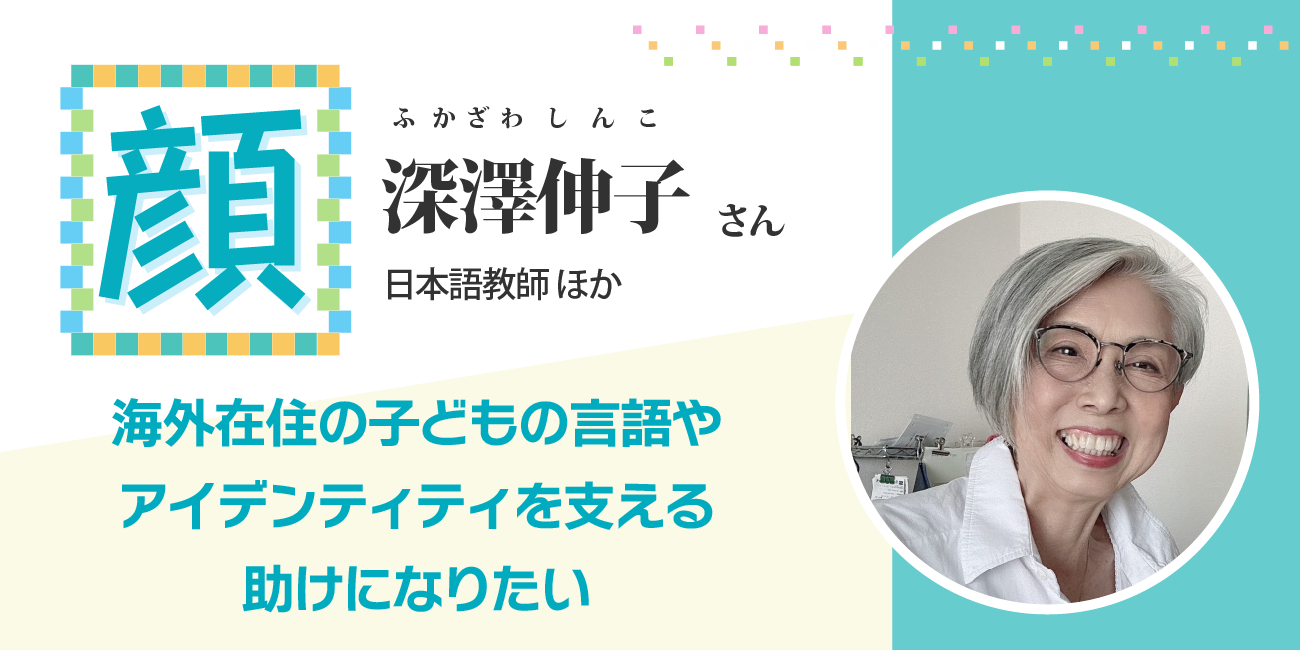大きく翼を広げるハゲワシ。バオバブの木の下で群れるワオキツネザル。樹上で思い思いにくつろぐカメレオン……。ZUVALANGA(ズワランガ)が作る世界には、アフリカの「ある日のある一瞬」が凝縮されている。
太陽を受けてやわらかく光るビーズ。そのゆらぎが作品に命を吹き込んでいるようで、いつまでも眺めていたくなる。
ZUVALANGAは、北窓恵利香さんと夫の綾平さんによるアートユニット。アフリカの大地で出合った動物たちを、ワイヤーとビーズで表現している。
動物のかわいい姿やわかりやすい形のアート作品はたくさんある。しかし、ZUVALANGAが目指すのは単なるゾウではなく、「あのとき、あのサバンナで出会ったあのアフリカゾウ」なのだという。
動物の動きには、水を飲んだり、何かの匂いを嗅いだり、獲物を追っていたり、何かしらの意味合いというか、ストーリーがある。そういう動物の生きている姿を切り取った作品をつくりたい。
「その動物の向こうに、アフリカの風景が見えてくるような……。だって、動物は自然の景色の中にいる時が一番美しいから」と言う恵利香さん。アフリカの色彩にあふれたアトリエで話を聞いた。
(取材・執筆:只木良枝)
この国に飛び込もう
北窓恵利香さんがアフリカン・ワイヤー・アンド・ビーズアートに出会ったのは、南アフリカだった。
2011年、小学校教師である夫の綾平さんがヨハネスブルグ日本人学校に赴任することになった。
「せっかく行くなら、日本にはいない野生動物に会いたいな」と考えていた動物好きの恵利香さんは、赴任先がアフリカ屈指の大都会と知って、最初はちょっと残念だった。しかしある日書店で「南アフリカ 野生動物とサファリの魅力」という本を見つける。大きな自然保護区があって、そこには野生動物がたくさんいるらしい。写真の中から動物が呼んでいるような気がして、毎晩のようにその本を開いてまだ見ぬ南アフリカを思い描いた。
東日本大震災の直後に出発。はじめてアフリカの大地に降り立った。
ヨハネスブルグ日本人学校では、すでに南アフリカ生活を経験している先輩教師がお世話役となって、生活用品を揃える手伝いをしたり、外国人が買い物をしやすいスーパーを案内したりするのが慣例だった。
ところが、北窓家の担当になった赴任3年目の中島先生は、ふたりをいきなりローズバンクというモールのサンデーマーケットに連れて行った。たくさんの人でにぎわうマーケットは活気にあふれ、あらゆるものがあった。
「たぶん、『この夫婦は、外国人向けのスーパーよりもこっちのほうが喜びそう』と思ってくれたんでしょうね」
世界有数のスラム街を擁し、「危険な街」と言われるヨハネスブルグには、外国人向けの生活ゾーンが整備されている。そこはスラム街からは想像できないような、安全で美しい場所だった。日本人学校も、日本人駐在員の子がほとんどだ。現地の人にかかわらずに暮らそうと思えばそれが可能で、実際、そのような生活をしている日本人も少なくなかった。
ところが中島先生は、スラム街の真ん中の教会に得意のギターを持って飛び込み、毎週のように現地の人と一緒に歌って家族ぐるみでつきあっているという。
「入ったら死ぬぞと言われていた場所は、実は下町のあたたかさに満ちていた。僕は、この街で今まで自分が持っていた偏見に気づかされたんですよ」
ヨハネスブルグの街と人々の魅力を語る中島先生の姿に、恵利香さんたちの心のスイッチも入った。

ビーズアートとの出会い
ローズバンクという大きなアートマーケットには、アフリカの色彩にあふれた様々な作品が並んでいた。
なかでも恵利香さんがとりこになったのがビーズアートだった。ガイドブックの片隅に載っていた「土産品」とは全く違う、迫力と魅力に魅了された。
日本人学校で図工と美術を担当する綾平さんも、現地のものを取り入れた授業づくりを模索中だった。アートマーケットにはそのヒントがあるはずだという。ふたりは、毎週のようにマーケットに足を運んだ。
たくさんのビーズアートを見て歩くうちに、恵利香さんは自分でもやってみたくなった。
在住外国人向けのテニスや料理、モザイク画などの教室はあったが、ビーズアートの教室はない。そこで、恵利香さんはマーケットで「教室どこにあるの」と聞いて回った。しかし教えてくれるところは見つからなかった。
「その頃、ジョセフさんと出会いました。彼のお店のビーズアートは品質がよいと評判で、その店先でビーズアートをつくっていたんです。この人なら教えてくれるかもと思ったんですが、『君たちには無理だよ』などと、やはりはぐらかされてしまって」
ジョセフさんの店の裏庭には何人かのアーティストがいて、もくもくと作業をしていた。その光景に心を惹かれた綾平さんは、深く考えずに持っていたカメラで撮影してしまった。
「サーッと空気が変わりました。みんなが『何だお前は』『写真を撮るな』『帰れ』と顔色を変えて声をあげました」
ビーズアートの技術を盗みに来たと思われたのかもしれない。さらに、意外な理由を後になって知った。
実はジョセフさんを含む彼らは隣国ジンバブエ出身だった。独裁政治が続き、厳しいインフレに悩まされるジンバブエからは、多くの人が南アフリカに流れて来ていた。つまり、ジンバブエ人は、南アフリカの中では「よそ者」で微妙な立場だったのだ。
「そういうセンシティブな状況の彼らのところに、僕はズカズカ踏み込んだわけですから、反発されるのも当たり前ですよね」
正直怖かった、と綾平さん。しかし、ふたりはくじけなかった。
「出会いは失敗してしまったけれども、だからこそもっと彼らのことを知りたいと思って」
その後も裏庭に通い続けた。ランチを買って行ったり、いなりずしを作って持って行ったり。自宅のたこ焼き器を持ち込んで焼いて、ふるまったこともある。
最初は無視されて、「そこに勝手にいるだけ」だった。いつしか誰かがイスを出してくれるようになった。「こっちの木陰に座れ」と涼しい場所をあけてくれた。そのうちにコーラが出てきたり、「ビール飲むか?」と声をかけてくれたりするようになった。
語り合ううちに、彼らの出身国やここに来た経緯など、様々な背景がわかってきた。ビーズアートがもともとは厳しい生活の中から生まれた廃材利用のオモチャからアートに進化していったこと、彼らにとっては生計をたてるための手段であるだけでなく、文化的にも重要なものであること……。ふたりは、ビーズアートを入り口に、アフリカの奥深いところに入っていったのだった。


アーティストへの敬意
「今日は何の話をしようかな」と思いながら通い続けて半年ほどたったある日、はじめて「やってみるか?」とジョセフさんから声をかけられた。裏庭工房のアーティストたちに、ふたりを受け入れてよいか相談してくれたようだった。
一生懸命つくったはじめての作品を受け取ったジョセフさんは、バラバラにして瞬く間に組み上げなおした。師匠と弟子になれた瞬間だった。
毎週末の楽しい修行が始まった。ふたりはますます熱心に裏庭工房に通うようになり、そこが居場所になっていった。彼らの日常生活の中に自分がいるという心地よさ、安心感。それは、よい形ではなかった出会いにもかかわらず、じっくり関係を紡いでいったからこそ得られたものだった。中島先生の「自分自身が飛び込んでみないとわからない」という言葉を実感していた。
作品づくりには時間がかかるし、週末に裏庭工房に入り浸っていると、どうしても日本人同士の集まりに参加する機会が少なくなった。「欠席ばかりでいいのかな、と思ったこともあったんですけど」と、苦笑しつつ振り返る恵利香さん。しかし周囲の仲間も「恵利香さんはランチ会よりビーズだよね」と、いつしかあたりまえのように受け入れていた。
北窓さんたちが「入り浸っている」ことを知って、ジョセフさんの店を訪ねる日本人も増えた。最初は怖いと思っていても、何かの手がかりさえあれば現地とかかわりたいと思っていた日本人は、たくさんいたのだった。


生きることに関わるアート
3年後に帰国。家電や家具はガレージセールに出すのではなく、物々交換でビーズ作品をオーダーした。冷蔵庫はキリンに、ベッドはカバになった。
作り手によってひとつずつ違うビーズアートには人と土地のこだわりが詰まっている。そう思うといくらでも欲しくなった。
「私、ギリギリまでオーダーしてしまって。これは間に合わないなあとあきらめていたところ、帰国当日の朝にホテルに届けてくれて感激でした」
船便を出す日、段ボールの蓋を閉める直前まで寸暇を惜しんで綾平さんが作っていたライオンは、つくりかけのまま海を渡った。大きなワシの作品には、引っ越し業者が特製の箱を作ってくれた。もちろん、ビーズもワイヤーもたくさん買い込んだ。
帰国後、ビーズアートのことを知った知人から、「面白いね。人に見てもらったら?」と声をかけられた。たまたま自宅近くのギャラリーが借りられることになったので、友人知人への帰国報告を兼ねて、展覧会を開催することにした。
「ZUVALANGA」というアートユニット名を付けたのはこのときだ。ZUVAとLANGAは、それぞれジンバブエのショナ語、南アフリカのズールー語で「太陽」を指す。「太陽に集い、太陽に笑う美しい生きものたちの世界を表現し続けたい」という願いを込めた。
展覧会は大盛況だった。ビーズアートに興味を持つ人がこんなにいる。ならば、もっと作ってみようと思った。
ただ、恵利香さんたちは「作ること」だけにフォーカスしたくなかった。
「ビーズアートはポップでかわいいと言われます。でもそれだけなら誰が作っても同じ。私たちは、師匠たちと語り合いながら作品を生み出してきた。ビーズアートにこめられた彼らの文化背景や思いを知っています」
作り手の文化をきちんと伝える。それが、ジョセフさんの店の裏庭で修行させてもらった自分たちの役割だと思った。
「ジョセフさんたちとは毎日のようにメールでやりとりして、様々なことを話しあいました。帰国してからのほうが、関係が深まったような気がします」
2016年と2019年にはジョセフさんを日本に招いた。数カ月間一緒に暮らし、ZUVALANGAとの合同展覧会も開催。各地を訪問し、雪の北海道では中島先生ファミリーが、東京では日本人学校の教え子や保護者たち20人あまりが歓待してくれた。
もうひとつ、大きな転機となったのが2017年に国立民族学博物館(大阪)で開催された「ビーズ—つなぐ・かざる・みせる」展だ。人類とビーズのかかわりを、素材や歴史、民族の背景などの視点から幅広く俯瞰した内容で、その後北海道や東京など日本各地を巡回した大きな展覧会だった。ZUVALANGAは、ここにビーズアーティストとして関わったのだった。
「ビーズアートという文化が、人間が生きるということに深く関わっているということを再確認しました。圧倒された、と言ってもいいかもしれません」
恵利香さんは、ますますビーズアートの民族学的な側面を掘り下げて考えるようになっていく。それは2023年、同館友の会機関誌の『季刊民族学』に掲載された「出稼ぎするアーティストたち~南アフリカのワイヤー・アンド・ビーズ・アート」と題した論考に結実していった。
ビーズアートから生まれるつながりと未来
アーティストZUVALANGAとしての夢は、いつかアフリカで個展を開くことだという。
「自分たちの作品が現地でどのように見られるか、興味ありますね」
もうひとつ大切にしたいのが、アフリカのビーズアーティストを日本に紹介することだ。今年5月に兵庫県宝塚市で開いた展覧会では、アーティストたちの肖像と作品を多数展示した。
「彼らの作品をもっと日本の人に知ってほしいと思います。一方で安価なお土産物のように取り扱われることのないように、文化背景や価値をきっちり説明していかないといけない」
なぜなら、ビーズアートは彼らの「生きるための文化」だから。それを教えてくれた師匠ジョセフさんは2023年にこの世を去ったが、ZUVALANGAの中には生き続けている。そしてアフリカのアーティストたちとのつながりは、これからも続いていく。
帰国して10年たった。「でもまだ半分アフリカの中にいるみたい」という恵利香さん。その指先で光るビーズは、今日も遠いアフリカを手繰り寄せている。

【プロフィール】 北窓恵利香(きたまど・えりか)さん 大阪府出身 オーストラリアでのワーキングホリデーを経験し、その後、モンゴルで日本語を教えた。 夫の綾平さんの赴任先である南アフリカででワイヤー・アンド・ビーズアートに出会い、現地のアーティストに師事。帰国後は綾平さんとアートユニットZUVALANGA(ズワランガ)を結成。日本で活発に創作活動をおこなうとともに、頻繁に南アフリカに足を運び、アフリカン・ワイヤー・アンド・ビーズアートの心と文化的背景を掘り下げ、伝える活動を続けている。