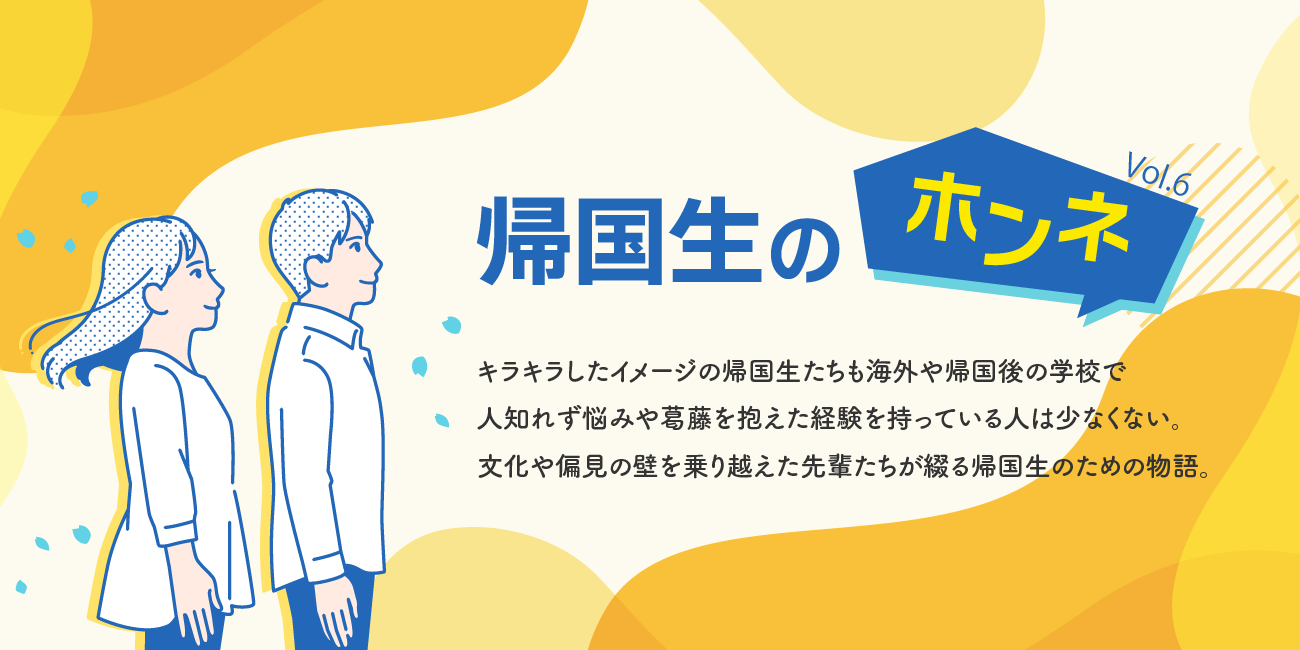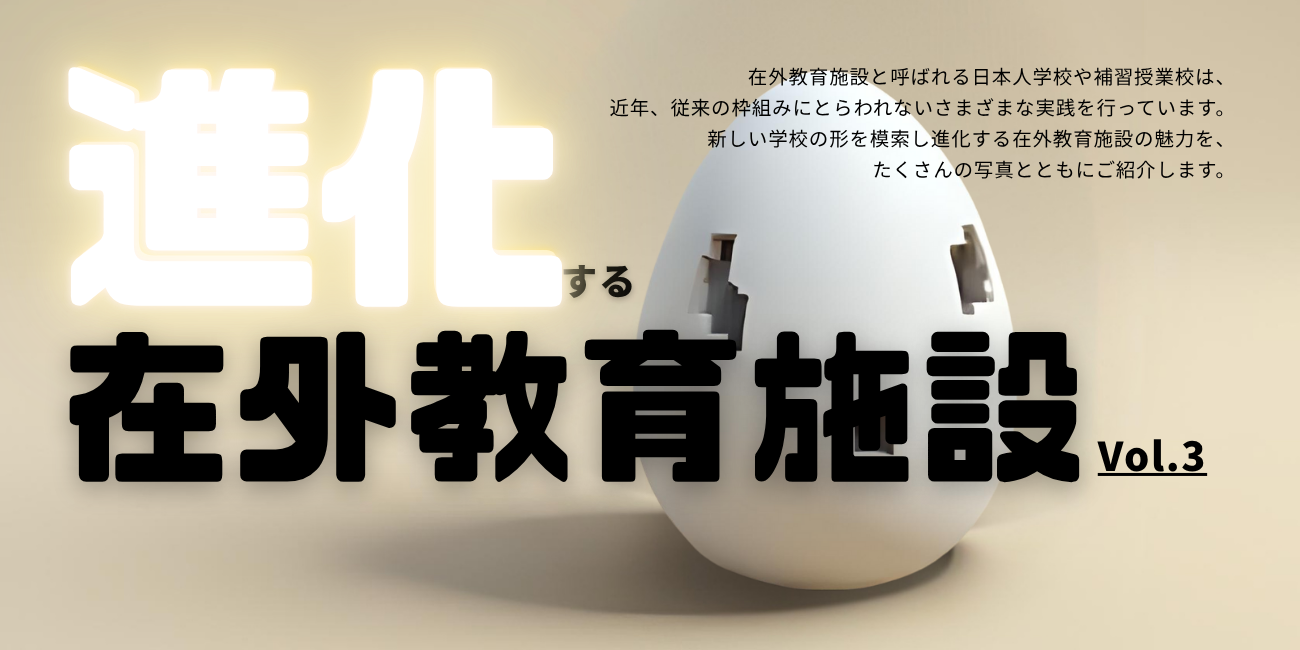第46回海外子女文芸作品コンクール 審査結果発表(作文その3)
海外子女教育振興財団主催の第46回海外子女文芸作品コンクールの審査結果が発表されました。このたび、特別賞受賞作品をご紹介します。
このコンクールは海外に在住する小・中学生が言語・風習・気候風土・治安など、日本と異なる生活環境の中で感じ、考え、感動したことを日本語で表現することを促すために、1979年から毎年行われています。
今回は、日本人学校や補習授業校に通っていない子どもたちからの作品が大幅に増え、滞在年数に関係なく優秀な作品が散見されました。
良質の作品の応募には先生方の指導や学校としての取り組み、家庭教育の大切さを痛感します。子どもらしい気づきや素直な好奇心に、文章の構成や語彙など日本語の知識を高める機会が加われば、さらに状況や気持ちの伝わる素晴らしい作品になることでしょう。
なお応募作品総数は31,927点(作文=2,484点、詩=2,880点、短歌=6,260点、俳句=20,303点)。すべての部門で昨年度に比べて多くの作品が集まり、コロナ禍以降で初めて3万点を超えました。
これらの作品は予備審査を経て9月19日、海外子女教育振興財団(東京都港区)で行われた最終審査会にかけられ、協議の末、文部科学大臣賞をはじめ、海外子女教育振興財団会長賞、後援・協賛者賞、特選、優秀、佳作が決定しました(特選・優秀・佳作・学校賞の審査結果は弊財団の文芸作品コンクールのサイトに掲載しています https://www.joes.or.jp/kojin/bungei)。
なお今年の12月には、作品集『地球に学ぶ 第46回』が刊行される予定です。
日本児童教育振興財団賞
強くなるってどういうこと?
トロント補習授業校(カナダ)
小3 岸田 帆生
カナダにすんでいると、友だちとおわかれするきかいが多い。そのたびにとてもかなしい気もちになる。わたしはカナダで生まれそだったから、これからもずっとカナダにいる。わたしはいつも見おくるがわだ。
友だちだけではなく、先生のいれかわりもはげしい。わたしは人とおわかれする時、いつもないてしまう。クラスのだれ一人ないていなくても、わたしはいつもなく。
「なぜわたしだけ、いつもないてしまうのだろう?」
わたしは自分の心が弱いから、ないてしまうのだと思った。わたしは強くなりたかった。
それからというもの、わたしは人とおわかれする時、なかなくなった。なくのをがまんしたら、なみだは出なくなったけれど心はさみしい気もちのままだった。ちっとも強くなれた気にはなれなかつた。それどころか、なみだをがまんすればするほど、心はどんどんかなしくなっていった。
二年生のおわりに、「一年生から二年生になって、できるようになったことはなんですか?」というワークシートがあり、わたしは、「先生や友だちとおわかれする時、なかなくなった。」と書いた。でも、これを書いた時、わたしはふくざつな気もちでいっぱいだった。なかなくなったのは、本当にいいことなのかな?なくことはわるいこと?そんな言葉が、わたしの頭の中でぐるぐるまわった。
ほ習校で二年生のさい後の日に、わたしの大好きだった、たんにんの先生が日本に帰ることになった。なかないでおこうと思ったのに、自ぜんとなみだがあふれてきた。もうカナダには帰ってこない先生のことを思うと、なみだがとまらなくなった。
「ああ、またないちゃったな。」
そう思ったしゅん間、先生が
「やさしいね、ありがとう。」
と言ってわたしをだきしめてくれた。先生はわらった顔をしていたけれど、どこかかなしそうな顔をしていたようにわたしには見えた。
「先生もおわかれするのがさみしいのかな?」
それいらい、わたしは見おくられる人たちの気もちも考えるようになった。きっと見おくられる人たちも、すごくかなしいんだな。日本に帰ったら新しい生活がまっていて、ふあんな気もちでいっぱいなんだろうな。そんなことを考えているうちに、日本に帰っても元気でいてほしいな、新しい友だちをたくさん作ってほしいなと、見おくられる人をおうえんする気もちがこみ上げてきた。
そう考えるようになってから、さみしい気もちはかわらないけれど、わたしの心がすうっと落ちついていくのがわかった。それからは友だちとの時間をもっと大切にすごそうと思えるようになった。
わたしは、これからもたくさんの人たちを見おくることになるだろう。でも少しくらいないてしまっても大じょうぶ。なくことはけっして弱いことではないということがわかったから。もしまた、とてつもなくかなしい気もちになったら、見おくられる人が日本でうまくやっていけるように、元気ですごせるようにおいのりしよう。そして、いつかまた会おう、そう強くねがう心が、わたしの心を強くしてくれると思うから。
クラーク記念国際高等学校賞
ぼくたちは人間だから
デュッセルドルフ補習授業校(ドイツ)
小5 河尾 有灯
ぼくは今、ドイツで移民の一人。母も。ドイツ人の父と、ぼくの弟と妹は、ドイツで移民ではない。でも、もしぼくたちが日本に住んだら、ぼくと母と弟と妹は移民ではないけれど、ドイツ人の父は移民だ。ぼくはもうすぐ、ドイツ人の父の養子になる、そうしたら、ぼくはドイツでも、移民ではなくなるのかな。ぼくの母は日本人で、ドイツではずっと移民のままだ。父と母がぼくに養子とは何か話してくれた時、ぼくは母に、母の国せきについて聞いてみた。その時母は、
「ママは日本人であることをほこりに思っていて、これからも国せきを変えることはないよ。」
と言っていた。そしてこの夏、ぼくたち家族は、みんなでアメリカへ引っこす。アメリカでは、ドイツ人の父も、日本人の母も、ドイツ人でも日本人でもあるぼくたち兄弟も、みんな「移民」になる。
今までぼくは、自分も「移民」の一人だなんて、考えたこともなかった。でも、今年の春休みに日本に行った時、祖父から、日本で移民の問題が起きていることを聞いて、ぼくはもやもやした気持ちになった。ぼくがくらしているドイツには、移民もなん民もたくさんいるし、それはぼくの学校の教室でも同じだ。だから、ぼくにとって世界中に移民がいることは、特別なことではない。ぼくが感じたもやもやした気持ちは、悲しいような、おどろいたような気持ちだったのかな。そしてふと、「移民」ってだれのことだろう、とぼくの心はそわそわした。IOM(国際移住機関)によると、「移民」とは、本人の法的地位や移動の自発せい、理由、たいざい期間に関わらず、本来の居住地をはなれて、国きょうをこえるか、一国内で移動したあらゆる人、と説明されていた。ということは、ぼくも「移民」なのだ。
ぼくは日本で生まれて、四才の時、ドイツに引っこしてきた。それからずっとドイツでくらしていて、今は小学四年生だ。ドイツの小学校は四年生までなので、この夏から、ぼくはギムナジウム(大学進学コース中高等学校)に進学する。ぼくたちは夏休み中にアメリカへ引っこすから、ぼくはアメリカにあるドイツ人学校のギムナジウムに入学する。ぼくは今、学校の休み時間も放課後も、毎日友達とサッカーをしているので、アメリカへ行っても、新しい友達とサッカーをすることを楽しみにしている。ぼくのしょう来のゆめは昆虫学者になって、ノーベル平和賞を取ること。そのゆめに近づくためにも、これからぼくは、アメリカで新しいことを学びたい。
日本でもドイツでもしていたように、アメリカへ行っても、ぼくは昆虫さがしや観察を続ける。昆虫の世界では、外来種による多くの問題が起きる。例えば、ざっ種がふえてざい来種がいなくなってしまったり、ざい来種と外来種がえさや住みかをめぐって争いや競争をしたり、害虫の問題が起きたりする。絶めつする昆虫が出て、生態系が変わってしまうことは、昆虫の世界では大問題だ。でも、昆虫の世界とちがって、人間の世界では人が移動することによって、いいこともたくさんある。ぼくのクラスにも、いろいろな国と関わりのある友達がいて、ぼくたちはおたがいに、いろいろな国の文化や言葉を知れる。移動してきた人たちは、もともといた人たちの言葉や生活になれるように努力することが大切だと思う。そして、もともといた人たちはきょう味をもって、おたがいに自分たちの文化や言葉を教え合えたら、世界は平和に楽しくなると思う。人間は昆虫とちがって話せるし、遠くまで行けるし、自分のありのままで相手と仲良くすることができる。人間だから、移動することによって問題を作り出すのではなく、助け合ったり、えいきょうし合ったりして、よりよい世界を一緒に作っていけると思う。
ぼくの日本人のパパは、ぼくが一才の時にメキシコでなくなって、今は天国でくらしている。母は、ぼくのパパがスペイン語がペラペラで、スペイン人の友達と一緒に、スペインでいつも笑ってくらしていた話をよくしてくれる。天国では何語で話しているのか分からないけれど、パパはやっぱりいつも、笑顔でくらしていると思う。天国には移民問題なんてないのだろうな、とぼくは想像する。天国では、国せきなんて関係なくて、みんな仲良く平和にくらしていると思う。ぼくたちが生きている世界もそんなふうに平和だったらいいけれど、ぼくたちの世界には国きょうがあって、それぞれの国に、それぞれの言葉や文化やれきしがある。だから、みんなが仲良くくらせるように、おたがいを大事に、おたがいをそん重し合ってくらせたら、世界はきっと天国みたいに平和になると思う。
早稲田アカデミー賞
四日間戦争
イスラマバード日本語クラブ(パキスタン)
小6 藤﨑 巴吏秀
五月八日木曜日、朝起きたら、父と母がニュースを見ていた。テレビでは、夜中にインドから攻撃があって、パキスタン各地でいくつも爆発があった動画が流れていた。母が今日は学校は休みだと言った。学校は試験期間中で、今日はコンピューターと僕の苦手なウルドゥ語の単語試験があるはずだったので、僕は飛び上がるほど嬉しい気持ちだった。嬉しすぎて、寝ていた弟を起こして学校が休みだと教えた。今まで、プロテストで学校が休みになったことは何回もあったけど、爆発があったから、というのは初めてだった。
母は仕事が休みになって、僕たちと家にいた。僕は弟とゲームをたくさんして、ずっと休みだったらいいのに、と思った。学校の友達のグループメッセージでは、これがずっと続くといいな、という人もいれば、すごい心配してる人もいた。僕はテストの勉強なんかしなくていいと思った。本当に明日はテストがあるのか分からないし、テストの勉強をしたって、どうせ無駄じゃないのか、と思った。国が戦争になるかもしれないのに、テストをやっている場合じゃない。
金曜日も学校は休みだった。朝から、インドのドローンがたくさん上空を飛んでいたので、外に出られなかった。ドローンは、僕の住んでるところから車で二十分位のクリケットスタジアムにも落ちた。そこは、僕がサッカーに行く時に何度も通ったことがある所だった。サッカークラブから、今日の練習はキャンセルです、ステイ・セイフ、とグループメッセージが来た。学校に行ったり、友達に会ったり、サッカーをしたり、毎日当たり前にしていたことが全部できなくなった。
この日の夜は、停電になった。僕は本当に停電なのか、戦争のせいかのか分からなくて心配だった。軍の飛行機が飛んでいる音が家の中まで聞こえて、なかなか眠れなかった。日本の祖父から大丈夫なの?と電話があった。日本の友達のお母さんからも母に連絡があった。パキスタンに住む日本人の友達の町では灯火管制が行われていて、電気を消して真っ暗な中で携帯を見ている、と連絡があった。僕はなんだかすごくヤバイ感じがした。
土曜日、朝早く起きたら急に状況が変わっていた。夜中に、近くの軍施設にミサイル攻撃があったらしい。母とソファに座っていたら、ドーンと大きな音が二回聞こえた。一瞬何か分からなくて、母と目が合った。こんな事は初めて。びっくりした。軍施設の近くに住んでいる親せき二家族が僕の家に避難してきた。直ぐにパキスタン軍もインドを攻撃した。みんなは空軍のパイロットの従弟のことを心配していた。僕も心配だった。
このままでは僕たちは日本に帰らないといけないかもしれない。でも空港はもう封鎖されているし、帰れるのか。もしも、僕が日本に帰れたとしても、パキスタンから帰るところがない人はどうなるのか。戦争が始まった時は、僕はこのまま学校が休みになって、テストもなくなればいいと思っていた。でも、こんなにひどくなるとは思わなかった。
五月十日、土曜日の夕方、パキスタンとインドは停戦に合意し、戦争は終わった。四日間は短かったけど、僕はすごく長く感じた。毎日、明日はどうなるんだろう、と思って怖かったから。夜にはパキスタン軍の長い記者会見があって、陸海空軍がそろって四日間の出来事を説明していた。僕は、すごく格好良いと思った。
翌日、日曜日にはサッカーの練習があって、月曜日は学校で予定通りにテストがあった。昨日まで戦争をしていたのに!こんなに直ぐに、普通の生活に戻るなんて。もうテストはないのかと思っていたので、日曜の夜に慌ててテストの勉強をした。
もし、停戦になっていなかったら、今頃僕たちはどうしているのか、考えるのも恐ろしい。去年の夏休みに広島の平和記念資料館に行った時は、まさか自分が戦争を体験することになるなんて思いもしなかった。僕は、このまま学校がずっと休みになったらいい、と思っていたけれど、たった四日間でも、戦争の後には、やっぱり普通の毎日が一番なんだと気が付いた。今日は、テレビでイランとイスラエルのニュースをやっていた。戦争を経験した僕は、今心から、世界中の人達が普通の毎日を過ごせるように祈っている。