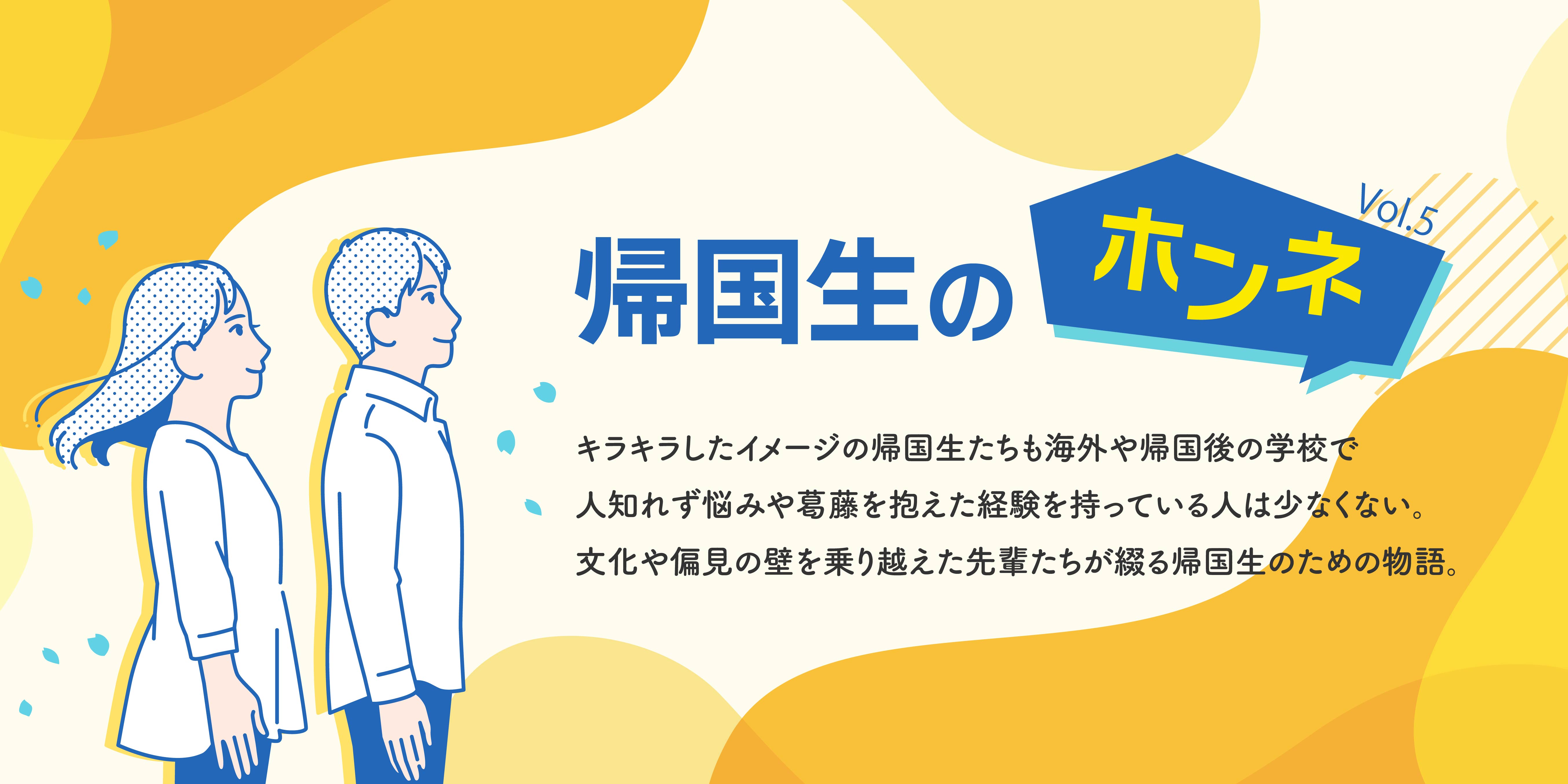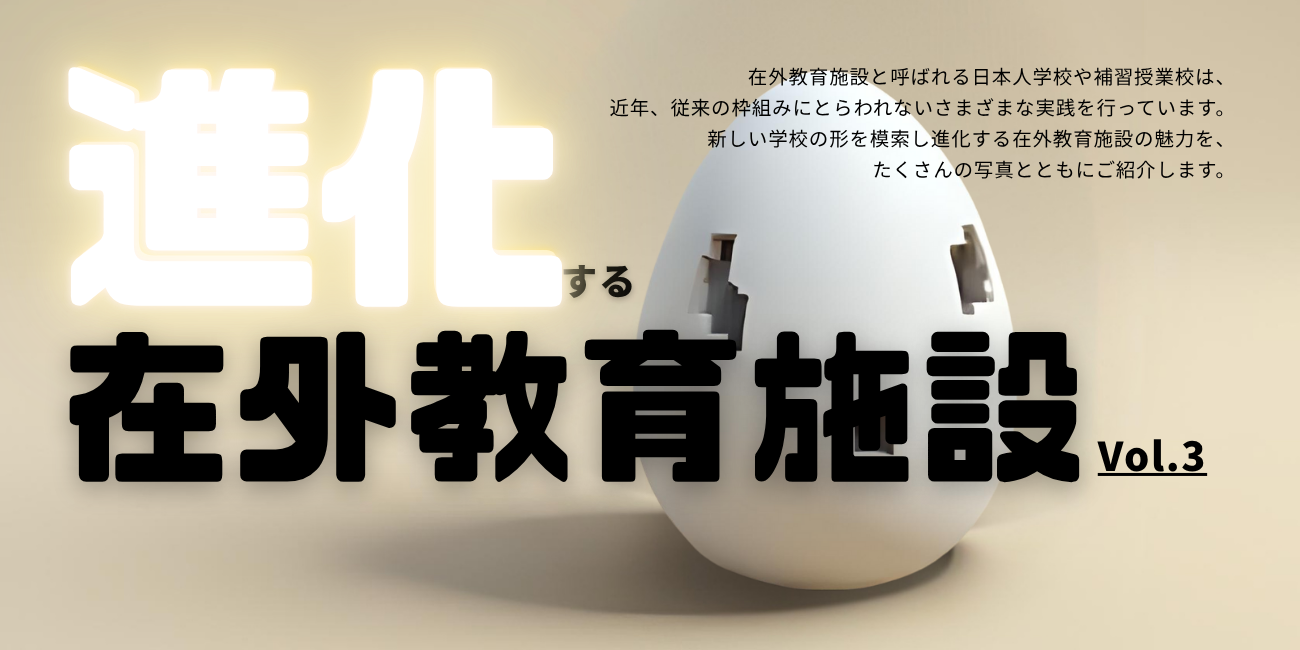アメリカ・イリノイ州シカゴ近郊で生まれ育った川勝慶成さんは、小学校3年生のとき、初めて日本に帰国し、公立小学校に通い始めた。しかし、スピードの速い日本語や「みんな同じ」を強制されるような雰囲気により、次第に劣等感を感じるようになる。学校で目立つことを避けるようになってしまった小・中学校時代を経て、川勝さんは高校時代にやっと自分の居場所を見つける。それは、困難を抱える若者を支援する活動。アメリカで多様性の中で暮らし、帰国後は勉強が苦手で疎外感を味わった経験が、困っている人に寄り添う活動と共鳴した。
取材・執筆:ミニマル丸茂健一
異国の不思議な文化に出会った感覚だった
「全校集会でみんなが行進している姿を見て、面白いなと思いました。何をしているんだろう?という感じで」
アメリカ・イリノイ州シカゴ近郊で生まれた川勝慶成さんは、8歳まで現地で過ごし、小学校3年生のときに、兵庫県の公立小学校に転入した。そして、登校初日に見た忘れられない光景が、子どもたちが一列になって校庭を行進している様子だった。8歳になるまで、一度も日本を訪れたことはなかった。だからこそ、「日本ってどんなところだろう?」とワクワクしていた。そして、通い始めた日本の小学校生活は、アメリカ時代とは大きく異なるものだった。
川勝さんが生まれ育ったのは、イリノイ州のエルクグローブビレッジ。シカゴ近郊のベッドタウンで、比較的大きめの家が建ちならぶエリアだった。川勝さんはここで、現地のプリスクールと公立小学校に通った。小学校は、250~300人規模で、白人をメインにアフリカ系、ヒスパニック系、アジア系の子どもたちも数多く通っていた。
「当時、団地のような集合住宅で暮らしていて、同じ建物に日本人の子どもたちも住んでいました。複数の棟の真ん中に芝生があって、いつもそこで友達と遊んでいました。日本人がメインでしたが、会話はすべて英語。近隣には、インド系の人なども多く住んでいて、敷地内にスパイシーな匂いが漂っていました。小さなコミュニティだったので、家族同士のつながりが深く、日本人の友達とは晩ご飯を食べた後もまた一緒に遊んだりしていましたね」
現地で通っていた小学校は、低学年だったこともあり、長机に複数の子どもたちが一緒に並んで座り、いつでも自由に発言しながら授業を受けた。授業といっても単語のスペルを当てるカードゲームなど、遊びの要素が多かった。教室には、色鉛筆や絵の具が備え付けてあり、ペンケースさえ持っていけば、問題なく学ぶことができた。そこには、机と椅子が黒板に向けてきれいに並べられ、授業中は私語禁止で自由にトイレにも行けないという日本の教室とはまったく違う世界があった。
放課後は日本語の補習校にも通った。ここで最低限の日本語の会話やひらがなの書き方などを学んだ。また、日曜には教会で礼拝に参加して、助け合いの精神などを学んだ。ここで気候変動や戦争で苦しんでいる人々がいることなど、国際社会の問題に関心を持つ意識を子どもながらに身につけることができたという。
「アメリカの小学校で印象に残っているのは、下の学年の子に勉強を教えるクラスがあったことです。確か1・2年生と3・4年生が一緒に受ける授業で、年下の子に算数を教えたのを覚えています。うれしそうな笑顔が忘れられません」
「みんな同じ」のカルチャーに馴染めなかった
生まれてから8年間のアメリカ生活を経て、川勝さんは小学校3年生の夏に、兵庫県の小学校に転入した。ここで、いきなり壁にぶつかる経験をする。日本の授業進捗がアメリカと比べ早く、日本文化に立脚した授業内容についていくのは大変だった。まず、日本語を話すペースが合わない。漢字などのテストも知識の蓄積がないので、どうしても点が取れない。先生が特別なテストを用意してくれたりはしたが、次第に劣等感を感じるようになり、教室ではあまりしゃべらなくなってしまった。
「みんな同じものを使う」のが基本となる日本の学校システムにも慣れることができなかった。習字セット、裁縫セット、彫刻刀セットなど、みんなと同じものをどこで買えばいいのかもわからない。ペンケースさえあれば、どうにかなったアメリカの小学校では、みんなが違うものを持っているのが当たり前。それに対し、日本では、みんなと違う物を持つことは、恥ずかしい行為なのだと思った。
「とにかく漢字もできないし、かけ算も覚えられない。さらに、いきなりリコーダーをやれと言われてもうまく吹けない……。すっかり勉強が嫌いになってしまって、人前に立つことを避けるようになってしまいました。先生との距離感にも戸惑いました。アメリカではもっと先生との距離が近く、自分に関心を持ってくれていることが子ども心にもわかりました」

地域の演劇サークルで表現の場を見つける
そんな様子を見かねた母親が、行政が行う演劇サークルや科学イベントなどに川勝さんを連れて行った。そこで人形劇などに挑戦することで、小学校高学年だった川勝さんは、次第に自分を表現する場を見つけていった。学校では劣等感を感じることが多い生活だったが、学校の外では自分らしくいられた。
小学校卒業後、進学した公立の中学校でも状況は変わらなかった。毎日通ってはいたが、学校での居場所を探す日々。成績も思うように上がらなかった。中学2年次から美術部に入り、大好きだった絵に没頭しながら過ごしたが、居場所といえるほどではなかった。部員の中で、男子はひとり。それでも作品をつくる過程で自己を表現することができ、心の拠り所にはなっていた。
「この頃は、キリスト教会のコミュニティに参加し、演劇やダンスの活動にも挑戦していました。教会は私にとってのサードプレイスでした。学校の成績に関係なく私を一個人として見てくれる唯一の場所でした。教会は私の心を育ててくれた場所であり、かけがえのない場でしたが、教会での体験を教会以外の人と人共有することはありませんでした」
困難を抱える中高生の居場所づくりの活動に参加
そんな川勝さんが次第に行動範囲を広げていくことになるのが高校時代。夜間の定時制高校に通い、1年次の後期から生徒会活動に参加した。中学校までは、「勉強が苦手」という劣等感と戦う日々だったが、高校では違った。定時制高校に集まっていた仲間は、さまざまな苦労があって、そこにいた。勉強ができることだけが共通の価値観ではない世界。やっと居場所といえる場所を見つけた川勝さんは、生徒会活動だけでなく、アルバイトや社会貢献活動にも参加しはじめる。
「高校時代は、困難を抱える中高生の居場所づくりや地域の若者支援活動にも参加しました。本気で取り組める活動を見つけたことで、自分の視野が一気に広がりました。それまで心のどこかで、地球温暖化や環境破壊、国家間の紛争など国際社会の問題に関心を寄せていました。しかし、地域の支援活動に参加するようになり、社会課題は身近なところにもたくさんあることを知りました。環境問題も大事だけど、目の前の困っている人を支えることも重要な仕事だと気づきました」
国際情勢に関心を持つようになったのは、父親の影響も大きかった。貿易関係の仕事をしていた父親は、国際社会の動きを常に意識していた。さらに、幼い頃から教会に通い、平和や自由をどう守るか?といった議論をしてきた経験も背景にあった。アメリカで身につけた社会問題への関心や困っている人を助けたいという意識が、ここでやっと地域社会とつながったのだ。

「自分のためにやることが、最終的にはみんなのためになる」
川勝さんは現在、大学に進学し、経済学部で学んでいる。さらに、学業と並行して、小学生向けの学習支援のアルバイトにも力を入れている。家庭環境や経済的な問題で、十分に教育を受けられない子どもたちに勉強を教えているのだ。施設に通う子どもたちは、勉強が苦手で劣等感を抱え、感情のコントロールができなかった小学校時代の自分と重なる部分が多く、「自分ごと」として支援に参加することができるという。
一方で、大学では「帰国子女」というレッテルを貼られることに違和感を覚えることもあった。どこでも、帰国子女だというと、「すごい」と言われる。さらに、英語を活かした仕事をすべきだと言われるが、英文法や英単語は受験生の方が詳しい。川勝さんにとって、英語ができることはそれほど特別なことではない。むしろ勉強が苦手になったきっかけが帰国であり、ネガティブな性格になったのも帰国がきっかけだった。それでも、それを外で言うことははばかられた。自分の考えは、頑張って活躍している帰国生や移住者の前ではただの甘えに聞こえると思った。こうした違和感は、同じように困難を抱える人々への共感へとつながっていった。
「日本に帰国してからの劣等感や疎外感は、確かにつらいものでしたが、それがあるからこそ『困っている人に寄り添いたい』という気持ちを持てるようになったのだと思います。将来的にも困っている人を支援する活動を続けたい。しかし、行政やNPO法人も持続可能な活動をするには、どうしても経済的な基盤が必要です。そのため、自分がやりたい活動を実現するためにも今はしっかり経済学を学びたいと思っています」
川勝さんの将来の夢は、地方の経済活性化や地域の居場所づくりに関わること。大学で学んでいる経済学の知識と、これまでの経験を組み合わせて、地域に根ざしたビジネスモデルを考えていきたいと考えている。インバウンド旅行者が増加する今、強みである英語を使って観光客をサポートする活動なども期待できるだろう。人口減少が続く今こそ、地域にチャンスがある可能性も大きい。地域でも希望を持てる社会をつくることが川勝さんの思い描く未来図だという。
「今振り返ると、8歳までのアメリカ生活は、自分の人格形成に大きな影響を与えていると思います。多民族が共存する環境で育ったことで、マイノリティの人々に心を寄せる意識が自然に身につきました。また、異なる言語や文化に触れること、新しい何かに挑戦することへのハードルも周囲の仲間と比べて低いと思います。最後に、同じように海外生活と日本での生活の間で揺れ動いている帰国生に伝えたいことがあります。それは、『自分のためにやることが、最終的にはみんなのためになる』ということです。周囲の期待やステレオタイプに縛られる必要はありません。自分自身を大切にし、自分らしさを失わずに歩んでいくことが、必ず誰かの力になると私は信じています」