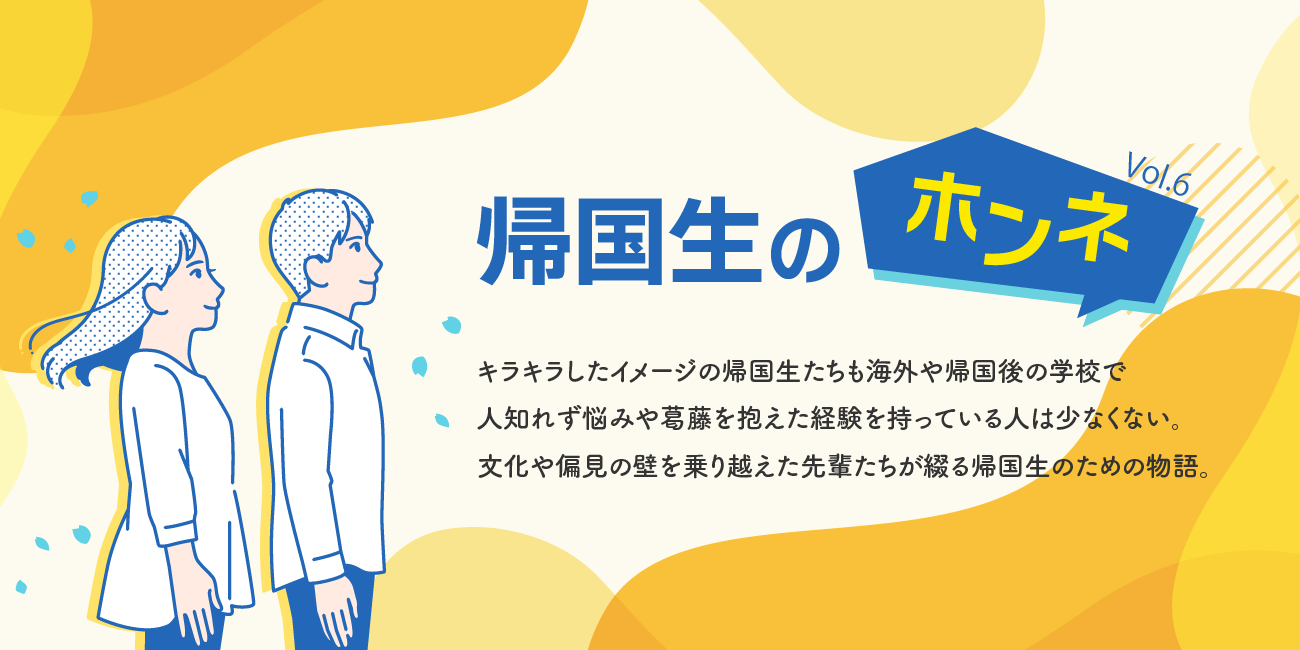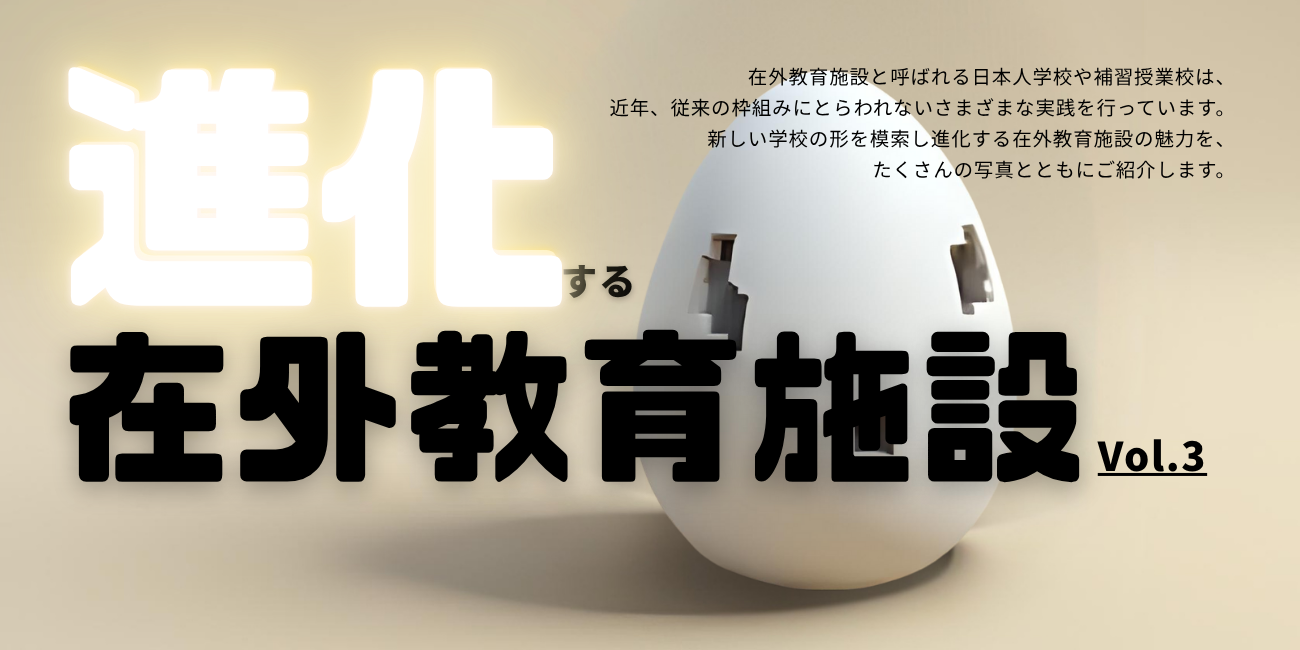ソニーのV字回復をけん引した元最高経営責任者(CEO)であり、現在は一般社団法人プロジェクト希望の代表理事を務める平井一夫氏は、まだ「帰国子女」が珍しかった1960~70 年代に、アメリカ・ニューヨークで小学1年から4年生まで、カナダ・トロントで中学時代を過ごした元帰国子女。当時の異文化体験は、その後の人生や考え方に大きな影響を与えているという。
このたび、公益財団法人海外子女教育振興財団理事長の綿引宏行がホストとなり、「異文化で育つとはどういうことなのか」について、お話を伺った。
<プロフィール>

平井 一夫(ひらい かずお)
1960年東京生まれ。幼少時代に父の転勤で海外生活を送る。㈱CBS・ソニー(現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)に入社。95年にソニー・コンピュータエンタテインメント・アメリカに転身、同社の北米プレイステーション事業を大きく拡大させる。その後、同社や㈱ソニー・コンピューターエンタテインメント(SCEI、現 ソニー・インタラクティブエンタテインメント)、ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)にてトップを担う。代表執行役社長兼CEO、取締役を経て18年に会長。19年より24年までソニーグループシニアアドバイザーを歴任。21年、子どもたちの未来創造のきっかけとなる「感動体験」をつくるプロジェクトを始動し、(一社)プロジェクト希望を設立、代表理事を務める。
 綿引 宏行(わたびき ひろゆき)
綿引 宏行(わたびき ひろゆき)
1957年東京・浅草生まれ。旧東京海上火災保険㈱(現・東京海上日動火災保険㈱))に入社し、情報産業や国家プロジェクトを担当。13年より同社常務取締役、16年退任、19年まで東京海上日動HRA(Human Resources Academy)社長。2009年から米国東京海上に社長として赴任し、ニューヨーク教育審議会副会長も務めた。19年に(公財)海外子女教育振興財団の理事、20年から理事長。現在、中央教育審議会臨時委員、横浜市教育委員会委員を務める。
大人の責任

綿引 平井さんのメッセージを読んでもらいたい人たちは、日本人の子どもたちをはじめ世界中にいます。
日本人学校や補習授業校に行っている子どもがおよそ4万人、現地校やインターナショナルスクールに通っている子どもが23万人ぐらい、そのうちの半分ぐらいは日本人学校や補習授業校があるのに行っていないという子どもたちで、日本人学校や補習授業校がないから通えないという子どもは約5・6万人いるのではないでしょうか。
平井さんはアメリカで幼少期を過ごされていますが、親の立場でもアメリカでの生活を経験されていらっしゃいますね。
平井 最初に家族を連れてアメリカ行ったのは1990年代で、当然、日本に帰るつもりでいたのですが、結局、私は永住権、妻と子どもたちはアメリカ国籍を取って、基本的にアメリカに永住するということになりました。
子どもたちは、はじめは補習授業校に通っていたのですが、途中でドロップアウトしてしまいましたね。
我が家は駐在員家庭だったのですが、特に娘は2歳の時に行っていますから、授業が日本に帰国する子どもたちを前提にしたものだと難しかったですね。
.jpg) 1990年代のニューヨーク
1990年代のニューヨーク綿引 先生のクラスマネジメントは重要ですよね。いまのお話を日本におきかえて考えると、日本に来た外国の子どもたちを包摂的に日本の学校で受け入れられないということになってしまう。
日本から海外に研修で派遣されている先生方には、失敗を恐れずに、いろんなことにトライしてマネジメント力を鍛えていただけたら、と思いますね。
平井 私の周りにも、日本の普通の公立小学校に通っている外国人の方が結構いて、いろんな人種の子どもたちがランドセルを背負って通っていますよ。親御さんが「現地校に入れる」という主義でやっているのでしょうね。
綿引 ラグビーのワールドカップの日本チームのような社会になるといいですよね。多様性の中で暮らしている在外の子どもたちを応援する意味はそこにあるんじゃないかと思っています。
平井 そうですね。あとは 、日本が二重国籍をいまだに認めないというのは結構大きいと思います。きちんと「認める」ということをしないと、「日本人」を選んでくれなくなる可能性もあります。そう考えると、残念なことですよね。親御さんからしてみたら心配ですよ。
綿引 そうですね。子どもも親も「社会から応援してもらっている」という気持ちを持てることが大事だと思います。
我々は2022年に日本人学校と補習授業校に関する法律を議員立法で作ってもらったんですよ。日本の駐在員の子どもだけじゃなく、日本のことを勉強したいという子どもは基本的に受け入れるというふうにしてもらいたいと思っているのですが、なかなか……。
平井 そうですね。これだけ子どもの数が少ないわけですから、1人でも多く、いろんな機会があって、いろんな可能性がある世界を、大人がきちんとつくってあげないといけないですね。
少子化なのに、子どもたちをきちんと扱わないというのは本末転倒ですよ。本当に、この国の将来ですからね。
アメリカでの原体験
.jpg) ニューヨークでの子ども時代。自宅でハロウィン、弟と。
ニューヨークでの子ども時代。自宅でハロウィン、弟と。綿引 平井さんの子ども時代についてお聞きしますが、幼少期、ニューヨークの現地校での学校生活で、特に記憶に残っていることとか、ショックを受けたこととかはありますか?
平井 小学1年だったのですが、当時は、日本人学校はなくて現地校に行くというチョイスしかありませんでした。初日に、両親に現地校のクラスの前まで連れて行かれたんですね。
先生がなにかベラベラしゃべって、ほどなくして母が「じゃあ、一夫、行ってらっしゃい」と、クラスの中に放り込まれたんです。日本国内で転校するのでもプレッシャーじゃないですか?
それが、1967年のニューヨークですからね、急に別世界に放り込まれたというのは、かなり……。いまだに、教室のどこに座ったか憶えています。トラウマだと思うんですが、全部憶えていますよ。
綿引 初日というのは、やっぱりインパクトが大きかったのでしょうね。そこからいかにしてアメリカ人の友だちのなかに溶け込んでいかれたのでしょう。
平井 私たちが住んでいた隣の部屋に、クリスとジェーンという姉弟がいたのですが、シングルペアレントの家庭で、お母さんは毎日、仕事に出ていました。
クリスとジェーンは帰ってきてもやることがないので、家のベランダで遊んでいたんですよ。ベランダは仕切り板みたいなのがあっただけでつながっていたのですが、私もなんとなくベランダにいて、彼らもいて、それでお互いにちょっかいを出し合っていくうちに、言葉はまったくできないのですが、身振り手振りで、コミュニケーションを取るようになりました。
彼らと遊ぶようになってから、英語力、それから文化力っていうのですかね、飛躍的に向上していきました。 彼らがいたおかげで、すごく助かったんですよね。
うちの母親も、ここぞとばかりに彼らを家に呼んで、日本のラーメンとかをつくって食べさせたりしていましたね。いっしょに遊ぶことが、英語が早く上達する策だと思ったのでしょうね。
「うちにおいで」と食べ物で誘って、遊ばせてくれたのが、自然に英語を身につけることにつながったのではないかなと思います。サンクスギビングだとかクリスマスだとか、いろんなイベントがあるじゃないですか。そんな時も、こんなことするんだよとか、その意味を教えてくれたりしていました。
英語がだんだんできるようになると、アメリカ人と同じように正しく話したくなってくる。いっしょにテレビを見て、あのコメディ番組は面白いよねとか。そうなると、英語の上達するスピードが一挙に上がってくる、早いですよね。アメリカ人の子どもたちとしっかりと渡り合えるぐらいコミュニケーションができるところまで吸収できたのは、クリスとジェーンがいてくれたのが大きかったですね。
そこが入り口で、あとはもう本当にうまく滑り込んでいったという感じでしょうか。最初は、何が何だかわからない、そもそも顔つきがみんな違うし、髪の毛はなんでこんな色をしているんだって。そういう時代でしたからね。
綿引 そういう中で、平井さんは友だちができて、そこから友だちの輪がワーッと広がっていきますね。「オレ、アメリカで友だちがいっぱいできたぞ」とか、「オレ、もしかしてニューヨーカーなんじゃない?」みたいな高揚感はありました?
平井 そうですね、ニューヨーカーっていうのはあまりなかったですけど(笑)。でも、いまでも、現地校に行った初日のことは全部憶えていますから、あの状態からしたら、よくぞここまで来たよね、というのはよく感じてはいました。
その頃には英語をきちんと喋っていましたから。普通に誰とでも会話できますし、テレビを見ても、英語のジョークは全部わかるし。それは本当に、クリスとジェーンのおかげだなという振り返りはありましたし、英語でだったら誰とも話せるという自信はありましたね。
綿引 世界中で子どもたちがこのお話を聞いていたとしたら、「平井さんはクリスとジェーンがいてラッキーでしたね。ウチはまわりに誰もいない一軒家なんですケド」とかいう子どももいるかもしれません(笑)。
平井 そうですね。国や地域によっても環境はまったく違うと思うのですが、私の場合、本当によかったなと思うのは日本人コミュニティがなかったことです。いまは、ほとんどのところで日本人コミュニティがあるじゃないですか?
そこに行けば楽ですよね。日本語を喋ったらいいし、話も合うし。2・3年で、親が日本に帰国になるからそれでいいじゃないかと日本人で固まっていたら、それで終わってしまうんですよね。
それがいいか悪いか別として、私の時代にはそれがなかったんです。現地の人たちと交流するチョイス以外はなかったのでよかったかもしれません。ただ、いろんな形で現地に入るチャンスはあるんですよ。
たとえば、夏休みにはサマーキャンプに行くとか、ローカルのコミュニティでも、いろんなアクティビティがあるので、そういうところに積極的に行ってみるとか。親御さんも子どもの背中を押してあげることが大事になってくると思います。
場合によっては、親御さんが同じ会社のローカルスタッフでも友だちでもいいのですが、休日に家族ぐるみで遊ぶきっかけをつくってみるとか。日本人コミュニティにどれだけ入っていくか、いかないかというので、結構違ってくると思いますよね。
綿引 異文化の中で友だちをつくるコツみたいなものでしょうか。 自分で壁をつくって、「日本人以外はダメ」とか「だからオレは英語ができない」とかと自分で壁をつくってしまうと、そのコツはつかめないですよね。
平井 ええ、それはダメですね。日本人だからというわけではなくて、日本に駐在する外国人の中でもまったく同じことが起こっていますよね。
私は帰国してアメリカンスクールに行っていたのでよくわかるのですが、親の仕事でアメリカから日本に来て、アメリカンスクールに入って、アメリカ人といっしょにワーッと盛り上がって、放課後もアメリカ人といっしょに遊ぶという生活を繰り返していたら、日本語を喋る必要はないし、日本の社会と関わる必要もない。
知っている日本人はアメリカンスクールの英語ができる日本人ぐらいで、そのままアメリカに帰っちゃいましたという人もいれば、逆にそれではダメなんだと、ローカルな日本人と交流を持っていたアメリカ人もいました。
どこの国に行っても同じだと思いますが、やっぱりチョイスなんですよね。私からしてみれば、ローカルの方々といろんな形で接することによって、語学も文化も知ることができましたし、いろんな視点を持つことができました。その時は、単なる遊び相手と思っているかもしれないですが、後になって必ずそれは資産になってきますよね。
綿引 それは重要なメッセージですね。「『違う』って面白い」とかね。
平井 自分は賛同しない場合でも、「言っていることはわかる」という理解を示すことができます。そういう視点もあるんだってことを、自分のポケットに入れることができる。そこから、ダイバーシティが生まれてくる。相手を論破したところで何のメリットにもなりません。
子どもの頃、アメリカでいろんなことを見ていて「ちょっと違う」と思いつつ、ここで違うと言っても仕方がないから「まあそうだよね」ぐらいにしておいた方がいいかなということはいろいろありました。
生活様式なんかは全部そうですよ。「君たち、家の中に土足で入るのか?」みたいな(笑)。あれは衝撃ですよ。だから、私はアメリカの家でもちゃんと靴は脱ぎます。アメリカ人の友人宅に行って、「靴のまま入ってきて」と言われても、「どうなんだよ」と思いつつ、なんか躊躇しながら入る、非常に変な感覚です。
あとは、「これは嫌いですよね?」と聞かれた場合、日本では「はい、嫌いです」という「イエス」じゃないですか。でも英語では“No,I don’t.”、ネガティブをネガティブで肯定するんですよね。そういったちょっとした違いというのは結構面白いなと思いますね。ある意味では、ゲームと言ったらおかしいかもしれませんが、そこを使い分ける楽しさ、ツールとして使い分けているぞという満足感はありますね。
綿引 平井さんのお話を伺っていると、子どもながらに「相手のことを受け入れる」ということができているのを感じるのですが。
.JPG)
平井 それは、自分がそうされたからというのもあるのかもしれませんが、一部の子どもたちから「ジャップ」とか、さまざまな嫌がらせの言葉を言われることがあったんですね。
そういうのは英語ができなくてもわかりますから、「なんで、そんなことを言われなきゃいけないんだ」と思いつつ、言い返しても意味がないから、受けていたんですよ。受け入れつつ、「なんか違うぞ」って思いながら過ごすことはありましたね。
綿引 ともに過ごすなかで、友だち同士でシンパシーが生まれる瞬間、「オレたち本当の友だちになったぞ」みたいな経験はありましたか?
平井 クリスマスとかに招いてもらって、いっしょに「セレブレーション!」と言い合って、プレゼントをあげたりくれたりとか。あとは、クリスとジェーンのお母さんがウチに来て、食事に誘ってくれたり。
そうやって、家族ぐるみの付き合いができたというのはすごく大きかったかなと思います。本当に仲間に入れてくれたんだというか、嬉しかったですね。
次のページ:コミュニケーションの価値
コミュニケーションの価値
.jpg) ニューヨークでの子ども時代、友だちと。後列中央が平井さん。
ニューヨークでの子ども時代、友だちと。後列中央が平井さん。綿引 欧米は個人主義の文化だとよく言われますが、家族やコミュニティを大切にする文化もあって日本人的には共感しますね。平井さんはいろんな強みをお持ちだと思うのですが、子どもの頃に自分の強みを感じられたのは、いつ頃でしょう?
平井 友だちは、私が日本人だということを知っていますから「日本のことを教えて」と言われることがありました。それなりに日本について説明する機会があったりすると、「これって私にしかできないことなんじゃないか」と。
日本はこうなんだよとか、家は全部が紙でできてはいないんだよとか、靴は脱いで上がってくださいよとか。 日本のことを説明できるし、聞いてもらえたというところで、付加価値を感じたというか、「求められている」という嬉しさはありました。
綿引 逆に、日本人が日本に入ってきている外国の子どもたちに接する時も、そういう姿勢はすごく大事ですよね。友情とか、友だちづくりとかは、興味を持つところから動き出す。興味を持たないで、閉じこもってしまったら何も生まれない。「違いこそが価値」なんだ、と。
平井 そうですね。いかにコミュニケーションを取るかということだと思います。子どもにこういったものを求めてはいけないのかもしれませんが、結局、現実として、海外に置かれた自分というものが、そこにあるわけですよ。
じゃあ、この機会を、どういうふうに使うのか、使わないのか。使うとすれば、何が大事で、何が大事じゃないのか。そういうことをよく考えて、どうするのかを決めることが大切だと思います。
よく考えて「私はどう考えても日本人といっしょに集まって、日本語だけを喋って日本に帰るのがいちばんいい」と思うのだったら、それでいい。でも、本当によく考えてそれをやってくださいね、と。
「友だちをつくりたい」と思ったら、行動すべきです。成り行きでそうなってしまったとか、日本人はこうだから、とかというのでは残念でならない。せっかく海外に行ったのですから。
綿引 仮に、親から「ここは危ないから、外出してはいけない」と言われたとしても、自分の興味とか関心事は、最善の注意を払いながらやった方がいいと思いますね。
平井 親は子どもからリクエストされた時、全部を否定するのではなく、一歩踏み出して「子どものため」ということを考えないといけないと思いますよね。
コンプレックスの価値
.png) 高校時代を過ごしたアメリカン・スクール・イン・ジャパンの卒業アルバム
高校時代を過ごしたアメリカン・スクール・イン・ジャパンの卒業アルバム綿引 異文化の中に入ると、コンプレックスを感じる機会があると思いますが、「コンプレックスを持つ意味」とは、どのように思われますか?
平井 どちらかというと、コンプレックスを感じたのはアメリカにいた時より、小4で日本に帰ってきた時ですね。今度は、日本の社会に適応しなければいけないという中で、明らかに、ずっと日本で育ってきた小学4年生からは遅れを取っている。
あらゆる面でコンプレックスがありましたし、1971年当時、日本の小学校で帰国子女は私一人なんですよね。私がアメリカ帰りだってことは、まわりに広がっていて、「ちょっと、平井、来いよ。馬鹿って英語でなんて言うんだよ」みたいな。
要するに、仲間じゃなくてアメリカ人扱いなんですよ。母国に帰ってきたのに、仲間に入れてもらえない部外者扱い。勉強も、補習授業校に行っていただけなので、漢字の読み書きとか、算数とかがちょっと遅れを取っていたので、どうしたものかなあと。「なんで、日本に帰ってきたんだろう」と感じていました。
綿引 そういう気持ちは、いま海外にいる子どもたちや帰ってきた子どもたちの多くが感じていると思いますね。
平井 当時は、いまとは違うとは思いますが、ダイバーシティとか、いろいろな考え方があるということを、先生もあまり受け入れてない時代でしたね。質問したり、違うことを言ったりすると、怒られたりしていました。
帰国当初、1年だけ、ある私立の学校に編入したんです。英語の授業があったのですが、先生は私をさしてくれないんですよ。あからさまに排除されているというか、でも逆に、コンプレックスを感じながらも「こういうのって、面白いよね」と(笑)。
私は結構、能天気な方で、そういうふうに考えるようにしていたので「学校に行きたくない」とかはまったくなかったかな。性格的に「しょうがないなあ」と思えたのが、よかったのかもしれないですね。
綿引 すごく大事なメッセージですね。 コンプレックスは、自分のなかで、それをどう解釈するか。それによって全然、道が違ってきます。
平井 「プロジェクト希望」ではいろいろなセミナーをやっているのですが、挫折とか悩みは大きなテーマとしてあります。話をしていると、「なんで、私だけがこんなに悩まないといけないんだろう」というのがよくあるのですが、ちょっと待ってください、と。
生徒が50人いたとすれば、49人が楽しそうな顔をしているかもしれません。でも実際にはほかの人たちだってそれぞれ悩むことはあるし、いま皆さんに話をしている平井も、この部屋にいる大人たちも、ニコニコしているけれどみんな悩みやコンプレックスを持っているんですよ、と。
だからこそ、自分がおかしいとかじゃなくて、みんな同じように悩みながら生きているという感覚が大事だということをよく話しています。
あとは、そのコンプレックスを感じた時にどのようなマインドセットをするか。どうしたら、「別にいいじゃない」と思えるように持っていけるか、いくつもアイデアや引き出しを持っていましょう、と。
挫折したり、コンプレックスを感じたりした時に、すぐに「別にいいじゃない」と思える人もいれば、「2日間は塞ぎ込んで、3日目には大丈夫です!」という人もいる。避けることはできないので「どうやって乗り越えるか」です。
どう対処するかは、場数を踏まないと出てこない。だからこそ、ネガティブなことが起きた時は、「よい勉強の場」としてそれを捉えられれば、結構、ハッピーになれますよという話をしていますね。
綿引 素晴らしいメッセージになりますね。 コンプレックス自体が自分を広げる可能性の場にもなるということですよね。
次のページ:リーダーに必要なもの
リーダーに必要なもの
.jpg) 2017年、オーストラリアでのタウンホールミーティング
2017年、オーストラリアでのタウンホールミーティング綿引 平井さんには「自分が置かれている環境を受け入れる」勇気があるのを感じます。
平井 いくら悩んでも悲しんでも、現実は変わらないわけですから、それはあるものとして、どう対処するかと考えた方がいいですよ。マネジメントと同じで、リーダーはマイナスなことが起きた時にいかにプラスに持っていくかということが求められていて、社員はそれを見ているわけです。
そういうネガティブなことが起こった時こそ、強いリーダーシップを発揮するチャンスなんですよね。「塞ぎ込んでいる場合じゃないですよ」と、よく話をしています。
子どもたちにはちょっと当てはまらないかもしれないのですが、マネジメントでよく言ったのは、一番よくないのは「決め」を出さないこと、ということでしょうか。一番いいのは正しい判断ができることですが、間違った判断をしても、間違ったとわかったら、そこで軌道修正すればいいんですよね。
判断しないと、みんなが宙ぶらりんの状態になってしまうので。「早い決断」と「起動修正」がペアになっていれば、うまく回ります。1回決めたので、間違いだとわかっても絶対変えないというのはダメです(笑)。 軌道修正するという柔軟性が必要です。
綿引 会社に入ると、いろんなスタッフとかチームのメンバーがたくさんいるわけですから、子どもの時にいろんな友だちがいた方がいい。ちょっと変な言い方ですが、子どもの頃から、意思決定する時にどういう友だちが周りにいるかというのはいい経験になります。
会社に入った後、どういうメンバーが自分の周りにいるのかという環境は、すごく大事ですよね。それを「つくっていく」という努力も必要だと思います。
平井 子どもの時は、気が合う仲間で盛り上がるくらいのレベルだったと思うのですが、会社では、友だちづくりではなくマネジメントづくりなので、イエスマンではなく、違う視点で「異見」を言ってくれる人を重宝しました。
「ノー、もしくは違うって言ってくれるから、そこにバリューがあるんだ。異なる視点をちゃんと提示してほしい」と、いつも言っていましたね。
綿引 平井さんが、本当にそういう視点を持たれているので「ノー」と言えるのでしょうね。違う考えを持った人たちが、平井さんの周りに集まってくるみたいな。
平井 発言の安全性が担保されていなければ、だれも言ってくれないですよね。だからこそ、出てきた良い意見はどんどん採用します。
そして大事なのは、採用した後にうまくいったら「〇〇さんの提案でした」と、取締役会できちんと説明すること。一方で、うまくいかなかったら「選んだ私が責任を取ります」と。
そこまでやって初めて、いろんな意見が出てきます。心理的安全性が守られ手柄はくれる、きちんと責任を取ってくれるリーダーだからこそ、うまくいきます。
綿引 なるほど。そういう人が集まって来れば来るほど、正しい意思決定、新しい意思決定をするチョイスが出てくるのですね。同質の社会はすごく居心地がいいけれど、違う。 いろんな考え方の人の中にいる方が面白いですよね。
平井 ええ。面白いし、「そういう見方があるわけ?」と刺激があります。特に、ソニーの場合は、映画もやっていれば、金融もエレキもといろんなことをやっているわけです。
私はゲームと音楽を専門でやってきたので、全部を知っているわけではないですから、きちんと議論のできるマネジメントチームがいてくれないと、全部を一人では決められません。彼らの専門的な見解に頼らざるをえないし、「そういった意見を尊重する」というのはしないといけませんね。
綿引 子どもたちに対するリーダー像としての心強いメッセージですね。日本人のいいところなのか、悪いところなのか、我々には相手が言ってほしくないことは口に出さない方がいいというようなところがありますよね。
失敗をできるだけしないように安全な道を行くとか、人様並にやるとか。でも、それでは企業はなかなか成長しないし、新しいものも生まれない。新しい友人もできないですよね。
.jpg)
平井 失敗は避けられません。避けるのではなく、どうやってリカバリーするか、そのためには失敗を重ねることが大切なんですね。
これはある大先輩に言われたことなのですが、「日本はトーナメント制、1回負けたらおしまいだ」と。
たとえば、サラリーマンで支店長までいったけれど、融資で失敗したらそこでおしまいとかですね。スタートアップを1回やって、潰してしまったらもうお金を貸してもらえないとか。そんなことでは「イノベーションを起こそう」というリスクをだれも取らなくなってしまう。
「リーグ戦」でないとダメなんですよ。失敗の中に学習があって、それを次に生かせるかどうかというのが大事だし、そういう環境をつくってあげるのが大人とかリーダーのやるべきことですよね。
アメリカではスタートアップでことごとく失敗しても、勉強して、新しいアイデアを出してくれば、審査して、よければまた投資してくれます。社会全般で、敗者復活ができるということは大切ですよね。
そういう環境をつくるために、私がよく例として出すのが、皆が頑張って素晴らしいアイデアだと思って、私もいいと思った商品が売れなかった場合です。一生懸命に考えて、マーケティングして、商品化までこぎつけたという努力と、そのイノベーティブなアイデアは決して無駄ではない。
打ち上げをして「プロセスまでは最高だった。ここまでよくやった」と労をねぎらいましたね。すると「よし、次また考えよう」となります。そして、周りはその様子を見ていますから、「失敗したわりには、なんか盛り上がっている。じゃあ、自分もアイデアを出してみようか」となるのです。そういった環境をつくっていかないとダメですよね。
ありとあらゆる場面で、リーダーは部下のモチベーションを上げるのが大事です。なにを言うか、言わないのか。行動するか、しないのか。それは、まさしく海外で、お子さんたちのモチベーションをどう上げるかにつながります。
親御さんや学校の先生も含めて、まわりの大人がどのようにして子どものモチベーションを上げていくか。子どもたちはつねに見ていますし、聞いていますし、大人の行動もしっかりチェックします。高い基準というか、ハイスタンダードに自分を置かないといけないですね。
綿引 たとえば、親御さんが、現地のことを子どもの目の前で悪く言ったら、子どもはその国を楽しもうという気持ちにならない。親として、せっかくここにいるのだから、楽しんで生活しようよと、子どものモチベーションを上げていくのは大事ですよね。
平井 親御さんの言動がポジティブなロールモデルにならないといけないですよね。
綿引 平井さんはこれまで、いろんな状況で、いろんなチームで働いてこられたと思いますが、チームの人たちといっしょに働く意味は、何なのでしょう。
平井 いちばんの意味は、一つのミッションなりビジョン、もしくは目標というのを共通認識として持って、共通の目的を互いにシェアし、理解し、「自分たちは何をするのか」を考え、同じ方向に向かっていく場をつくるということでしょうか。よしなに「よろしく」ではなく、「ミッション・ビジョン・バリュー」をきちんと説明して、腹落ちしてもらうことが大切です。
次のページ:「あなたは、あなたの人生の最高経営責任者(CEO)」
「あなたは、あなたの人生の最高経営責任者(CEO)」
綿引 平井さんは、「感動体験が子どもの希望となり、原動力になる」という理念のもと「プロジェクト希望」を立ち上げられていますが、「プロジェクト希望」でやっていらっしゃることや、海外にいる子どもたちの体験に通じるものがあれば、ぜひメッセージをお願いします。
平井 いろんな「感動体験」を子どもたちに提供しようと、体験活動や体験の格差に取り組んでいる NPOさんとコラボレーションして、互いにいろんなアイデアを出し合って活動しています。
さまざまなアクティビティに子どもたちを連れていくというのをやっていますが、今年度は初の試みで、英語を頑張って勉強しているのに海外に行くことが難しい6名の子どもたちに、オーストラリアで11日間ほど海外体験をしてもらいます。異なる文化や価値観に触れることで生み出される「自分の軸」のようなものを感じてもらえれば、と思います。
私も小1でアメリカに行ってから旅行やスポーツ観戦などいろんな経験をさせてもらいました。ある程度社会に貢献できるようになったいま振り返ると、子どもの頃のそうした体験はすごく大事だと感じます。だからこそ、体験する機会になかなか恵まれない子どもたちはスタートラインに立った時に非常に不利になるな、と。
この少子化で9人に1人が相対的貧困にも苦しんでいる現実もあります。その中から将来、企業、もしくは日本のリーダーが出てくるかもしれないと思うと、「経済的に困窮していたので花開きませんでした」というのでは日本にとって大きな損失だと思っています。将来、「あの時こんな体験をしたから、いまこんな仕事をしています」と言ってくれる子どもを一人でも多く増やせればいいと思います。
 Ginza Sony Parkで最新のテクノロジーと音楽を体験
Ginza Sony Parkで最新のテクノロジーと音楽を体験.jpg) 女子高校生対象のSTEAMプログラム IFUTOでの講義風景
女子高校生対象のSTEAMプログラム IFUTOでの講義風景綿引 いいですね。私どもの財団は海外側から、逆に日本に来てもらったらどうかと思っています。永住の子どもでも日系人の子どもでも、飛び出せジャパンをもじって「飛び込めジャパン」。平井さんがされている取り組みとなにかクロスできるといいですね。
最後に、私どもは、海外にいる子どもたちに対して「未来のコモンセンスを作るのは君たちだ」と思っています。彼らに向けて「グローバル社会で生きていくというのはどういうことなのか」、ぜひ、メッセージをお願いします。
平井 海外にいるということは、日本国内で勉強してきた子どもたちよりアドバンテージがあるわけです。そういった環境に置かれているわけですから、それを利用して、現地のことを勉強したり、言葉や文化を吸収したりするということを考えてほしい。そういったチャンスが巡ってきているということを認識しましょう。
テイクアドバンテージをするのは大事です。自分の人生の「ミッション・ビジョン・バリュー」を考えてください。流れに任せるのではなく、自分のことは自分で考えることが大事です。周りから反論されても、言い返す勇気をもってください。
そうしないと、ある程度の年齢になってから、「自分はこんなことをやろうと思っていたわけじゃない」と他人のせいにしてしまうんですよね。親に言われたとか、誰々に反対されたからこんなことになってしまった、と。そうなったら、本当にもう取り返しがつかない。そうならないためにも「自分で考えて、自分で決める」。
毎日考えて、毎日変わってもいいんですよ、医者になろうと思っていたけれど、消防士になる、でもいい。ただ、よく考えてください、自分の人生なのですから。
あなたは、あなたの人生の最高経営責任者(CEO)です。
綿引 本日は、素晴らしいメッセージをたくさんいただきました。有難うございました。
.jpg)

綿引 宏行(わたびき ひろゆき)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)