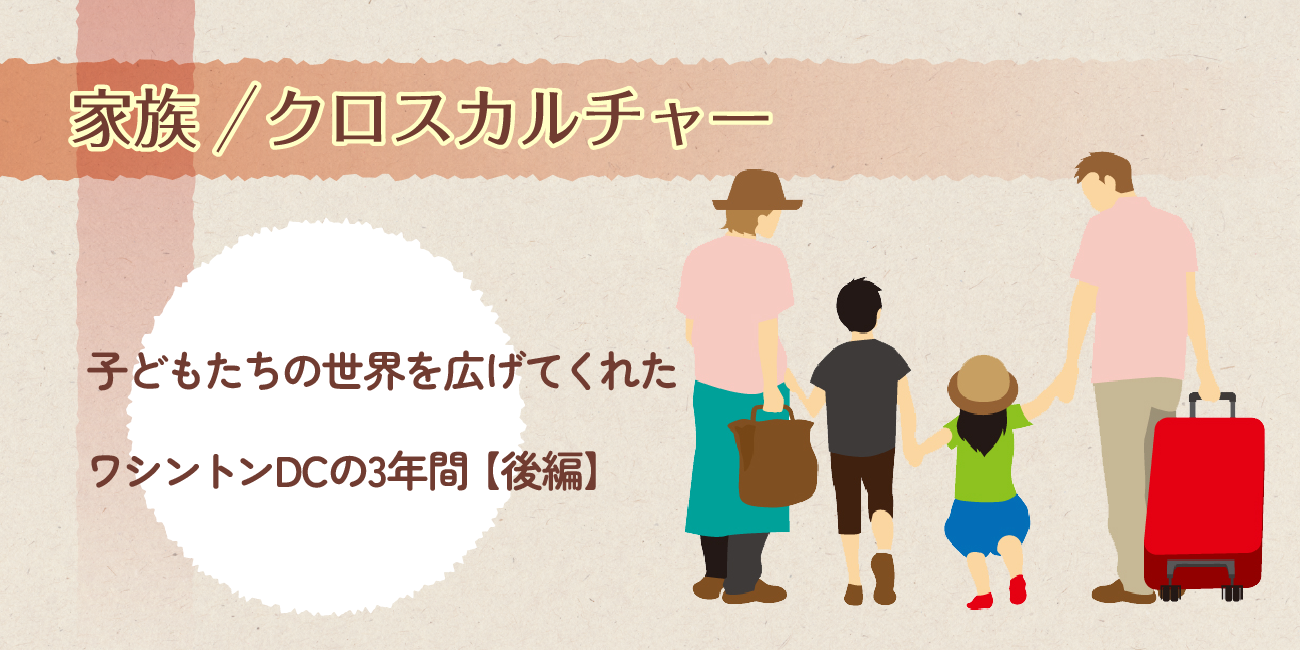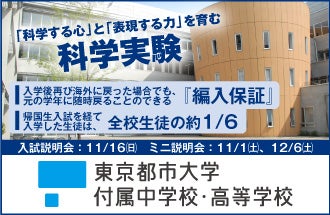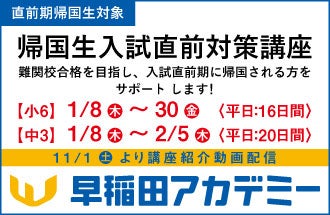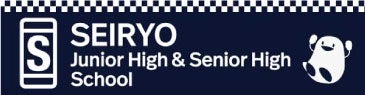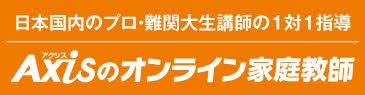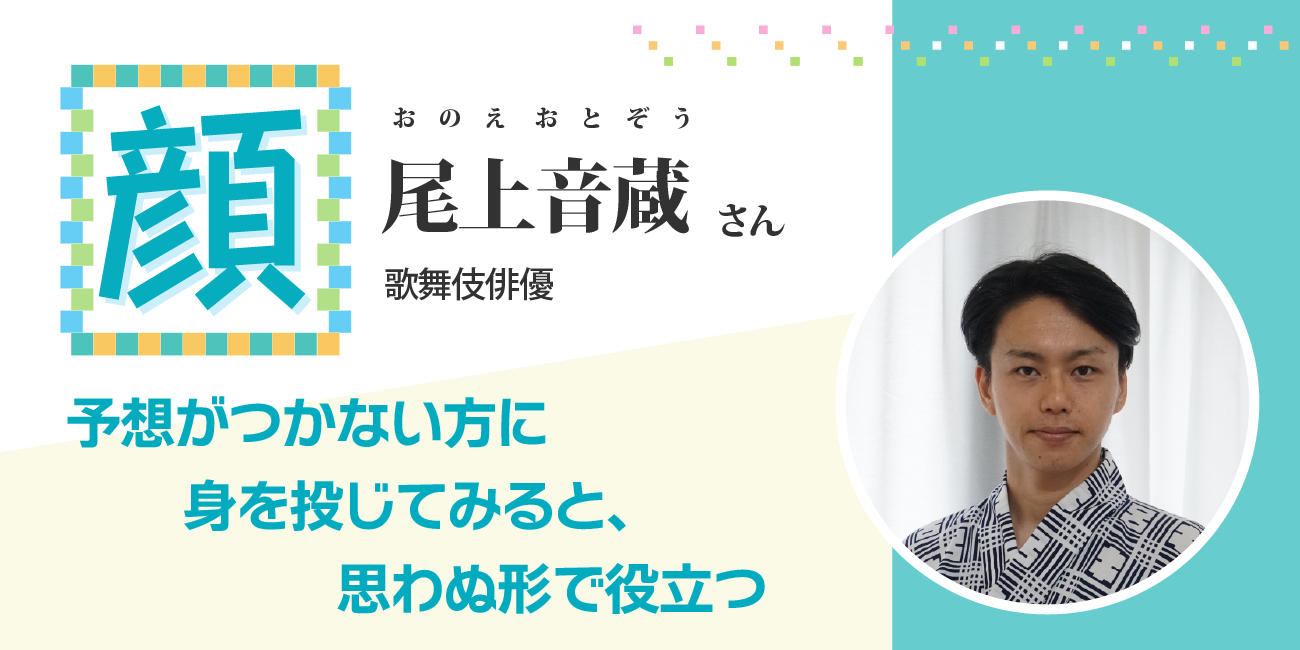
予想がつかない方に身を投じてみると、思わぬ形で役立つ 歌舞伎俳優 尾上音蔵さん
7代目尾上菊五郎に入門し一般家庭から歌舞伎俳優となった尾上音蔵(おのえおとぞう)さん。彼のルーツは、生後半年から5歳まで暮らしていた南アフリカ共和国・ヨハネスブルグにあった。一見つながりを感じさせない南アフリカでの日々が、歌舞伎俳優として音蔵さんの今に意外な部分でつながっていると話す。これまでの海外経験や言語習得によって培われた力について話を聞いた。

挑戦! にほごんの日本語検定【敬語編】
文部科学省後援事業「日本語検定」は、日本語を使うすべての方のための検定です。敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記・漢字の6領域と総合問題で、日本語力を幅広く測ります。小学生から社会人まで、幅広い年齢、職業の方が受検しています。
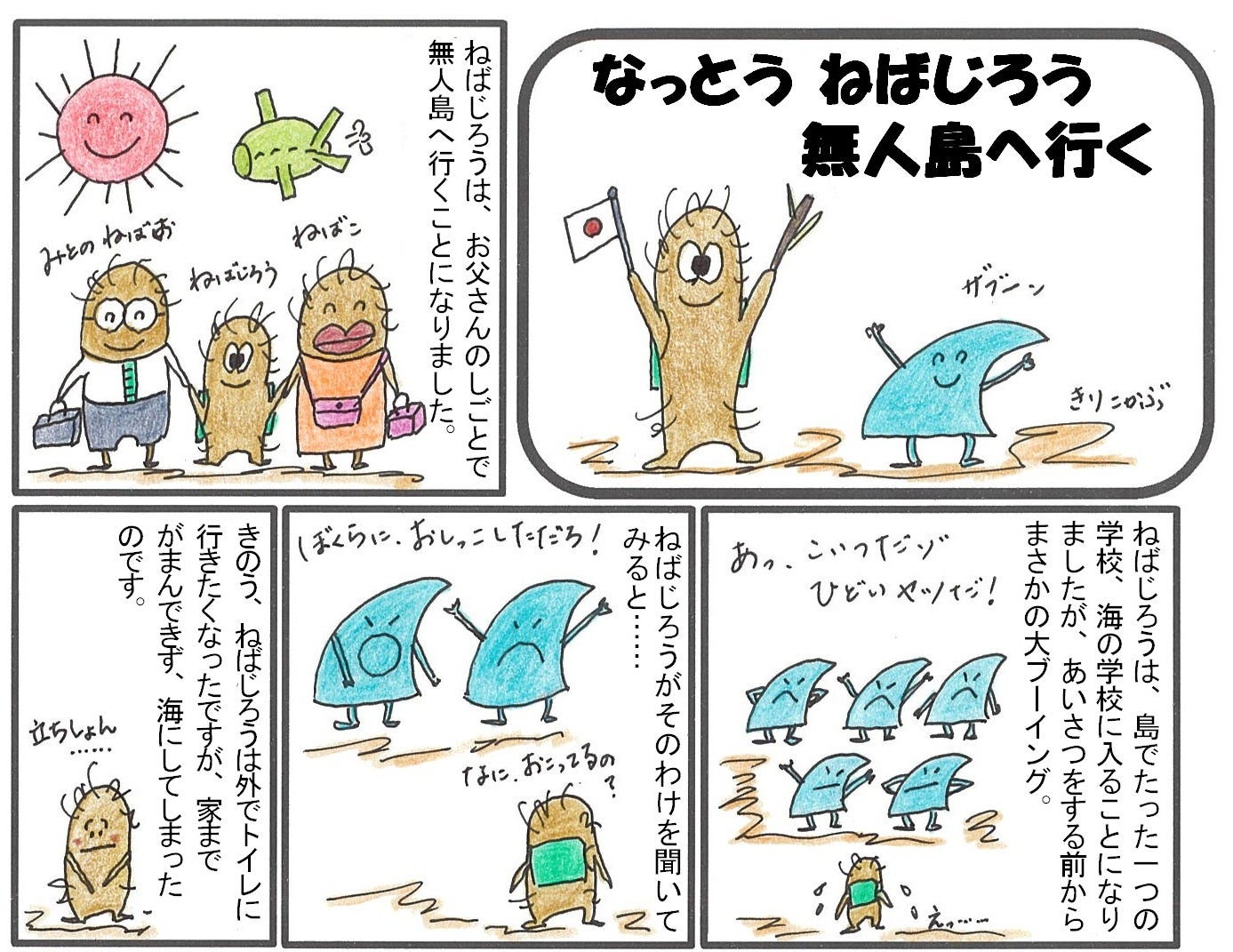
なっとう ねばじろう 無人島へ行く
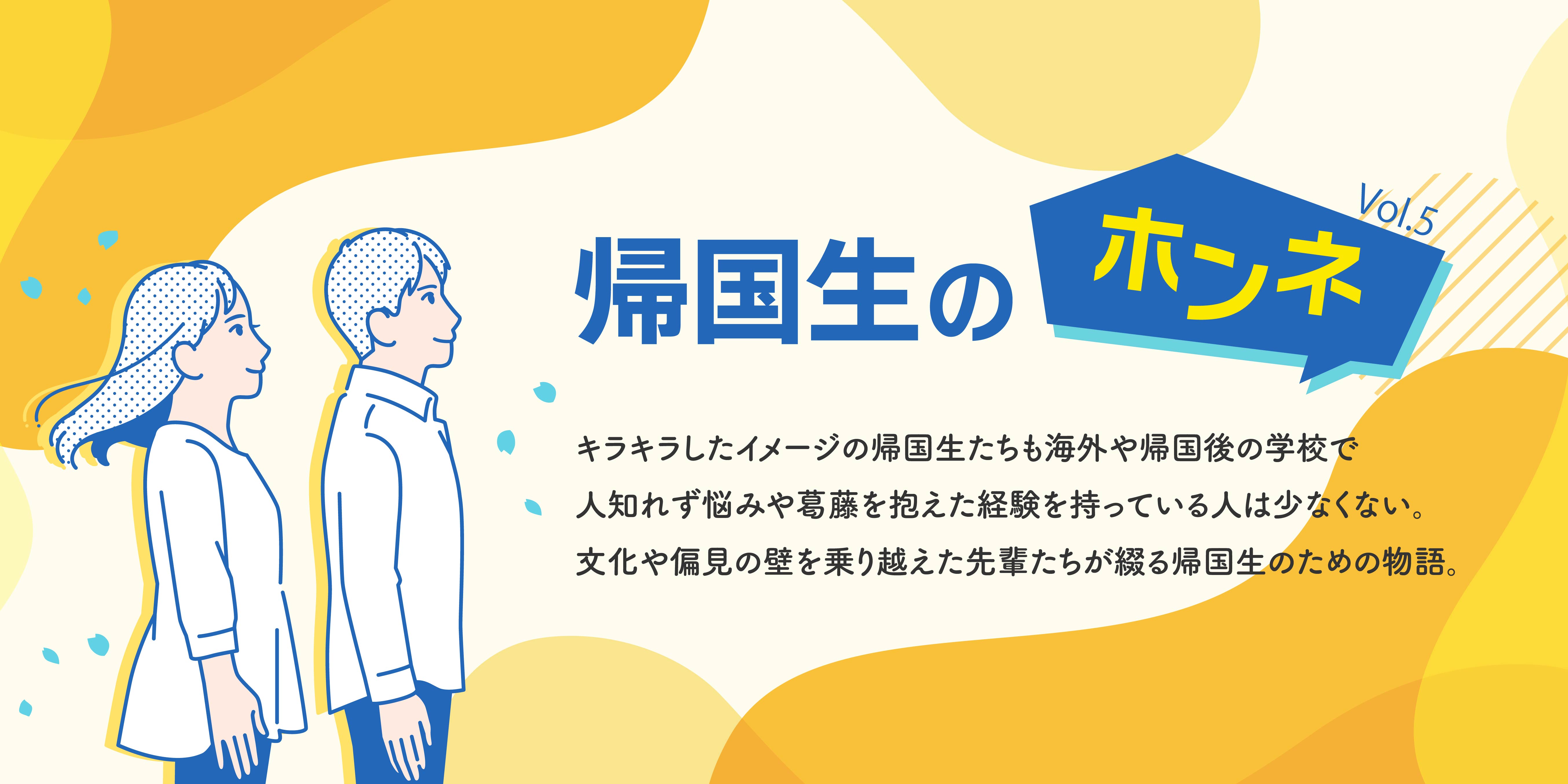
帰国後も自分らしく歩んでいくことが必ず誰かの力になる!
アメリカ・イリノイ州シカゴ近郊で生まれ育った川勝慶成さんは、小学校3年生のとき、初めて日本に帰国し、公立小学校に通い始めた。しかし、スピードの速い日本語や「みんな同じ」を強制されるような雰囲気により、次第に劣等感を感じるようになる。学校で目立つことを避けるようになってしまった小・中学校時代を経て、川勝さんは高校時代にやっと自分の居場所を見つける。それは、困難を抱える若者を支援する活動。アメリカで多様性の中で暮らし、帰国後は勉強が苦手で疎外感を味わった経験が、困っている人に寄り添う活動と共鳴した。

キング・オーガストさん「日本の学校をずっと続けたい」
父親の仕事で日本に来たアメリカ人のオーガストさん。日本の幼稚園と小学校に通い、転居先でのグアムでもグアム日本人学校に通った。現在は神奈川県の私立中学に通う彼女に、日本の学校の「魅力」について話を聞いた。
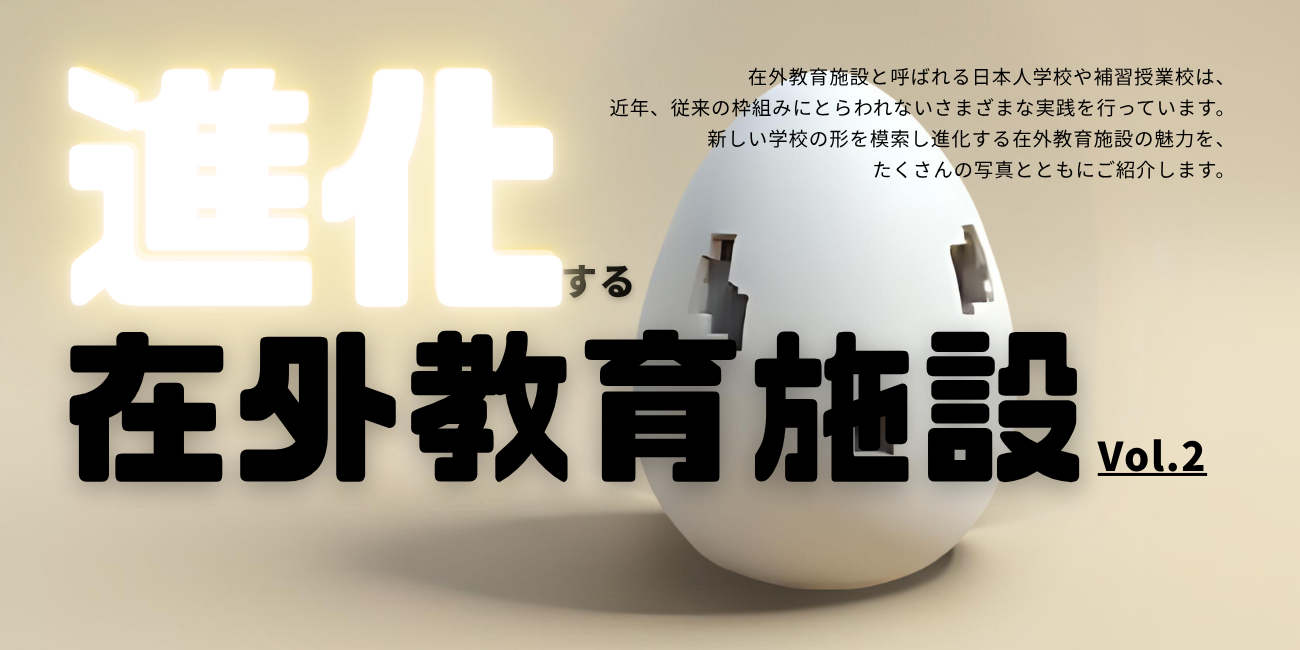
日本人学校幼稚部に宮城教育大学の学生がやってきた! ~グアムにおける海洋教育に関する実証研究(宮城教育大学)~
「進化する在外教育施設」シリーズ第2弾
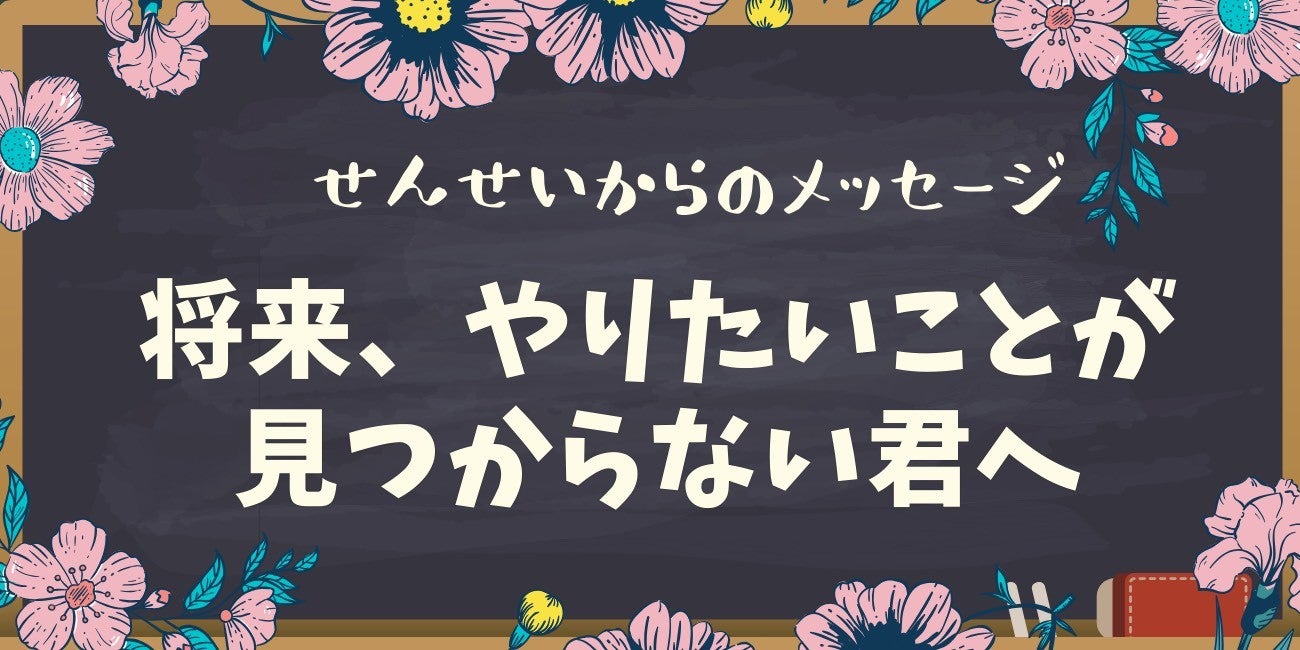
将来、やりたいことが見つからない君へ
悩んでいる子どもたちへ、先生がメッセージを届けます。

攻玉社中学校・高等学校 ―国際学級レポート―
さまざまなバックグラウンドを持つ生徒に向けて、個性を伸ばしながら確かな学力を育む授業を展開している攻玉社の「国際学級」を紹介。
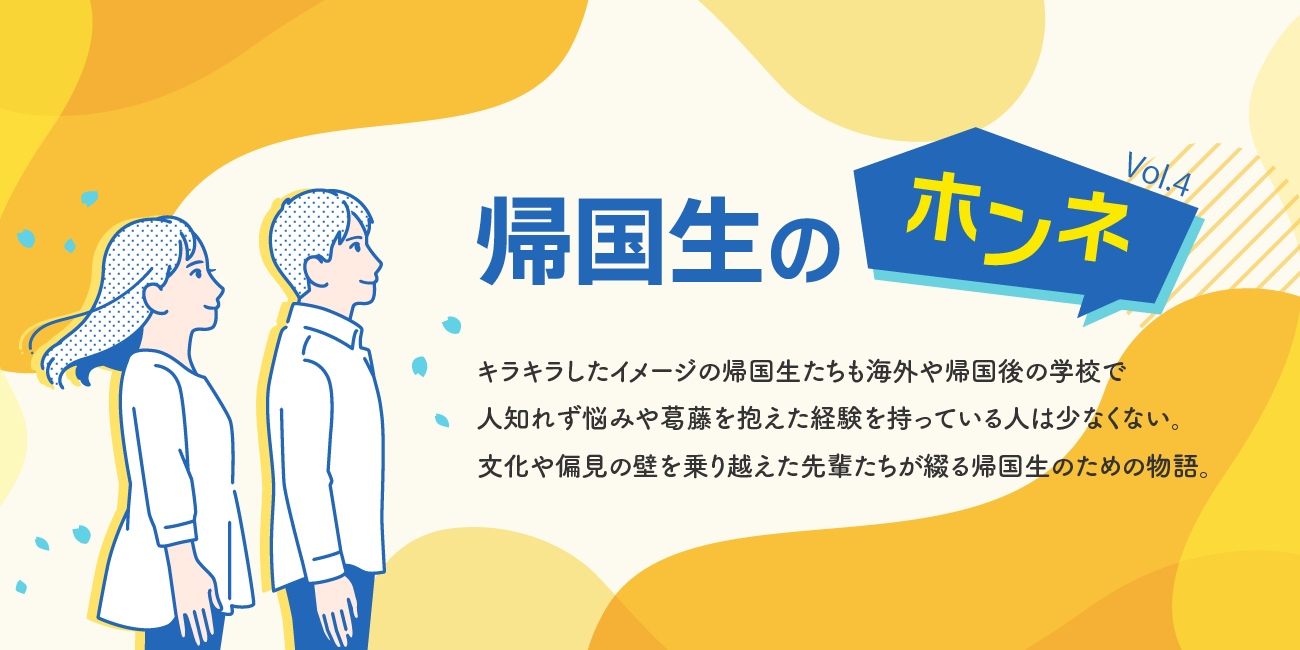
“違和感”の先で掴んだ「世界のどこでも働ける自分」
現在、外資系企業で働く下村友里さんは、幼少期からシンガポール、マレーシア、台湾で計7年間学んだ経験を持つ。社会人になってから自ら貯めた資金でMBA留学も経験し、ヨーロッパで学んだ経験もここに加わった。「世界のどこででも働ける自分でありたい」と語る下村さん。しかし、海外生活はいつも順風満帆だったわけではない。ときにカルチャーギャップに困惑しながら、手探りでキャリアを切り拓いてきた。下村さんが歩んだ道のりを振り返っていこう。

ピュイ・ド・ドーム日本語補習授業校校歌
各校自慢の校歌を紹介してもらいました。今回紹介するのは、フランスにあるピュイ・ド・ドーム日本語補習授業校校歌です。
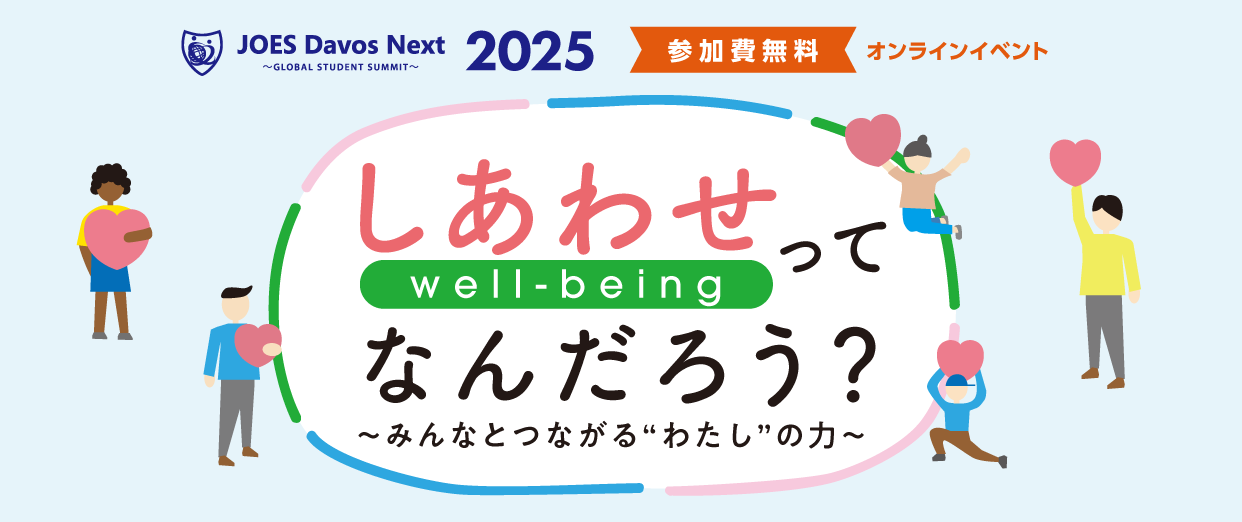
基調講演講師 馬奈木俊介先生インタビュー
8月からいよいよ参加者受付を開始したJOES Davos Next 2025。申込者からは、「待ってました」「今年も楽しみ」という声が届きはじめています。 今回のテーマは「ウェルビーイング」。ちょっと抽象度の高いこのテーマについて基調講演でお話しくださるのは、九州大学主幹教授 都市研究センター長の馬奈木俊介先生です。「しあわせ」や「持続可能な社会」について考える国連委員をつとめるなど、「しあわせとはなにか?」について、社会に広く語りかけていらっしゃいます。 世界中を飛び回ってご活躍中の馬奈木先生ですが、実は24歳で留学するまでは、ほぼ地元・福岡を出たことがなかったとか。そして英語が苦手だったとか……そんなプライベートも交えて、気さくな口調でインタビューにお答えいただきました。

プラムのタルト
アメリカ駐在中の料理研究家柏木京子さんの料理コラム