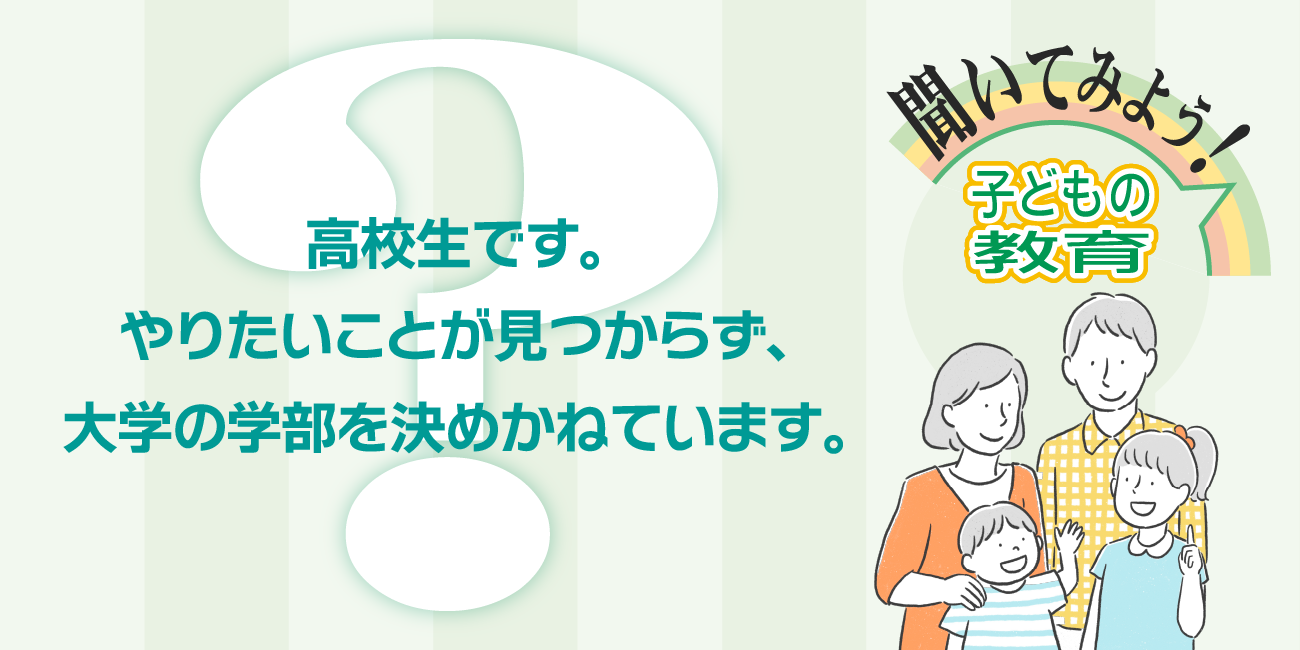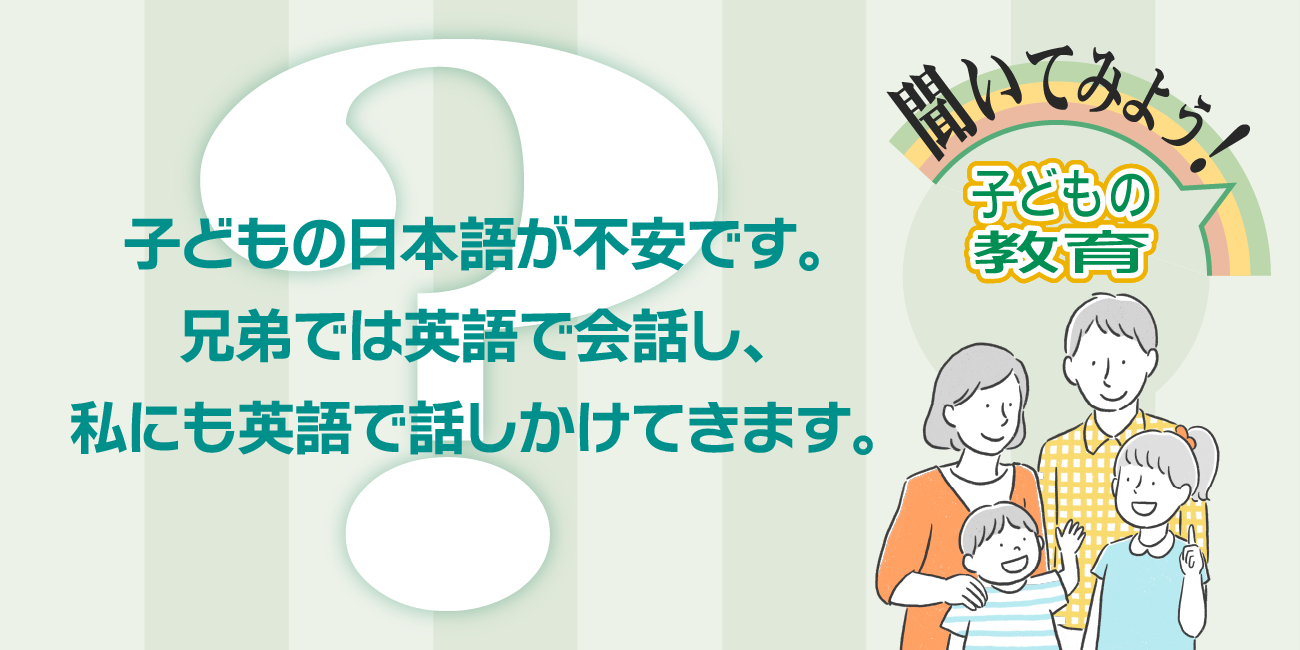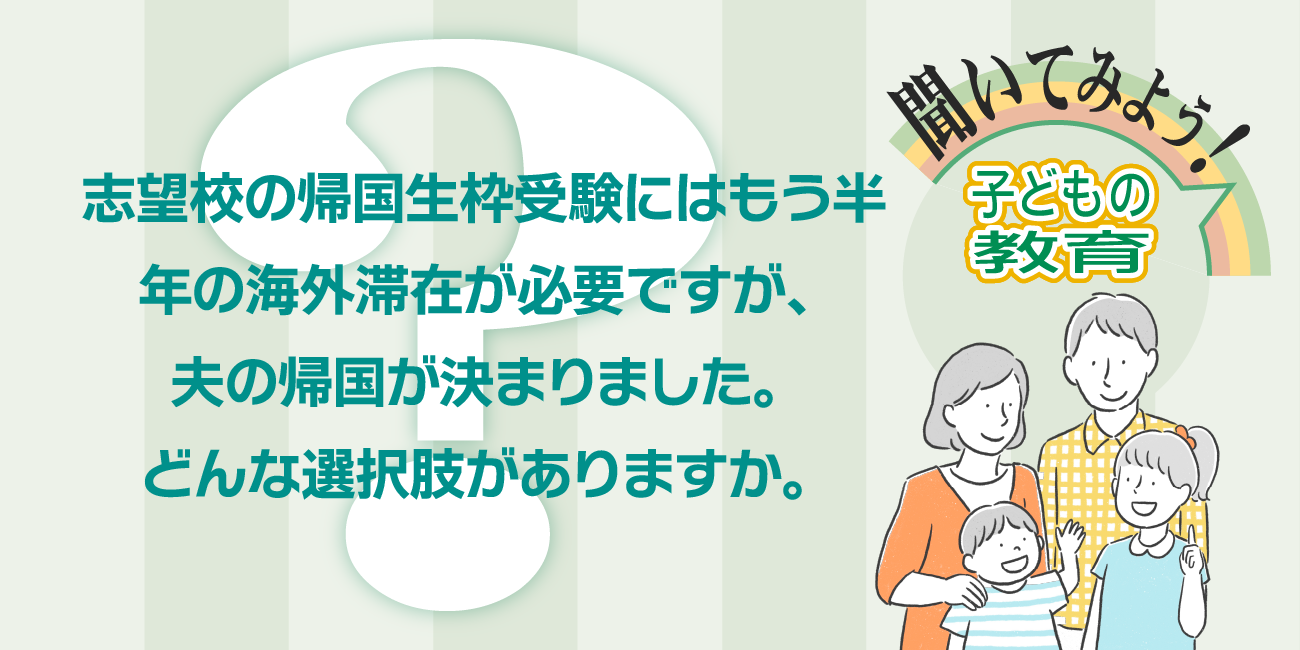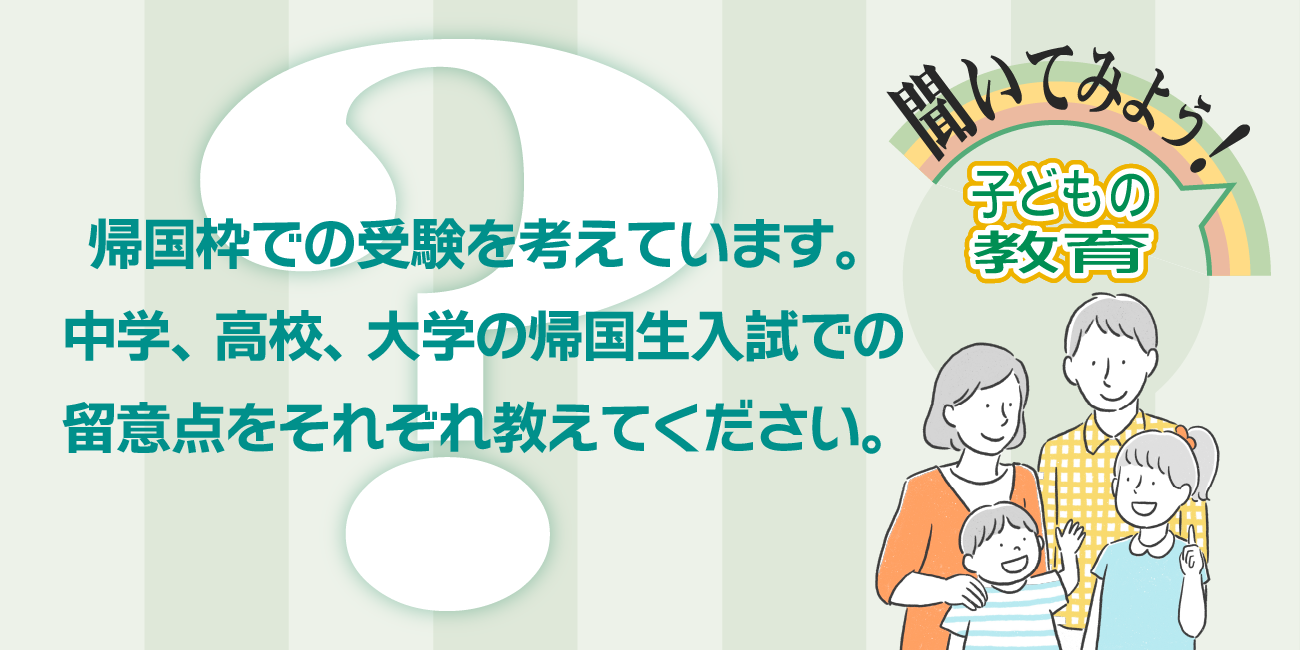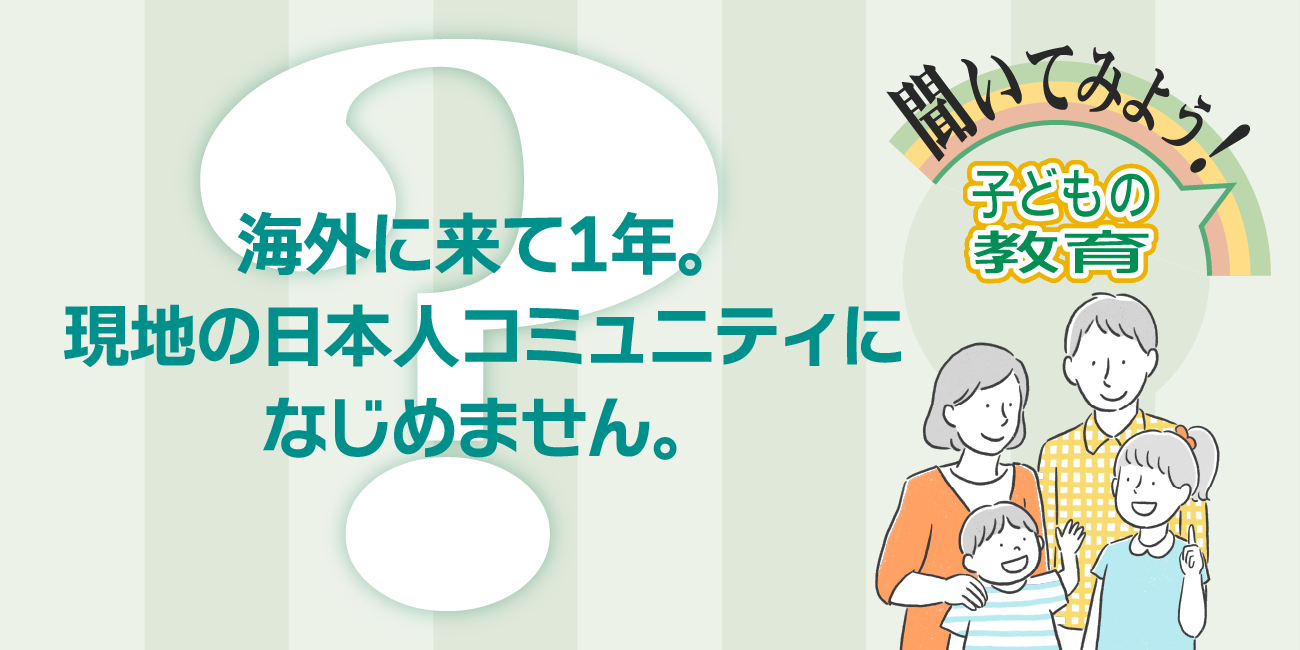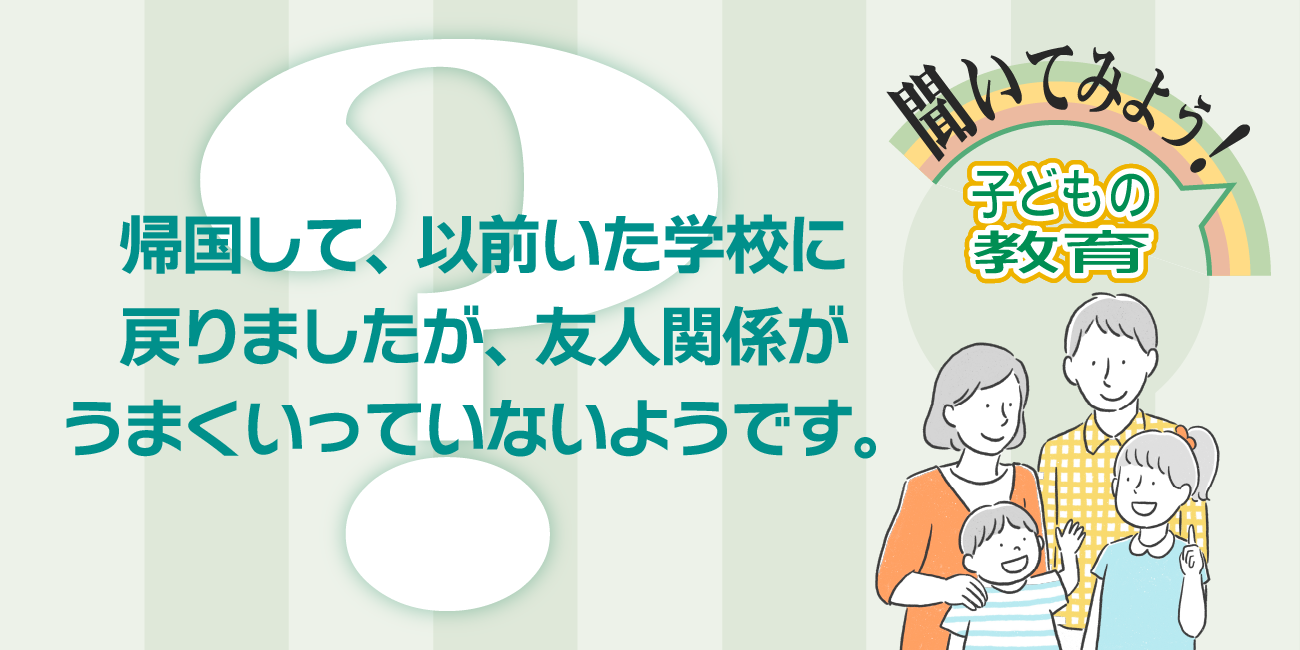<質問> 子どもは発達障害です。海外赴任に連れていっても大丈夫でしょうか。
家庭の雰囲気
「明るい家庭、笑顔の絶えない家庭、温かい雰囲気の家庭、家族全員が助け合う家庭、子どもの適性を見付け可能性を伸ばそうとする家庭」こういった家庭であれば日本国内はもちろんのこと、海外でも適応能力が高く、物事を前向きに捉えることができると考えます。
発達障害についての理解も深く、日頃から適切な対応がなされていることと思います。
私たち大人は、子どもの障害を受け入れるだけではなく、それ以上に「子どもの特性」を受け入れ、家族が同じ意識をもって子どもに向き合っていくことが大切です。子どもの特性に合った適切な対応ができるようになれば子どもも家族も心が満たされた生活ができるようになるでしょう。
最大の理解者である保護者のかたの前向きな気持ちがあれば、海外であっても充実した生活を送れるはずです。焦らずに歩みましょう。
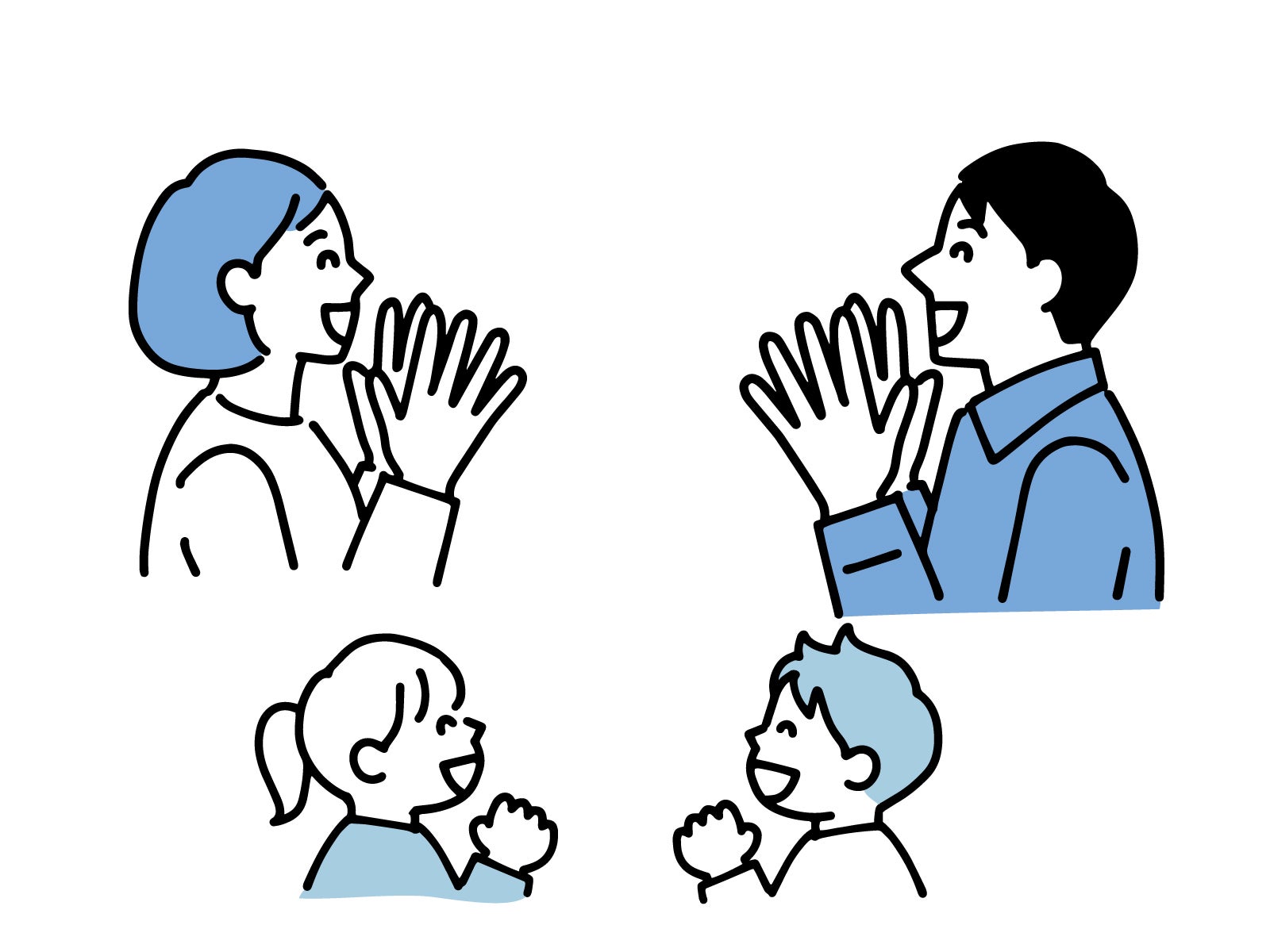
情報収集
誰でも地図や財布、携帯電話を持たずに、言葉の通じない外国で迷子になったらとても不安になることでしょう。発達障害の特性がある子どもは、毎日がこのような大きな不安の中にあるといっても過言ではありません。それは、保護者の方も同じでしょう。子どもばかりでなく保護者の方も安心できるよう、海外での生活について、できるだけ多くの確かな情報をもつように心がけましょう。
障害のある子どもを海外に帯同する場合、現在、日本国内で受けている支援の一部或いは全部が受けられなくなる可能性があります。そのため、現地の情報をできるだけ多く収集し、教育や医療・福祉がどのような状況なのかを細かく把握することが大切です。この現状把握が帯同できるかどうかの判断材料になります。
加えて障害のある子どもは、環境の変化に敏感で、情緒不安定となって現れることもありますので、この点も考慮する必要があります。

設置団体別に見た特別支援教育
~日本人学校、現地校、インターナショナルスクールの場合~
日本人学校の場合
日本人学校は私立の学校ですので、その運営は現地の運営委員会や理事会が担っています。特別支援学級や通級指導学級を設置すること、或いは特別支援教育支援員を配置することは、各日本人学校の判断に委ねられています。ですから、A日本人学校には特別支援学級が設置されていても、B日本人学校に設置されているとは限りません。さらには、対象の子どもがいない場合、特別支援学級が廃止になっていることもあります。
日本人学校を希望する場合には「特別支援学級が設置されているか」「状況により通常学級を活用しながら、一緒に生活することができる」「特別支援教育支援員が付くか」など、事前に直接、学校に問い合わせをする必要があります。
現地校の場合
学校で使用する言語が日本語ではないので、子どもがこの状況を受け入れられるかどうかを確認する必要があります。一方で子どもによっては、言語感覚に優れた力を発揮する場合がありますので、言語習得に挑戦してみるかなど慎重に検討するとよいでしょう。全く話せなかったのに、ある時、急速に発話する場合もあります。この見極めには少し長い時間が必要になります。
現地校の場合、国によってはインクルーシブ教育が進み、通常学級で受け入れられることも十分に想定されますので、学校や管轄する教育委員会とよく相談されてください。
インターナショナルスクールの場合
インターナショナルスクールでは、各校によってその対応が違います。受け入れが行われている学校の多くはインクルーシブで、通常学級で健常の子どもたちと一緒に生活しますが、授業料とは別に費用がかかります。また、私立学校ですので学校の方針として受け入れていない場合もあります。子どもの個性をとても大切にしている数十人単位の小さなインターナショナルスクールも存在し、子どものニーズに合わせた教育が行われています。こういった小さなインターナショナルスクールは「現地での口コミ」によって見つかる場合も多くありますので、前任者に話を聞いたり、日本人会などで情報を収集したりしてみてください。
問い合わせのポイント
学校に問い合わせる場合には、できるだけ詳細を聞くようにしましょう。
1.障害のある子どもの受け入れ状況
- 特別支援学級が設置されているのかどうか。
- 設置されている場合、種別(知的障害、自閉症・情緒障害等)はどうか。
- どういった子どもであれば受け入れられるのか(入学の基準や条件等)。
- 実際に受け入れている子どもの様子はどうか。
- 受け入れている子どもの人数や対応する教員の数はどうか。
- どのような教育が行われているか。
- 施設・設備の状況はどうか。
- 学校に対する家庭の協力はどの程度必要か。
- 持参した方がよい書類はどのようなものか。
など、具体的な場面を想定した質問をされるとよいでしょう。 さらには、現在の在籍校で作成している個別の教育支援計画・指導計画や専門機関の資料を持参して必要な時に提示するなど、子どもの実状を具体的に伝えることをお勧めします。
2.現地の医療事情
日本からの赴任者が多い国や地域では、日本語が通じる医療機関もあります。また、現地の医療機関を利用する場合には、英語を使えるかどうかを確認すると共に、場合によっては通訳を利用するなども考えるようにします。さらには、薬や検査など日本と異なることも多くありますので、互換性を確認すると共に、診断書や処方箋の翻訳を必ず持参するようにします。
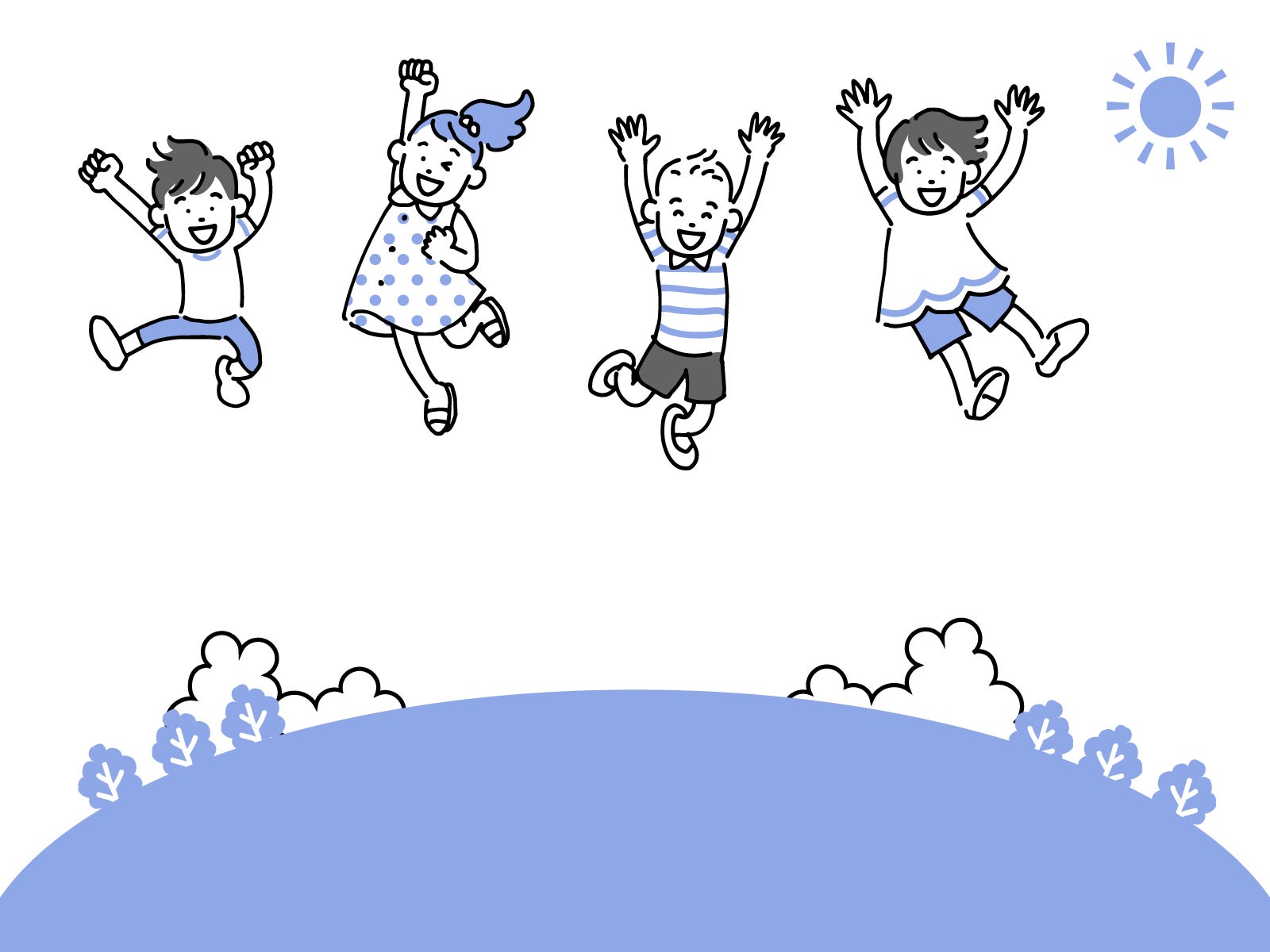
発達段階別に見た子どもの様子
帯同する場合、子どもの発達段階により着目する点も変化しますので留意してください。
1.乳幼児期
親子のかかわりが最も重要な時期ですので家族が揃って生活することが大切ですが、子どもが医療的な対応を必要とする場合には、より詳細な現地の医療機関情報を集める必要があるとともに、現在かかっている主治医の判断がとても大切です。また、母親一人で子育てをするのではなく父親は当然のこと、子育てサークルなどの情報を得て「多くの大人で育てる」意識をもつことも大切です。
2.幼稚園期
親子のかかわりと同時に子ども同士のかかわりも大切にしたい時期です。また、母語の基礎も3~4歳からこの時期にかけてできますので、子どもが将来的にどの言語を母語とするのか十分に考えておくことが大切です。さらには、子どもが集団生活に十分適応できるかどうか、支援がどの程度必要なのかを確認することも必要です。
3.義務教育段階
子ども同士のかかわりを深めると共に学習を積み重ねていく時期ですので、滞在予定年数や義務教育段階終了後の進路を考えておく必要があります。
4.義務教育段階終了後
自立に向け社会とのかかわりがとても大切な時期ですが、日本国内の国公私立特別支援学校高等部や発達障害の支援体制が整っている通信制高校など、いろいろな選択が可能です。
海外では国や地域によってその対応はさまざまですので、言語や生活習慣などの違いを踏まえた上で子どもの状況に即した判断ができるとよいでしょう。

地域別に見た特別支援教育
~アメリカ、イギリス、ドイツの場合~
1.アメリカの特別支援教育
特別な支援を必要とする子どもは、その教育が0~21歳まで保障されており、「全障害者教育法(IDEA)」に無償で適切な公教育を提供することがうたわれています。
学校で支援を受けるには「受給資格」の認定が必要で、保護者を含むチーム会議で種類分けされたどのカテゴリーが最も適しているかが決定されます。住居が決まった段階で必要書類を整え、学校を管轄している教育委員会に申し込んでください。障害認定を受けて、支援の内容や頻度・時間数が確定されます。
2.イギリスの特別支援教育
特別な支援を必要とする子どもは、できる限り通常の学校で支援を受けられるように定められており、学校内にSENサポート(Special Educational Needs)があります。編入学時にLA(Local authority)に申請し、その後、在籍校でSEN coordinator(特別支援教育コーディネーター)と相談します。
なお、特別支援学校に編入学したい場合は、日本での特別支援計画を合わせたプランを立ててもらう必要があります。
3.ドイツの特別支援教育
特別な支援を必要とする子どもは、促進学校あるいは特別支援学校へ通学します。一部の州ではインクルーシブの考え方が取り入れられていますが、州によって制度や考え方が違いますので注意する必要があります。特別支援教育を受けさせるかどうかについては、州教育省の州学務局が保護者からの申請を受けて決定します。

結び
情報収集をした結果、帯同が難しい場合も想定されます。家族が揃って生活するのが理想ですが、無理に帯同したことで二次障害を併発することもあります。言語が変化したことで自分の意志が伝えにくくなったり、環境の変化でルーティンがこなせなくなったりすることは、子どもにとって大変辛いことです。さらには、子どものために環境を整えようとするあまり、心身に不調を抱える保護者の方もいらっしゃいます。
できることとできないことを見極め、帯同が難しいと判断した場合には、長期の休暇に配偶者の赴任先に出かけ家族でゆっくり過ごすとか、赴任者が日本へ一時帰国した際に多くの思い出を作るなど工夫されるとよいかもしれません。
冒頭に書きましたように家庭の雰囲気が一番です。「子どもが真ん中」の生活は、潤いのあるすばらしい空間と時間になるはずです。
さまざまな課題があったとしても「乗り越えられない課題はない、いずれ風向きも変わる」と捉え、現状での最善を尽くしましょう。保護者の方だけで抱え込まず、多くの方と手を携えて子育てをしてまいりましょう。
<参考文献>
- 「海外赴任ガイド2024」監修JCM 2023,12,01
- 「障害のあるお子さんを連れて海外で生活するご家族へ」国立特別支援教育総合研究所2018,1
- 「障害のある子どもの海外学校生活を支援するガイドブック~社員の海外赴任をサポートするために~」国立特別支援教育総合研究所2009,12
- 「新・海外子女教育マニュアル」(公財)海外子女教育振興財団 2020,11,16
- 「発達障害のある子と家族によりそう安心サポートBOOK」小学生編 岡田俊 著 ナツメ社 2023,6,10
- 「図解よくわかる発達障害の子どもたち」榊原洋一 著 ナツメ社2017,07,20
- 「発達障害の子どもの心と行動がわかる本」田中康雄 監修 西東社2023,10,5
【順不同】
<回答者> 海外子女教育振興財団 教育アドバイザー 明石 清二(あかし せいじ) 1982年 仙台市立小学校に教諭として勤務開始 1987年~1990年 フランス・パリ日本人学校に教諭として勤務 2009年~2011年 仙台市教育委員会に主任指導主事として勤務 2011年 校長として勤務開始 2016年~2018年 ポーランド・ワルシャワ日本人学校に校長として勤務 2019年 宮城県国際理解教育研究会の会長として活動 2020年~2023年 ベトナム・ハノイ日本人学校に校長として勤務 2023年~ 海外子女教育振興財団に教育アドバイザーとして勤務 2023年~ 宮城教育大学に教育支援コーディネーターとして勤務
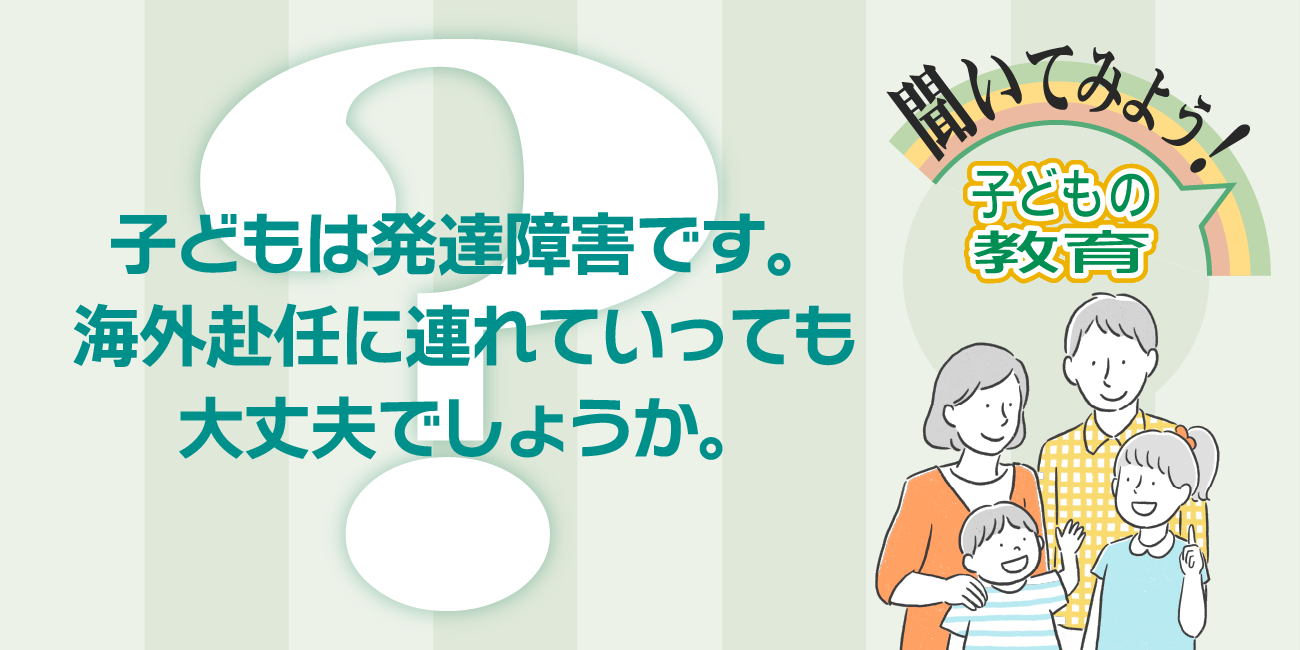
.jpg)