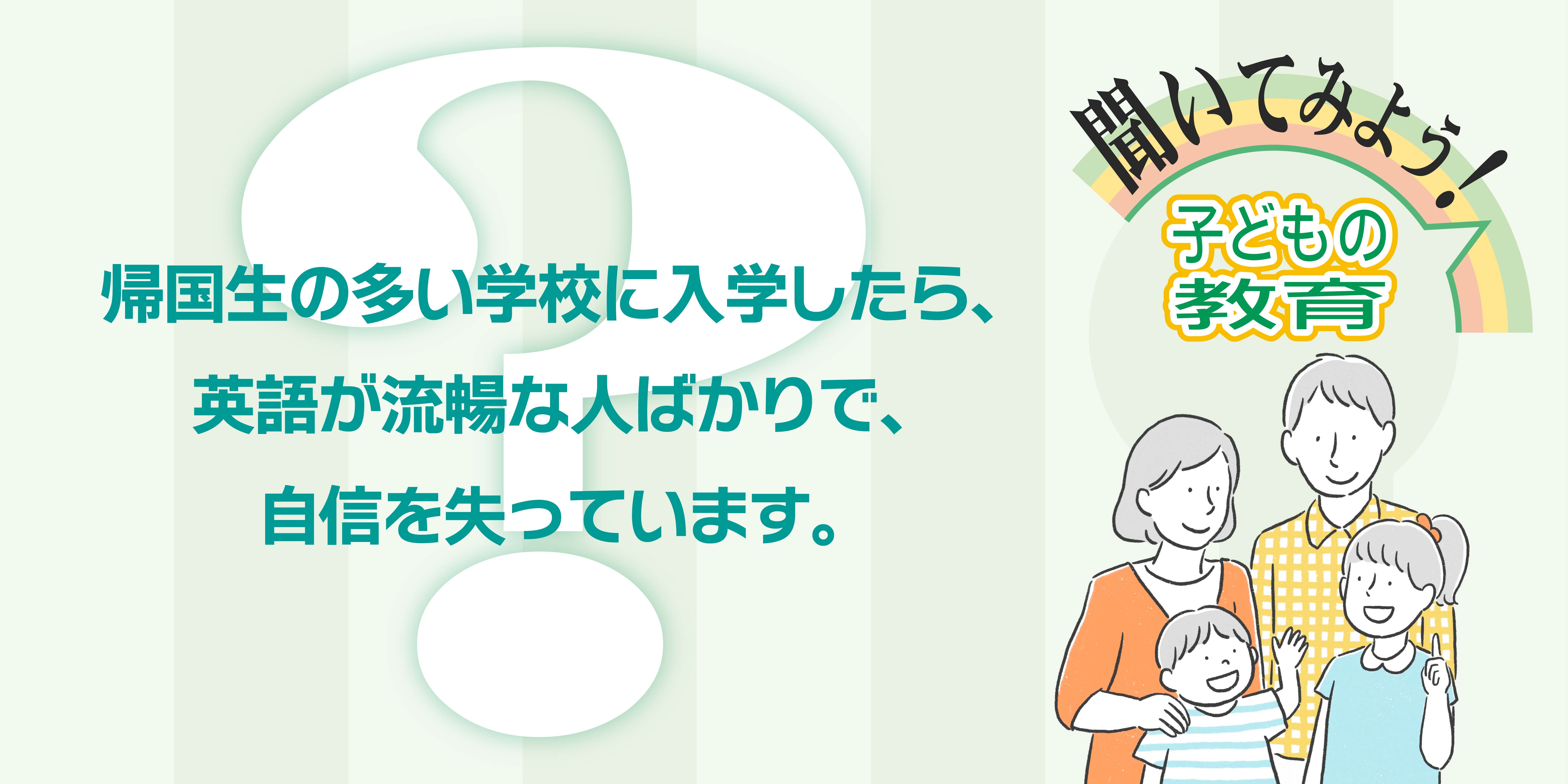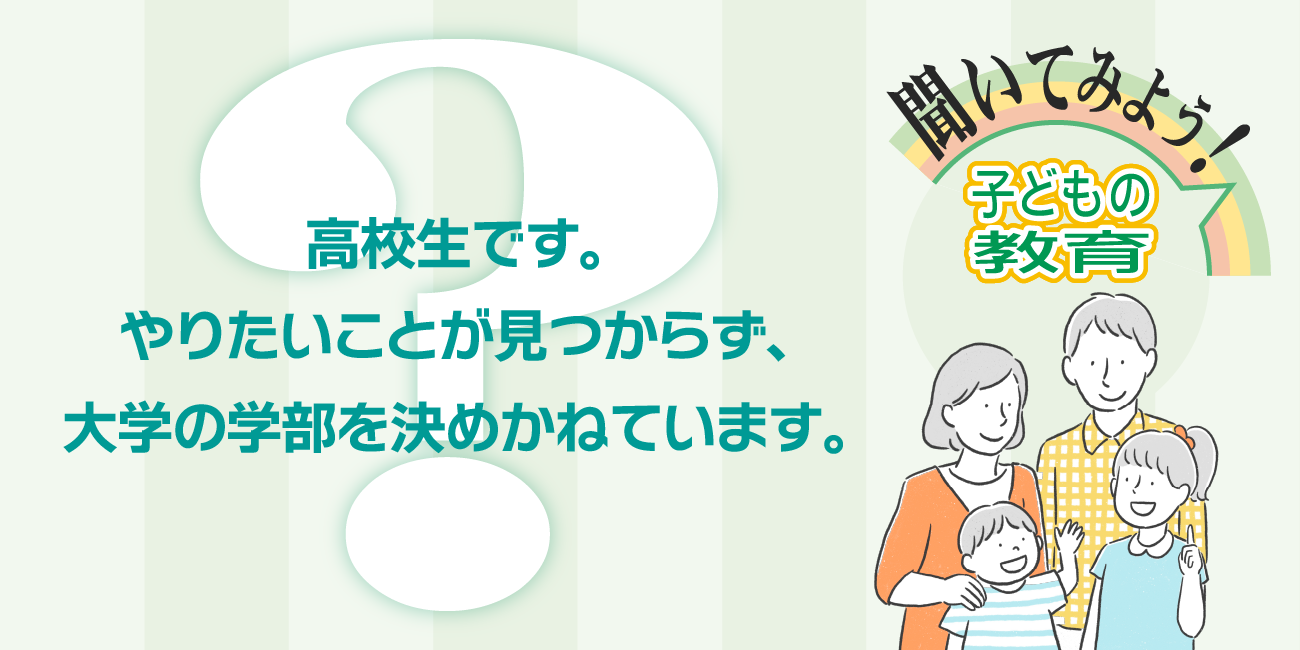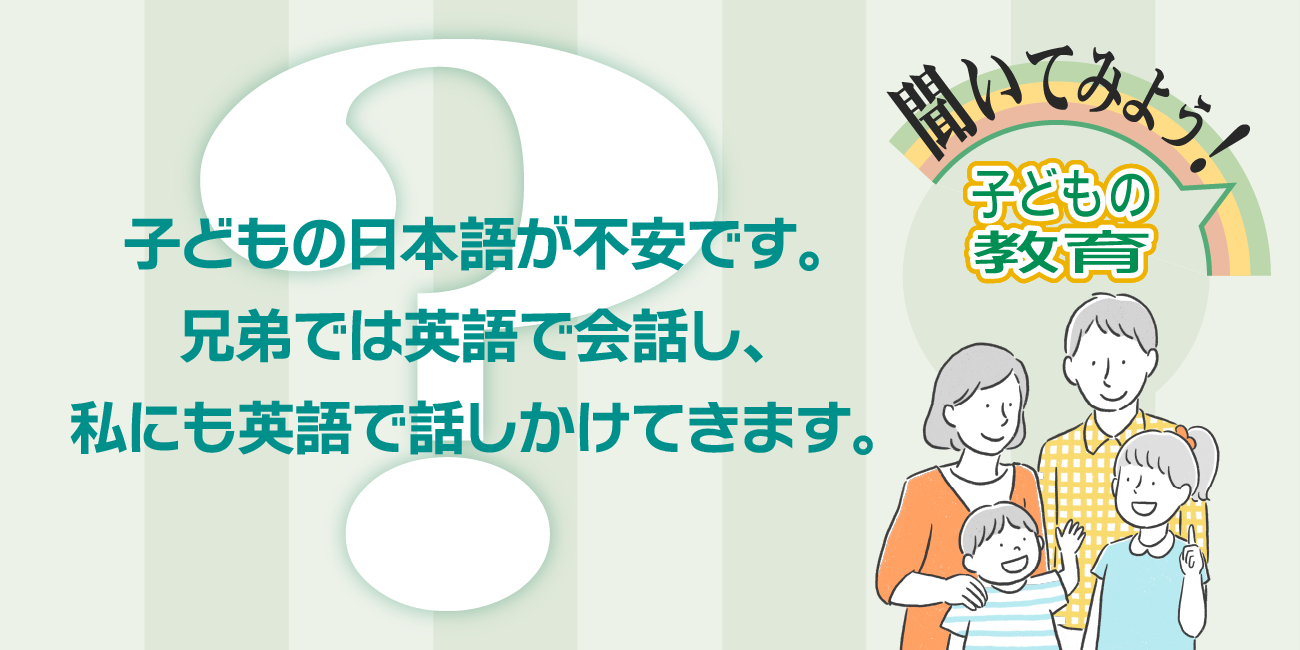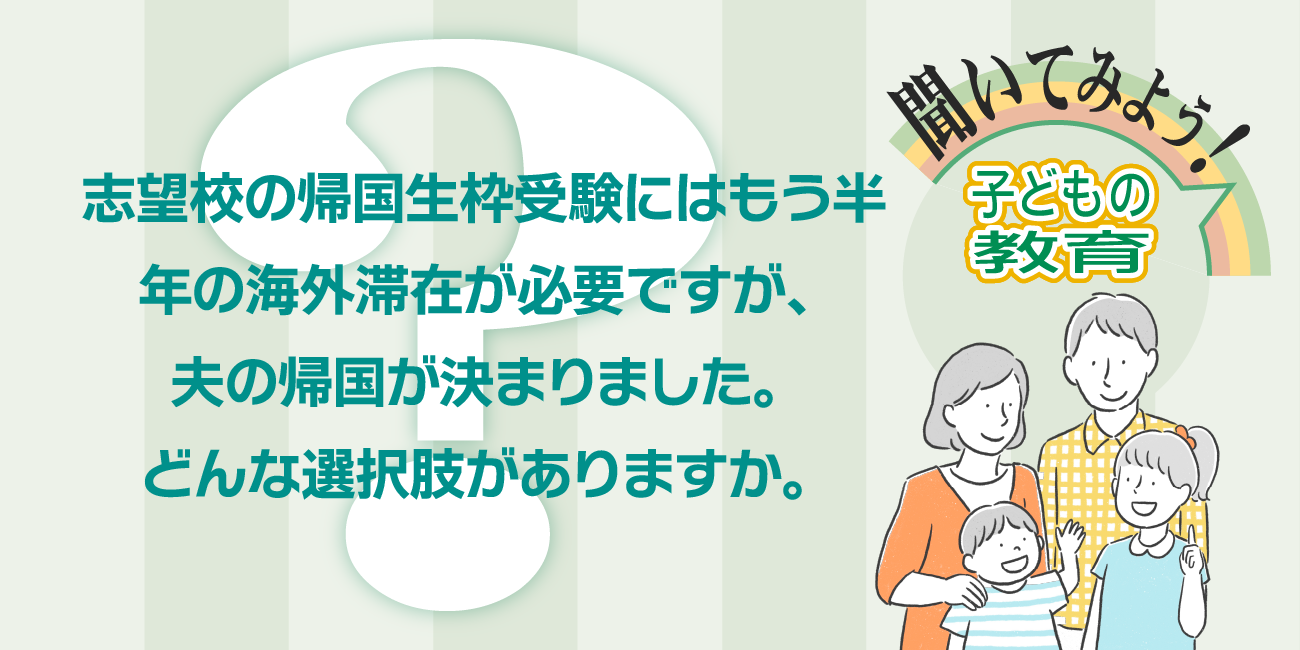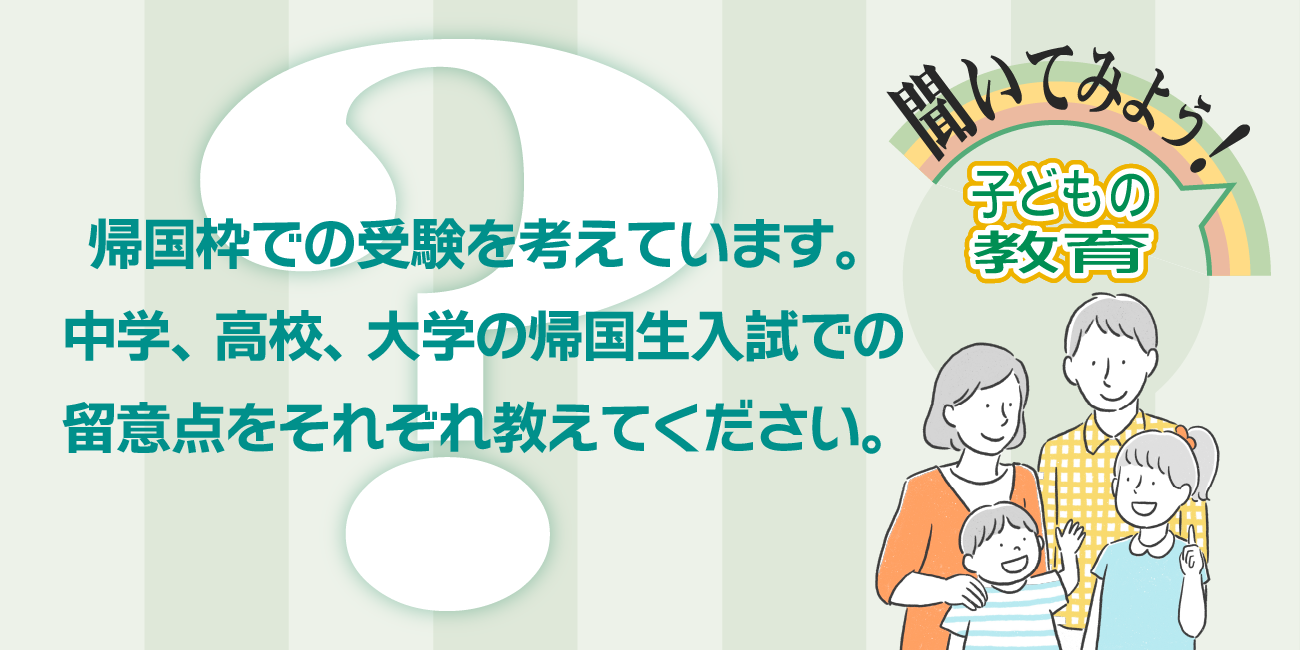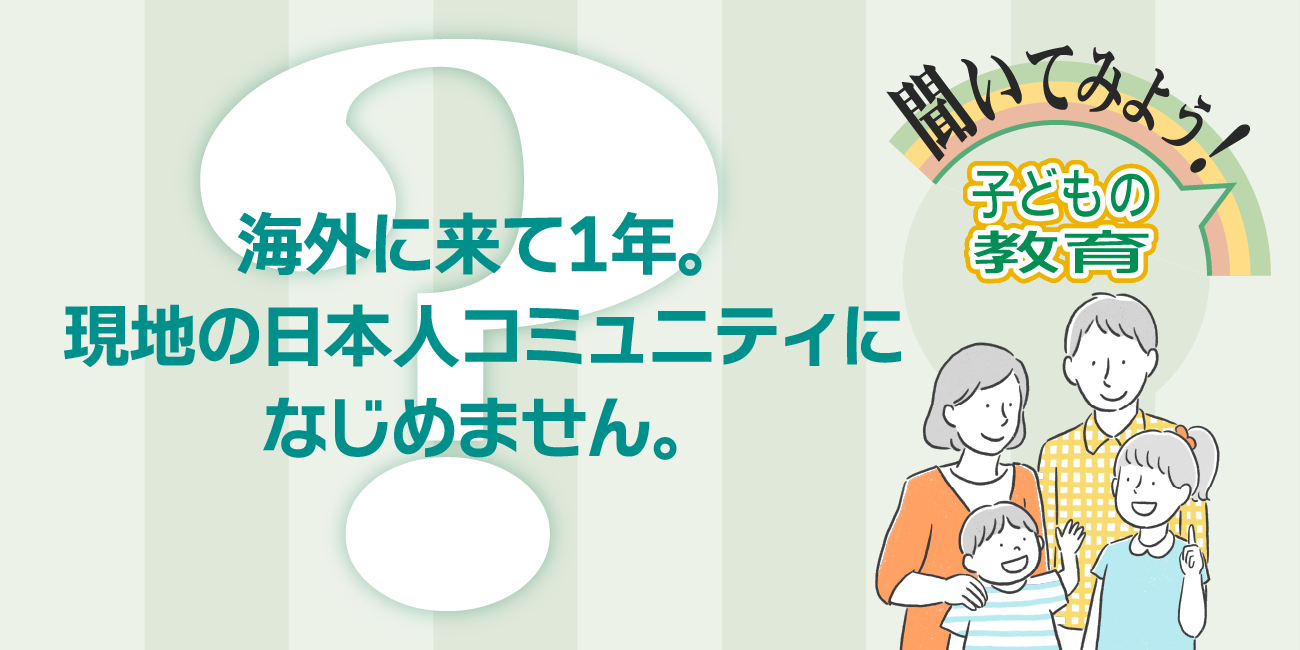<質問> 海外赴任が決まりましたが、中学生の子どもは行きたがりません。できれば、家族といっしょに赴任したいのですが……。
海外赴任は家族がまとまるチャンス
海外赴任が決まった時、家族それぞれの大きな期待と不安が動き始めます。
とりわけお子さんの教育に関することは、保護者にとってもお子さん本人にとっても大きなウエイトを占めることでしょう。
赴任する国や、その国の教育環境、滞在期間の長さ、そしてお子さんの年齢によって考えなければいけないことが多く出てくると思います。 そんな時こそ、まずは家族でしっかりと話し合うこと、情報を共有し、全員が納得できる結論を出すことが大切になります。家族そろって赴任するのか、別々の暮らしを選択する結果になるのかはそれぞれだと思いますが、しっかり話し合うことが家族の絆を強くし、家族がまとまるチャンスだととらえてください。

中学生のお子さんが抱える不安とは?
中学生というのは、思春期の多感な時期です。 まずは行きたくない理由を聞いてあげることが必要です。 お子さんなりの思いや不安はどんなことなのでしょう。いくつか例をあげてみましょう。
言語(学習)に対する不安
何といっても海外で生活するうえで一番不安なのは言語の問題です。特に中学生のお子さんにとっては、「学校生活はどうなるのだろう」「そこで友達はできるのか」「勉強についていかれるのか」など、不安な点を想像するとすべて言語に対する不安から発生するものと言ってよいでしょう。
現在の友達と別れたくないという不安
思春期のお子さんにとっては、現在仲良くしている友達の存在はとても大きなものです。家族よりも友達と一緒にいたいという気持ちが強いお子さんもいるかもしれません。
「数年たてばまた会えるから」というのは大人の論理であり、お子さんが友達との時間を大切に思っていることは尊重してあげなければなりません。
受験に対する不安
中学生であれば、高校受験という大きなターニングポイントが目の前にあります。高校進学は将来的に大学進学やその後のキャリアにもかかわることです。
その時期に海外で過ごすということは、先に述べた言語や学習への不安と連動して、目の前に迫っている高校受験がどのようになっていくのかという大きな不安になるはずです。

いくつか例をあげましたが、ほかにもお子さんが感じる不安はさまざまだと思います。
「なぜ行きたくないのか」、その気持ちをよく聞きだし、共感し、そのうえで「こんな解決方法があるよ」「こんな情報があるよ」と、家族で話し合うようにしましょう。家族で過ごすその時間が貴重なのです。
不安を取り除くための情報の共有
その上で、次に大切になるのがお子さんの不安を取り除くために、お子さんにとっての有益な情報を家族で共有するということです。
.png)
前任者からの情報
実際に海外に赴任する人、例えば父親だとします。その場合、会社の転勤であれば、前任者がいらっしゃるでしょう。その方のご家族はどうしたのか、特に同じ年頃のお子さんがいらっしゃる方はどのように不安を乗り越えたのか、話を伺うことができればとても有益です。できるだけ具体的に現地の様子、学校の様子、言語の壁の乗り越え方などの話が聞けるといいですね。
教育相談や赴任者子女教育セミナーの活用
海外子女教育振興財団では、海外赴任が決まったご家族向けに「赴任前子女教育セミナー」を行っています。海外での学校選択の方法や教育の様子、言語の習得について、また帰国後の学校選択や受験情報、小さなお子さんの母語の保持についてなど、さまざまな情報を伝えるものです。
また、赴任される国、お子さんの年齢、滞在年数などに合わせて、ご家族ごとに寄り添う個別相談も実施しています。個別相談も行っています。 保護者の方はもちろん、お子さん本人が参加することもできます。
受験に特化した専門家による受験相談も実施しています。お子さんが抱いている不安に対して、できるだけ有益な情報を専門家から収集し、海外生活を前向きにとらえられるようにすることをお勧めします。
また、「インターナショナルスクール入学オリエンテーション」や「現地校入学オリエンテーション」「日本人学校入学オリエンテーション」では、海外での実際の学校の様子を現地で勤務しているスタッフから聞いたり、海外での学校生活を経験し、現在帰国している大学生の方からの体験談などを聞いたりすることができます。特に経験者からの話は、皆さんがとても安心できる情報であるという感想をいただいております。
そしてこのような情報は、渡航を前向きにとらえているお子さんにも必要です。単に海外で生活できるという楽しみだけでは なく、実際に厳しいことがあること、それをどのように乗り越えればいいかなどを出国前に聞いておいて、心の準備をすることも必要です。
友達とのつながり
これは一番難しいテーマかもしれません。思春期のお子さんにとって友達の存在はとても重要であり、逆に現地に行ってからも信頼できる友達さえできれば、多少の困難は乗り越えられるものです。 まずはお子さんの寂しさ、不安な気持ちに寄り添い、共感した上で新しい世界で新しい友達を作ることの価値を伝え、さらにSNSなどを活用すれば日本とつながることは難しくないことなどを伝えてあげましょう。
海外生活を前向きにとらえる
.png)
グローバルな視点で考える力が身につく
世界の情勢が年々複雑化していく中で、これからの時代で生き抜くためにグローバルな視点でものを考える力を若いうちに身につけることは大変意義深いことです。
何よりも日本で生活しているだけでは気づくことのできない海外のさまざまな立場の人の考え方や価値観を学び、多様なものの見方を身につけることは将来必ず進路選択やキャリアに役立つことを伝えてあげましょう。
日本と異なる学校文化の中で培われる積極性や対話力などが、後のキャリアに大きく役立つことも有益な情報です。
マイノリティの立場を経験することの価値
海外に行けば、日本人は「外国人」、時には自分の思いが伝えられなかったり、仲間に入れてもらえなかったり、辛い思いをするかもしれません。しかしそうした辛い状況を乗り越える力を身につけること、また逆に、日本で外国人として辛い思いをしている人たちの気持ちを理解し、思いやりや協調性を身につけるよいチャンスであることを伝えてあげましょう。
その国の良さについて家族で情報収集する
今やインターネットなど、さまざまな方法で情報収集できる時代です。その国ならではの文化、自然、歴史、生活などについてたくさんの情報を集め、現地でなければできない体験を楽しみに思えるようにすることも有効です。

親御さんの前向き姿勢が大切
最後にお伝えしたいのは、まず親御さん本人が海外生活に前向きな姿勢を示してほしいということです。
「多少の困難があっても、きっと貴重な経験が待っているから家族そろって海外で過ごそう」「言語の不安はお父さんやお母さんも同じだから一緒に勉強しよう」など、親御さん自身がこの赴任を前向きに受け止めていることをお子さんに示してあげてください。 これはそろって現地に行った時にもずっと継続していただきたいことです。
また、どうしてもお子さんが行きたくないということであれば、それを尊重するのも一つの選択肢です。
一緒に行ったけれど、辛ければ帰国する、受験が終わってから現地に来るという選択肢もあるなど、さまざまな可能性を示してあげることも必要です。
これをきっかけに家族の絆が深まることを期待してやみません。
<ご参考>
海外子女教育振興財団
<回答者> 海外子女教育振興財団 教育アドバイザー 中村昌子 (なかむらまさこ) 1984年から帰国生だけの特設学級(国際学級)を併設する東京学芸大学附属大泉小学校に35年間勤務する。その間、国際学級主任、担任を経験し、帰国生への相談・面接等も担当する。2012年より同校主幹教諭。退職後19年より、同校非常勤講師、東京学芸大学非常勤講師を務める。20年10月より海外子女教育振興財団の教育アドバイザー。
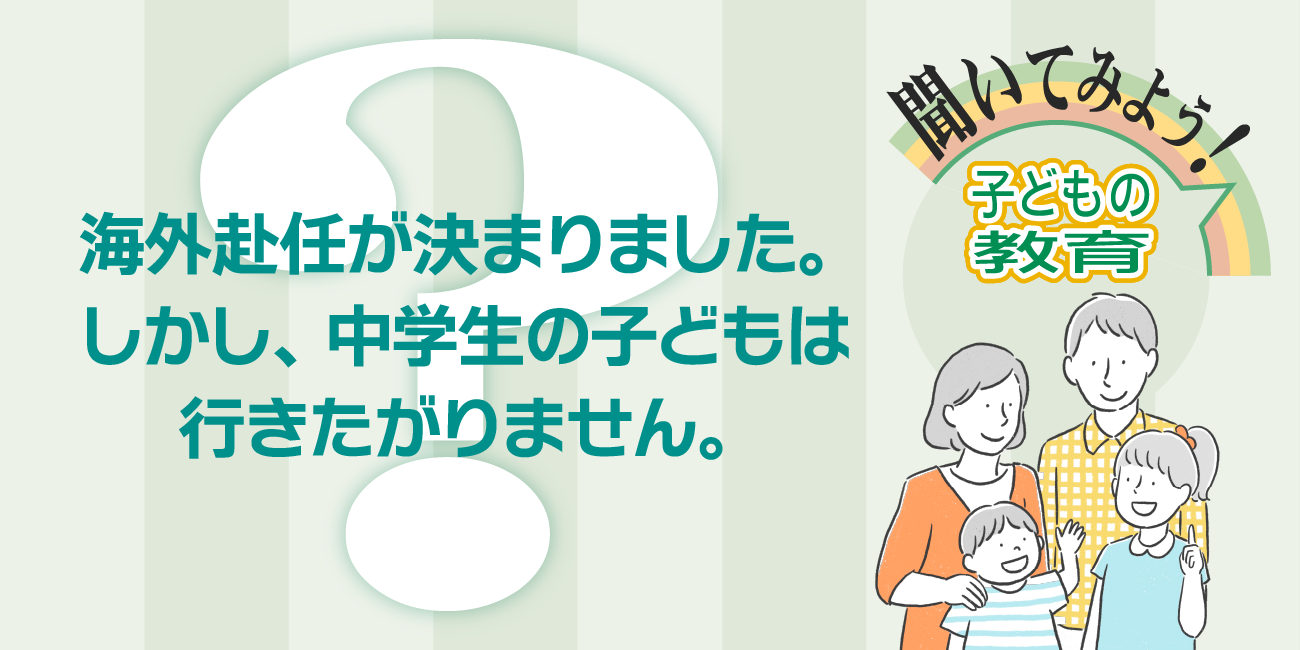
.jpg)