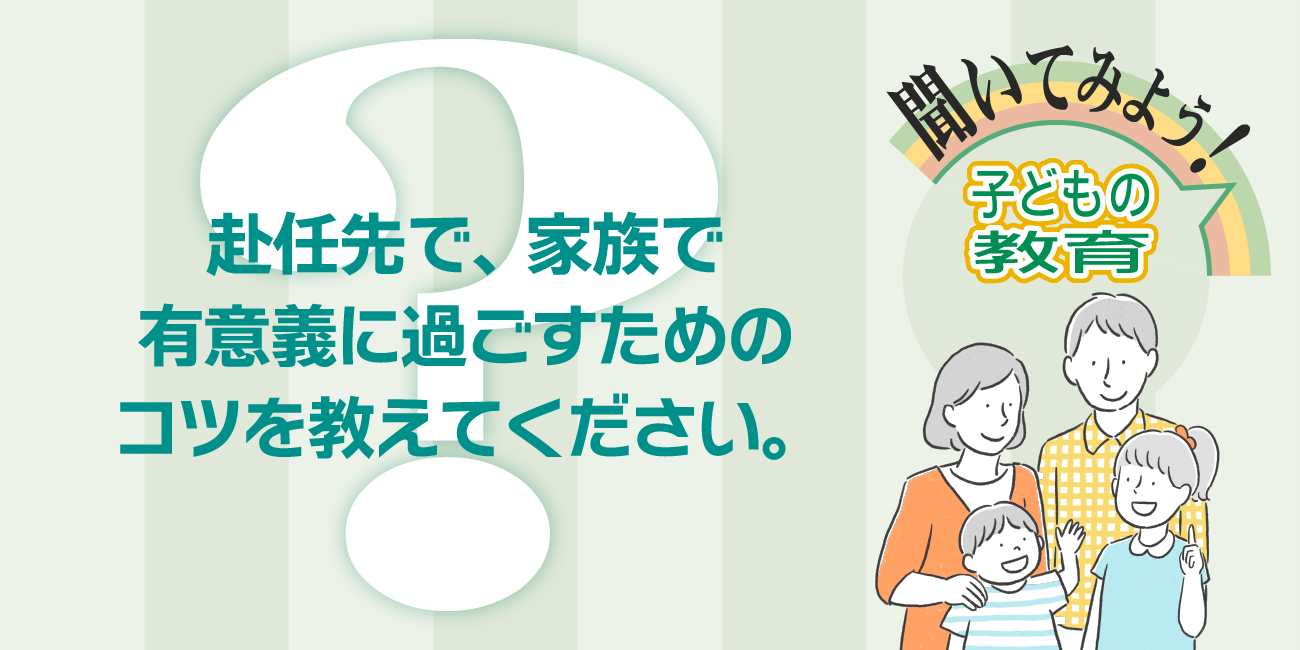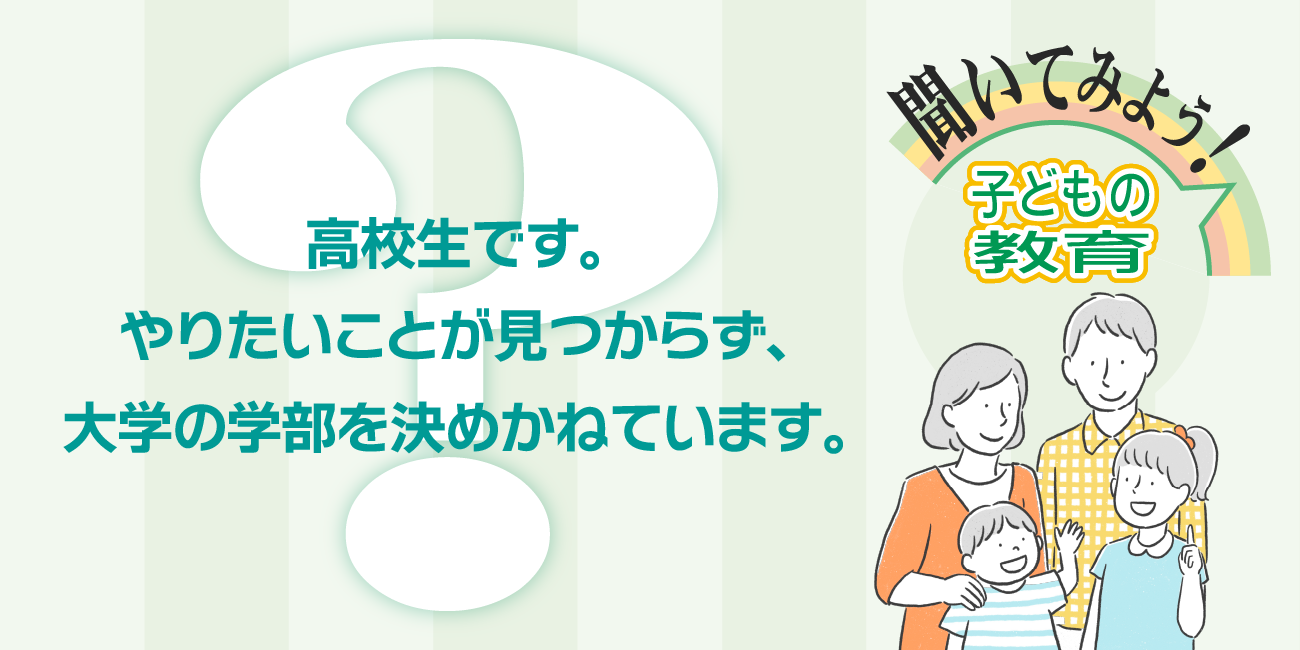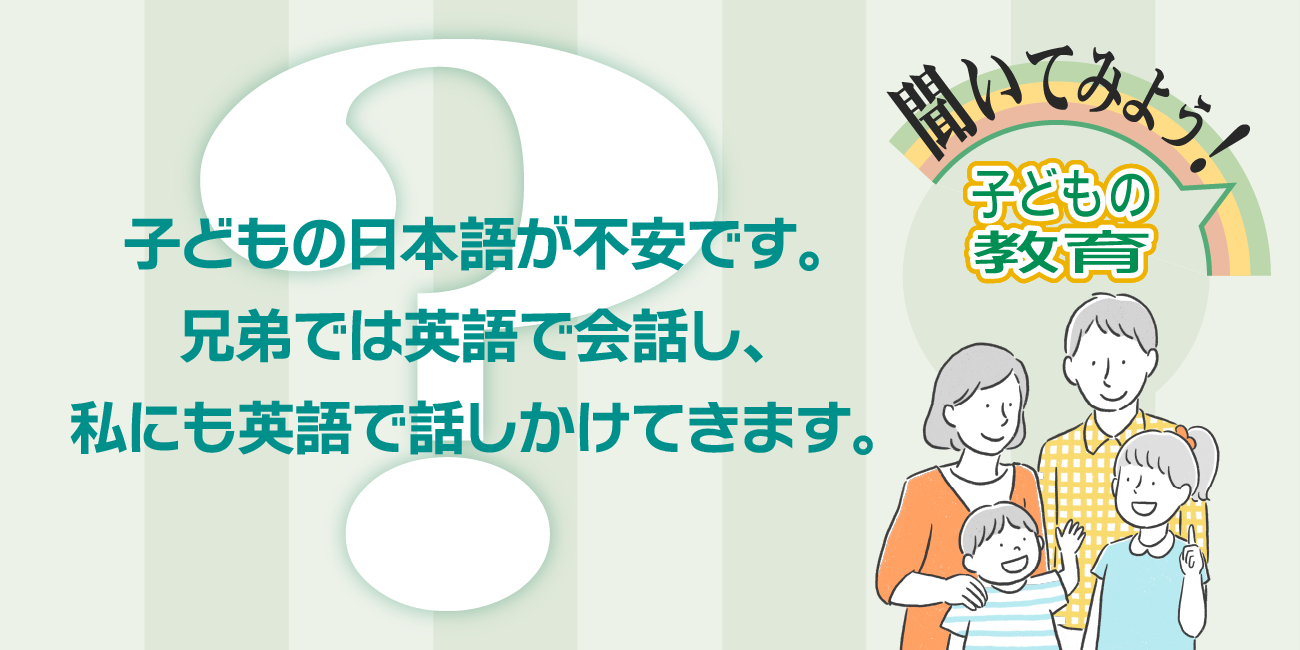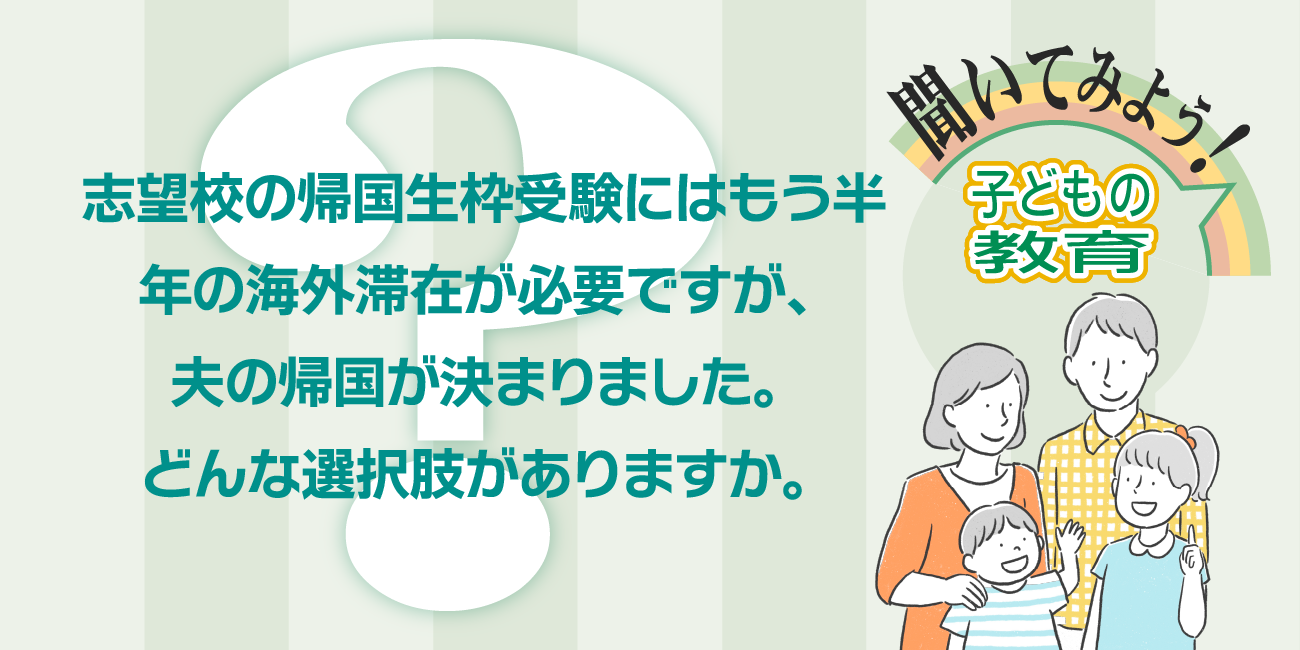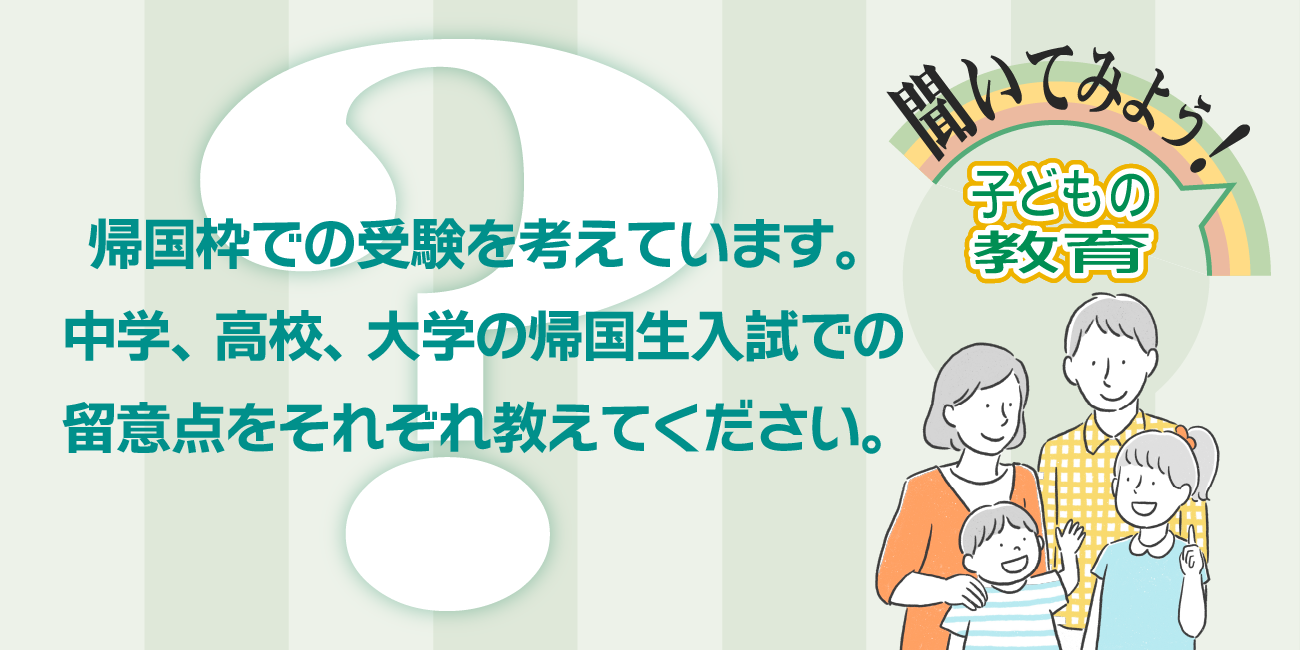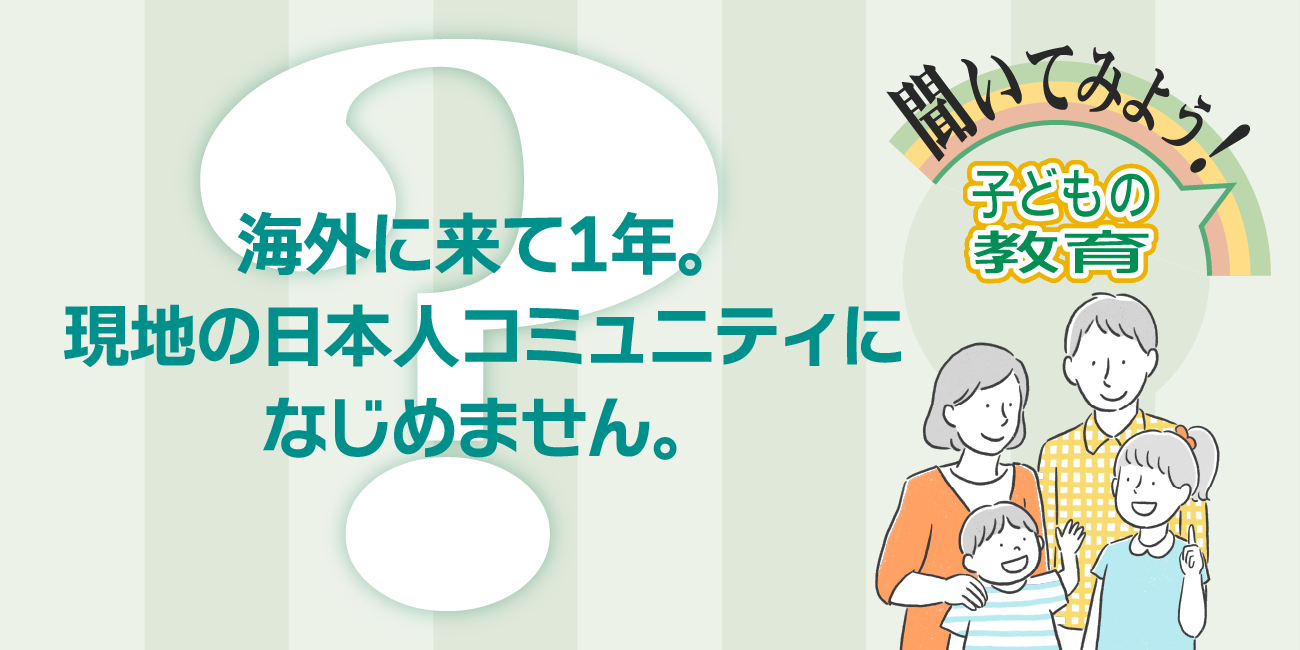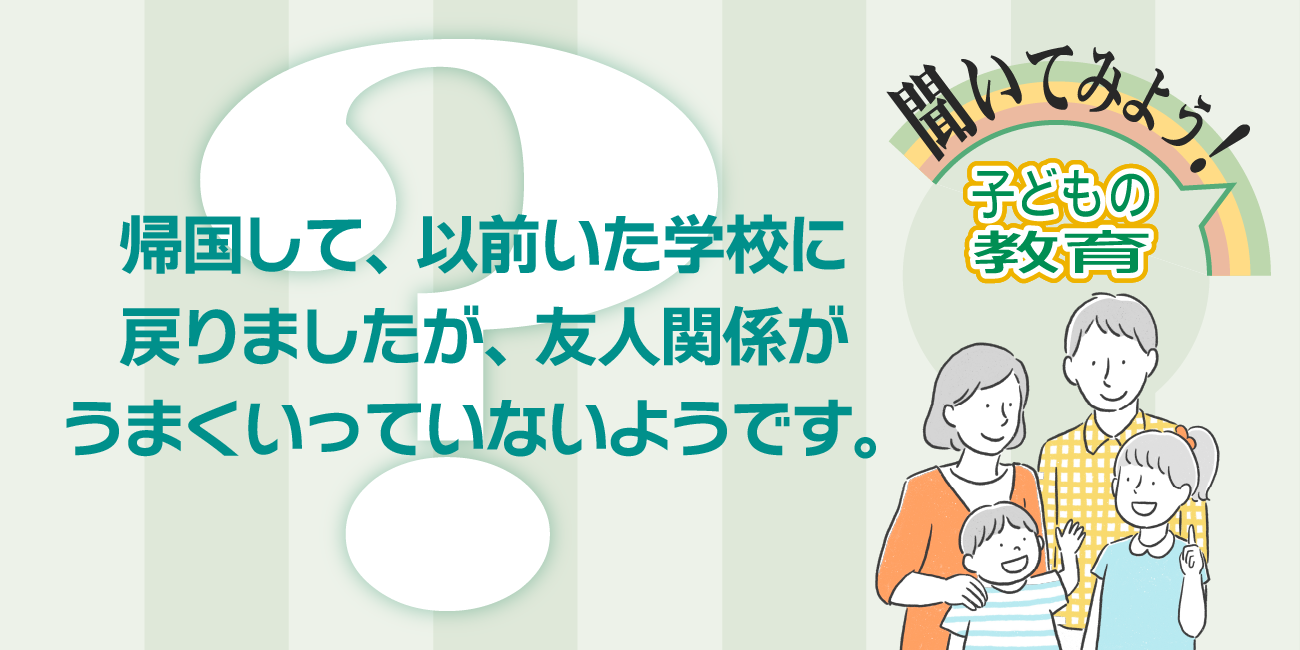<質問> 赴任先で、家族で有意義に過ごすためのコツを教えてください。
はじめに
海外赴任が決まると、不安と期待が入り交じり何かと落ち着かなくなるものです。特に初めての海外生活となればなおさらです。駐在員であれば多くの場合、3年から5年の任期となるので、限られた時間の中でやりたいことは次から次へと出てくるものです。
そこで、今回は赴任先でご家族が有意義に過ごすにはどうしたらよいのか、考えていきたいと思います。
家庭とは
家庭は人間が社会生活を営んでいくための、最も基本的な場です。人間という文字に示されているように、私たちはひとりで生きていくことはできません。生まれてから死ぬまで、人と人との何らかの間柄の中で生活していきます。その出発点となる最小の単位が家庭であり家族なのです。
皆さんは、「家庭」という言葉から、どのようなイメージを描くのでしょうか。おそらく人それぞれ、千差万別といっても過言ではないでしょう。以前でしたら、家庭から出て社会で活動し、家庭に帰ってくるという男性の側からすると、家庭とはそのまま妻のいる家というイメージになってきます。それは子どもにしても同じことで、家庭とは母のいる家ということになります。現在は女性も社会進出をする時代であり、このような考え方は古いかもしれませんが、多くの場合、実家を「おばあちゃん家」と呼ぶ方が多いのではないでしょうか。ちなみに私の孫は、わが家を「ばあばの家」と呼んでいます。一応、家の名義は私なのですが、妻の存在感の方が強いというのが現実です。
このように考えると、家庭の要は、妻であり母である女性の力が大きいように感じます。
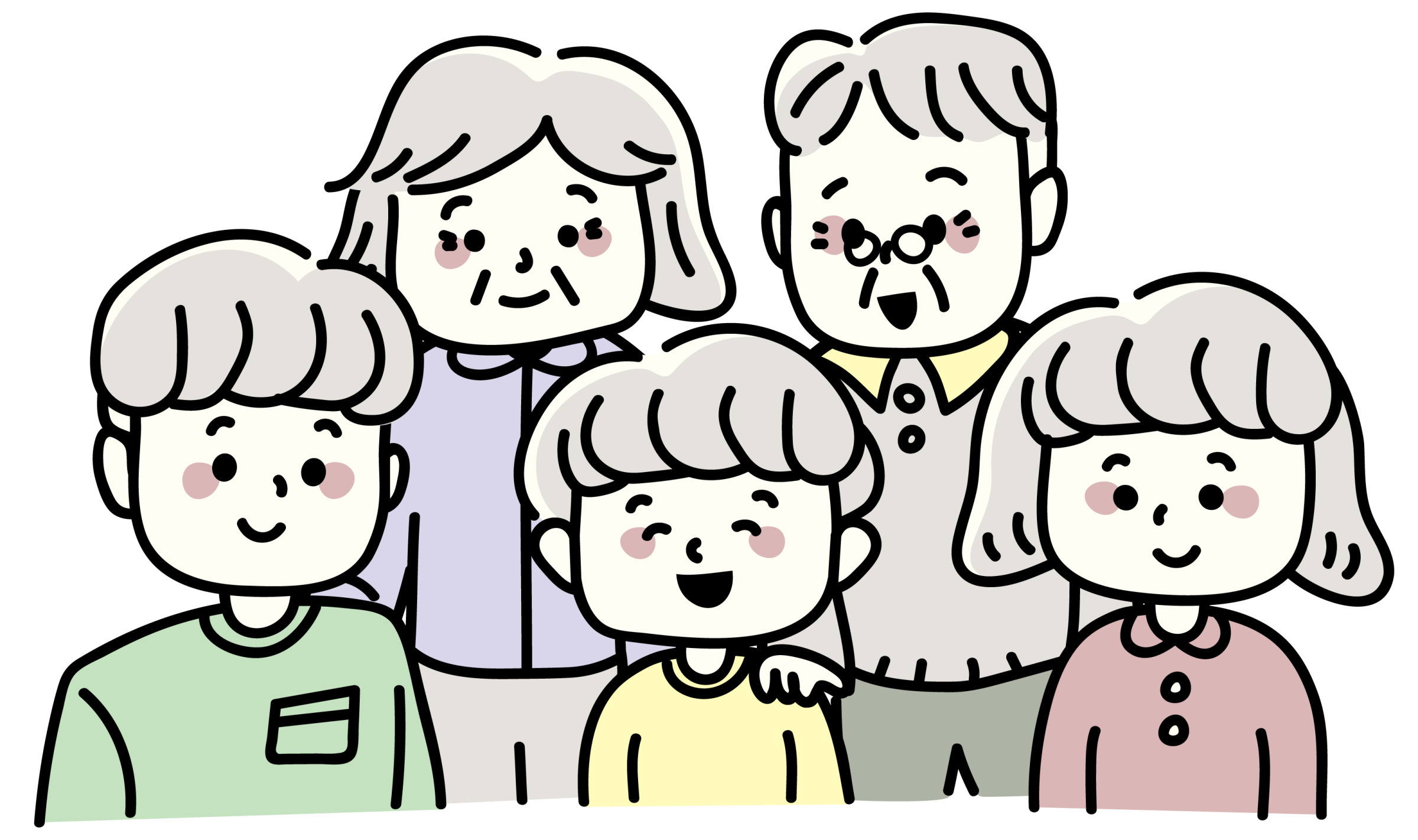
何でも話し合える場に
この「家庭」で最も大切なことは、何でも話し合えるということです。国内にいるときは、何かと忙しく、家族で話し合う機会はあまりなかったかもしれませんが、海外生活では、家族の意思疎通こそが最も重要となってきます。
そもそも、人間の意思伝達方式は言葉です。私たちはテレパシーを使えるわけでもなく、身振り手振りや、口ほどにものを言う目も、伝達の補助手段ではあっても、十分に意を尽くすことはできません。
文字が現れたのはたかだか数千年前のことで、人間は元来、言葉で意思を通じるようにできているのです。ですから、年齢に関係なく同等の人格として、何でも話し合える環境づくりをしていただきたいと思います。
現地に友人を
せっかく異国の地に行きながら、何もしないで帰ってくるのはもったいないことです。子どもの頃に海外で生活できるお子さんは、全体のたった1%程度です。
その貴重なチャンスを充実した日々にしていただくには、「現地に馴染む」ことが大事です。国や地域によっては、日本と同じように安心して暮らせない地域もありますが、可能な限り現地の文化や慣習など積極的に体験してきてほしいと思います。
平日はなかなか難しいかもしれませんが、週末は家族が一緒に行動する時間を設けましょう。地元の観光や近場の旅行などで、その国・土地ならではの文化を経験することは家族にとって貴重な経験となります。
また、長期休業中は、近隣国に出かけて、さらに多くのものを見聞きしてくるのもお勧めしたいところです。
子どもは親の背中を見て育ちます。その土地の人たちと積極的に関わろうとしている親の姿勢は、必ずお子さんに通じます。できれば、仲の良い現地の友人を作れれば最高です。現地の習い事に参加するのも良いでしょう。
日本との違いに文句ばかり言っている親からは、その国の良さを知ることはできません。親自らがポジティブな気持ちで積極的に地域に関わることで、子どもたちも地域と関わるようになります。
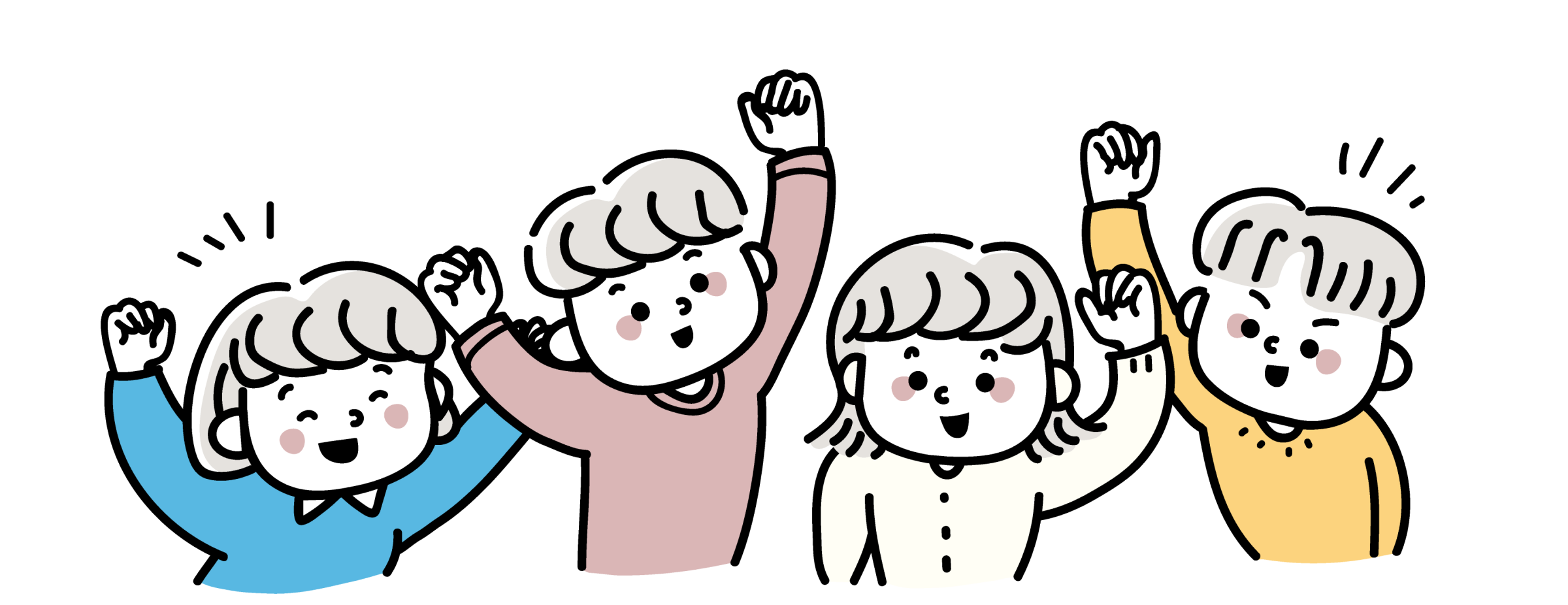
食べて、比べて
食文化にはその国の特徴がよく現れます。その国ならではの食べ物を味わうことはとても楽しいことです。
かつて住んでいたブラジルでもその国特有の食文化がありました。ブラジルの国民食といえば、豆料理の「フェイジョアーダ」が有名ですが、地域によって少しずつ味付けに違いがあります。ファーストフードでは、「コシーニャ」というブラジル風のコロッケや、小麦粉ベースの生地にひき肉やチーズなどの具材を包んで油であげた「パステウ」が好んで食べられていました。
「パステウ」のルーツに日本人が関わっていた、など、食べ物のルーツを調べてみることで、その国の歴史まで知ることもできます。
日本との違いや似たところを親子で見つけながら、その国の良いところや日本の良いところを発見できると、海外生活がより充実していくのではないでしょうか。

思い出を記録に残そう
そんな様子を、家族の歴史として綴ってみてはいかがでしょうか。
かつて、私は2歳の娘を帯同してシドニーで生活をしたことがありますが、その時にやっていたのが家族新聞の作成です。今はSNS等ですぐに情報を共有できますが、当時はアナログの時代で、新聞ができるたびに、実家や親戚に郵送していました。祖父母にとって、孫の成長を含め私たち家族の様子を見ることが楽しみの一つだったようです。
今、まさにデジタルな世の中だからこそ、手紙というアナログな形でお便りが届くのも趣があっていいのかもしれません。
あれから30年以上たって、その時の新聞が出てきました。当時借りていた家の真っ白な壁一面に、クレヨンで絵をかいてしまった娘と一緒に、消しゴムで絵を消す親子の様子や、初めて行ったアイスショーで、迷子になってしまった娘の姿を必死に探す親の気持ちなど、今ではすっかり忘れていた当時の様子が描かれていました。
二人の子どもを持つ母になった娘は照れくさそうな表情でしたが、今では家族にとって大切な思い出となっています。家族新聞は単なる記録ではなく、20年先30年先に、貴重な記録として家族の宝物となることは間違いありません。

ひき算の発想で
世界で活躍するアスリートを育てた親が子どもの前で「絶対にやらなかった」ことは、「頭ごなしに怒らないこと」と「子どもの考えを否定しないこと」だったそうです。
「なぜ、できないのか」「お前はダメだ」と言われた瞬間、子どもはコンプレックスを植え付けられ自己肯定感が失われてしまいます。その二つを「しない」ことが、子どもの個性を大きく育てていくのだそうです。
どうしても子育ては、あれもこれもと「たし算」の発想になりがちですが、時には、「何をしないか」という「ひき算」の発想も大切ではないでしょうか。
あれもこれもと欲張ってしまうと、お子さんにとっては容量オーバーにもなりかねません。お子さんの気持ちも大事にしながら、子育てに取り組んでいただければと思います。
終わりに
ご家庭によって生活スタイルはさまざまですので、楽しみ方もみな違います。そして、赴任される地域によっても状況は違ってきます。
しかし、その場所で得られることはたくさんあります。子どもの時に海外生活を経験できるというチャンスはめったにあるものではありません。そこで何を感じ、何を得るかはお子さんそれぞれですが、その後の成長の大きな糧となることは確かです。
国際人として最も大事なポイントは、語学ができるということより、まず、相手を理解し、互いの幸福のために何ができるのか、そして、人間として尊敬されるかどうかです。
どうかこの海外生活という貴重な経験を、ご家族で有意義にお過ごしください。
<回答者> 海外子女教育振興財団 教育アドバイザー 渡辺 稔(わたなべ みのる) グローバル化が進む現代において、海外での生活は、お子さんにとってかけがえのない経験となり財産となります。言語や文化・習慣の全く違う国での生活は、苦労も多いかもしれませんが、その分、得るものも多くあります。お子さんにとって有意義な学びとなるよう、教育相談を通してお役に立ちたいと思います。 プロフィール ・元神奈川県公立学校校長
・元シドニー日本人学校教諭、リオデジャネイロ日本人学校校長
・2023年より現職