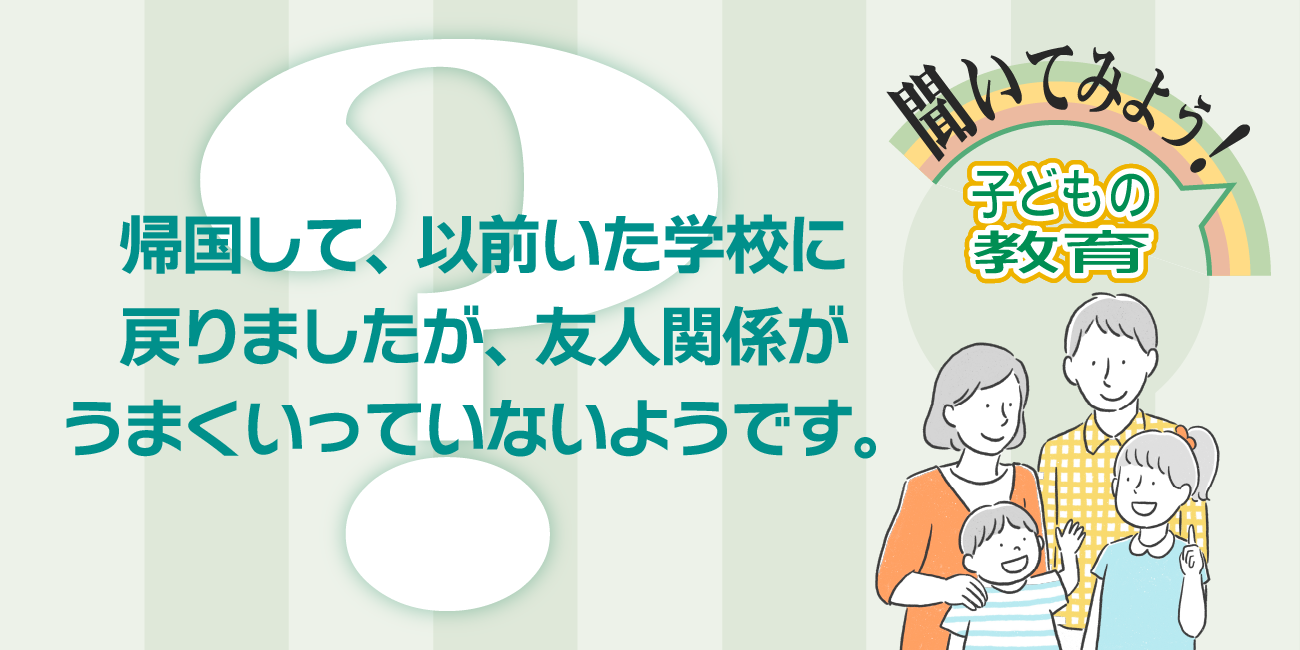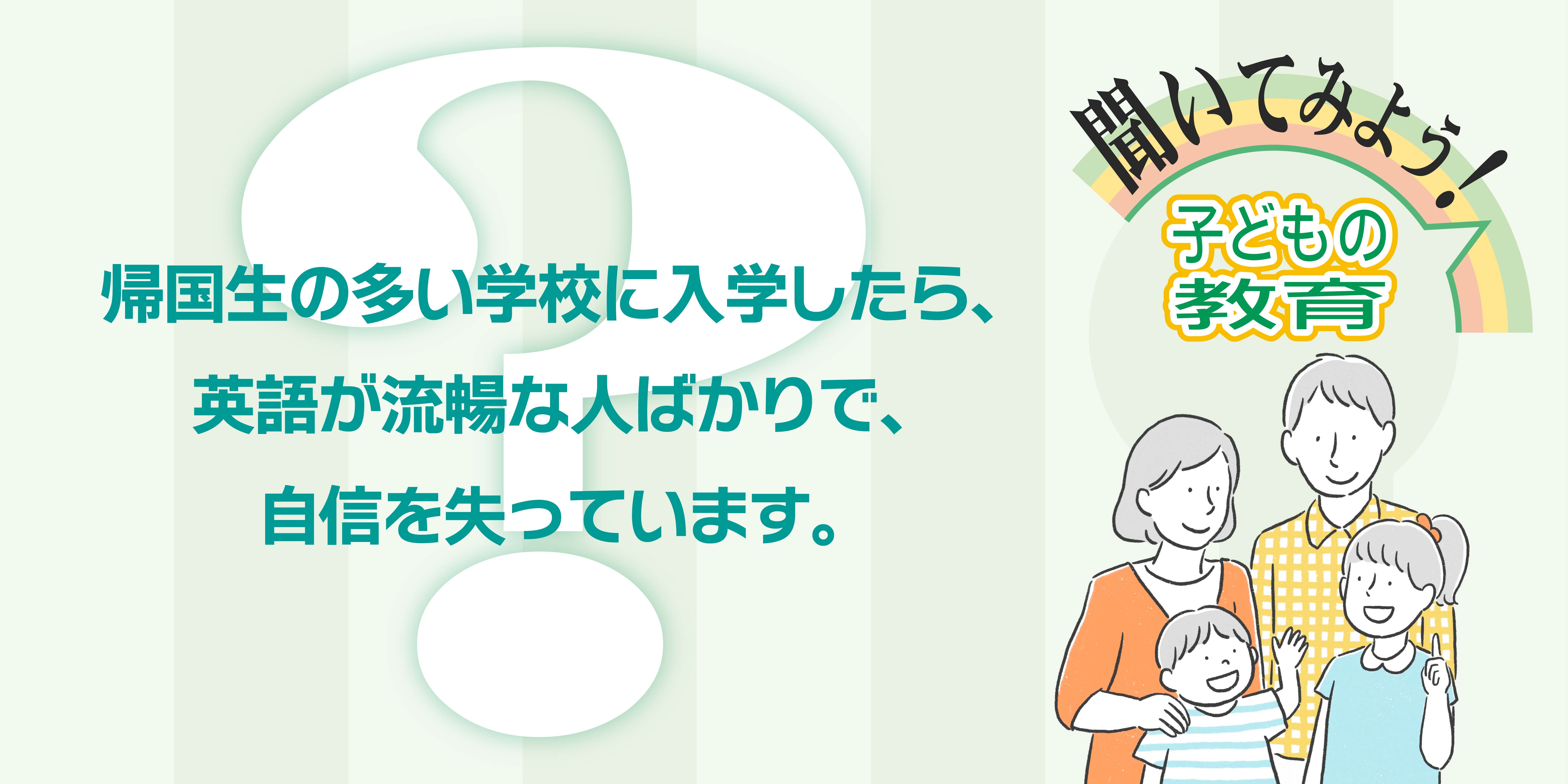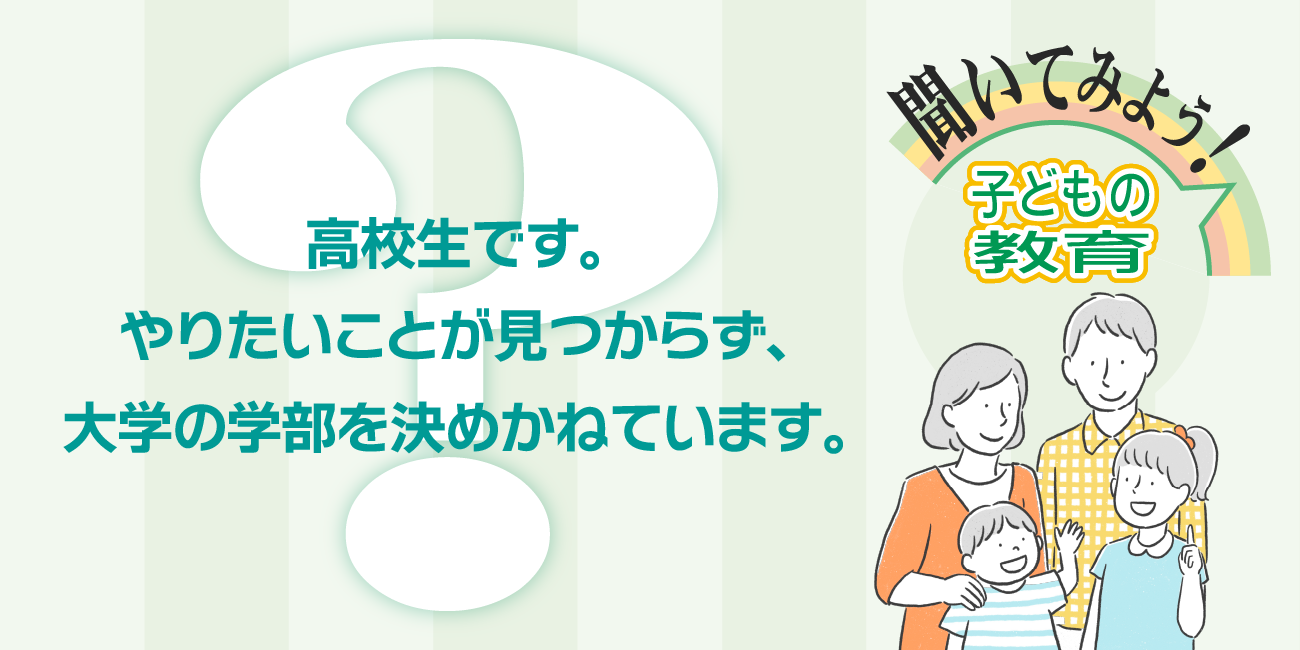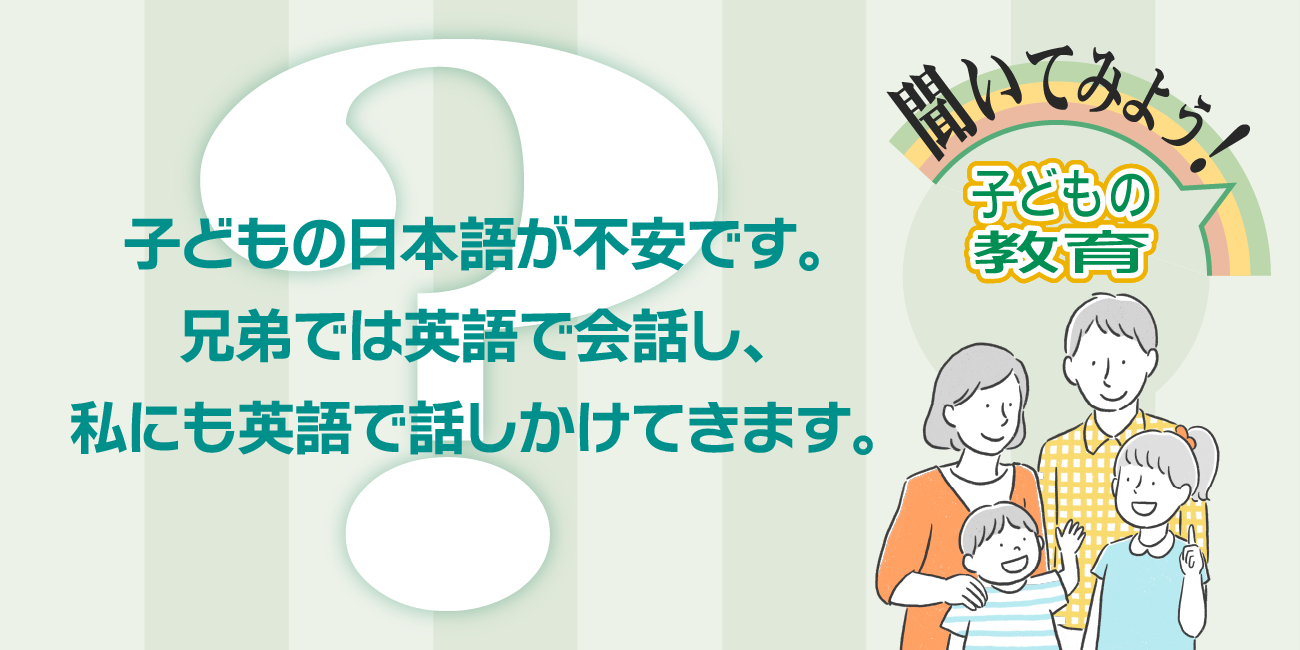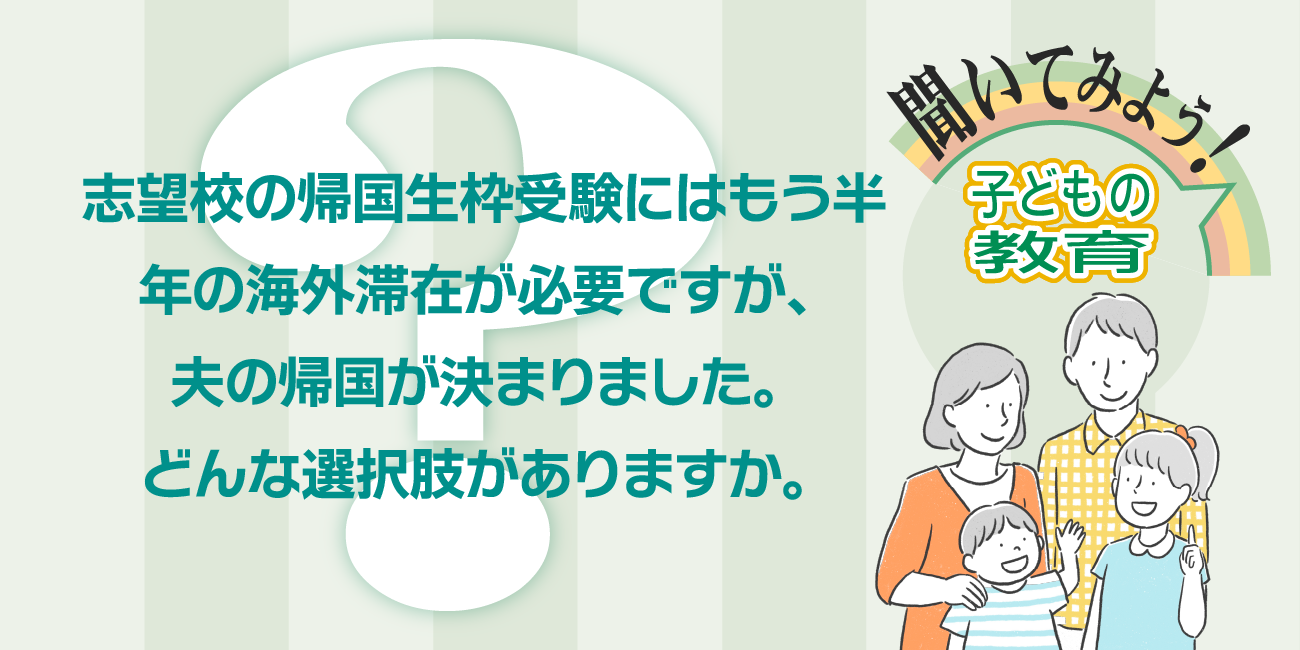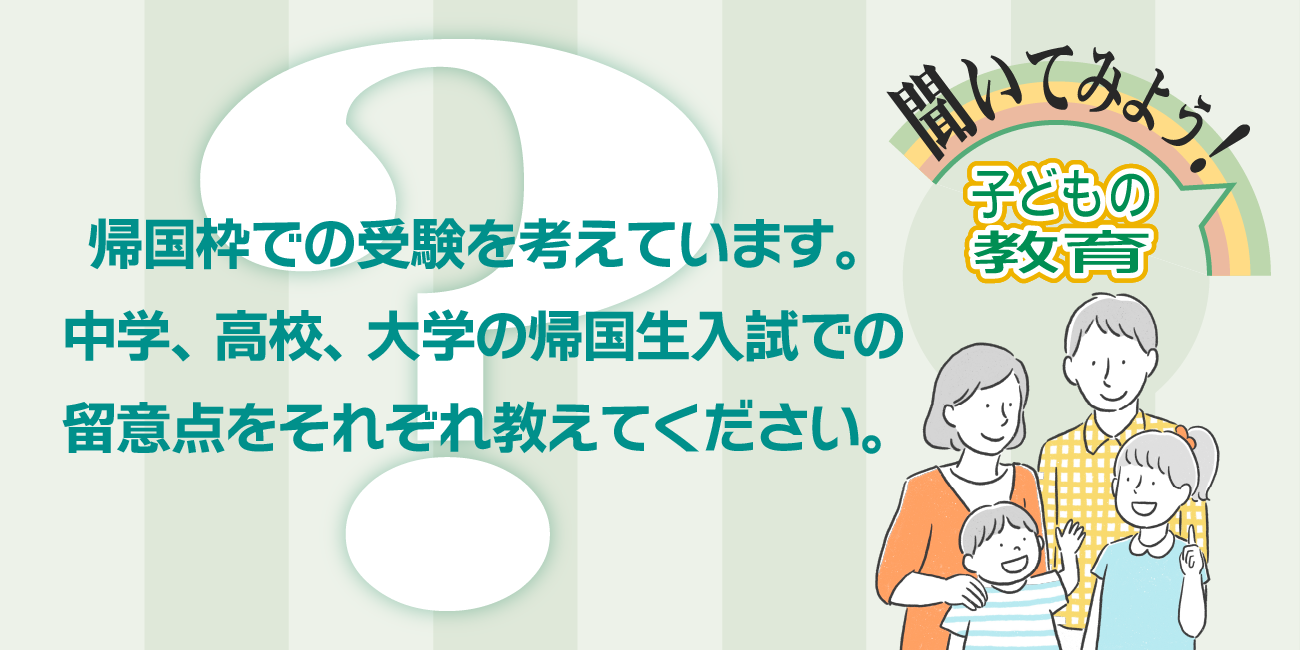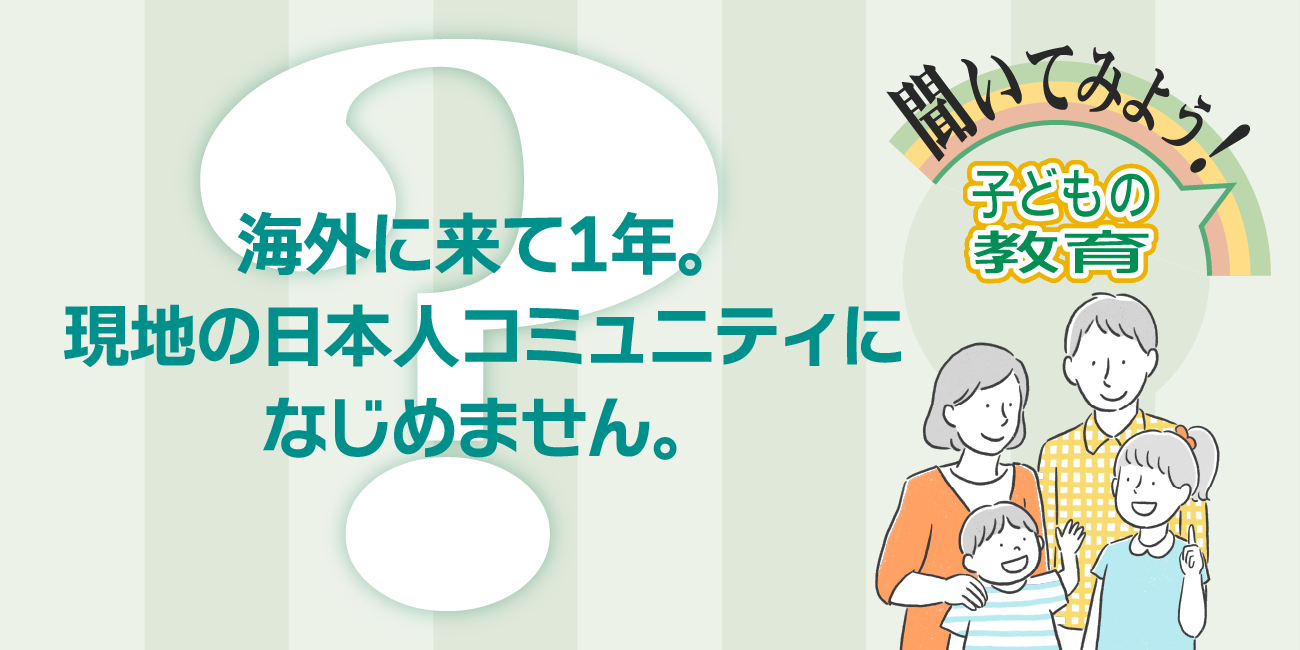<質問> 帰国して、以前いた学校に戻りましたが、友人関係がうまくいっていないようです。どうしたらいいのでしょうか。
はじめに
親の海外転勤に伴って慣れ親しんだ学校を離れ、それまで毎日一緒にいるのが当たり前だった仲の良い友人たちと会えなくなってしまうこと、それは特に中学生や高校生にとっては大変なことです。最近はSNSのおかげで、たとえ海外に行ったとしても、それまでと同様に、まるですぐ隣にいるように気軽に連絡をとりあうことができるようになっています。とはいうものの、実際は何千キロも離れたところにいるわけですから、時差の影響でタイミング良く返信できないことも、微妙に話題についていけないこともあるでしょう。
でも、そんな時でも子どもは「自分は外国にいるのだから当然だ」とあまり気にせずいられるものです。大変なのは、帰国後の方かもしれません。「自分の国に戻ったのに、なんで?」ということが、結構あるのです。
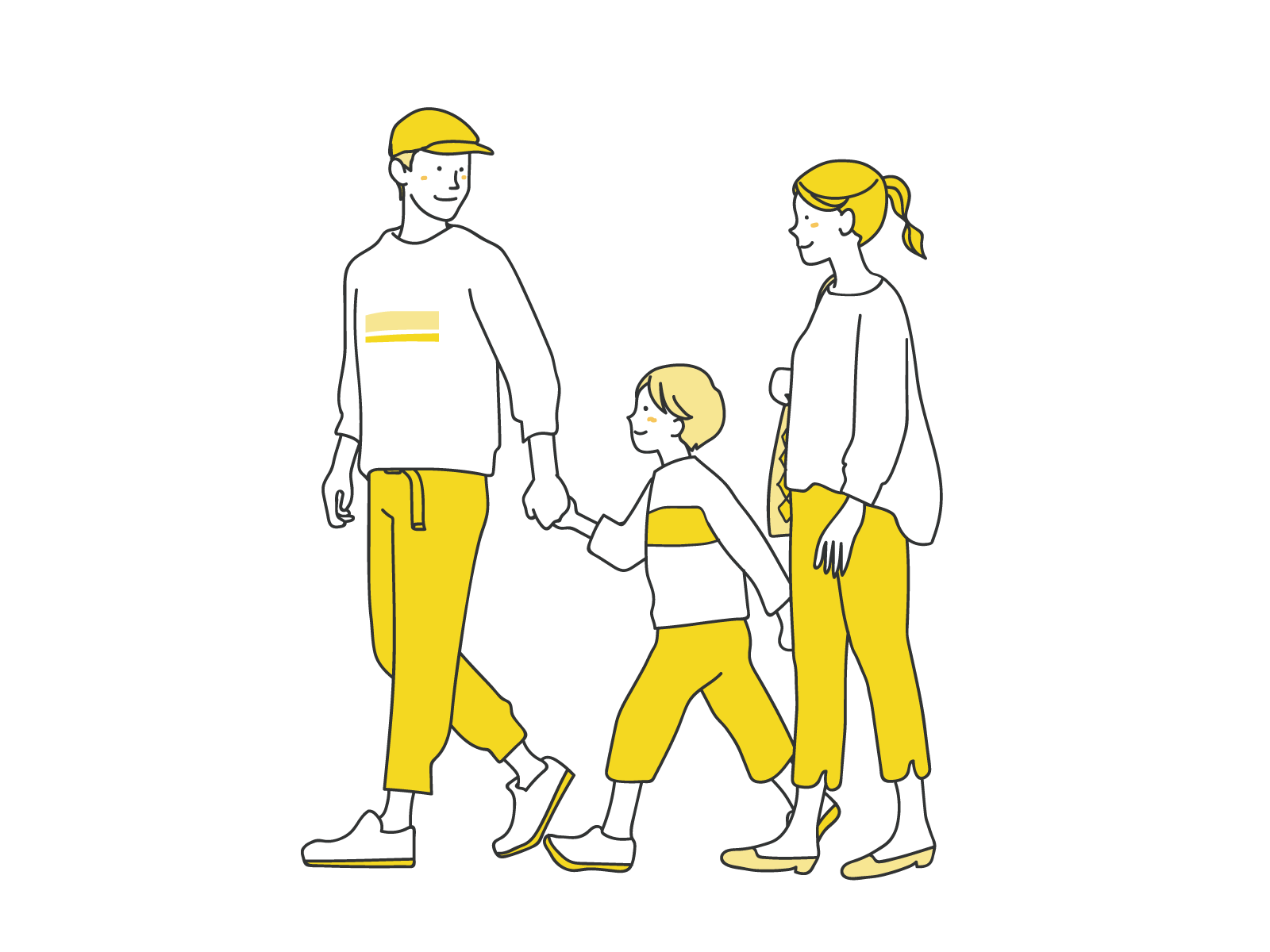
例えば、次のようなストーリーです。
渡航したお子さんは、やがて数年が経過し、ついに日本に帰国する日がやってきました。それも以前、住んでいた街に戻ることになり、学校も出国前に通っていた学校に決まりました。
お子さんはいそいそと昔の仲間に連絡します。友達も大変よろこんでくれました。
登校初日、お子さんは慣れ親しんだ制服を再び身につけ、学校に向かいます。今日からまた以前のような楽しい毎日が始まる。そう考えると自然と気持ちも高まります。
こんなはずじゃなかった
このようにして始まった日本での学校生活。最初の数日は元気に登校していたお子さんですが、だんだん朝起きてくるのが遅くなり、体調も思わしくない様子。
心配になった親御さんは、夕食後に話を聞いてみることにしました。最初はなかなか気持ちが言葉にならなかったお子さんですが、しばらくたって一言、
「こんなはずじゃなかった」。
よく話を聞いてみると、友人とうまくいっていないとのこと。「一緒にいても話題も合わないし、なんかよそよそしいんだ。『どうしたの?』と聞いてみても、『別に』としか言わないし、私だけが浮いているみたい。みんなも気を使ってくれているみたいなんだけど、それがかえって疲れる。あんな人たちだったっけ……」と寂しそうに話します。でも休み時間は、今でもその友達と一緒にいるのだと言います。
海外に行く前からずっと仲良しだったのに、どうしてこんなことになったのでしょう。一体どうしたら良いのでしょうか。
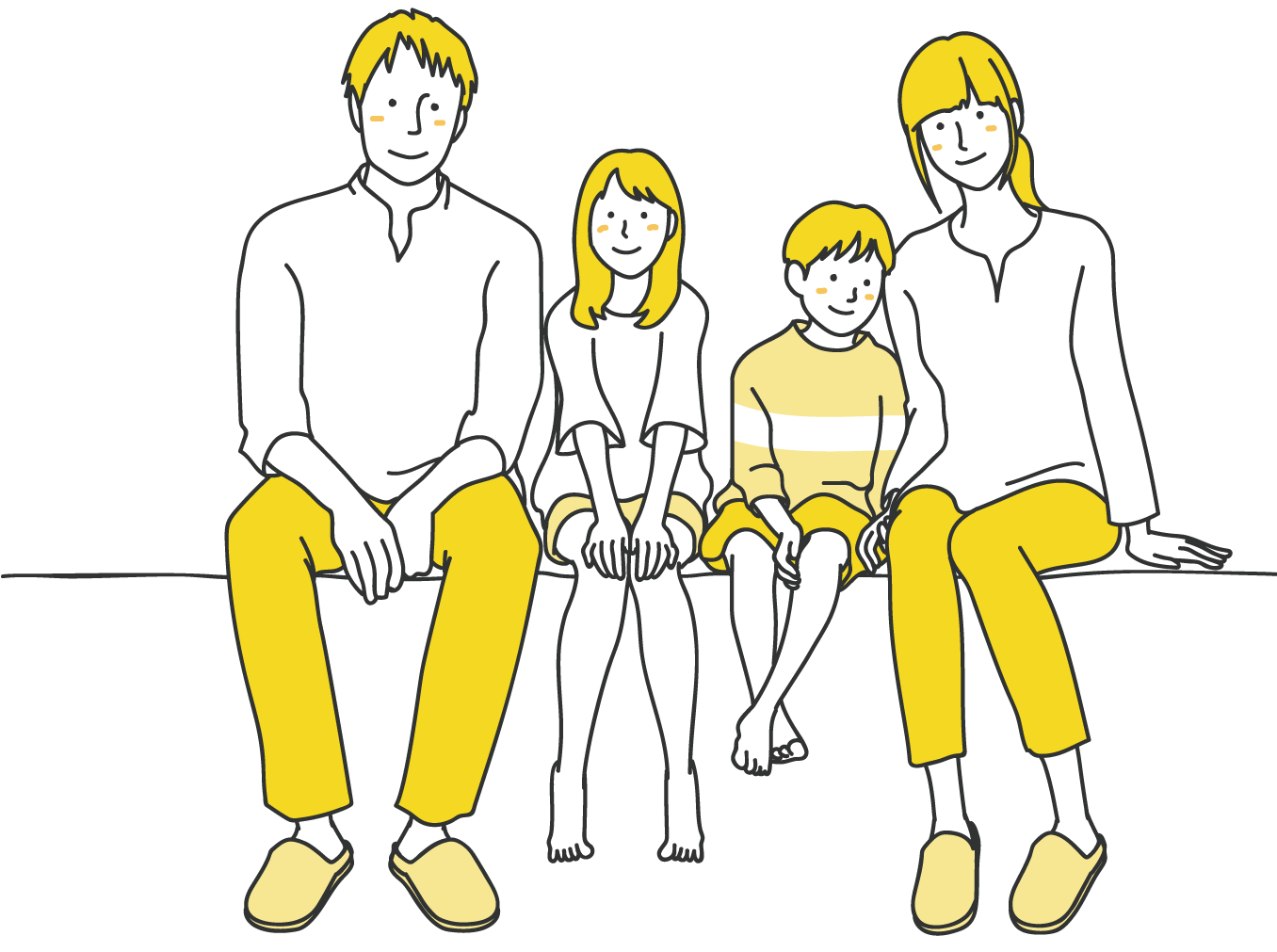
仕方のないことかも
以前はいつも一緒にいて、海外にいる時も、ずっと親しく連絡を取り合っていたのに、帰国してみたらうまくいかない。
これはある意味仕方のないことかもしれません。誰が悪い訳でもないのです。かつては何でも共有していた仲の良かった友達も、お子さんが海外にいる間に、それぞれに自分の道を歩いているのです。もちろんお子さんもそうです。異なった環境で過ごした数年の間に、お互いずいぶん遠く離れてしまったのかもしれません。
数年ぶりに海外から戻って、昔の仲間に再会する。以前であれば帰国したお子さんも、迎える側も、お互い一定の距離感を感じつつ、慎重に関係を再構築していったかもしれません。
それが冒頭に書いたように、SNS等の普及により、表面的にはつながっていられるので、そのあたりの意識が前より希薄になる傾向があるように感じます。
あるがままの自分で
今回のようなケース、いったいどうしたら良いのでしょう。一番重要なことは、今の自分の気持ち、あるがままの自分を大事にするということです。
以前の仲が良かった頃の関係に戻ろうとして、今の自分を否定することはしてはいけません。まずは友達と率直に話をしてみてはいかがでしょう。案外、友達も同じような違和感を持っているかもしれません。これまで私が見てきた生徒たちも、少し話をすることで以前同様の親しい関係に戻ったことが何度もありました。
大人の関係に
話をしてもうまく行かない、もしくは話自体が成立しない、そういうことも十分考えられます。いえ、その可能性の方が高いのかもしれません。
そんな時は、いつまでもその関係にだけ頼ろうとしないで、新しい一歩を踏み出しましょう。
移動教室など、通常の教室から出て行われる授業に参加する際にこれまで話したことがなかった人とも話してみたり、新たな部活動に参加してみたりしても良いかもしれません。
これは別に、以前の友達との関係を絶て、と言っているのではありません。「その関係にだけ頼ろうとしない」というのは、自分の付き合いの幅を拡げ、「自分の居場所を複数作る」ということです。
交友関係が広がることで、以前の友人との距離感も調整され、無理のない形での関係性ができていきます。以前からの関係を一旦リセットして、いわゆる「大人の関係」を改めて築くということです。
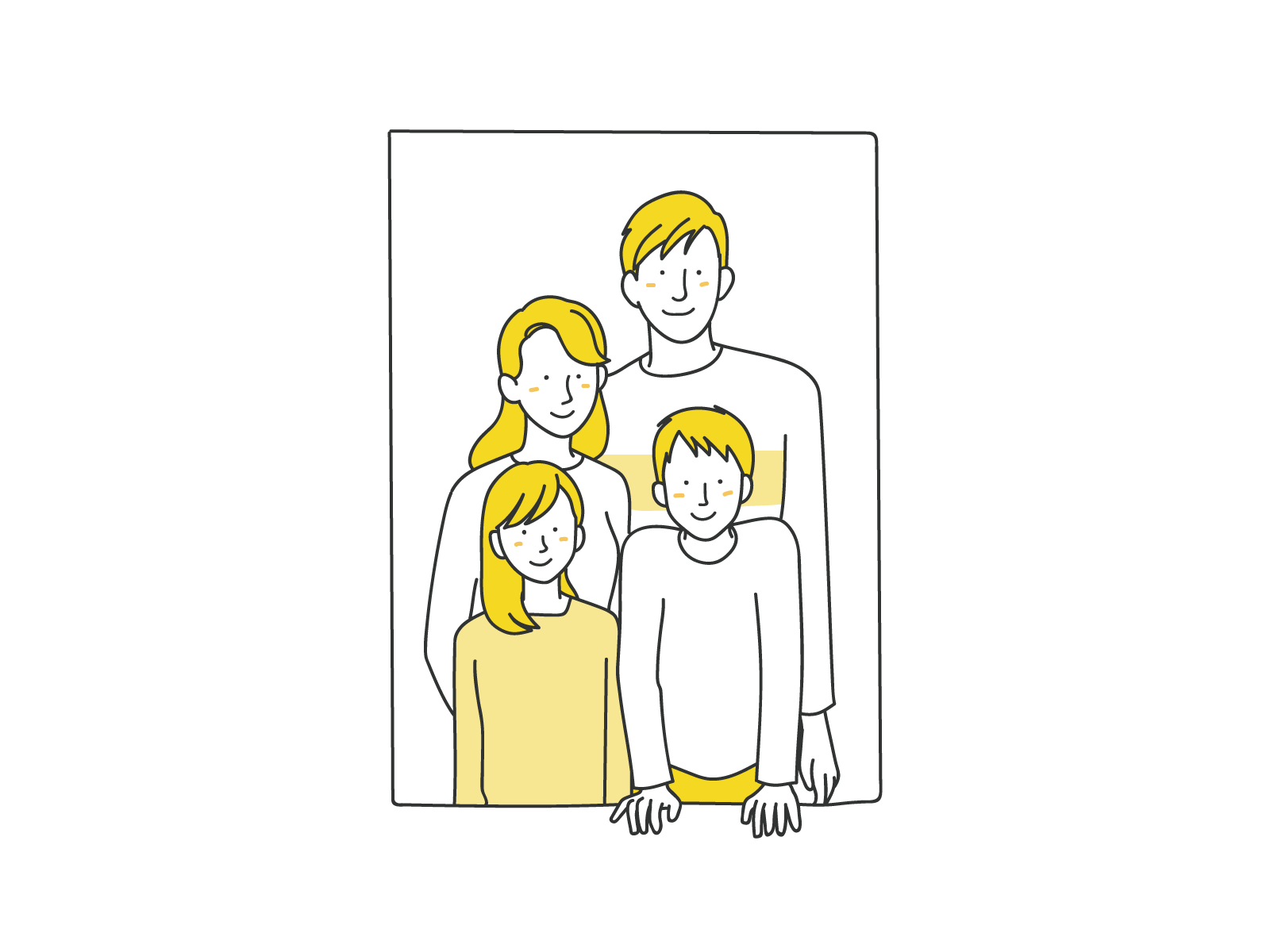
日本に「帰る」?「行く」?
今回のような話は「子どもが成長する過程で、以前の友人との関係性が変化する」という文脈で捉えられがちです。もちろんそういう側面があることも事実ですが、海外で何年か過ごしたのちに帰国する場合、文化的な視点からのケアも必要です。
海外から帰国する、特に出発前と同じ町、同じ家に戻る場合、大人にとっては当然「日本に帰る」「我が家に帰る」と感じられることと思います。慣れ親しんだ環境に戻り、ほっとすることでしょう。
しかしお子さんにとっては事情はまったく異なるかもしれないということを、周囲の大人、特に保護者の方は意識しておく必要があります。
お子さんにとって、海外で過ごした期間がたとえ2、3年であっても、大人と比べて人生の中で大きなウエイトを占めます。特に海外の学校制度のもとで学んだお子さんは、その学校生活を通して、そこで使用される言語をはじめ、様々なことを学習し、身につけていきます。
その際お子さんは、その土地の文化や価値観も同時に吸収し、自然に自分のものとしていきます。海外の学校に馴染んだお子さんが日本に戻ること、それは大人の場合とは異なり、慣れ親しんだ海外での環境を離れ、日本という「異国に行く」と表現するのが適当な場合もあるのです。
海外に向けて出発する際には、お子さんが文化の違いに戸惑わないよう、十分心を砕いた保護者の方も、日本に戻るときには「帰国する」との安心感からその配慮を怠りがちです。
お子さんは、安心している保護者の姿を見て、「自分も大丈夫」と思ってしまい、あまり心の準備をすることもなく、日本での学校生活をスタートしてしまいます。
こうして起こるのが「逆カルチャーショック」と呼ばれるものです。「外国に行くのだから、文化の違いはあって当たり前」という覚悟を持って臨んだ出国時とは異なり、不意打ちを食らうように発生する「逆カルチャーショック」は、海外に行った時よりも深刻になるケースがあります。
お子さんが帰国後、学校に馴染めないと訴えた時には、この「逆カルチャーショック」である可能性もあります。お子さんによっては、学校でうまく行かないことを「自分のせい」だと思って自分を責めたりします。
まず、お子さんには「これは誰にも起こりうる普通のことだ」と伝えて安心させ、その上でどうしたら良いかを話し合いましょう。 お子さんが学校で、どのように感じているかをよく聞き、寄り添うようにしてください。必要なら学校の先生にお子さんの気持ちをお伝えしましょう。
JOESの教育アドバイザーは、同様の事例を多く見てきています。お子さんと一緒に教育相談をお受けになることもご検討ください。
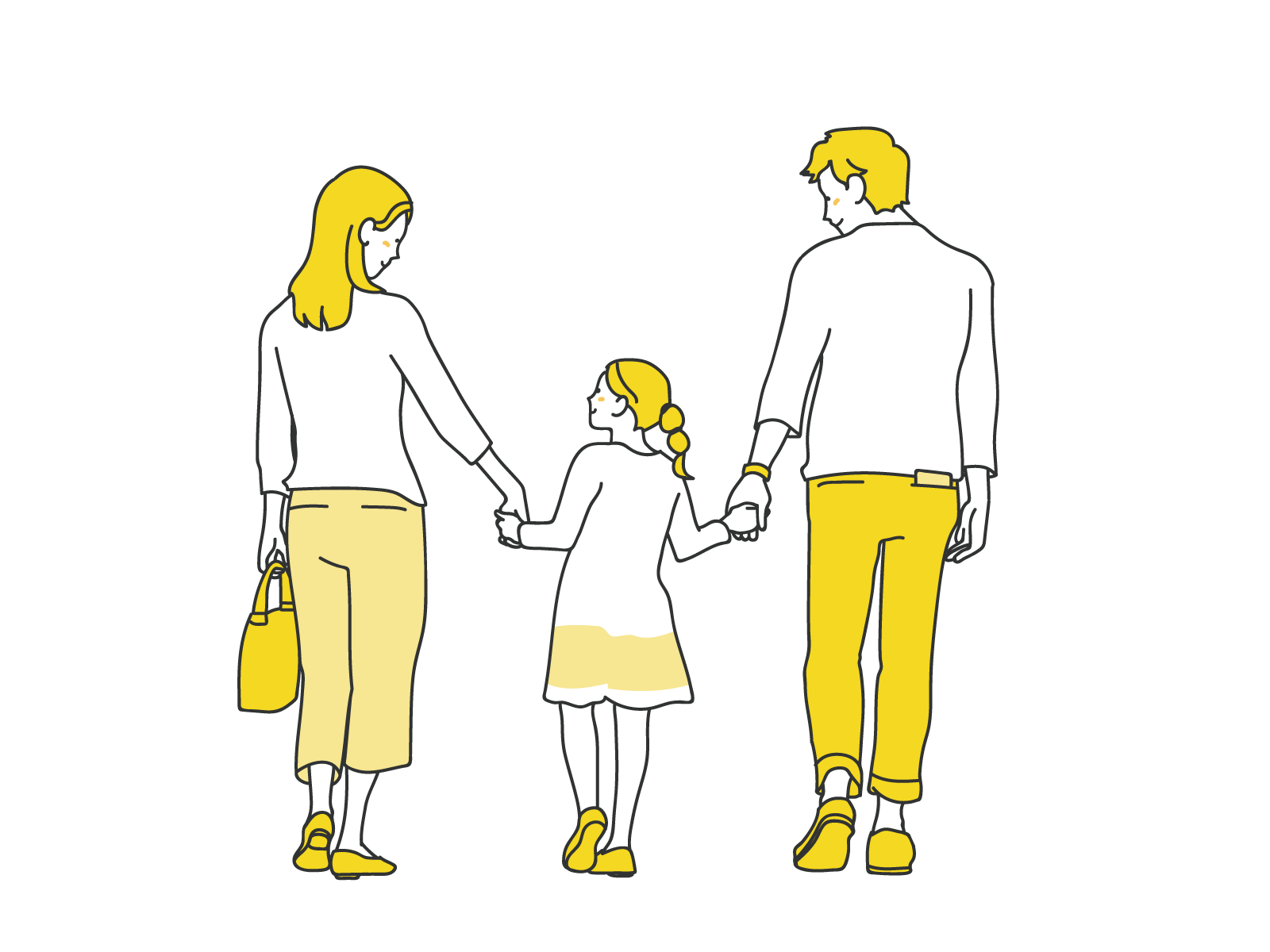
終わりに
今回のようなケースで一番大切なのは、保護者の方がお子さんの気持ちに寄り添い、「あなたの側に立っている」ということをお子さんにしっかり伝えることです。そうすることでお子さんも安心して日々の学校生活に向き合うことができるようになります。
前向きな気持ちで毎日を送ることで、学校での人間関係にも変化が起こり、楽しく学校に通えるようになる可能性は十分あると思います。
<回答者> 海外子女教育振興財団 教育アドバイザー 熊野 孝(くまのたかし) 1959年に帰国生受け入れを開始した桐朋女子中学校・高等学校に39年間勤務し、長年にわたり教頭・国際教育センター主任として海外からの帰国生受け入れ業務全般と、学校の異文化理解教育プログラムの立案・運営に携わる。1975年から約4年間ニューヨークで過ごした元帰国。2024年より現職、帰国生受入校コンシェルジュも兼任。