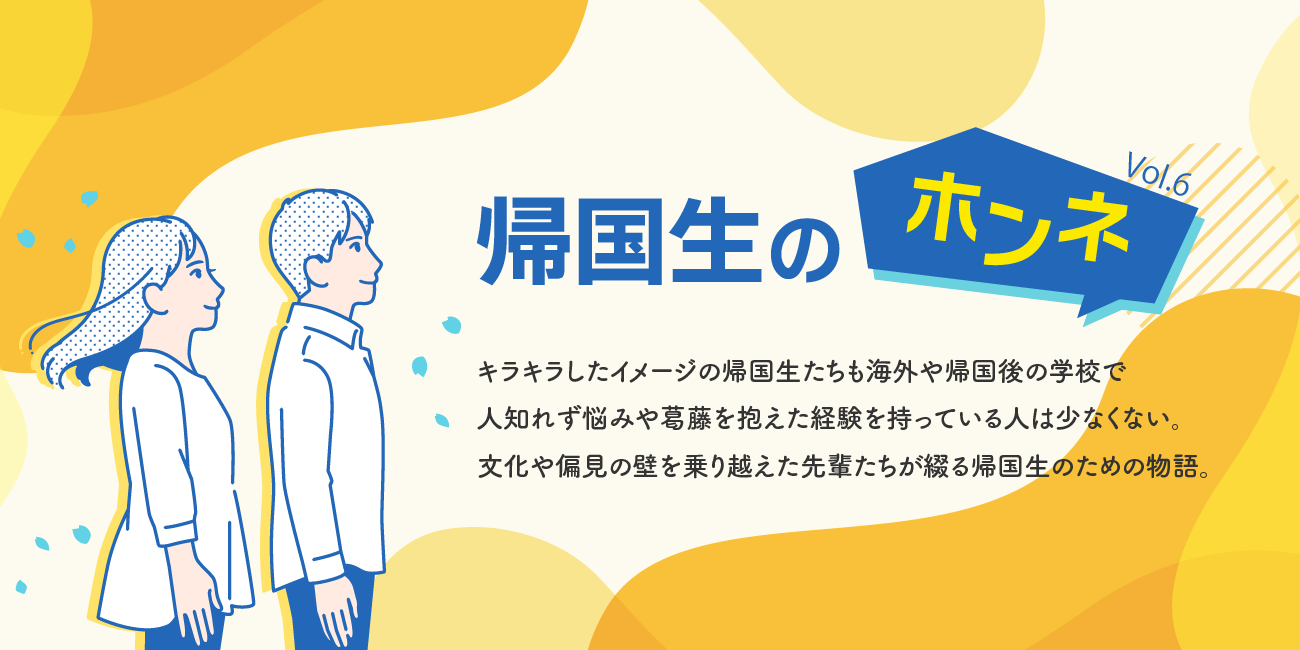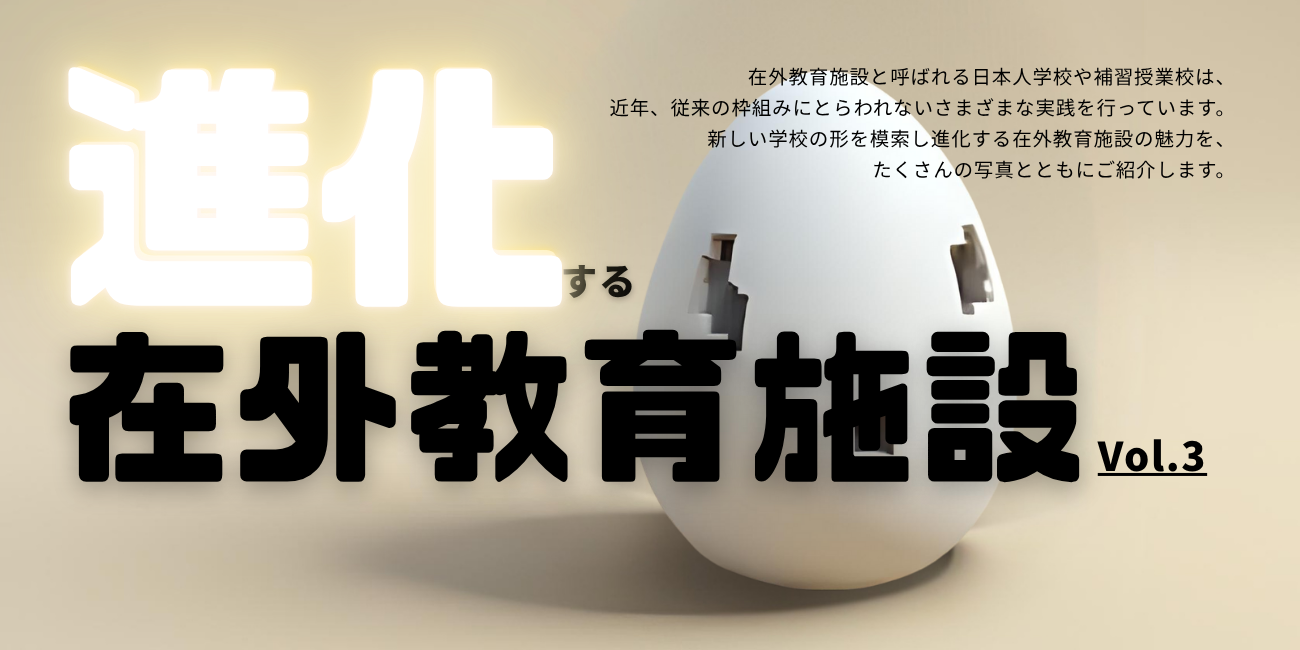海外子女教育振興財団主催の第46回海外子女文芸作品コンクールの審査結果が発表されました。このたび、特別賞受賞作品をご紹介します。
このコンクールは海外に在住する小・中学生が言語・風習・気候風土・治安など、日本と異なる生活環境の中で感じ、考え、感動したことを日本語で表現することを促すために、1979年から毎年行われています。
今回は、日本人学校や補習授業校に通っていない子どもたちからの作品が大幅に増え、滞在年数に関係なく優秀な作品が散見されました。
良質の作品の応募には先生方の指導や学校としての取り組み、家庭教育の大切さを痛感します。子どもらしい気づきや素直な好奇心に、文章の構成や語彙など日本語の知識を高める機会が加われば、さらに状況や気持ちの伝わる素晴らしい作品になることでしょう。
なお応募作品総数は31,927点(作文=2,484点、詩=2,880点、短歌=6,260点、俳句=20,303点)。すべての部門で昨年度に比べて多くの作品が集まり、コロナ禍以降で初めて3万点を超えました。
これらの作品は予備審査を経て9月19日、海外子女教育振興財団(東京都港区)で行われた最終審査会にかけられ、協議の末、文部科学大臣賞をはじめ、海外子女教育振興財団会長賞、後援・協賛者賞、特選、優秀、佳作が決定しました(特選・優秀・佳作・学校賞の審査結果は弊財団の文芸作品コンクールのサイトに掲載していますhttps://www.joes.or.jp/kojin/bungei)。
なお今年の12月には、作品集『地球に学ぶ 第46回』が刊行される予定です。
文部科学大臣賞
個性が咲く私達の花畑
オタワ補習授業校(カナダ)
小4 東村 萌
「お母さん、今日は寒いかなあ、それとも暑いかなあ。」
最近の私は、春が来て毎朝ウキウキしています。マイナス十五度、時にはマイナス二十度にもなるカナダの冬がようやく終わり、洋服選びが楽しくなるからです。スノージャケットやスノーパンツとももうさよなら。お気に入りの夏服がズラリとならんだクローゼットを見つめ、どの服にしようかなと考える時間が私は大好きです。
母によると、今日の最高気温は十二度。私はきれいな青空のTシャツと、白のレースが付いたショートパンツを選んで鏡を見つめます。
「うん、かわいい!」
着がえ終わった私は、明るいたんぽぽのような元気な笑顔で、スキップするように階段をかけ下りていきました。
すると、母がびっくりした顔で私にこう言うのです。
「今日は十二度しか上がらないんだよ!着がえ直してきて!」
私は首をかしげます。
「十二度しか上がらない、じゃなくて、十二度も上がるんだよ!」
そんな私を見て、母はまたびっくりしていたけれど、いつものおだやかな表情にもどって、「萌が大丈夫ならいいよ。」とうなずいてくれるのでした。
カナダでは雪がとけて、気温が五度をこえると、半そで半ズボンで外を出歩き始める人が多くなります。まるで冬みん中にずっととぐろをまいていたヘビが、春の太陽を感じて大はしゃぎでスキップしながらお散歩をしているかのようです。
私もそんなはしゃいだヘビの一人です。と言っても、私は十度を超えない限り、半そでは着ないので、カナダ人には勝てません。日本人の母は、半そでの人たちを見る度に「信じられない」といつも言っていますが、カナダに住んでいると、これが当たり前に思えるから不思議です。
学校に着くと、私はすぐに校庭で遊んでいる友達にかけよります。
「おはよう!」
親友のマチルダは、真冬と同じようなダウンジャケット。その横で私は半そでにショートパンツ。あまりにも自分達のかっこうがちがうので、
「暑くないの?」
「寒くないの?」
と、声がぴったりと重なって、思わず二人で笑ってしまいました。
周りを見わたすと、みんなの服そうはバラバラ。サマードレスや半そでの子もいれば、あたたかいセーターやブーツの子もいて、それぞれ快てきに感じる服を自由に選んでいます。おしゃれというよりは、動きやすい服そうの子ばかりです。
小学二年生の冬、私は日本に一時帰国をしました。小学校にも通いましたが、子ども達の洋服がおしゃれでおどろきました。レースやリボン付きのかわいい服だけではなく、着方にもこだわりがあるのです。Tシャツをスカートやズボンの中に入れたり、シャツのすそを結んだり、おしゃれな洋服をさらにおしゃれに着ています。くつ下をくるくると足首まで丸めてはいているのも初めて見ました。みんな、まるでファッションショーに出ているモデルさんのようで、私もまねしておしゃれを楽しみたいと思いました。
私は日本にいる時も、カナダにいる時と同じように、セーターやパーカー、動きやすいレギンスばかり着ていました。周りの子ども達に比べると、なんだか自分が男の子っぽくなったように感じました。だけど、私は自分で選んだ服が大好きです。母はいつも「かっこいいね」「おしゃれだね」、「かわいいね」、とほめてくれます。
カナダの「快てきで自由なスタイル」も、日本の「おしゃれな着方」も、どちらもすてきだなと思います。自分の好きな服を、好きなように着ると、心が空を飛ぶくらいはずむし、自分がかがやいているように感じるからです。
「あっ、これにしようっと!」
今日も晴天。母によると、今日は十七度まで上がるそうです。大好きなドラえもんのTシャツにハーフパンツ。かわいいのに動きやすいのでお気に入りの組み合わせです。くつ下はくるくると足首まで丸めてみました。
「うん、やっぱりかわいいな!」
学校に着くと、今日もみんなの服そうはバラバラ。でも、みんなよく似合っています。ポカポカした太陽が私達を明るく照らすと、みんなの服の色がまるで野原に広がる花のように見えました。色とりどりの、私達だけのきれいな花畑です。
海外子女教育振興財団会長賞
友達はたから物
オースチン補習授業校(アメリカ)
小4 松丸 莉々
私は五才の時に、東京からアメリカに来た。英語は話せなかったけれど、学校の最初の日、おとなりの席の子が私の方を見てニコッと笑いかけてくれた。笑顔のサクセンは私の初めての友達。クラスに日本人は一人もいなかった。英語でみんなが話していることが全くわからなくて、何も話さず一日中だまっていたら、「ドゥーユースピークイングリッシュ?」とクラスメイトから聞かれたりした。話しかけられても分からなければ、「アイドンノー」といつも答えた。休み時間は、一人で絵を描いたり、日本のおばあちゃんに手紙を書いたり、ブランコに乗ったり。「何であの子は一言もしゃべらないんだろう?」とみんなふしぎに思っていたみたい。
学校は好きだし、行きたくないと朝泣いたことも一度もない。先生はいつもやさしいし、意地悪な友達もいない。でも、私は家では日本語で話しているし、みんなとは何かちがうなぁと思うこともあった。
ある日、お弁当にご飯をもって行くと、ある男の子が「何それ?ドッグフードみたい!」と言った。「こんなに美味しいのに、この子はお米を食べたことがないからこの美味しさを知らないんだなぁ。」と私は思った。でも、それからしばらくはお米を持って行きたくなくて、「お弁当にご飯は入れないで。私も、みんなみたいにサンドイッチがいい。」とお母さんにたのんだ。
キンダーガーデンも終わりに近づくころには、友達もふえて、休み時間はみんなと鬼ごっこや鉄棒で遊ぶようになった。
でも英語はまだパーフェクトじゃない。「あなたこのゲームのルール分かる?(英語分からないから)ルールが分からないと遊べないかも。」とある子に言われた。すると「もし分からなければ私を真似したらいいよ。」と、私に言ってくれた友達がいて、それを聞いてみんなも「それは良いアイデア!じゃ、一緒に遊ぼう。」と言った。
「真似したらいいよ」とその時言ってくれた友達は、そこから四年間ずっと私と同じクラス、今では大親友のオードリー。
覚えているのは、好きなおもちゃや絵本を皆の前で発表する「Show and Tell」。最初は何も話せなくて、毎週発表の日には、お母さんにカタカナで書いてもらったメモを持って行って、みんなの前で一生けんめい読んだ。言葉につまってしまうと、先生も手伝ってくれた。
学校では日本語で話さず英語だけ話すようになっていく私に、日本に住むおばあちゃんが「日本語の美しさと日本のきせつの行事も忘れないようにね。」といつもきれいなカードを送ってくれた。日本語のきれいな文字のお手紙も入っている。桜の花やおひな様のきれいなカードを発表の時に見せたら、みんな、わぁっと感動していた。
キンダーガーデン最後のShow and Tellの日。私は初めてお母さんのメモを見ず、自分の言葉で発表した。クラスで一番元気な男の子、リードがおどろいた顔をして急に立ち上がって「すごい!初めて何も見ないで言えた!!」と大よろこびして飛びはねながら大きな拍手をしてくれた。他の生徒も次々と立ち上がって拍手してくれた。先生のミス・マイカスコルも、「本当によくがんばったね、Ⅰ am so proud of you!!!」とたくさんほめてくれた。そして、ミス・マイカスコルは「お友達のことを自分のことのようによろこべるこのクラスもとってもすてきですよ。」とみんなのこともほめた。私は、うれしくて家に帰ってすぐにお母さんに話した。
私はもうすぐ十才、アメリカに来て丸四年。ジムナスティック、サッカー、水泳、バレエ、ジャズダンス、ギター、ミュージカル、ガールスカウト、何でもやってみている。昔の私はとてもはずかしがり屋だったけれど、今では大きなステージでダンスをするのも好き。ちょっと勇気を出せば何だって出来る気がする。最近は仲良し八人組で毎日休み時間にジムナスティックごっこをする。その中には、私の初めての友達サクセンと大親友のオードリーもいる。ランチの時間、私は友達と話して笑いころげている。
ここまで一人で何でも出来るようになったわけじゃない。困った時には、先生、友達、家族がたくさん助けてくれた。アメリカのフレンドリーで笑顔で助けてくれる文化が私は好き。これからポツンと一人でいる子がいたら、ニコッと笑いかけて話しかけてみよう。困っている子がいたら、やさしく声をかけて助けてあげよう。人のすてきなところは「すごいね!」とたくさんほめてあげよう。私がみんなからたくさんそうしてもらってきたように。
日本放送協会賞
ピースサインが教えてくれた文化のちがい
カナダ在住
小6 曽根 隼人
写真撮影の際、人々はどのようなポーズをとるだろうか。僕は自然とピースサインをしてしまう。日本で暮らしていた経験がある僕は、「写真を撮る」イコール「ピースサインをする」という一連の動作が体にしみついており、無意識に指が動いてしまうほどである。
一時帰国の際に参加した小学校の遠足でも、集合写真では全員が当たり前のようにピースサインをしていた。できあがった写真には、笑顔がより明るく映っており、写真全体が楽しい雰囲気に包まれているように感じた。僕もその写真をとても気に入っていた。
その後、カナダに戻ってからも、僕は何気なくピースサインをしながら写真に写っていた。ところがある日、友人から「なぜ隼人はいつもピースサインをするの?」とたずねられた。僕はとっさに「日本では写真を撮るときによくやるポーズなんだ」と答えたが、その質問がずっと心に残り、後になって深く考え込んでしまった。
思い返してみると、確かにカナダの友人達は、写真を撮るときに特別なポーズをとることは少ない。彼らは自然な笑顔を見せ、歯を出して明るく笑い、仲間と写るときには肩を組んだり、寄りそったりして、親しみや楽しさを表現している。その自然さと一体感に、僕は以前から心地よさを感じていた。
その日の出来事を家に帰って母に話すと、母からも興味深い話を聞くことができた。かつて母がギリシャを旅行した際、現地の人に写真撮影をお願いしてピースサインをしたところ、相手はみ間にしわを寄せ、明らかに不快そうな顔をしたという。また、ケーキ屋でケーキを二つ買う際に、人差し指と中指で「二」というジェスチャーをしたところ、にこにこしていた店員が突然無表情になったという経験をしたそうだ。調べてみると、そのジェスチャーには「くたばれ」というぶじょく的な意味があり、かつて犯罪者に物を投げつける際に使われていた歴史があるという。
この話から僕は、国や文化が違えば、同じジェスチャーでも全く異なる意味を持つことがあると学んだ。そして、自分の国では普通のことが、他の国では失礼に当たることもあるため、誤解を避けるためにも、異なる文化や習慣について事前に知っておく必要があると感じた。
僕はそれまで、「ピースサイン」イコール「平和の象徴・勝利のしるし」といった意味が世界中で共通だと思い込んでいた。しかし、その考えは一面的で、視野がせまかったと気付かされた。
一方で、自分の国の文化を紹介することが交流のきっかけになる場合もある。日本ではピースサインは写真撮影時の定番ポーズであり、楽しさや親しみを表す手段として親しまれている。若者の間では「小顔効果」があるとも言われ、ソーシャルメディアなどでもよく使われている。これを外国の友人に紹介することは、自分の文化への理解を深め、視野を広げることにもつながる。
僕が暮らしているカナダは多民族国家で、様々な文化や価値観を持つ人々が共に生活している。その中で、異なるふるまいや考え方に触れることはとても興味深く、学びが多い。しかし、「郷に入っては郷に従え」ということわざがあるように、新しい環境に入ったときには、その土地のマナーに従う姿勢も大切だ。例えば、カナダでナイフとフォークを用意しているのに、「自分の国では手づかみが普通だから」と、手で食べ始める人がいたら、多くののカナダ人はとまどうだろう。このように相手の文化を尊重する心はとても大切だ。
実は、僕に「なぜピースサインをするのか」と聞いた友人が、最近そのポーズを真似してくれるようになった。僕はそのことが嬉しかった。自分にとって当たり前だった文化が、相手にとって新鮮で興味を持ってもらえることがあるんだと気付いたからだ。同時に、もし何も聞かずに「変だ」と思われていたら、誤解されたままだったかもしれない。だからこそ違いを知り、伝え合うことが大切だと思った。
僕はこれまで、「自分の常識」イコール「世界の常識」と思っていた部分があったが、それはとてもせまい見方だった。国際社会で生きるということは、相手と違って当たり前という前提で人と接することだ。そして、その違いに出会ったときにはすぐに否定せず、なぜそうするのだろう、と興味を持つ姿勢が大切だと思う。写真一枚の中にも、国や文化によっていろんな意味が込められていることを知った今、僕はこれからも「伝える」「学ぶ」「尊重する」という三つの姿勢を大切にしたい。そして、自分の文化に誇りを持ちながらも、他者との違いを受け入れられる広い心を持った人間になりたい。