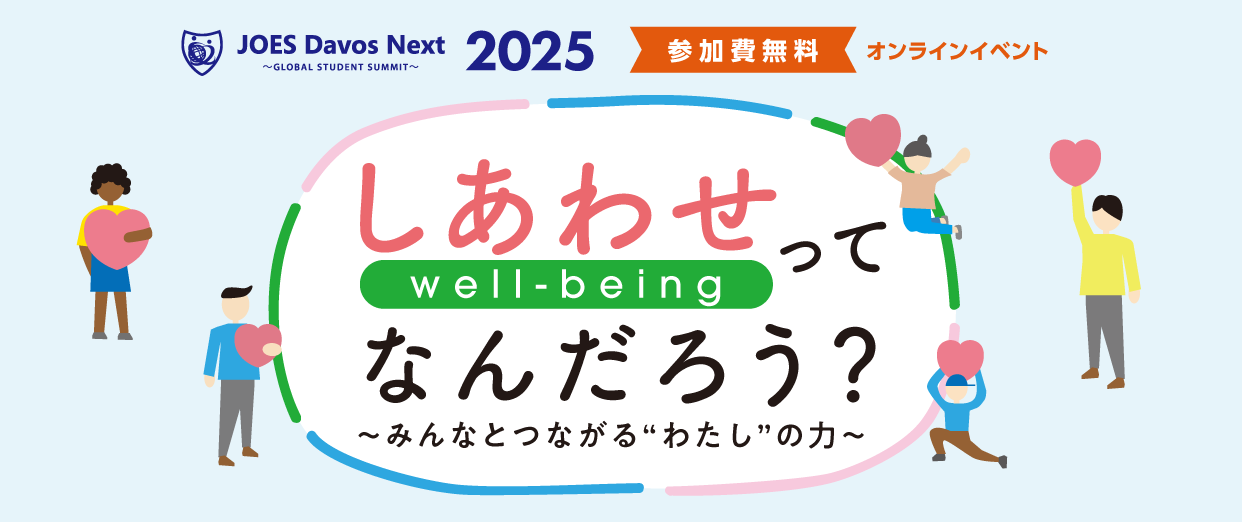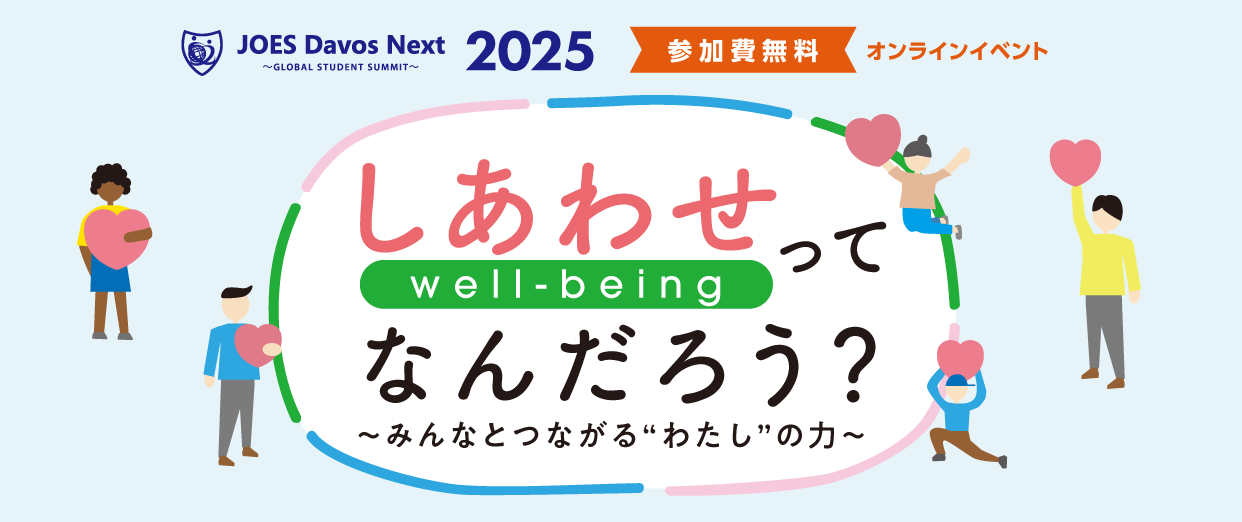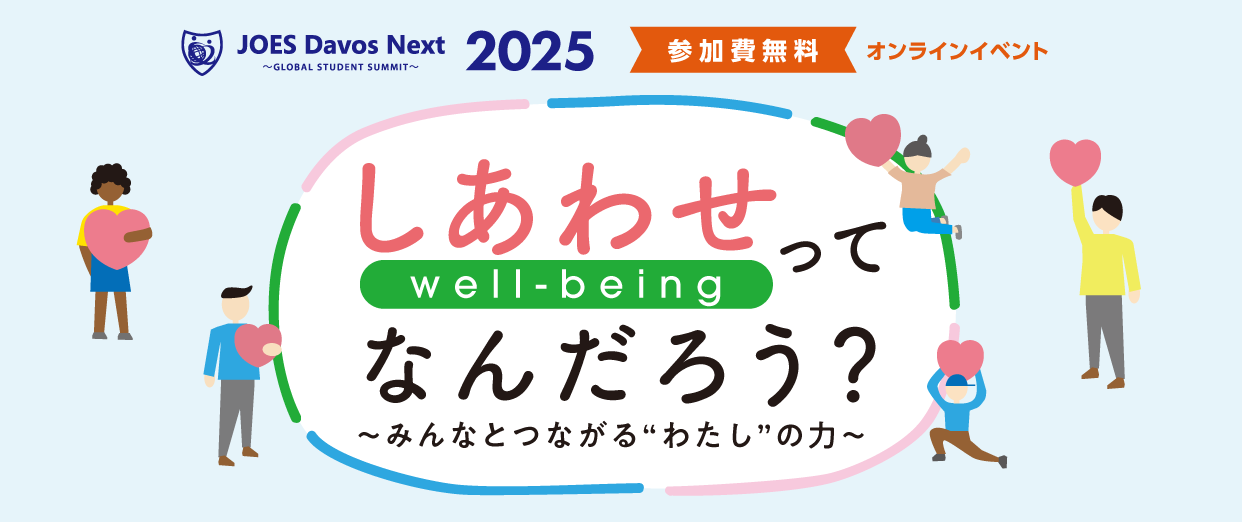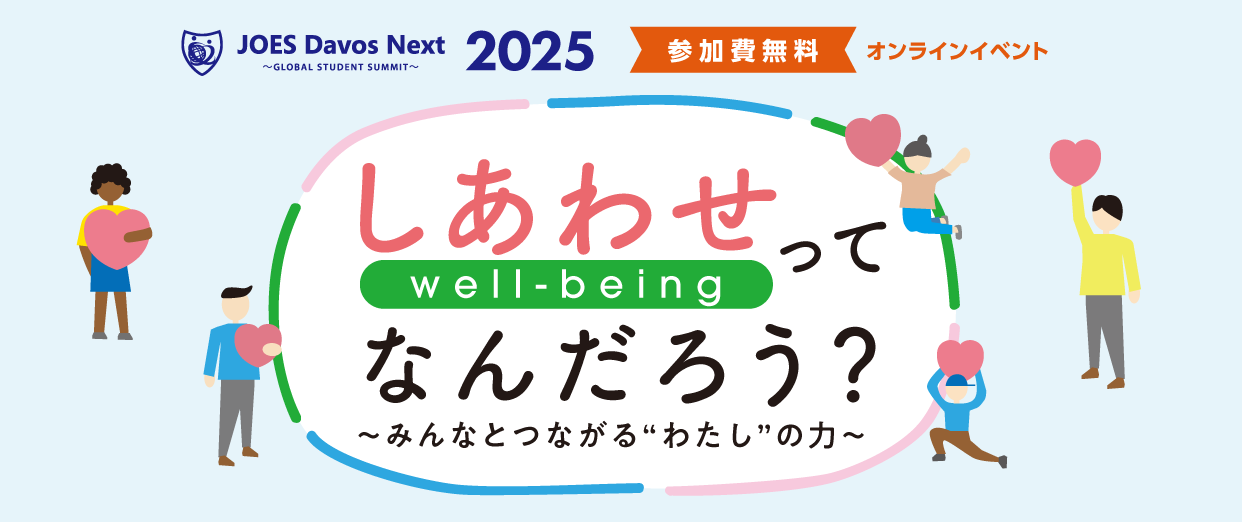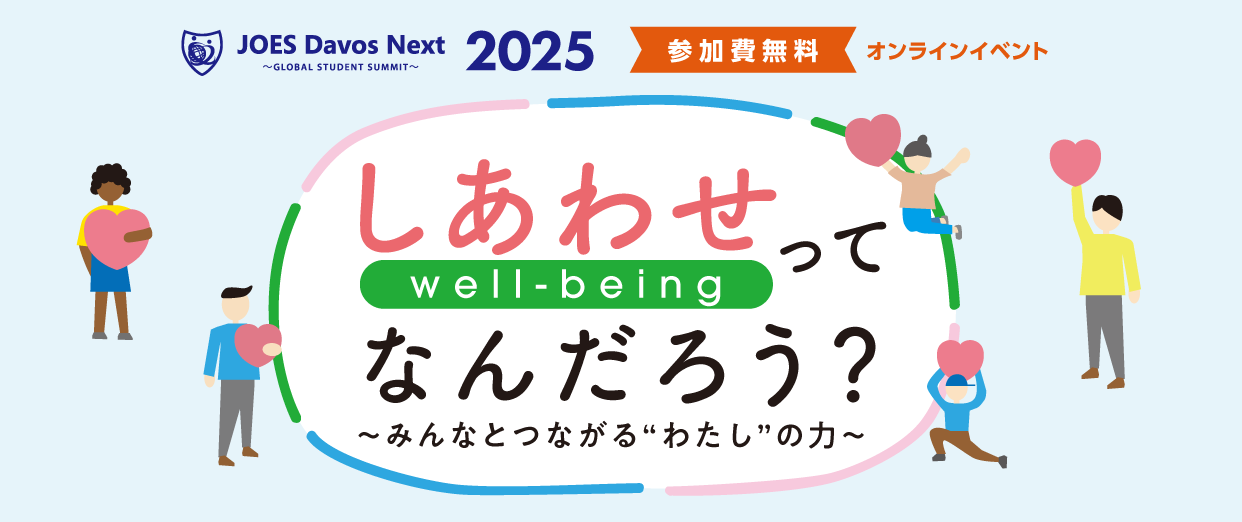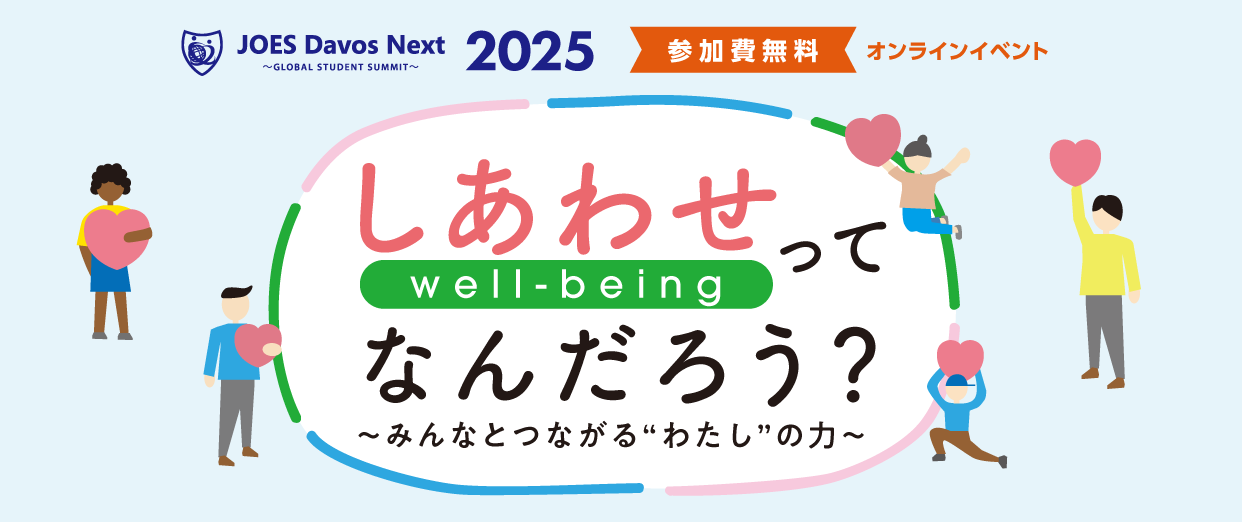過去3回のJOES Davos Nextにおいて、基調講演の司会やQ&Aセッションの司会者として子どもたちからの質問を先生に投げかけてきたフリーキャスターの桑原りささん。参加者にリピーターの多いJOES Davos Nextですから、子どもたちにも保護者にももうすっかりおなじみになりました。イベント当日の司会だけではなく、高校生・大学生ファシリテーターへの研修も担当するほか、運営委員として、JOES Davos Nextを立ち上げ時から強力に支えてくださっています。
4回目を迎える今年度のJOES Davos Nextにも、桑原さんはもちろんご登場いただきます。今回の基調講演講師の馬奈木俊介先生から、桑原さんはどんなお話を引き出してくださるのでしょうか。
ヨーロッパ出張中の桑原さんは、イタリアの素敵な街角のカフェから、オンラインでJOES Davos Nextへの想いを語ってくださいました。
(取材・執筆:只木良枝)

——JOES Davos Nextとの最初の出会いは?
10年ほど前、ある会合で、後にJOES Davos Nextの運営委員をされることになる辻村清行先生(現・東京女子大学客員教授)と出会いました。それ以来、辻村先生と色んなお仕事をご一緒させて頂きました。
今ではオンライン会議は当たり前になりましたが、世の中がまだオンライン会議に馴染みがなかった当時から、先生が「未来は世界中がオンラインでつながって、世界中の人とリアルタイムで会議したり、海外の大学の授業を受講したりすることが普通になる」と、熱っぽくお話しされていたことをよく覚えています。
「そんな機会があったら手伝って」と言っていただいたので、私もいつか実現したらいいなあと思っていたのですが、新型コロナ禍をきっかけとしてオンラインミーティングが爆発的に普及して、それが現実のものとなったのです。 そんな中で、辻村先生からJOES Davos Nextの構想をお聞きしました。「世界中の子どもたちをオンラインでつないで、普段は話を聞くことができないような専門家たちと共に、みんなで地球の未来を考えよう」というお話に、「今のこの時代だからこそできる最高の企画だ!」と思いました。
——JOES Davos Nextは、基調講演+Q&A+グループディスカッションというスタイルを基本にしつつ、毎回少しずつ実施方法が違いますよね。
山中伸弥先生(第1回)と山崎直子宇宙飛行士(第3回)の講演は先生によるレクチャーで、私はその司会をしました。第2回の阪口秀先生の講演では、聞き手をつとめました。今回の馬奈木先生の基調講演は対話形式になる予定です。馬奈木先生のお話をどう引き出せるか、とても楽しみにしています。
Q&Aセッションは、子どもたちが超一流の専門家に直接リーチできるという、最高の機会ですよね。とてもJOES Davos Nextらしいセッションです。 講師の先生に投げかける質問は事前に受け付けていますが、当日の配信中にリアルタイムで入ってくるものもあります。すべての質問には意味がありますから、できるだけみんなが興味を持っている質問をピックアップできるようにしようと思っています。いくつかの質問を関連づけることもあります。
先生の魅力が視聴者の皆さんに伝わるように、また、「今ここだけで視聴できる」というユニークな内容を引き出せるようにと心がけています。
——参加者の子どもたちについて、どんな印象をお持ちですか?
海外に住んでいたり、海外生活を経験していたりする子どもが多いからでしょうか、子どもたちの思考がグローバルで、しかも多様性に富んでいて、いつも感心しています。「自分が小学生・中学生の頃に、ここまで知っていたかな、考えていたかな」なんて思うこともありますね。
それと、複数回の参加者が想像以上に多いですね。特に、最初は参加者側だった子が、翌年は高校生になってモデレーターとして参加し、ディスカッションを引っ張ってくれる姿を見て、その成長を嬉しく感じています。
——桑原さんにとって、JOES Davos Nextとはどんな存在でしょうか?
希望です。
世界中にいる子どもたちがつながり、共通の課題について一緒に考える。そんな場は、他にはないのではないでしょうか。世界の子どもたちがつながるプラットフォームとして機能していってほしいと願っています。
JOES Davos Next がこれまで一番大切に守ってきたのは、大人が正解を押し付けるのではなく、「子どもたちが自分たちで考えて解を見出していく」ということですよね。
ものすごい速さで新しい時代が進む中、正解が教科書に書かれているわけでもなく、また、私たち大人の考えが正解とは限りません。そんな時代に生きる子どもたちには、自分で考える力をつけてもらいたいです。
住んでいる場所が違うと、文化や価値観もそれぞれ違ってきます。その違いを持った人たちがつながって、違いを認め合い、理解しようとすることこそが、世界をよくしていくことだと私は信じています。JOES Davos Nextは、そういう場になれると思っています。
——さて今年のテーマは「しあわせ(ウェルビーイング)」。ちょっと抽象度が高いような気がしますが?
たしかに「ウェルビーイング」って形として見えにくいので、どう伝えるかは課題ではありますね。でも、「ウェルビーイング」は、私たちにとって極めて身近な事柄です。でも今までは見過ごされてきた。最高にいいテーマだと思っています。
実は「ウェルビーイング」は、私自身にとっても大切なテーマなんです。
新型コロナが流行っていた頃に、ひどい歯痛で虫歯だと思い歯医者を受診したところ、虫歯ではなくて、歯を食いしばっていることが原因だと診察されました。当時は、世の中は暗いし、オリンピック・パラリンピックが延期されるなど仕事も激減。気づかないうちにストレスがたまっていて、食いしばりにつながったようなのです。
そして、意識的に体を緩めてみたら、歯の痛みが一瞬にして消えたのです。その時に初めて、見えないストレスによって心だけでなく自分の体を実際に痛めつけることがあることを実感しました。
それ以来、メンタルヘルスについての学びを深める中で、ヨガと出会いました。ヨガはエクササイズだけが注目されがちですが、呼吸法、考え方、瞑想など多くの要素があります。それらを体系的に学んで言語化していくうちに、当時私が抱えていたモヤモヤを解消することができました。そこから興味が深まって、全米ヨガ協会認定ヨガ講師の資格も取得しました。
——なるほど、桑原さんご自身がウェルビーイングの大切さを実感されているんですね。
はい。とても大きな出会いでした。
馬奈木先生はデータの面からこの「ウェルビーイング」を研究されている専門家です。それをみなさんにどうわかりやすく伝えるか。私にとっても興味深いテーマだからこそ、力が入りますね。
——ところで、桑原さんはいま「しあわせ」ですか?
そうですね。私は、「しあわせ」は、何でも「あたりまえ」と考えないところにカギがあると思っています。あたりまえがあたりまえではないと、自分が気付けているとき。
たとえば、いまイタリア出張中に、この素敵なカフェでオンラインでインタビュー受けていますよね。でもそれってあたりまえじゃないでしょう。さまざまな人の支えがあって、今自分がここにいて、自分がやりたいことをやっている。何かをやらされているのではなく、自分が「意味がある」と考えることを自由にできる。それが可能なのは、私が今、いろんな人々に支えられているからですよね。
人と出会って、人と支え合って今がある。それが自分の原動力になっているから、それを次は人に返せるようになりたいなと思えるんです。
そして、そういう心の幸せって、世界平和につながりますよね。
ユネスコ憲章の前文に、「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」とありますが、まさにそれなんです。
——こういう時代だからこそ、「平和のとりで」を築く努力をしたいですね。今年も世界中からたくさんの子どもたちが参加してくれます。子どもたちへのメッセージをお願いします。
多様な価値観に接してそれを受け入れることは、凝り固まった自分を楽にするという効果があります。そのためにどうしたらいいか。それには、海外の人と交わるのが最もな近道ではないでしょうか。
日本を飛び出して暮らしている子たちは、日々大変なことがいっぱいあると思います。海外から帰国した子もそうでしょう。でも、それは様々な価値観を吸収できる、恵まれた環境でもあるのです。ぜひ、いろんなことを吸収してほしいし、自由な発想で自由に生きて行ってほしいと思います。
——ありがとうございました。今年のJOES Davos Nextも楽しみにしています。
JOES Davos Next 2025公式サイトはこちら
https://www.joes.or.jp/kojin/jdnext
.jpg)