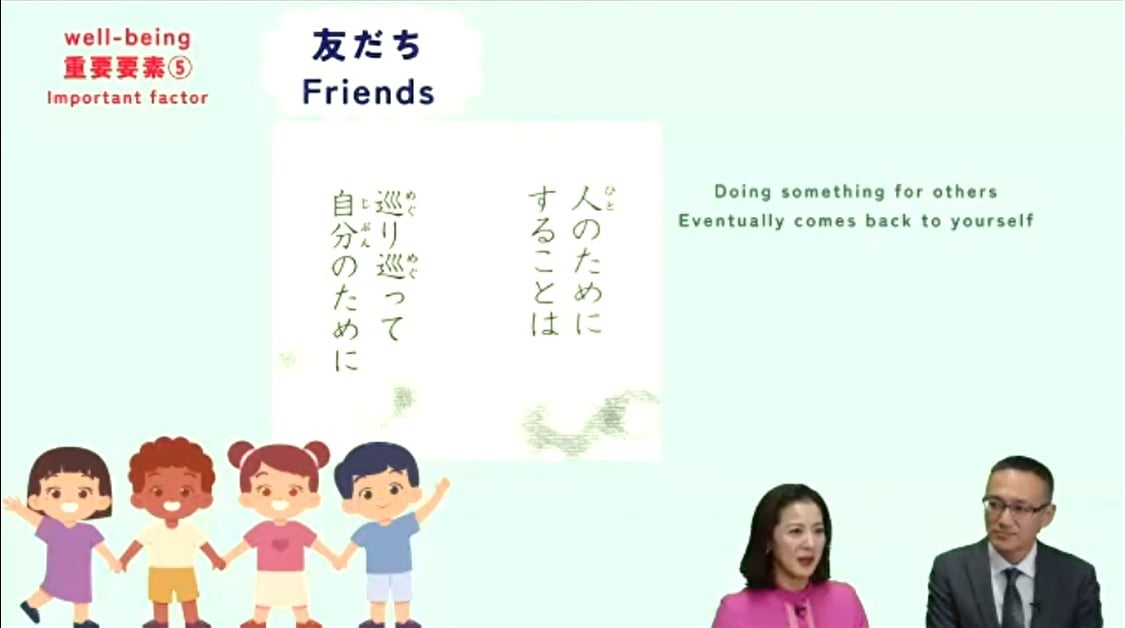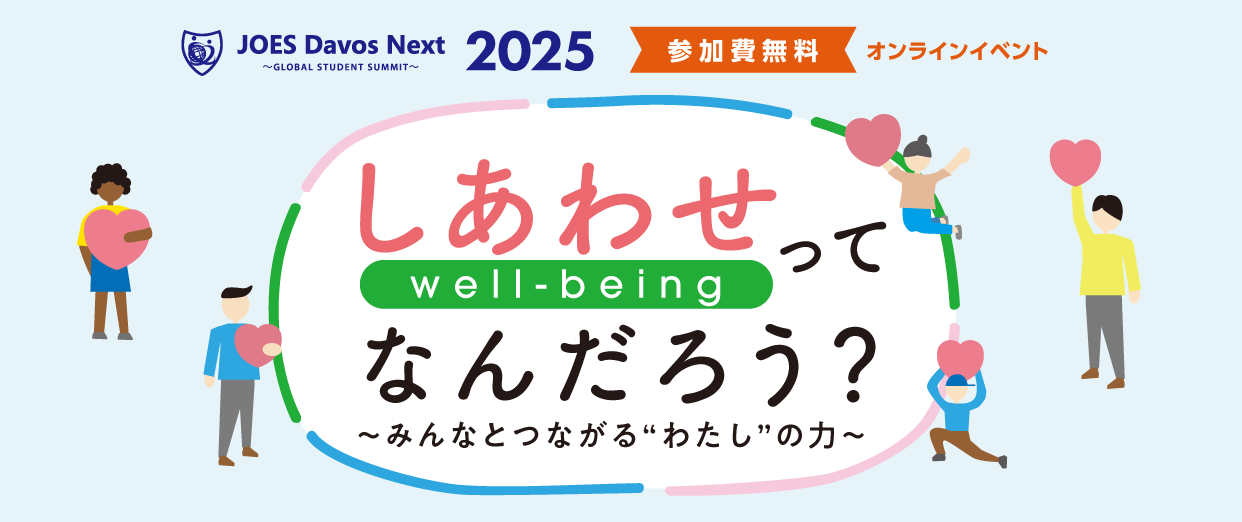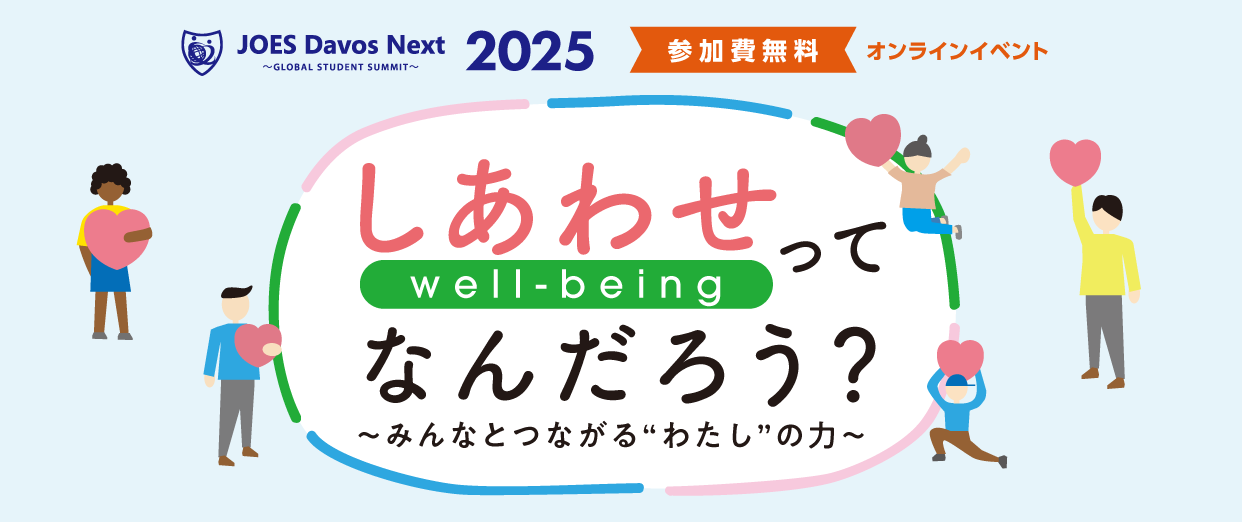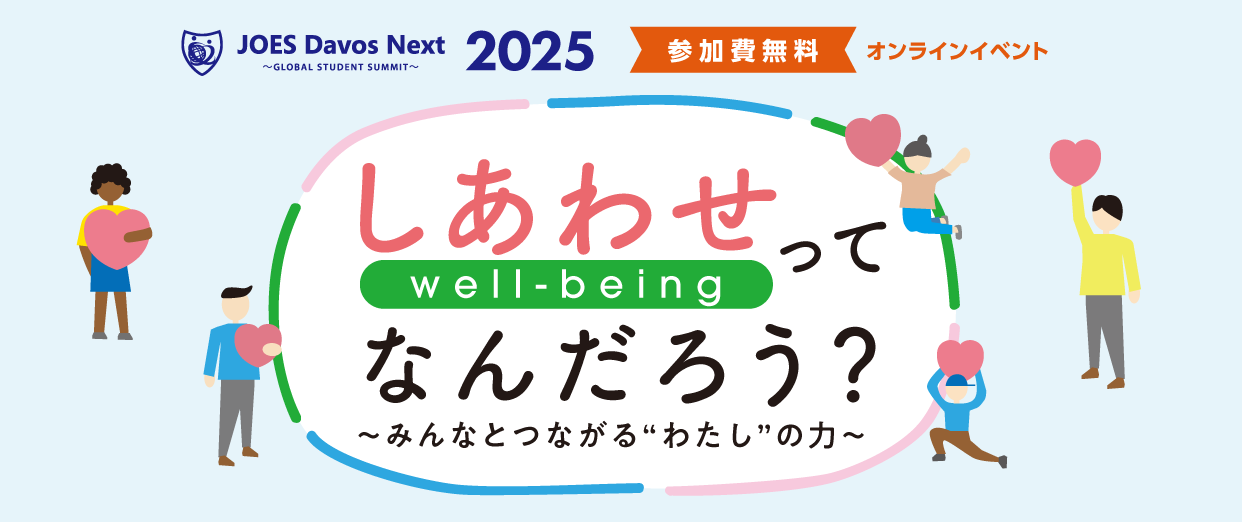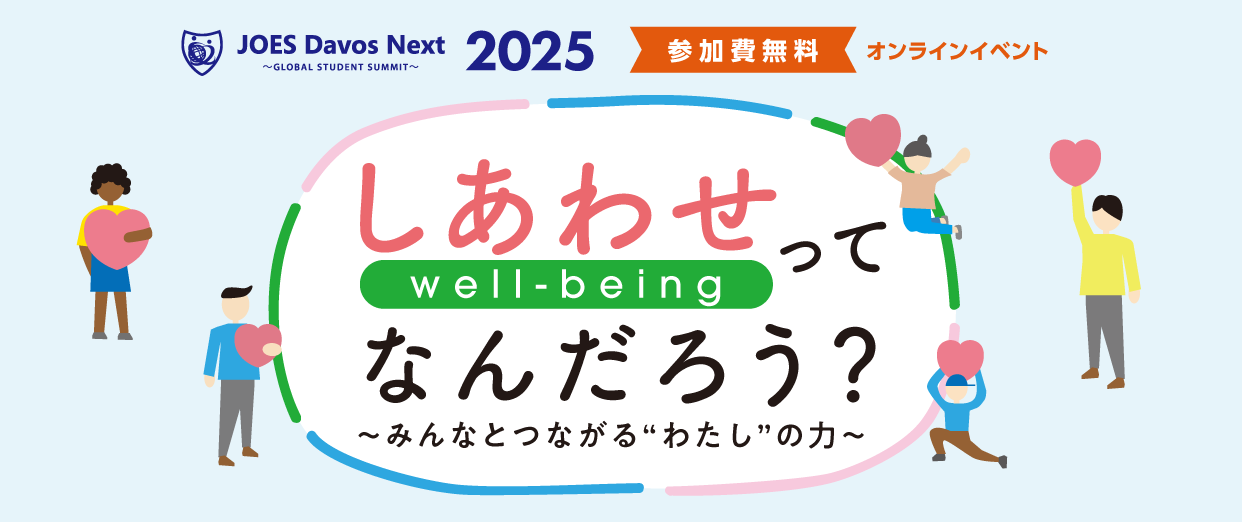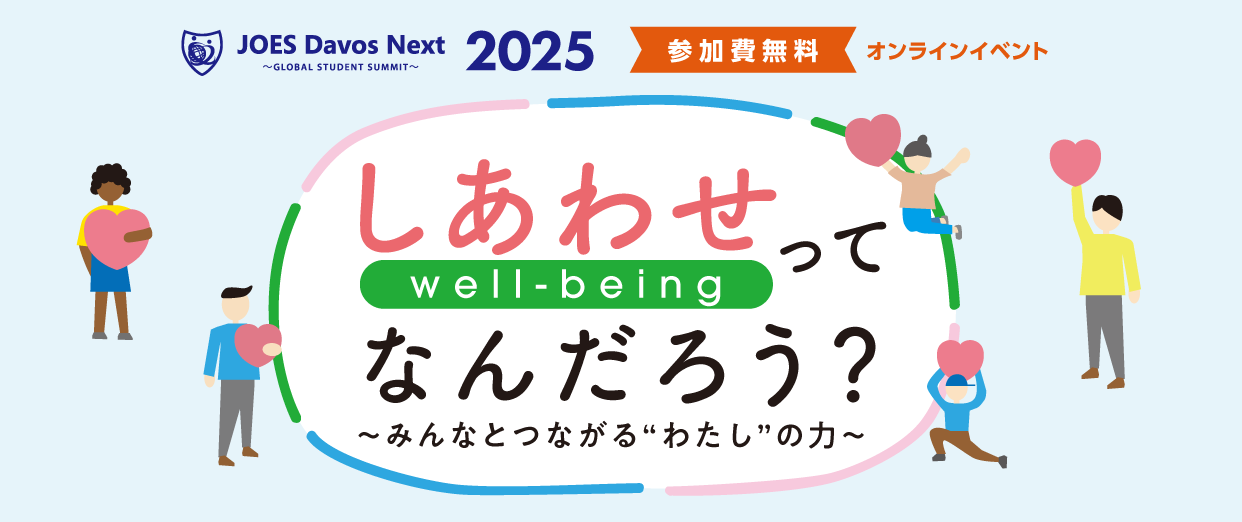青い地球の子どもたち
~JOES理事長綿引宏行インタビュー~
3回目を迎えたJOES Davos Nextは、基調講演オンデマンド配信にはじまり、リアルタイムのQ&Aセッション、オンラインミーティングのグループディスカッションと進み、各グループが成果動画を収録して全日程を終えました。
「宇宙」という、身近なようで遠く、簡単なようで難解なテーマに取り組んだ子どもたち。今回も素晴らしい学びとディスカッションが生まれました。かかわってくださったすべての方に厚く御礼申し上げます。
今回のイベントの締めくくりとして、JOES理事長綿引宏行のインタビューをお送りします。
(取材・執筆:只木良枝)
——今回のJOES Davos Nextも、盛況のうちに幕を閉じましたね。
はい。今、子どもたちによる成果動画を見ているのですが、途中で再生を止めて何度も見返しています。
こんなことをどうやって思いついたんだろう、ここにいたるまでにどんなディスカッションがあったんだろう、などと考えながら。だから、ちっとも動画が先に進みません(笑)。本当に素晴らしい発表がたくさんありました。
——イベントの手ごたえはいかがですか?
家族で話し合う機会が増えた、という嬉しい声が届いています。
JOES Davos Nextのテーマになっているのは、大人たちも未だ解決できない世界的な課題です。親世代だって、その答えを知っているわけではありません。それを、子どもと保護者が一緒に、家族みんなで考えることができたと。
子どもが一方的に教わるのではなく、学校や家庭、地域が子どもと一緒に学び、ともに育つことを「共育」と言いますが、まさにそういう機会を提供することができたのではないかと思っています。
——今回のテーマは「宇宙」で、基調講演はオンデマンド配信されました。
はい。基調講演をしてくださったのは宇宙飛行士の山崎直子さんです。講演の内容は、事前に寄せられた声から、「宇宙からの地球観測」、「宇宙デブリ」、そして「国際協力」に絞り込みました。
基調講演は今回はじめてオンデマンド配信にしました。その結果、配信時間にとらわれることなく、個人の都合に合わせて、また学校現場の時間割に合わせるなど、多様な活用が可能になりました。
それを受けて、ディスカッショングループや学校参加の子どもたちから寄せられた質問に山崎直子宇宙飛行士が答えてくださる場として、Q&Aセッションを設けました。
——Q&Aセッションはリアルタイム配信でしたね。
事前に送られてきていたビデオレターに続いて、ライブ配信中にも質問がどんどん届きました。ファシリテーターの桑原りささんが、うまく場を進めてくださいました。内容は専門的なものから山崎さん個人に関することまで、幅広いものでしたね。山崎さんはひとつひとつ、本当に丁寧にお答えくださいました。
宇宙という未知のものに対する関心の入り口が様々であることがよくわかりました。これらの質問を入り口にして、もっと掘り下げて学んでいこうとする子が、世界中に生まれたのではないかと思います。
——質問のなかで印象的だったのが、「国際宇宙ステーションではみんな仲良くできるのに、なぜ地上では戦争が絶えないのでしょうか」というものでした。
そうですね。ビデオレターで参加したジャカルタ日本人学校の子どもたちから「国際宇宙ステーション(ISS)ではケンカしないのですか」という問いかけがあり、そこに、ファシリテーターの桑原りささんが、「ISSでは各国協力ができているのに、なぜ地上ではそれができずに、紛争が起こるのでしょうか」という、グループディスカッションから生まれた疑問をご紹介くださいました。
これは、大人の私たちを撃つ質問だったと思います。
昨年のJOES Davos Next 2023でも、海の環境保全に関して「どうして大人が決めたルールを大人たちは守れないのか」という質問があったことをご記憶でしょうか。 こんな大事なことを、私を含めて世界の大人たちは未だ解決できていない。今回もまた、それを突き付けられたような気がしましたし、身が引き締まる思いでした。
同時に、大きな希望も感じました。
日本人や〇〇人等という国籍にこだわるのではなく、地球人としての視点を持ってもらいたいというのが、JOES Davos Nextをはじめた私たちの願いでした。それが現実のものになっていると実感することができたのです。
そして、こうした問題意識を持つ子どもたちが、課題を解決する先導役になってくれるのではないかとも思いました。まさに、鳥肌がたつような経験でした。世界的作曲家・シンセサイザー奏者の冨田勲『青い地球は誰のもの』や、ディスニーの名曲『イッツアスモールワールド』が、セッションを視聴している間ずっと、頭の中で鳴っていました。
——参加者も多彩でしたね。
地球のどこからでも、時差があっても、ビデオレターなどの形で参加できるのがオンラインイベントのいいところですね。
今回はじめて、南米ペルーの日系人学校の子どもたちが、基調講演とQ&Aセッションに参加してくれました。
たまたまJOESの別のプロジェクトで一緒に活動している日系人学校にこのイベントをお伝えしたところ、「日本人の子どもたちとつながれるよい機会、喜んで参加したい」と。世界的な科学者や宇宙飛行士と子どもたちが直接やりとりできる素晴らしいイベントだと評価してくださり、初参加にいたりました。
また、工学教育に力を入れているアメリカの公立学校に通う生徒も、基調講演を視聴して質問を寄せてくれました。
——グループディスカッションは今年も盛り上がりましたね。
そうですね。参加者はもちろんですが、ファシリテーターが今年も期待をはるかに超える大活躍をしてくれました。
ファシリテーターの多くは海外で育った経験を持っていて、縦割り活動の楽しさや面白さ、楽しさをよく知っているのでしょうね。ディスカッションのレベルも高くなってきていると感じます。
そして今年も、昨年の参加者がファシリテーターになってくれた例がありました。これはイベントを毎年続けてきたからこそのことですから、本当に嬉しいですね。特に高校生のファシリテーターが増えてきています。
——グループディスカッションには、頼もしい「助っ人」の存在もありました。
宇宙は漫画やアニメの題材もなっていて子どもたちにはおなじみである反面、実際に行くことは極めて難しく、自分の目で見ることができない。身近ではあるけれども、距離がある存在でしょう。それがディスカッションのテーマになるわけですから、ある程度前提となる専門知識の理解が必要になります。 そこで、日本の宇宙開発を担う宇宙航空研究開発機構(JAXA)と、宇宙開発フォーラム実行委員会(SDF)に協力を依頼しました。
JAXAの方々は第1回ディスカッションの後に「ミニ講演会」として、山崎さんの基調講演にも登場した超小型の変形型月面ロボット「SORA-Q」について解説してくださいました。ライブ配信だったので、終了後は子どもたちから質問が相次いで大いに盛り上がりました。
宇宙開発フォーラム実行委員会(SDF)は、広い視野から宇宙について語り合う場をつくり、宇宙開発に貢献している学生団体です。ここのメンバーがグループに入り、ディスカッションのなかで出てくる専門的な内容について解説するなどのサポートをしてくれ、丁寧に子どもたちの関心の芽を育ててくれました。
彼らは、宇宙に興味を持って勉強し続けているみずからの姿を、子どもたちに見せてくれました。素晴らしいロールモデルになったのではないかと思います。
——さて、JOES Davos Next 第4回のテーマは「ウェルビーイング」だそうですが。
「ウェルビーイング」、このことばは最近よく使われていますよね。教育振興基本計画にもすでに明記されていて教育現場にも登場しているのですが、実はうまくあてはまる日本語がないのです。
単純に「幸せ」と訳すわけにはいかない複雑な「ウェルビーイング」ということばを、どのように理解したらよいのか。ことばの定義をするのではなく、その内容について子どもたち自身に考えてもらえるようなイベントにしたいと思っています。
——抽象度の高いテーマですね。
このテーマは、みんなでディスカッションしながら考えるというよりも、自分自身との対話が中心になるのではないかとも考えています。今、どんな学びのスタイルが良いか検討を進めているところです。
実は私の中では、JOES Davos Nextの開始当時から第1回から第5回までの流れはすでに決まっています。4回目の「ウェルビーイング」、このために今までの3回があったと言っても過言ではありません。
今回のこのテーマこそ、ぜひ家族と、そして学校や地域の仲間と、対話してほしいのです。今まで積み重ねたJOES Davos Nextという場を活かせば、きっとそれができるのではないかと思っています。
——今年も楽しみにしています。