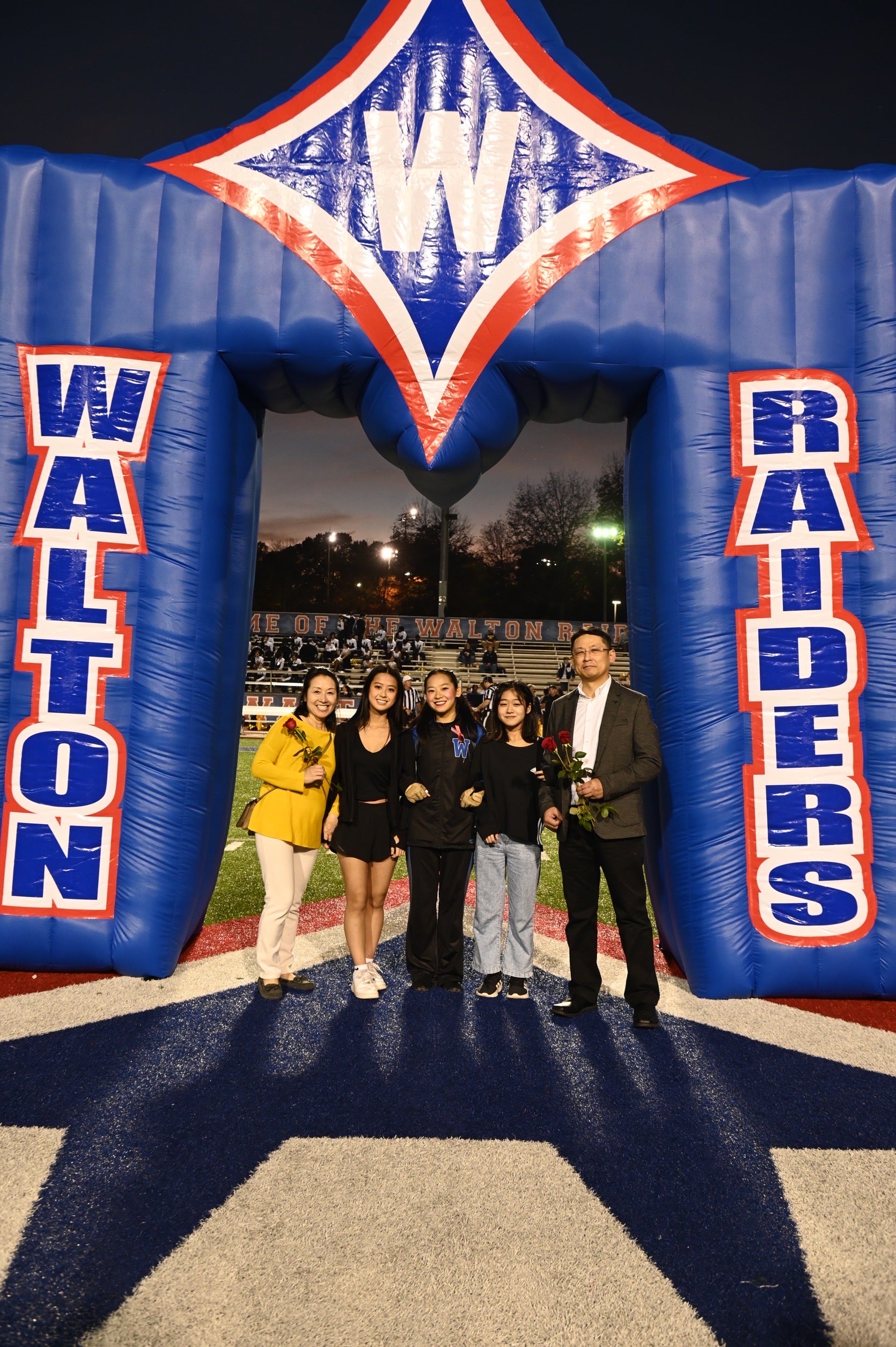イギリス在住の山本佳奈さん。父親の駐在により幼少期をドイツとイギリスで過ごし、小学校6年生で帰国。日本の大学を卒業後、大手企業勤務を経て、ロンドン大学ゴールドスミス大学院にて心理学を専攻し、卒業したばかり。中学受験での帰国、日本の中高時代での苦労や再渡英に至るまで、大学院での研究内容などについて、話を聞いた。
(取材・執筆 Makiko)
イギリスでの原体験と、難しかった日本への適応
—ロンドンで大学院を卒業されたばかりとのこと。どんな研究をされていたのですか?
2歳から少しだけドイツに住み、3歳から12歳までイギリスで育ちました。イギリスではアジア人がほとんどいない、現地の私立校に通いました。小さい頃は自分が日本人だという意識がなく、心はイギリス人なのに、外見だけが違っていると感じていました。小6で日本に戻ると、徐々に日本文化にも馴染み、日系企業で仕事もしましたが、日本にいると今度は外見は同じなのに心が違うという意識が拭えませんでした。このような、いわゆる「サードカルチャー」(注)について考えたいと思い、会社を退職してイギリスの大学院で心理学を専攻しました。
大学院では、言語がその人の性格に及ぼす影響を研究しました。性格には色々な要因がありますが、話す言語の国が集団主義か個人主義かによって個人の性格に影響が出るなど、面白いデータがあります。ただ、言語能力やその人の資質など数値化できないことが多く、一概にはっきりとした結果を出しにくい、難しい研究ではありました。
(注)サードカルチャー:「Third Culture(第3文化)」とは、両親の文化(第1文化)と移住先の外国文化(第2文化)の間の「母国とは異なり、また現地のものでもない」独特の文化 『新版サード・カルチャー・キッズ 国際移動する子どもたち』より抄訳
—12歳まで育ったイギリスではどのような過ごし方をしていましたか?
幼稚園から高校まで一貫の私立の現地校に通っていました。土曜日は補習授業校です。現地校はアジア人がほとんどいないような状況でしたが、乗馬、ダンス、フルート、演劇のほか、季節によって色々なスポーツをするなど、たくさん課外活動をしていました。帰国前には塾にも通いましたが、受験するという実感が湧きにくい環境だったので、勉強をするのは苦痛でしたね。
—帰国子女枠で入った神奈川県の女子校を経て、その後、慶應大学総合政策学部に進学されます。
中学校・高校では勉強で苦労しました。歴史などは学ぶ内容がイギリスと全く違っていて、成績はずっと下の方。英語はもちろんできましたが、帰国生が多くない学校だったので面白いと思えるような授業を受けることができなくて、態度も悪かったと思います(笑)。
自分ではわかりませんでしたが、その頃は周りから「怖い」と思われていたみたいですね。日本語には問題ありませんでしたが、思っていることをストレートに言ってしまうのが、他の子の話し方と違っていたのでしょう。敬語ができない訳ではなくても、同級生ほどうまく丁寧語と組み合わせては使えませんでした。
英語以外の成績が取れないので、大学はAO入試に的を絞ることにして、早いうちから準備をしました。英語の資格をできるだけ取得し、ダンスや演劇を通してコミュニケーションを取ることついての研究を自分で進めました。「英語ができるから楽できていいね」と言われることもありましたが、決して楽な道のりではなかったです。高校生活の大部分をこの研究とAO入試の準備に充てました。
.jpg)
社会人になって見えてきた「サードカルチャー」の壁
—どのような流れで大手企業を退職し、イギリスで大学院に進まれたのですか?
大学時代にインターンをした会社にすんなり入社させてもらえたのですが、社会人になってから、いろんな壁が見えてきたんです。仕事で細かなニュアンスを伝えるときに「英語だったらこう言えるのに」と思う場面が出てきたり、納得できない日本の風習を目の当たりにしたり。私みたいに海外で育つなどの背景を持った、サードカルチャーな人たちについてもっと勉強したいという思いが湧いてきました。自分の貯金で大学院に行ってみたいという目標ができ、社会人生活では人に恵まれたのもあって5年半働きましたが、会社を辞めて大学院に行くことを決めました。
.jpg)
—今後の展望は?
いずれは日本に戻り、サードカルチャーや言語で困っている子どもの助けになれるようなことをしたいと思っています。こちらで学位を取ると、あと2年はイギリスに残れるので、お金を貯めつつ、考え続けていきたいと思います。イギリスでは、ダンスや音楽などの分野と心理学の掛け合わせが盛んなので、そういった視点も取り入れていきたいですね。
ただ、日本では心理カウンセラーの需要が海外より少ないので、本当はそのような方向で励みたいところですが、悩ましいです。
海外での生活が長いのですが、この先も日本人として、日本の「プレゼンス」を上げることに貢献していきたいです。