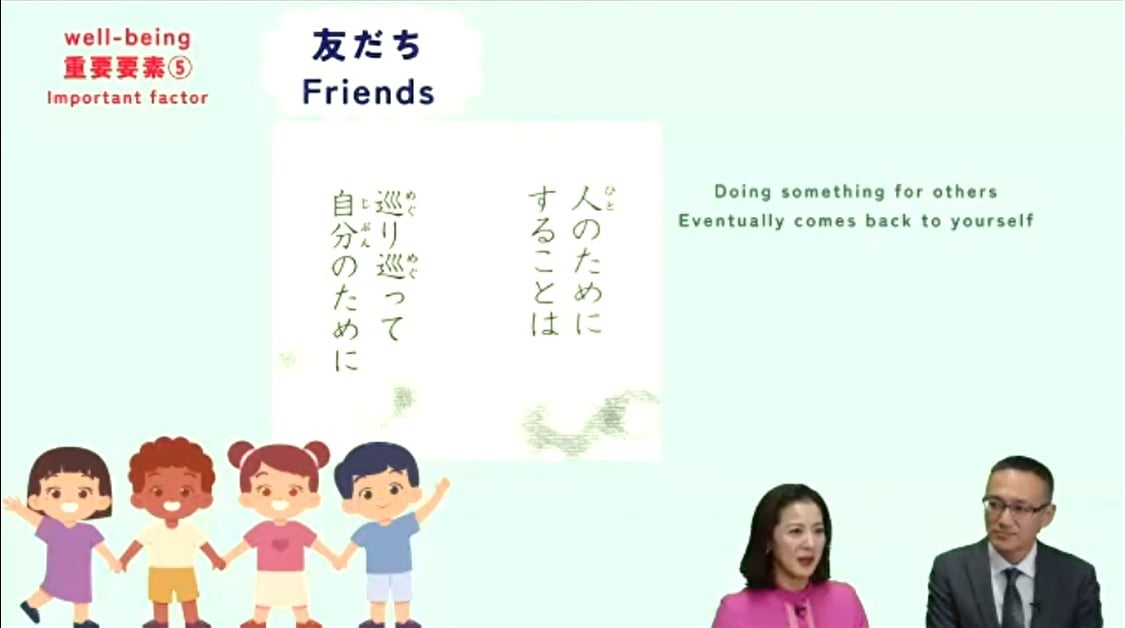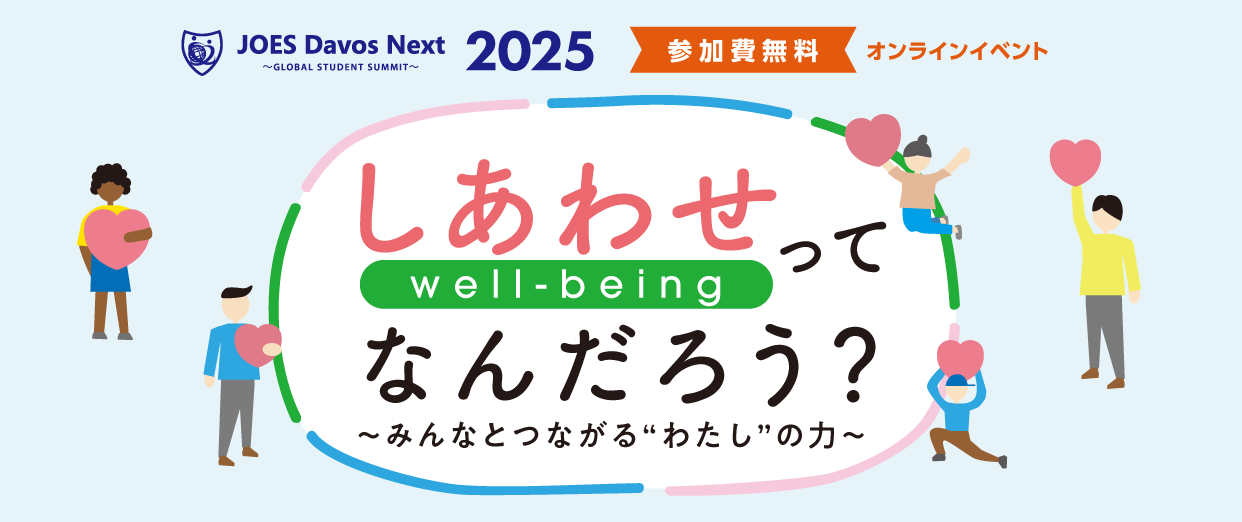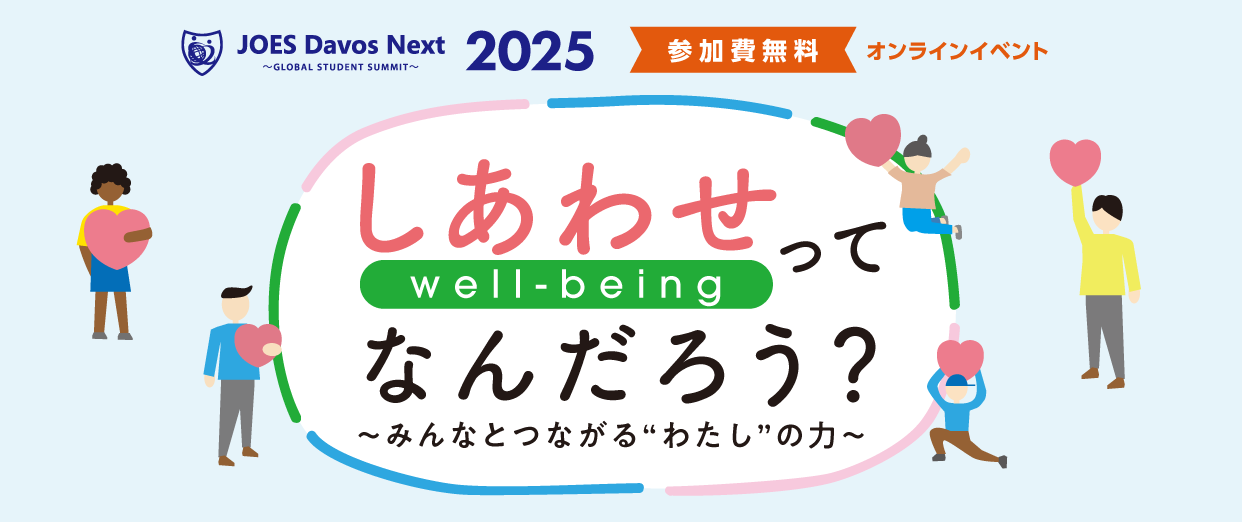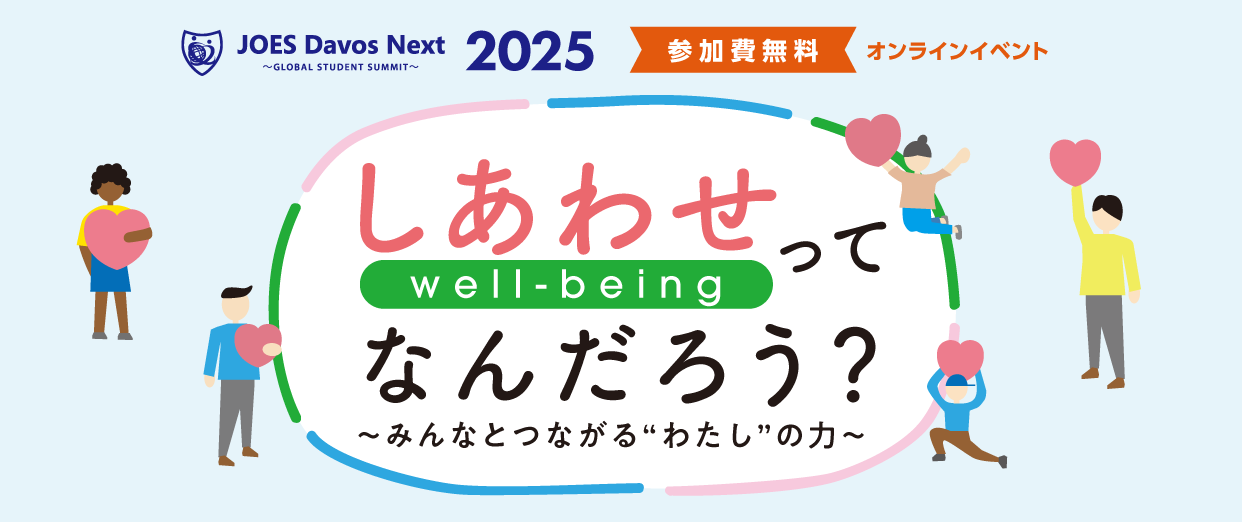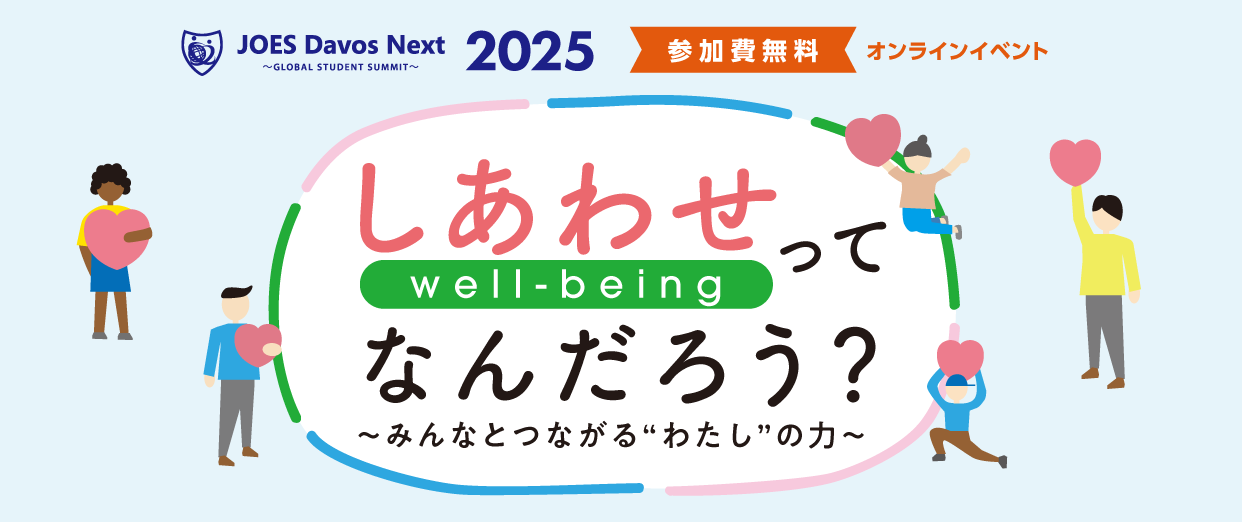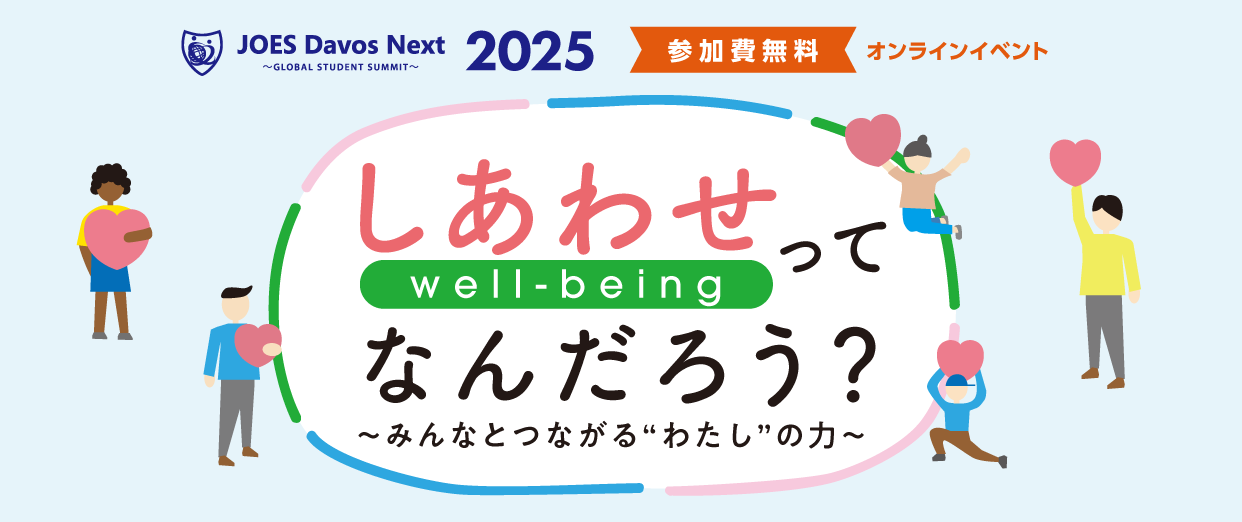世界をつないだグループディスカッション
JOES Davos Nextの主要イベントのひとつであるPART2のグループディスカッションでは、今回も活発な議論が行われました。
日程は1月19日、2月2日、2月16日、そして3月2日。世界中どこからでも参加しやすいように、また、参加者のスケジュールに合わせられるように、日本時間日曜日の午前8時、11時、午後5時の3回設定されました。
2024年12月に公開開始となった山崎直子宇宙飛行士の基調講演を視聴してから迎えた第1回のディスカッションではグループの仲間とはじめて顔を合わせ、続く第2回・第3回は、宇宙と地球の話題について話し合いました。各グループには、高校生・大学生によるファシリテーターと、宇宙開発フォーラム実行委員会(JOESマガジン2025年2号)の大学生が参加して、ディスカッションを支えました。
回を重ねるごとにグループの雰囲気がやわらかくなっていきます。最終回の第4回では各グループが成果動画を録画して、フィナーレを迎えました。この成果動画は、今回もDavos Next特設サイトで公開される予定です。
ところで、子どもたちのディスカッションの様子、気になりませんか。今回、いくつかのグループにお邪魔してみました。その中から、印象的なシーンや発言を紹介しましょう。
(取材・執筆:只木良枝)
ISSの国際協力、地球の現実
2月7日に行われたQ&Aセッションでは、山崎直子さんに、「国際宇宙ステーション(ISS)では国際協力ができているのに、なぜ地球では戦争がおこるのか」という質問がありました(JOESマガジン2025年3月号)。
この問いは、グループディスカッションの中から生まれてきたものでした。
山崎さんの講演のなかで、ISSでは国際協力のもとにプロジェクトが遂行されているということが、子どもたちの心に強く残ったようです。現実社会では、テレビやインターネットのニュースが連日、戦争被害の拡大を報じています。それらを世界各地で日々見聞している子どもたちは、大人たちが思っているよりもずっと深く、戦争や平和について考えているようでした。
「なぜ戦争が起こるのか」「平和ってなに?」「peacefulとは具体的にどういう状態を指すのか?」「safeとは誰が対象なのか?」「国際協力ってどうやったらできるのだろう?」……。
大人でも考え込んでしまうような、素朴であるがゆえに根源的な問いがディスカッションのなかから生まれ、子どもたちは真剣に話し合っていました。ほぼすべてのグループが、多かれ少なかれ、このテーマについて考えていたのではないでしょうか。
あるグループでは、「いじめやレイシズムなど小さい不寛容が、戦争につながっているのではないか」という発言がありました。
ISSでは多文化が共生していて、「お互いの違いを認めて受け入れること」がすでに実現している。「だから、私たちも、本当はいつでもどこでも国際協力ができるはず、戦争もなくせるはずだ」、と展開していくディスカッションを聞きながら、この子たちに託される未来への大きな希望を感じました。
宇宙の話題が、自分たちの話題に
山崎さんへの質問について話し合っていた、あるグループの会話です。
「山崎さんに、宇宙でホームシック感じる?って聞いてみたいよね」
「っていうか、グループのみんなは、日本を離れたり、現地から帰ってきたりして、何かしら、引っ越しって経験しているよね」
画面のなかで、参加者たちがうなずきます。
「ホームシックって感じたことある?」
「あるある」
「私はシンガポールに7年いたんだけど、帰国してからホームシックというか、友達に会いたいなーと思うことはある」
「そうだよね」
「僕は10歳からずっとアメリカに住んでいて、来年本帰国なんだ。むしろ帰ってからのほうがどうしようかと心配になってる」
「わかる! でも大丈夫だよ。日本に帰ってからもこのグループみたいなフレンドリーな仲間ときっと出会えるから、心配しなくていいよ」
JOESにかかわる子どもたちの多くが海外生活を経験し、海外と日本を移動しながら育っています。
ただ、その形は千差万別。日本で育って自国の文化と言語をある程度習得した上で渡航するケースも、反対に、言語形成期を海外で過ごしたケースもあるでしょう。なかには、海外で生まれて全く日本を知らないまま育ち、「帰国」という名の文化的・言語的移動をはじめて経験する子もいるはずです。
さまざまなバックグラウンドを持つ子どもたちと、ほんの少し年上で同じく海外生活を体験したファシリテーターたちが、お互いの経験を話し、共感し、励まし合い、時には不安な子に寄り添う……。
そこには、「宇宙と地球の課題」というテーマについて語り合うだけでなく、お互いの体験や思いを共有できる、あたたかい場が生まれていました。
.png)
日本語版と英語版が用意された