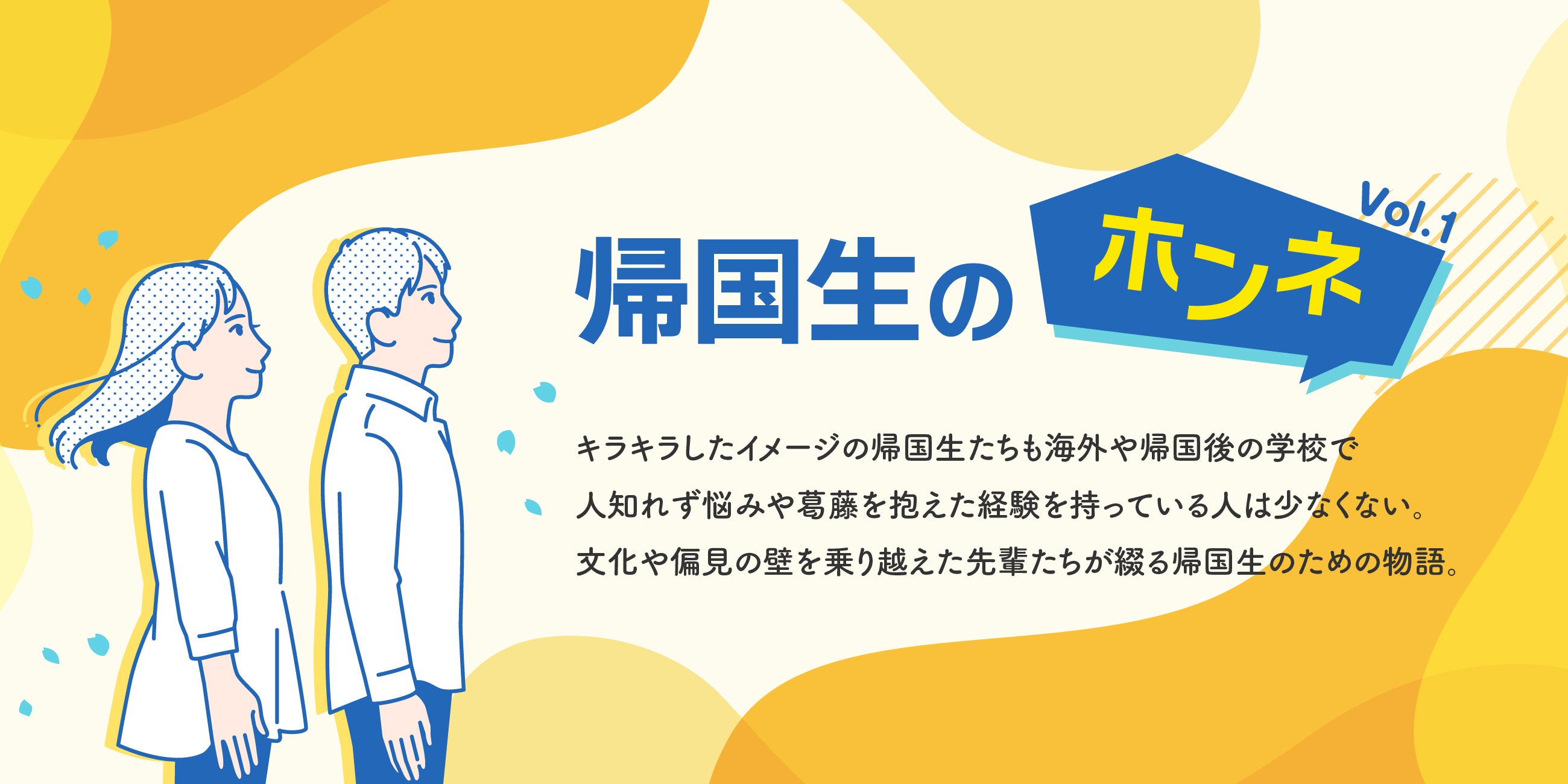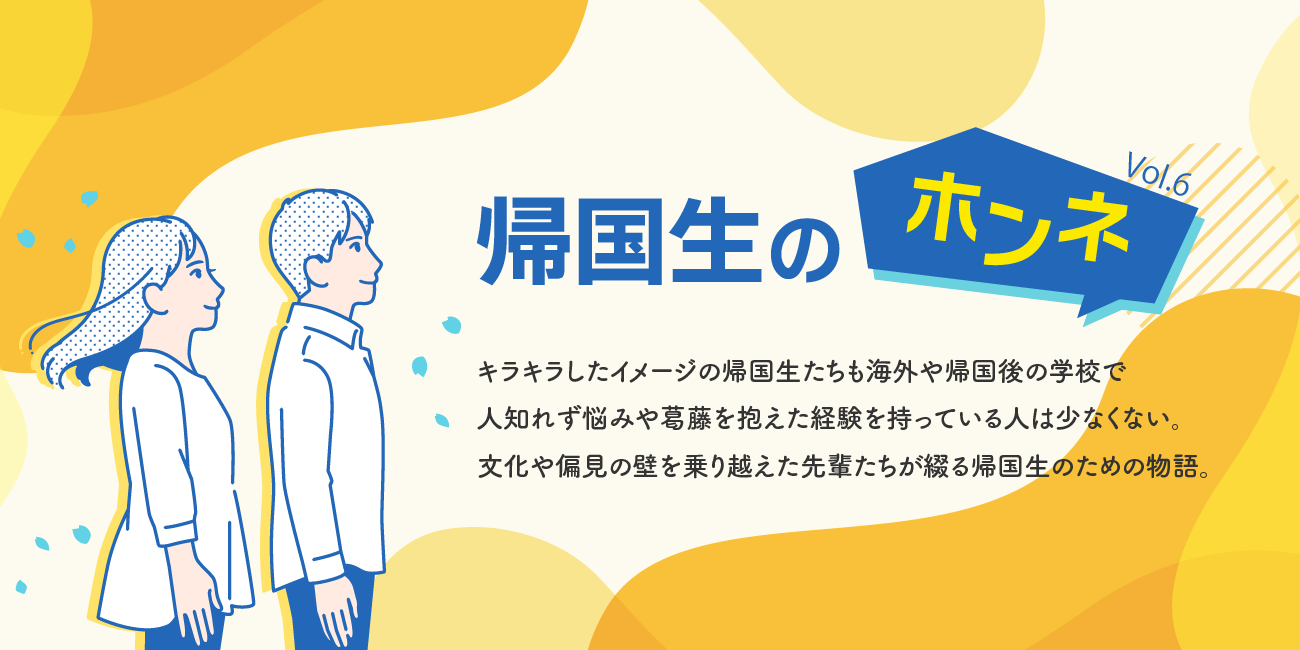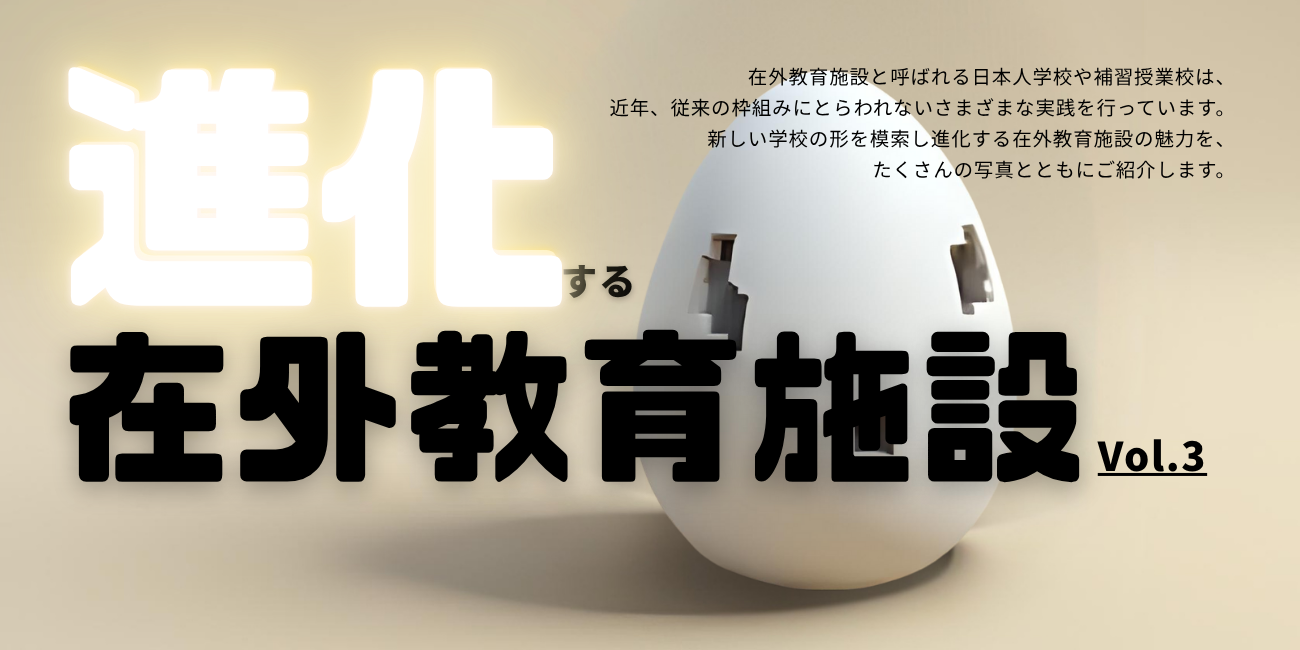.jpg)
小学校の5年間をイギリス、ウィンザーで過ごした渋谷真帆さんは、日本に帰国後、カルチャーギャップに苦しむ数年間を過ごした。あれから20年経った今、イギリスの小学校で学んだのは、「個性の違いを理解する姿勢」だったと振り返る。個性が認められず、「キコクのまほちゃん」のレッテルを貼られた自分に違和感を覚えていた中学校時代に渋谷さんに寄り添ってくれたのは、イギリス時代に出会った「馬」だった。
多様性のなかで過ごした小学生時代
馬は差別をしない——。自分が言おうとしていることを全身で聴こうとしてくれる。イギリスでの5年間の小学校生活を経て、日本の公立小学校の6年生に編入した渋谷真帆さんを救ったのは、馬とのコミュニケーションだった。
「馬はその場その場で人間と1対1の関係を築きます。あの人は日本人だから、あの人は帰国生だから、あの人は英語をしゃべるから……といって、態度を変えることはありません。馬は嘘をつかないし、こちらが隠しごとをしても馬にはバレてしまいます。日本の小中学校でなかなか居場所を見つけられなかった私ですが、馬となら信頼し合える関係をつくれました。乗馬をやっているときだけ、自然体でいることができました。価値観も属性も気にせず向き合ってくれる馬に、あの頃の私は救われたのです」
渋谷さんは、父親の赴任に同行する形で、小学校1年生から6年生の途中までをイギリスのウィンザーで過ごした。ロンドンから車で40分ほど。壮大なウィンザー城で知られるこの街で、カトリック系私立女子校の小学校に通っていた。制服があり、マナー教育も徹底されていたが、決して厳しいルールはなく、自由な雰囲気のなかでのびのびと学んだ。
「1学年11~17人くらいの小さい学校で、イギリス系のほか、イタリア系、パキスタン系、中国系、ベトナム系など多様なルーツを持つ子どもたちが一緒に学んでいました。英語が十分にできない時期もありましたが、現地の子たちは何も気にせず、遊んでくれました。子どもだったこともあり、コミュニティに馴染めない経験もしなかったので、イギリスでの自分こそが、本来の自分だという感覚を持っていました」
生涯における価値観が形成される大切な時期を「多様性」のなかで過ごした。そして、この時期にイギリスで出合ったのが「乗馬」だった。いろいろな国の友達がいて、自然豊かな大きな公園があって、そばに馬がいる……。小学生だった渋谷さんは、そんな世界が大好きだった。
日本の小学校はどんよりと暗く映った
日本に帰国になると聞かされたとき、いつかはその日は来ると思っていたものの日本での暮らしがまったく想像できなかった。馬術のできる寄宿学校を調べて、自分だけイギリスに残る道も模索したが叶わなかった。帰国して6年生として小学校に通い始めてみると、イギリスの私立女子校と日本の公立校のギャップは想像以上に大きく、まさにカルチャーショックを受けた。
「通い始めた小学校のクラスは、どんよりと暗く映りました。みんなイキイキしていない。中学受験組は、勉強で疲れているのか、さらに覇気がない様子でした。また、私のクラスはたまたま男子と女子の間に大きな壁があって、一切一緒に遊ばなかったんです。さらに、『きもっ』『うざっ』『死ね!』といった言葉が当たり前に飛び交う環境にも慣れることができませんでした」
イギリスでも日本語の塾や補習校に通っていたので、日本語の理解で困ることはなかった。それでも「イギリスではこうだった」という話をすると自慢だと思われて、会話は進まなかった。一方で、音楽の時間に、スコットランドのバグパイプ隊の男性がキルトと呼ばれる民族衣装をはいていることを「うわ!スカートだ!」と笑った児童に対して、まるで自国の文化を否定されたような感覚を持った。「イギリスの自分」と「日本の自分」の間で、アイデンティティが揺らいでいた。
「キコクのまほちゃん」としか見られない私
その後、中学からは私立中高一貫の女子校に通った。カトリック系のミッションスクールで、イギリス時代との共通点も多く、居場所はそれなりに見つかった。中学校では、フランス語のサークルに所属し、次第に気の合う友達も増えていった。
それでもどんよりと横たわる“違和感”は拭えなかった。その理由は、「対マス」のコミュニケーションにあったのではないかと渋谷さんは振り返る。「マス」とは、つまり「集団」。日本の学校では、帰属する「グループ」として、自分が判断される。好きなことも嫌いなことも帰属するグループに合わせる必要があった。渋谷さんはいつも「キコクのまほちゃん」。「英語しゃべってみて」と言われることは数え切れなかった。「対マス」でしか自分を見てもらえないことにずっと孤独を感じていた。
現実逃避するために乗馬にのめり込んだ
そんな帰国後の居場所となったのが乗馬クラブだった。中学校受験を控えながらも両親は一緒に、渋谷さんに合う乗馬クラブを熱心に探してくれた。そして、たまたま家の近所に理想の乗馬クラブが見つかり、週末に通うことに。中学校時代は、土日だけではなく、金曜日の放課後にも乗馬クラブに通っていた時期もあったという。

「今思うと、イギリスの自分のアイデンティティにしがみつきたい気持ちが大きかったのだと思います。日本の文化や価値観を受け入れてしまうと、イギリスの自分が消えてしまうのではないかという恐怖感があり、現実逃避するために乗馬にのめり込んでいた気がします。日本を受け入れることは、イギリスの価値観の否定であり、当時の自分のアイデンティティロスになると考えていたんですよね」
当時の渋谷さんから見た日本は、人々の個性がない、個性が尊重されない、そんな異文化の塊に見えた。一方で、馬には個性があり、それぞれが違う。そして何より、馬は差別をしない。当時は、ちょっと癖のある馬が好きだった。馬に個性があることが安心感になっていた。自分にも個性があって大丈夫、帰国子女とかイギリス人とか日本人とかそんなことはどうでもいいと馬が教えてくれた。
「馬は個体認識ができないので、毎日新しい自分として私を見てくれるんです。なので、前日にコミュニケーションに失敗しても翌日は新しい関係がつくれる。日本の友達とのコミュニケーションで失敗を経験したり、失敗が怖れたりしていた自分にとって、馬は失敗しても何度でもやり直しができ、心を開いてくれる癒しの存在でした。そういう馬の懐の深さに救われたのだと思います」
乗馬を辞め、英語エッセイライティングに注力
帰国後も自分なりに居場所を見つけつつあった渋谷さんだったが、中学3年生のときに転機が訪れる。参加する馬術の種目のレベルが上がったことで、経済的にも時間的にも学業との両立が難しくなり、乗馬クラブを辞める選択をすることになったのだ。
「乗馬を辞めることは、まさにアイデンティティの崩壊でしたね。今思い返せば、自分でも自分に対して、『私は帰国生で馬が好き、以上』というレッテルを貼っていたんです。中学3年の時点で、イギリスを離れて4年。小学生時代のイギリスの友達は、いつの間にか大人の英語を使うようになっていることにも薄々気づいていました。自分は英語力の維持こそしていても成長はしていない。つまり、英語と馬というアイデンティティがまとめて崩れ去ろうとしていたわけです」
乗馬を辞めるなら、英語を頑張るしかない——。渋谷さんの何かにスイッチが入った。フランス語サークルの顧問だった恩師のアドバイスもあり、中学3年生から高校1年生にかけて、自分の意見を述べる英語エッセイライティングに力を入れるようになった。恩師から「視野が狭い」と指摘を受け、乗馬以外のさまざまなジャンルの本を読むようになった。それは、自分のアイデンティティについて熟考する機会となり、結果的に自分の中の“もやもや”を英語で言語化できるようになっていく。
「個性」をテーマにした英文スピーチでコンテスト入賞
この時期、渋谷さんは、英語のスピーチコンテストに積極的に応募した。高校1年次に神奈川県のコンテストに応募したスピーチのタイトルは「Individuality」。当時、「個性」の重要性について考えていたことをみごとに言語化している。
スピーチの内容はこうだ。イギリスの小学生時代、自分が大切にしているものを紹介して、みんなでシェアする時間があった。イギリスの子もパキスタンの子も自分の大切なものを持ち寄って、それについて話をする。そこに人種や文化の違いはなく、みんながみんなの“大切なもの”を受け入れていた。渋谷さんも自分のことを話すとみんなが喜んでくれた。それが本当にうれしかったし、リラックスできた。そこには差別も偏見もなかった。「個性」が尊重されていた。
そんな記述に続いて、日本に帰国した後の違和感について語られる。「イギリスの自分」に閉じこもり、学校では個性を殺して、浮遊していた中学時代。しかし、この原因は自分にあり、自分こそが日本の文化や価値観を受け入れていなかったことに気づく。日本を受け入れることで、仲間が増え、自分の世界も変わっていく。そして、戦争や差別がなくならないこの世界において、個性を認め合うことが何よりも大切だと結ばれる。
このスピーチは、神奈川県のコンテストで準優勝となり、渋谷さんに大きな自信をもたらした。
スピーチは、以下からダウンロードできます。
シンガポールで自分の視野の狭さに気づく
もうひとつ、「津田塾大学 高校生エッセー・コンテスト」に応募した作品も印象に残っている。こちらのテーマは、「100人の村に手紙を書こう」。有名なネットロア(インターネット上の民話)「世界がもし100人の村だったら」に登場する村に手紙を書くという課題だった。
渋谷さんはこの時期、父親の海外赴任をきっかけにシンガポールを訪れる。イギリス以外のアジアの国に初めて訪れた彼女は、大きな衝撃を受けた。そこには、多民族のさまざまな階級の人々が、多様性を受け入れながら一緒に暮らしていた。イギリスでも日本でもない世界。自分の視野の狭さに気づかされた。現地で渋谷さんは、街行く人々を「あの人はインド系」「あの人は中国系」という色眼鏡で見ていたが、3週間シンガポールで過ごした頃、「人種なんてなんの意味もない」と気づく。外見ではその人のことはわからない。もっと個人として人を見る視点を大切にしないといけない。それはまさに日本で自分が日々感じていた違和感にもつながるものだった。
津田塾大学のエッセイコンテストの作品には、シンガポールで考えたことを書いた。そして、自分がどれだけ小さい世界で生きていたのか気づかされたときの気持ちを素直に英語で表現した。この作品は、2009年 津田塾大学 高校生エッセー・コンテストの最優秀賞を受賞した。
エッセイは、以下からダウンロードできます。
ロシアからの留学生の視点で日本を見る
英語のエッセイライティングに没頭していたのと同じ時期、忘れられない出会いもあった。高校1年生の秋、クラスでロシアからの留学生を受け入れた。名前は、Zoe(ゾーイ)。英語ができることを通じて、彼女と仲よくなり、次第にお互いの英文エッセイを見せ合うようになる。さらに乗馬クラブがなくなった週末もZoeと出かけるようになった。
「Zoeは、どんなことに対してもこれは違う、これは嫌いとハッキリ言える子でした。それは日本の友達にはない感覚で、私はすごく信頼できました。彼女と一緒にいることで、自分もみんなと違ってOKなんだと気づいて、自由に動けるようになった気がします。当時、クラスにあったさまざまなグループの外に居場所を見つけたような感覚でしたね」
留学生の親友ができ、エッセイコンテストでも評価を受けることで、自信を得ていく渋谷さん。エッセイで自分の気持ちを言語化するなかで、「日本を受け入れていないのは自分だ」と気づくことになる。振り返れば、日本のいいところに目を向ける余裕さえなかった。留学生のZoeが見る日本はなかなか魅力的で、彼女の視点で気づくことも多かった。帰国から5年、ここでやっと「イギリスの自分」と「日本の自分」が融合していく。
「日本人は多様性に対する不安感が根強い」
乗馬を諦めた後、渋谷さんは国際ボランティアや教育の分野に興味を持つようになる。高校卒業後は、上智大学外国語学部に進学。在学中に1年間インドネシアで国際インターンシップに参加したほか、東北支援のボランティア活動にも力を入れた。高校までと違い、大学では個性を出すことができた。中学・高校時代は、どうしても自分ひとりで世界を選べない。それだけに悩みを抱える帰国生も多いが、渋谷さんはなんとかその時期を乗り越えた。そんな彼女に、改めてイギリスと日本の教育の違いについて聞いてみた。
「どちらが正しいという話ではありません。その上で、イギリスの小学校では、『みんな違って当たり前』という前提で教育が行われていました。そして、その子のいいところを見つけて、どんどん伸ばすようにしていました。みんな違うことが前提なので、互いにジャッジすることもないし、同調圧力もありません。これに対して日本は、やはり同じ教育を押し付け、同調圧力をかける文化が残っていると思います。子ども同士は『対マス』のコミュニケーションをしていて、個人の関係性は希薄だと私は感じました。また、個人的な経験としては、高校時代に英語の勉強を頑張っていたときに、『どうせ(英語は)できるんだし』『英語より古文をやりなさい』と言われたのには驚きました。幸い理解してくれる先生もいたし、コンテストでも評価いただけたので、やり抜くことができました」
例えば、イギリスの小学校のアートの課題では、みんながまったく違う作品をつくっているのが当たり前。先生は全員に対して、それぞれの視点でほめるという。子どもたちには、常に表現の機会があって、アートや音楽、ストーリーづくりに挑戦し、ほめられることで、自己肯定感を高めていく。そして、このやりとりを通じて、「自分はこれが好き」「自分はこれが得意」という自己理解を深めていく。
また、渋谷さんの視点で見ると「日本人は多様性に対する不安感が根強い」という。つまり、グループの中で違う意見を持つ人を受け入れる寛容性が足りない。渋谷さんがイギリスの小学校で自然と身につけたのは、「多様性を受け入れる素地」。マイノリティであることへの想像力、さらにマイノリティと呼ばれている人々にどう寄り添えばいいかを日々の生活の中で学んでいたことに気づいたという。
馬から学ぶ「共感力」を教育プログラムに
「私がイギリスで身につけたのは、まず違いを理解しようとする姿勢です。その上で、自分で自分のことを決める力も鍛えられました。日本のように『正解は何?』と聞いてもそもそもみんな価値観が違うので正解はありません。なので、自分でこうしたいという意見を持つしかない。就職活動で、『あなたは自由すぎる』と言われたこともありましたが、今は『これが私だ』と自信を持って言うことができます」

渋谷さんは、大学卒業後、教育関連の仕事を経て、現在、新たな挑戦をしようとしている。それは、「共感力」を育む教育プログラムをつくるというもの。そこで登場するのが、ずっと大好きだった「馬」だ。馬は差別をしない——。それは、悩みを抱える子どもたちを救うキーワードになるのかもしれない。
「高校時代にフランス語サークルでお世話になった恩師から、生徒たちの『共感力』を育てるプログラムをつくりたいと相談を受け、『馬しかない』と答えました。そこで、馬を使ったセラピーなどの資料を集め、教育プログラムとして提案をするつもりです。私は帰国後、馬に助けられて今があります。馬から学べる共感力をしっかり言語化して、日本の教育に役立てていきたいと思っています」