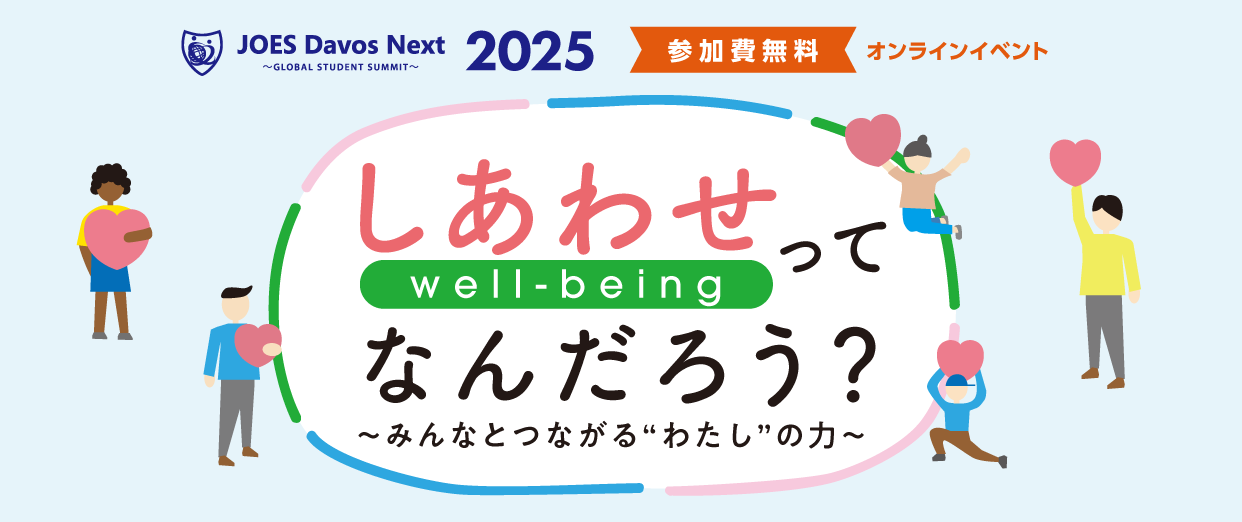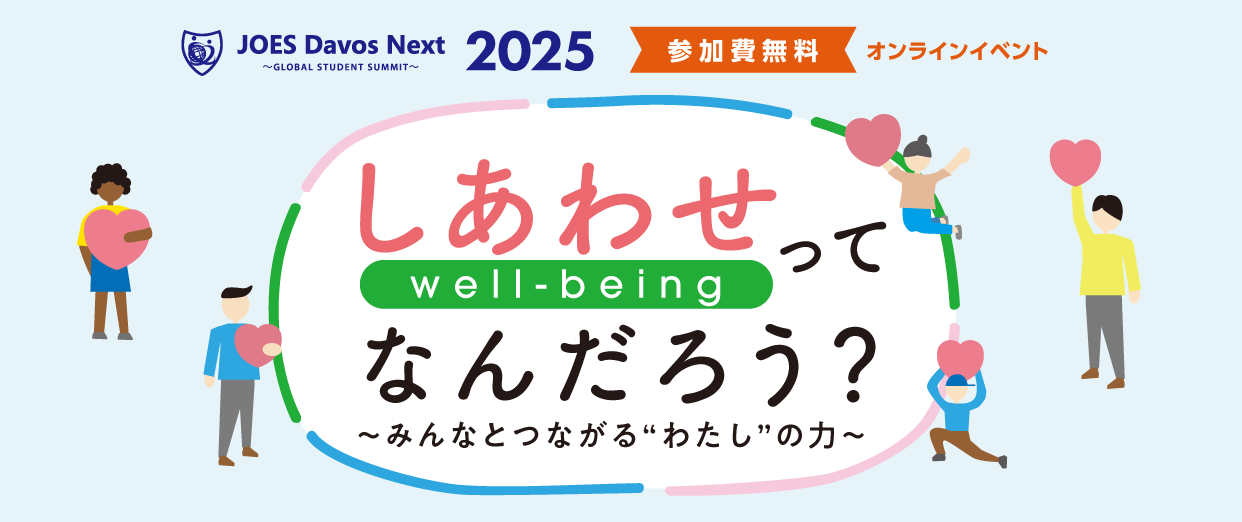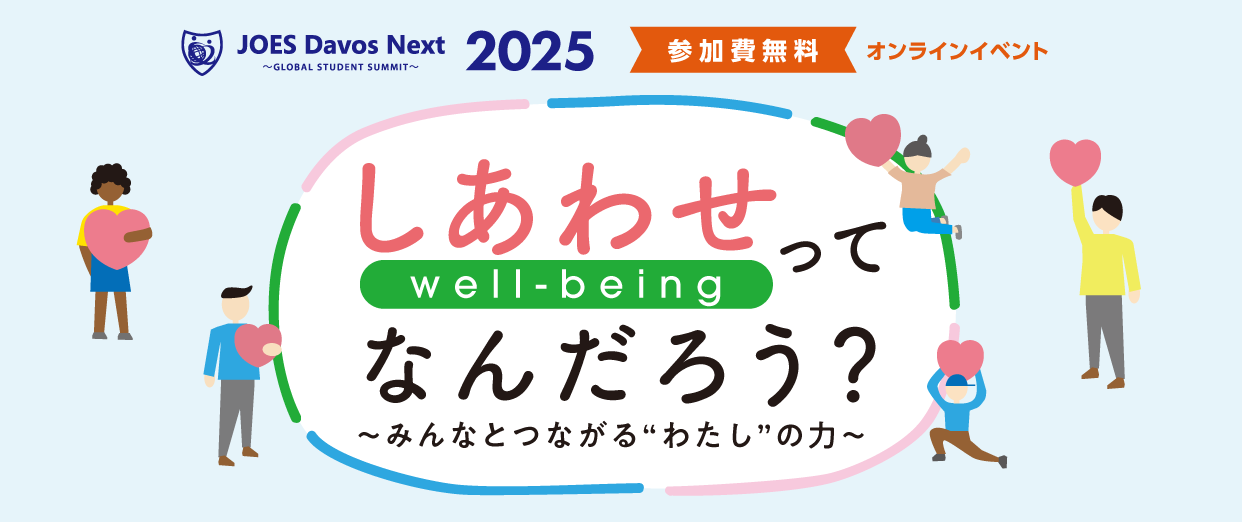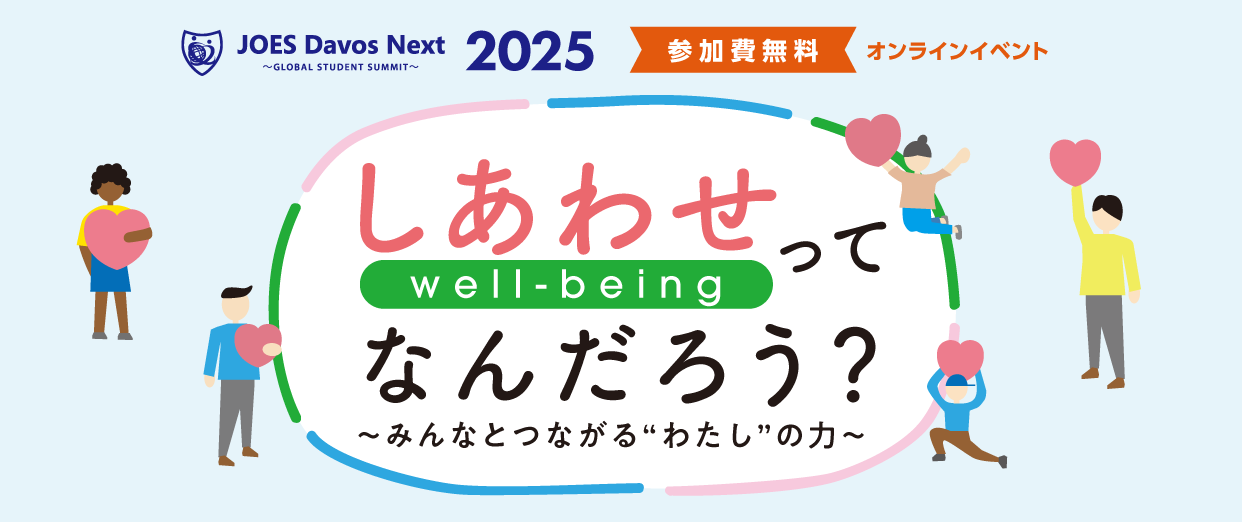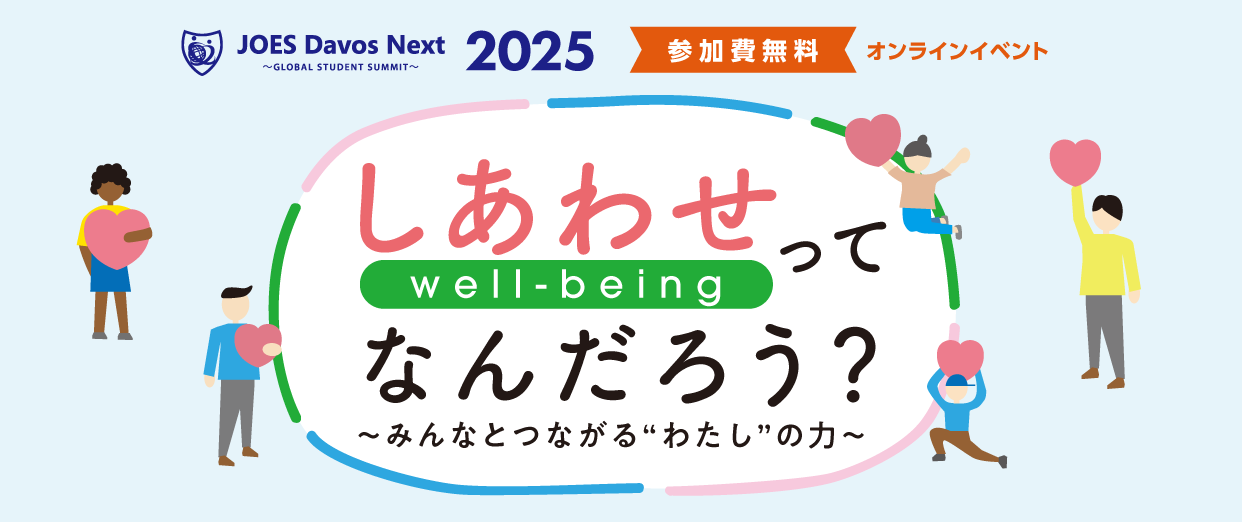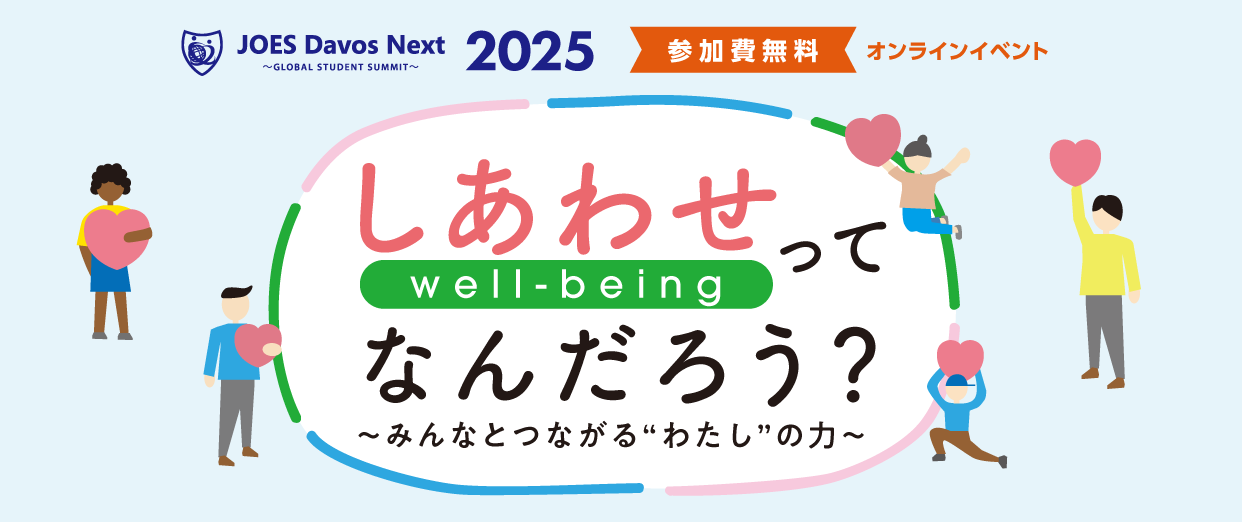8月からいよいよ参加者受付を開始したJOES Davos Next 2025。申込者からは、「待ってました」「今年も楽しみ」という声が届きはじめています。
今回のテーマは「ウェルビーイング」。ちょっと抽象度の高いこのテーマについて基調講演でお話しくださるのは、九州大学主幹教授 都市研究センター長の馬奈木俊介先生です。「しあわせ」や「持続可能な社会」について考える国連委員をつとめるなど、「しあわせとはなにか?」について、社会に広く語りかけていらっしゃいます。
世界中を飛び回ってご活躍中の馬奈木先生ですが、実は24歳で留学するまでは、ほぼ地元・福岡を出たことがなかったとか。そして英語が苦手だったとか……そんなプライベートも交えて、気さくな口調でインタビューにお答えいただきました。
(取材・執筆:只木良枝)
.jpg)
馬奈木俊介先生
——JOES Davos Nextについて、どのような印象をお持ちでしょうか?
基調講演講師のオファーがあったとき、JOES理事長の綿引さんが、「小さい子どものうちから大きな視点を持つべきだ」「世界には格差があることを知ってほしい」「これからやるべきことを子どもたち自身に考えてほしい」とおっしゃったんです。その気持ちにとても賛同して、これは面白いイベントだなと思いました。
ただ、僕は子どもに向けてお話をする機会があまりないので、「子どもに通じるかな、大丈夫かな?」とも思いました。気候変動などの大きなテーマで話したことはあるんですが、今回のテーマはウェルビーイングという個人のこと。大人でも、正直わからないでしょう。だから今、何をどんなふうに話そうかなと考えているところです。
基調講演のあとに掲示板での意見交換の場が用意されているようですが、そこで他の参加者の意見を読めるのはいいですよね。講演を聞いた子どもたちがどう感じているか、どんなことを考えたかを、私も理解できたらうれしいです。
ただ、ウェルビーイングって、比較するものではないんですよ。人間は成長の過程で人のことを気にしなくなります。まったく気にしないというのはダメですが、自分がこういうことをしたいということが固まって満足度が上がっていきます。だから、そのひとつのステップとして、まわりの意見を知る機会になるといいですね。
子どもは、学校教育だけで人との接し方をすべて学ぶわけではないですよね。学校という場に合わない子だっていますし。だから学校以外で、「いつもと違う場で考える」ということがとても重要だと思いますし、JOES Davos Nextはそういう機会を作っているんだと思いました。
人間って、何かのショックがあると考え始めるんですよ。たとえば、東北の震災がきっかけになって原子力の議論が起こりました。でもなかなかみんな発言しない。子どもの場合は、やっぱり恥ずかしいということもあるでしょう。意見を言えるほどの知識がないこともある。大人も勉強不足だったり、あるいは立場上言えなかったりします。議論って極論に偏りやすいものですが、原子力だって「賛成」と「反対」の間に様々な意見がありますよね。自分の考えにやや近い、あるいはやや離れているという人たちと、自分の頭で考えながら、きちんと議論をしていくことが大事なんです。そういう「考える場」に、JOES Davos Nextがなれればいいですね。
——これまでのJOES Davos Nextが扱ってきた「夢」「海」「宇宙」というテーマと、今回の「ウェルビーイング」というテーマは、どのようにリンクするとお考えでしょうか?
「夢」って、必ずしも持たなくてもいいし、途中で変わってもいいんです。私は子どもの頃スポーツばかりやっていて、サッカー選手とか水泳選手になりたいな、なんて思っていました。でも今、それになれなかったからって、どうということはないですよね。夢が長期的なものである必要もありません。「今日のご飯おいしかったな、明日もおいしいといいな」だっていいんですよ。
でもね、「夢を持つ」っていうのはどういうことなんだろう、と考えることはとっても大事なんです。
——子どもたち自身が生きる「未来」について考えることになりますからね。
そうです。「宇宙」も「海」も同じです。宇宙を知ることは地球の成り立ちを知ることになりますし、いつか人類が行けるかもしれないという長期的な可能性について考えることができます。海はもっと身近で、現時点でもたくさんの課題を抱えていますし、特に魚など水産資源の問題は私たちが食べるという行動に直結しています。自分が今、この瞬間にどうやって社会で生活していくか、どうやって生きていくかを考えることになりますよね。
でも、社会に対して何か良いことを何かしようと思っても、そんなに簡単にはできない。それにはまず自分をより良くしていかないといけない、じゃあ今の自分に何ができるか…それをどうやって自分に落とし込んでいくかを考える……そういう意味で、「ウェルビーイング」はこれまでのJOES Davos Nextのテーマともつながっていると思います。
——馬奈木先生が環境問題やウェルビーイングに興味を持たれたきっかけは?
実は、もともと環境意識が高くて興味を持ったというわけではないんです。高校時代は勉強に主体性を持てなくて、英語と国語が苦手でした。数学はできたので、だったら理系かなと。受験先を検討しているうちに、工学部の土木工学科が残りました。当時の九州大学のパンフレットに「海に新幹線を通す」「世界一の技術」みたいな夢のプロジェクトの絵が載っていて、高3の私は単純に「おお、これカッコいいな」と思ったんですね。
まあ、そんな積極的じゃない理由で選んだ大学なんですが、入学後、ちゃんとやろうと考えなおしたんです。で、何を目的に学んだらよいのかを真面目に考えた。哲学などたくさんの本を読んでいるうちに、社会課題を解決するという方向が見えてきました。
自分は工学のエンジニアの勉強をしているんだから、何の役に立つだろうと思っていたときに、解決すべき課題として環境問題と出会ったんですね。環境問題と言っても、当時は気候変動は今ほど話題になっていなくて、排水処理がクローズアップされていたので、自分はこれをやるべきだと思ったんです。
ただその後、留学先のアメリカで、ロビイング活動が国の環境政策に大きな影響を与えていることを目の当たりにしました。「良い技術であるというだけでは社会に普及しない」という現実に直面したわけです。
——そこで馬奈木先生が、ロビー活動や政治活動を目指さなかったのは?
そうですね。当時、様々な分野の本をたくさん読んでいく中で、社会は、個々の政治家が変えていくものではなくて、基本は民意に基づいたものなんだと考えるようになったんです。一見過激な言動をする政治家も、実は民意を汲み取っていて、それが大衆受けするから、あえて過激なことを言っている。だから、長期的に何かを変えていこうとすると、結局、民意、つまり人の考えを変えていくしかないわけです。
だから政治家に対してのロビイングを頑張るよりも、本当に何が正しくて何をすべきなのかを、ロジックで説明できるような専門家になろうと思ったんです。そのためには経済学が必要だと思って、資源経済学を学びました。
ひとりの政治力ではなく、人々がみんな納得しないと世の中変わっていかない。そのためには専門家がみんなにちゃんとわかるように語ることが重要で、考えるための指標になるものを提示していく必要があるんです。
——民意を形成するのは私たちですから、一人一人が考えていかないといけないのですね。基調講演の対象は「大人から子どもまでどなたでも」ですから、ぜひたくさんの人に視聴していただきたいです。
最後に、海外で育っている子どもたちと、それを支えている保護者や教員などの大人たちへのメッセージをお願いします。
24歳の時、アメリカ留学で降り立ったボストンの空港が、生まれて初めての海外でした。父が警察官で何かあったらすぐに戻らないといけないので、家族で遠くに旅行をするという機会もなく、スポーツばかりしていました。ですから英語の素養もまったくなかった、もっと言えば、やる意味も感じない。学校の授業も興味を持てませんでした。大学に入ってから英語の勉強を始めたけど、やはりアメリカ留学の最初の1年間は、途中で専門を変えたこともわざわいして、全く通用しませんでした。
今海外に住んでいる子どもたちは自分の意思で行ったわけではなく、親の都合ですよね。私も、子ども心に「親が警察官だから自分は悪いことをしてはいけない」と強く思っていました。人によって違うけれども、子どもにも大変なこと、嫌なことがたくさんあると思います。でも、今のその環境をつくったのはたしかに親だけど、その中でいくらでもやりようはありますから、自分なりに精一杯やればいいんだと思います。
親の立場から見るといろいろ考えますが、子どもは子どもの人生を生きているんですから、親が思う通りには育ちません。子ども時代の経験に格差が生じているのが問題だと言われますが、経験がただたくさんあればいいかというと、そうでもないでしょう。子どもの頃からいいものばかり食べていたら、大人になってからの喜びがないですよ。親に連れられて見た景色と、自分の力で見た景色は違います。
私、今朝タイ旅行から帰ってきたばかりなんですけどね。やっぱり自分で行って現地の料理食べて「おいしい」と感じるのが、一番重要なんじゃないでしょうか。
——ありがとうございました。基調講演を楽しみにしています。
みなさんの積極的なお申し込みをお待ちしています。
JOES Davos Next 2025公式サイトはこちら
https://www.joes.or.jp/kojin/jdnext