キング・オーガストさん、アメリカ海軍に勤める両親を持つ14歳。現在、横須賀に家族で住み、鎌倉女学院中学校の2年生になる。
アメリカ・ミシシッピ州生まれの生粋のアメリカ人だが、これまで通ったのは、ほぼ日本の学校。アメリカの学校に在籍したのは、横須賀基地内のアメリカンスクールに通った小学校4年生の後半から小学校5年生にかけての約1年半だけだそうだ。その後、グアムに転居した際も、日本人学校を選んだ。
オーガストさんにとって、「日本の学校」の魅力とは何なのだろう。

私は日本で育ったアメリカ人
両親の仕事の関係で、4歳から日本の横須賀で育ちました。地元のキリスト教系の幼稚園に通い、同じくキリスト教系の小学校に進みました。11歳のときにグアムに行って、13歳の時にまた横須賀に戻ってきました。

とても流ちょうな日本語で淀みなく話す姿は、中学生とは思えないほど落ち着いている。オーガストさんの「日本語」は4歳から始まるが、そもそも、基地の中にはアメリカ海軍の子どもたちのための幼稚園もあるのに、なぜ日本の幼稚園を選んだのだろう。

海軍の子どもたち全員が基地の中の幼稚園に行くわけではなくて、日本語を学ばせようという気持ちがあるのか、幼稚園は日本の園に行かせようという親も結構いたんです。私には弟が二人いますが、弟たちも私と同じ日本の幼稚園に通いました。
小学校に上がるとき、基地内のアメリカンスクールに行くという選択もありましたが、「続けたい」という気持ちがあって、日本の小学校に進みました。グアムに行くことが決まったときも、やっぱり「続けたい」と思って、グアム日本人学校を選びました。
オーガストさんのご両親はアメリカ人だが、娘の選択を快く受け入れ、背中を押してくれたという。
じつは、小4の途中から小5までは基地内のアメリカンスクールに通ったんです。そろそろアメリカに引っ越すことになるかもしれなくて、そこに日本人学校がなかったら現地校に行くことになるので、英語の力を高めたり、アメリカの学校について知っておいたりした方がいいという理由でした。
でも、アメリカンスクールは「自分が思っている学校とは違うな」という感じでした。それまで、日本の学校しか知らなかったので、通い始めて「日本の学校ではないな」と。
日本の学校はきれいだし、全体的に「協力し合う」文化があるのが魅力的です。給食も美味しいし、給食当番があって、みんなに分ける量とかを考えながら育っていけるし、食べ物に関する勉強がきちんとされているのも好きなところです。
それに、日本の友だちだと、うるさくならないで落ち着いて話せるし、日本の先生は面倒見が良くて、できないところを手伝ってくれるところがいいなって思います。
ただ、アメリカンスクールに通っていた間、日本語より英語で勉強する方が簡単だなとか、人間関係もこっちの方がラクだなとかと思う時期もあって、そのときはアメリカの学校が好きでした。
結果的に、親の赴任先がグアムになって、日本人学校があったので、私が「日本の学校をずっと続けたい」と言ったら、父も母も「いいよ」と応援してくれました。
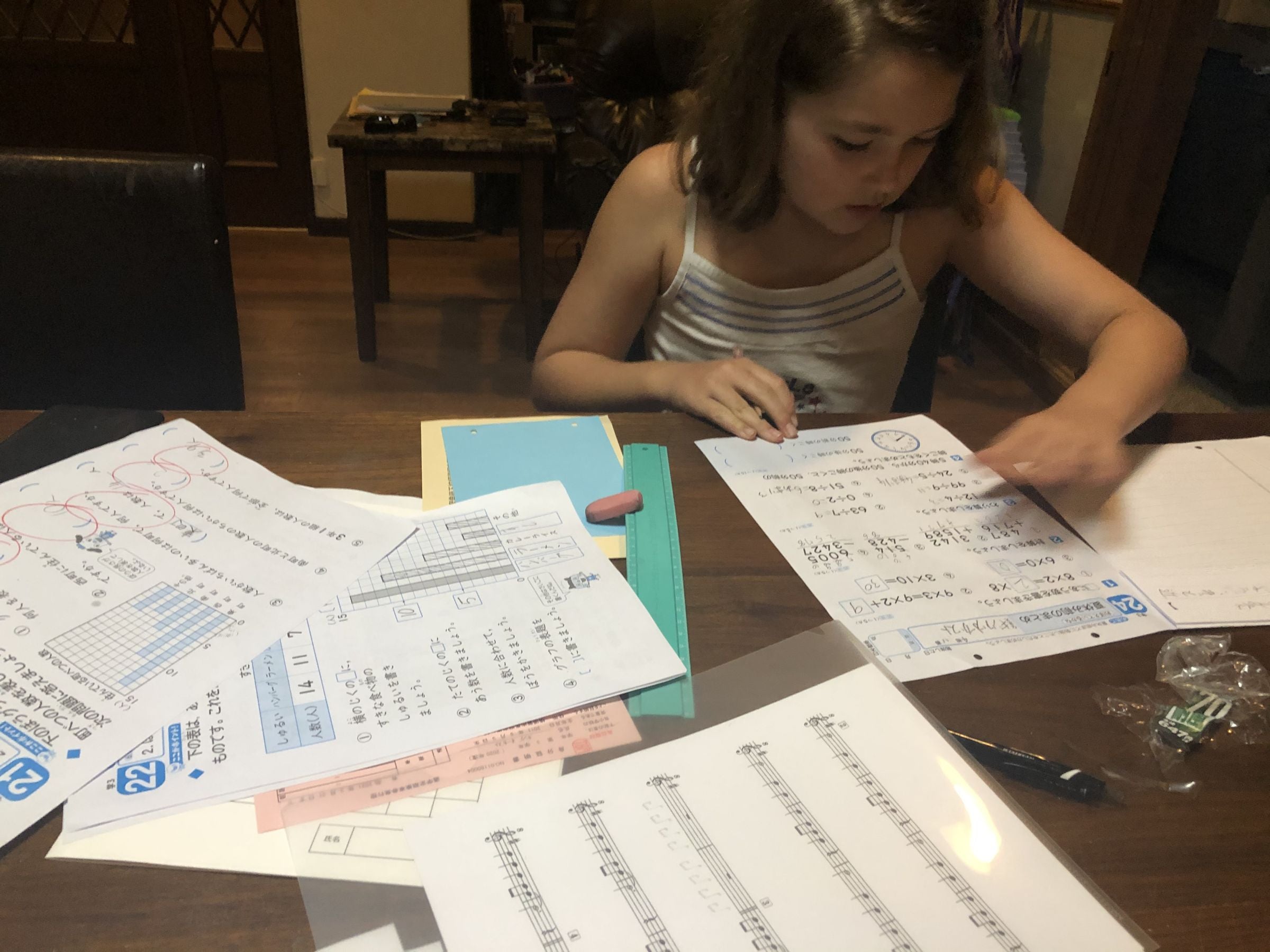
オーガストさんの弟さんはふたりとも、オーガストさんと同じ日本の小学校に1年半通い、アメリカンスクールに転校してからは、そのままアメリカの学校に通っているという。
ご両親は、子どもそれぞれの考えを尊重し、最後に決めるのは子ども本人、そして決めたことに関しては応援するというスタンスだ。
.png)
.png)
グアム日本人学校の仲間たち
グアム日本人学校は日本の文部科学省から認可されて1988年に開校、今年の4月、グアム政府からも認められるインターナショナルスクールとなり、「グアム国際日本人学校」に改名した。
幼稚部から中学部までがそろい、日本語にも英語にも力を入れ、日本国内同等の教育が行われている。
オーガストさんが通ったのは、コロナ後のグアム日本人学校。日本語を使って日本国内の学校と同じカリキュラムで授業が行われていた。在籍者数は多くなく、小学部と中学部あわせて50人弱。中学校1年生のときは、「クラスがひとり」の時もあったという。
日本の小学校に長く通っていたので、人数が少ないこと以外は、そんなに驚くことはなくて、すんなり入れました。初日は「友だちと仲良くなれるかな」とか「授業についていけるかな」とか、不安はありましたが、日本で通っていた学校とスタイルがそんなに変わらなかったので、良かったです。
人数が少なかった分、全校で行事が行われることが多く、私は学年が上だったので、みんなが仲良くなれるように頑張っていたように思います。
低学年の子ができないことがあったら手伝ってあげたり、つまらなさそうにしていたら、こちらから話しかけてあげたり、遊んであげたり。全校でハイキングに行くことがあったのですが、危なくないように気をつけてあげたりしていました。
小さな学校だったので、先生の数も少なくて、話す機会がたくさんありました。特に中1のときは、同学年の子がいなかったので、私と先生だけという時間が多くなって、仲良しというか、近い関係でいろいろ話せたのは良い思い出です。
サンクスギビングには、友だちや先生を自宅に呼んで、パーティーをして、家族をまじえていっしょに素敵な時間を過ごしました。当時の友だちや先生とは、今もLINEとかで繋がっています。
人数が少ないから仲良くなれる一方で、だからこそのトラブルも起きる。関係が密になる分、意見の食い違いは顕著になる。
友だちと話すのが大好きなオーガストさんは相手との距離感について考えた。
小さな社会なので、ケンカをすると友だちが減ってしまうんですよ。だから、普通のケンカのときは、自分が悪かったなというときは、すぐに謝るようにしていました。ただ、あまりにひどいケンカのときは、すぐに行動しないで、なんでこんなことになったのかをよく考えて、時間が経ってから話し合うようにしていましたね。
.png)
アメリカ・日本、それぞれへの思い
オーガストさんには、グアム日本人学校で忘れられない思い出がある。小学校6年生のときのスクールパフォーマンスで、第2次世界大戦の末期に行われた沖縄戦に関する劇をしたこと。
総合学習の時間に自分たちで調べたことをもとに、先生が脚本を書いて劇にしたものだが、公演後、観客が感激している様子が嬉しかったそうだ。
自分が、ひとをそんなに感動させることができるんだというのが、すごいなあと思いました。両親も観に来てくれて「日本語はわからないけれど、内容はなんとなくわかって、心を揺さぶられた。上手だったよ」と言ってくれました。
オーガストさんはアメリカ人だ。沖縄戦について調べたり、劇の練習をしたりしているときは、どのような気持ちだったのだろうか。
アメリカと日本、両方の気持ちが分かる感覚でした。友だちが、日本はアメリカにやられた、みたいな発言をしたときは、「アレ?」って。それは、日本サイドの言い分で、アメリカにはアメリカサイドの言い分がある。だから、「アレ?」っていうときは、どちらがいいとか悪いとかと決めつけるのではなく、まずは自分でよく調べて、アメリカ・日本、両方からアプローチして考えるようにしていました。

「生命は何よりも大切なもの、命こそが一番大事な宝である」という意味。
今、そして将来
.png)
オーガストさんは中学1年生を終えて帰国し、鎌倉女学院に編入した。母親が友人から鎌倉女学院を勧められ、オーガストさんも学校のホームページを見て、その雰囲気に魅かれた。
「女子校」という普段とは違う生活を経験できそうなところや、鎌倉という歴史ある土地柄も気に入り、編入試験を受けて見事に合格した。
試験を受けるときは緊張しました。でも、終わったら「結構、できたかな」って思いました。受験勉強は、グアム日本人学校の先生たちが親身になって助けてくれました。合格できたのは、先生たちのおかげもあると思っています。
そして今、オーガストさんは中学校生活を楽しみ、バレーボール部で活躍している。
グアム日本人学校にいた頃は人数が少なかったので、部活動は近くの現地校の活動に参加させてもらってバレーボールをやっていました。でも、今は、学校の中で部活動もできます。バレーボール部は週5で活動していて、土曜日や日曜日には、たまに試合もあります。「勝ちたい」という気持ちで試合に出るのが好きです。クラスは40人もいて、話せる人がたくさんいるので、毎日、できるだけ多くの人に積極的に話しかけるようにしています。
「ひととコミュニケーションを取るのが大好き」というのが伝わってくる笑顔。将来の夢を尋ねると、さらに目が輝いた。
英語と日本語を使える仕事に就きたいです。私の家族は、旅行が大好きで、よく飛行機に乗ります。なので航空会社、できれば日本の航空会社に就職して客室乗務員になりたいと思っています。
10年後の姿を想い浮かべ、思わず頬が緩んだ。幼い頃からアメリカと日本の文化をさまざまな環境で身に着けてきたオーガストさん、たくさんの人と触れ合い育まれた感性には、国や人種を問わない素晴らしいサービスを創り出していく力があるような気がした。






