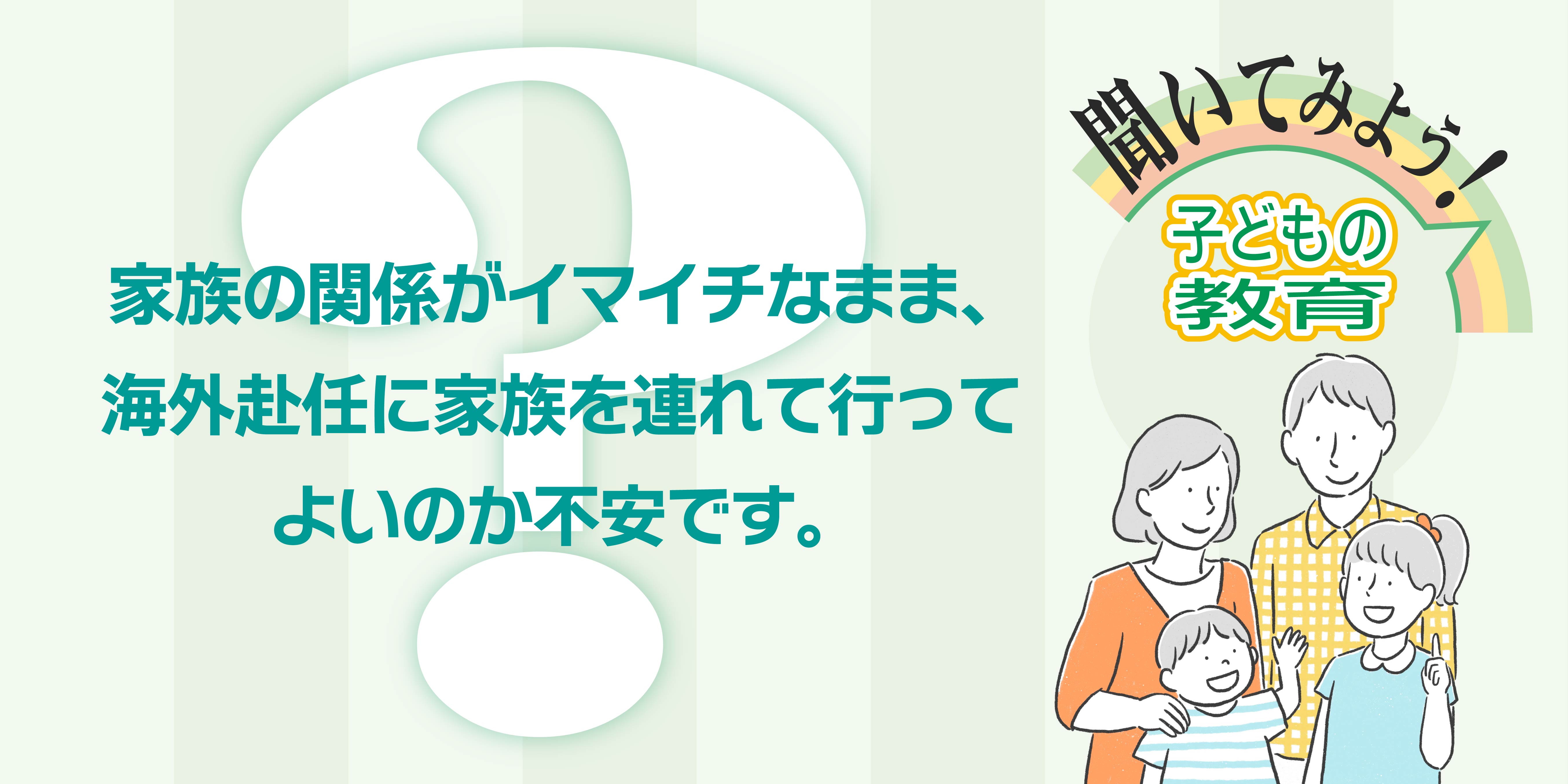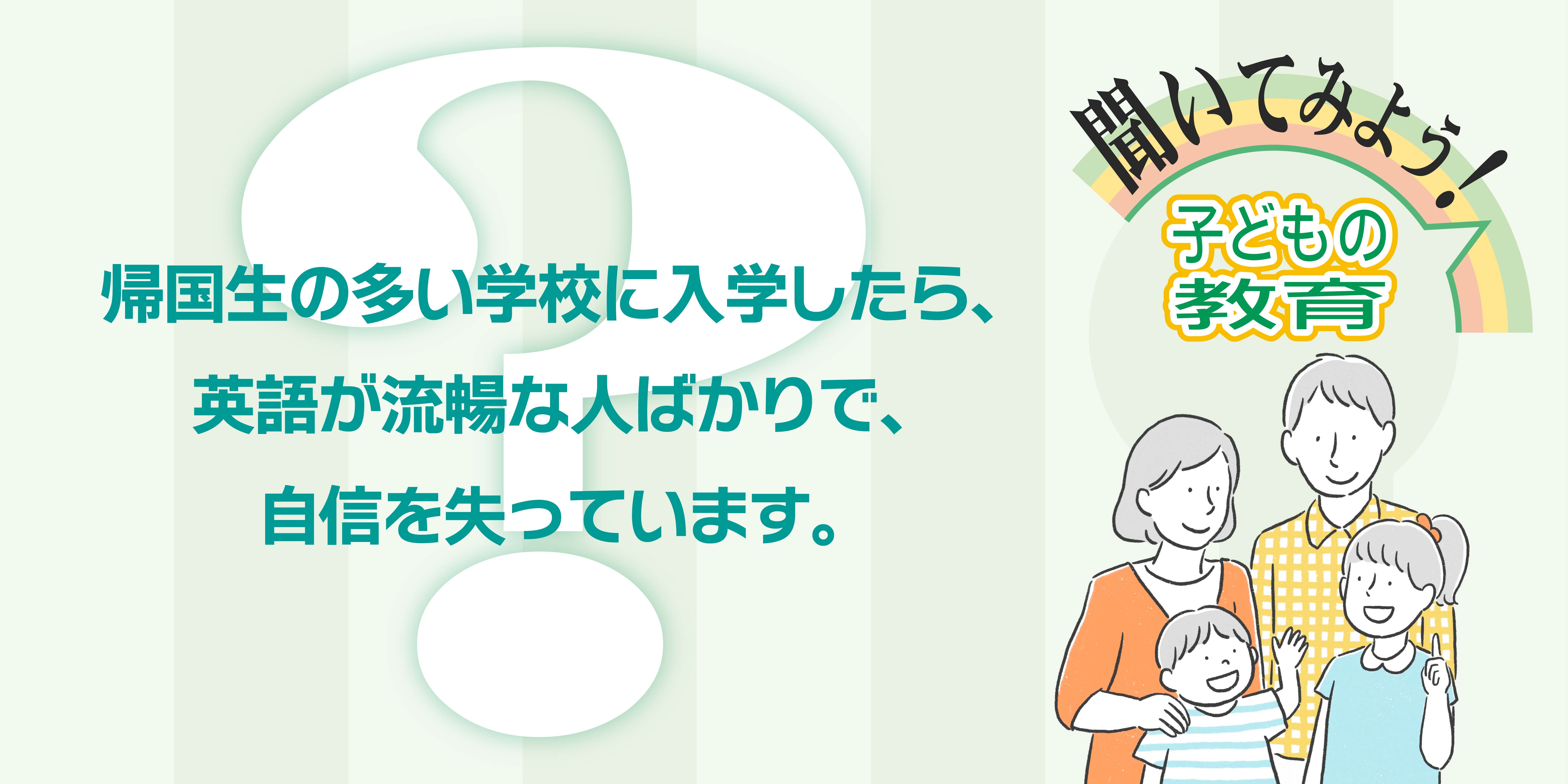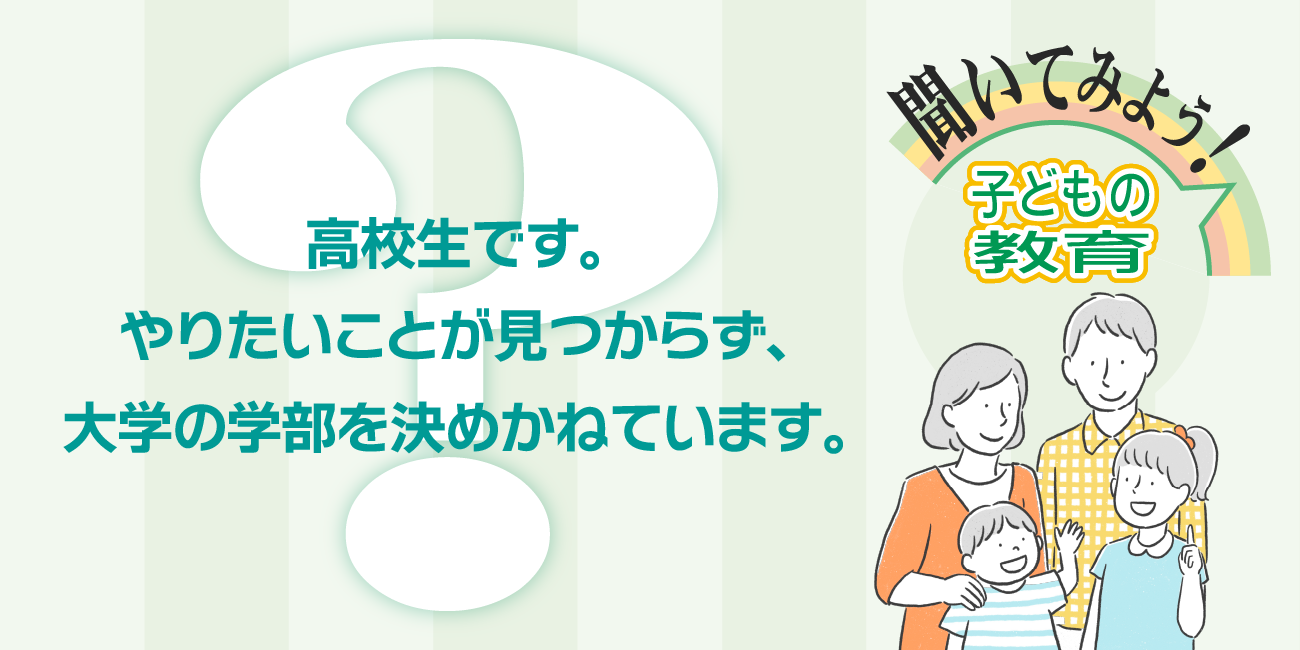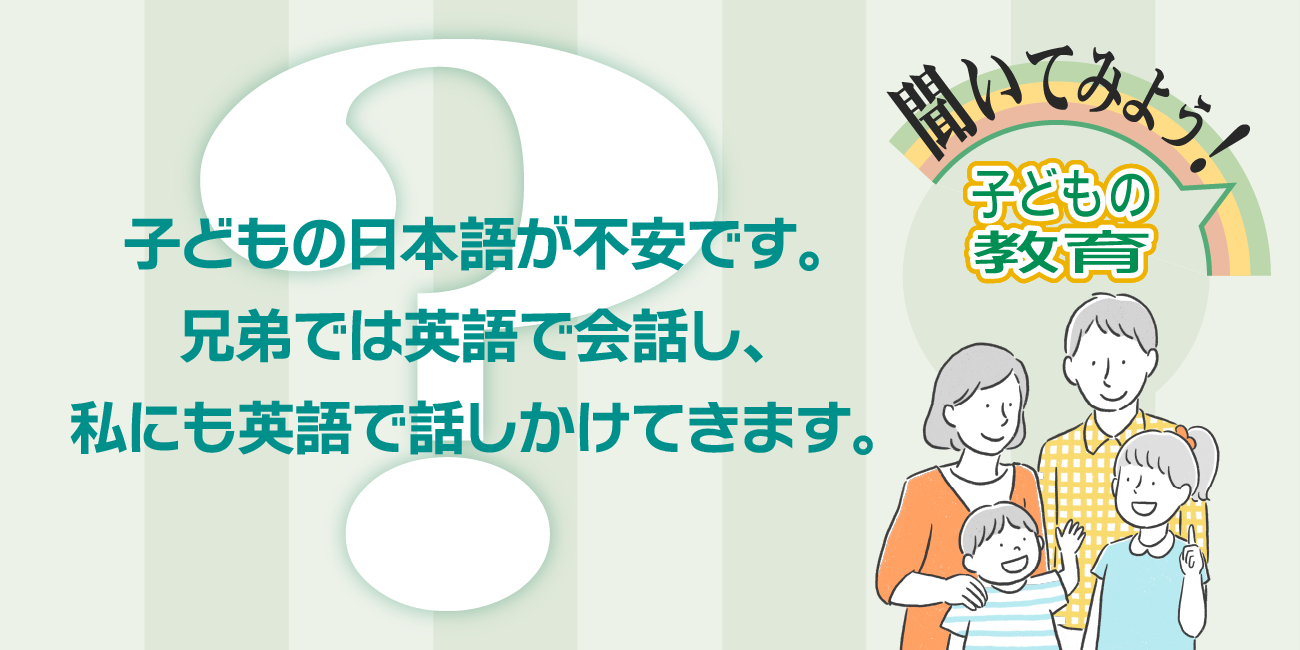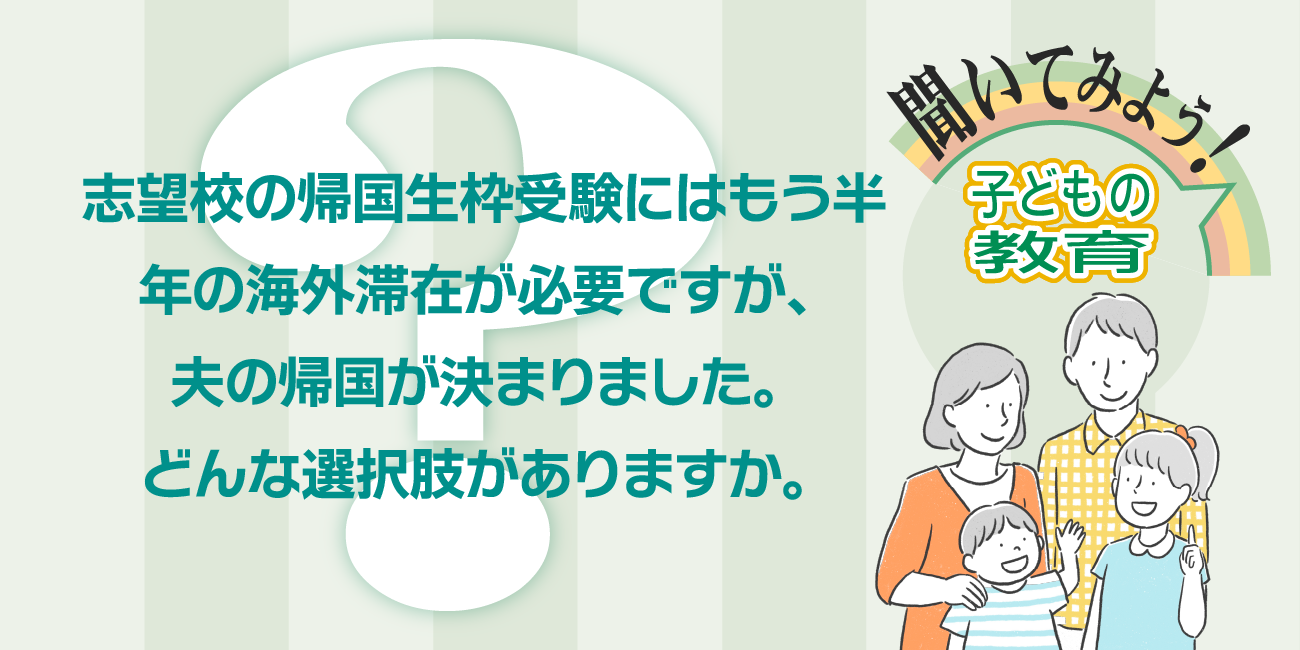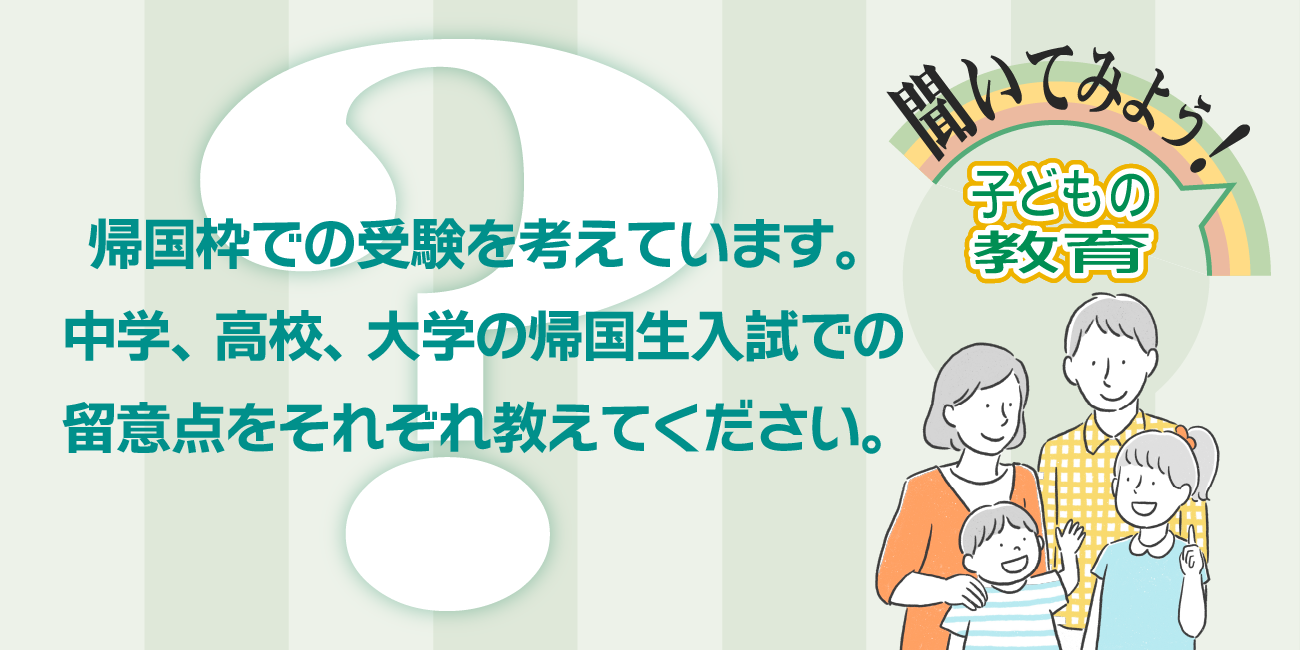<質問> 習い事と補習授業校の時間帯が重なってしまいました。どちらを優先させるべきでしょうか。
はじめに
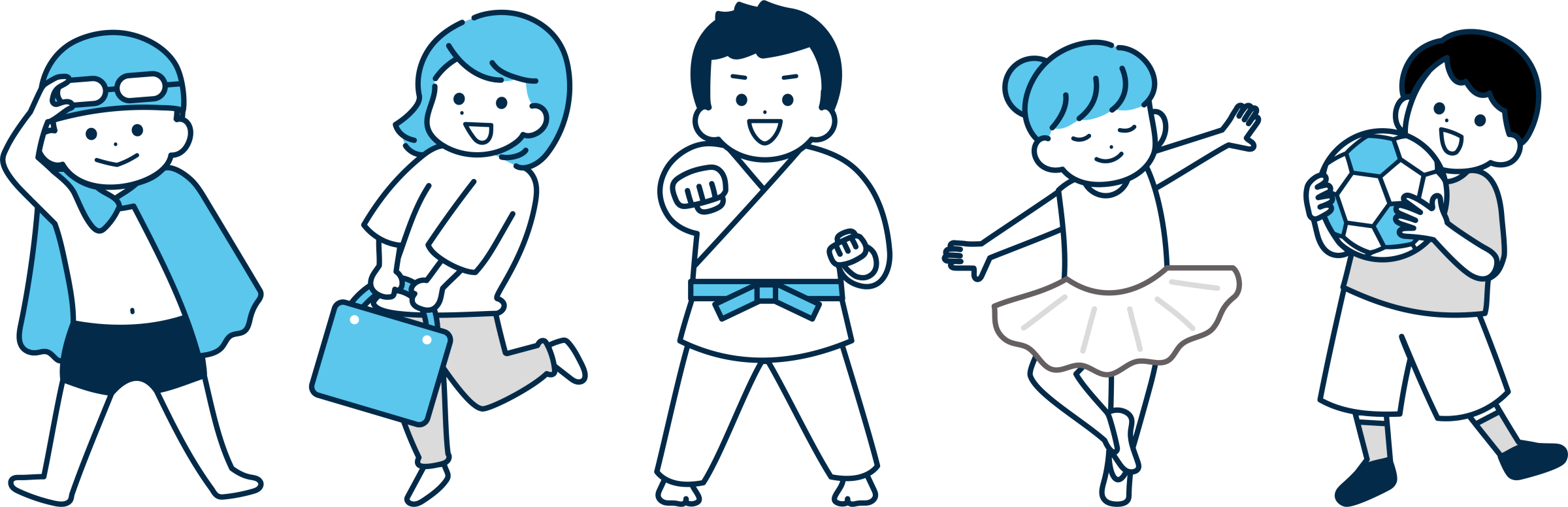
以前勤めていた同志社国際中学校・高等学校の校外学習であった出来事です。内容は音楽鑑賞、オーケストラ演奏でした。曲の合間に進行役の司会者の方が中学生に対して、「学校以外で楽器を習ったことがある人、手を挙げてください」と尋ねられたところ、8割ほどの生徒が挙手をしました。
学校以外で習い事をする子どもたちは、どんどん増えていっているようです。人気は水泳を始めとしたスポーツ、次に情操教育という観点からピアノをはじめとした音楽。勤務していた学校では他にカートやフィギュアスケート、クラシックバレー、アーチェリー、自転車競技、ロボットをはじめとするプログラミングなどもあり、学校の課外活動以外で世界大会に出場したり、後にその道でプロになったりした生徒もいました。
海外ではアクティビティは日本以上に盛んです。地域のコミュニティセンターや専門の教室など、その種類は多岐にわたっています。また渡航したての時期にアクティビティに参加することで、現地の子どもたちとの触れ合い、言語の壁をクリアできる場合が少なくないという点で、積極的に習い事をされる場合も多いと聞きます。学校では決められたカリキュラムをしっかりこなしていくことを求められるのに対して、習い事はお子さん自身の興味関心からその内容を選択ができるという点で面白みが増していくと考えられますが、習い事にはまっていく要因はそれだけではないようです。

習い事の意味
これも同志社国際中学校・高等学校での例ですが、アメリカで運動系の競技を専門に習い事をしていた経験があるという生徒に聞くと、多くは日本の事情とかなり異なっていることがわかりました。よく言われることですが、アメリカでは日本でいう課外活動、いわゆる部活動がシーズンによって変化する場合が多いという特徴があります。さらに、学校以外のスポーツクラブで単独の種目を行う場合であっても、かなり細かく競技者のスキルに応じたレベル分けが行われていて、地域の大会なども、競技者のレベルに応じた大会が開催され、それぞれ優勝、準優勝などの栄冠を勝ち取ることができるようになっていると言われています。
独立行政法人国立青少年教育振興機構の『高校生の進路と職業意識に関する調査報告書(令和5年6月発行)によると、日本の若者は他の先進国に比べて「自己肯定感が低い」という結果が表れています。その原因は複雑多岐にわたると思われますが、先の例も無縁ではないでしょう。
レベル別に細分化された競技においては、現在の自分自身の力に応じた努力が求められ、それを達成した時には、自分の努力に対して自己評価できる自己を肯定する視点が生まれてきます。スポーツに限らず、音楽、クラフトなど、自分なりの目標を達成し、またそのことを周囲の仲間や大人がそのプロセスを含めて評価してくれる環境があると、自己肯定感は育まれていくのではないでしょうか。

補習校とは
今回、問題となっているのはこの習い事と、補習授業校とのバッティングです。ではそもそも補習授業校とはどのような存在なのでしょうか。 海外で最初に補習授業校が設立されたのはワシントンDCです。1958年、現地在住の日本人保護者の要望から端を発し、日本人会・現地の日本企業などによって設立されました。世界に点在する同様の補習授業校も同様のケースがほとんどです。
文部科学省は1,000人以上児童生徒が在籍する大規模補習校には、校長を派遣しています。少し珍しい例としてインドのチェンナイ補習授業校を取り上げてみましょう。ここは「準全日制」という形態の補習授業校です。在外教育施設のなかで「準全日制補習授業校」はチェンナイのほか、ダルエルサラーム(タンザニア)、オマーン(オマーン)、グアダラハラ(メキシコ)など、全世界に4校しかありません。昼間は現地校・インターナショナルスクールへ通学している子どもたちが、放課後に登校し、現在は小学部が毎日2時間、中学部は土曜日に6時間、国語・数学など主要教科を中心とした学習をしている学校です。
最近は、現地校・インターナショナルスクールが終わった後、補習授業校には行かずにそのまま在籍校のアクティビティに通う生徒児童が増えてきているという話もあると聞きます。やはり習い事と日本語学習の両立が問題になっているようです。 日本人学校や補習授業校が作られた意味、保護者や子どもたちの要望や思いはどのようなものであるかを考える必要がありそうです。
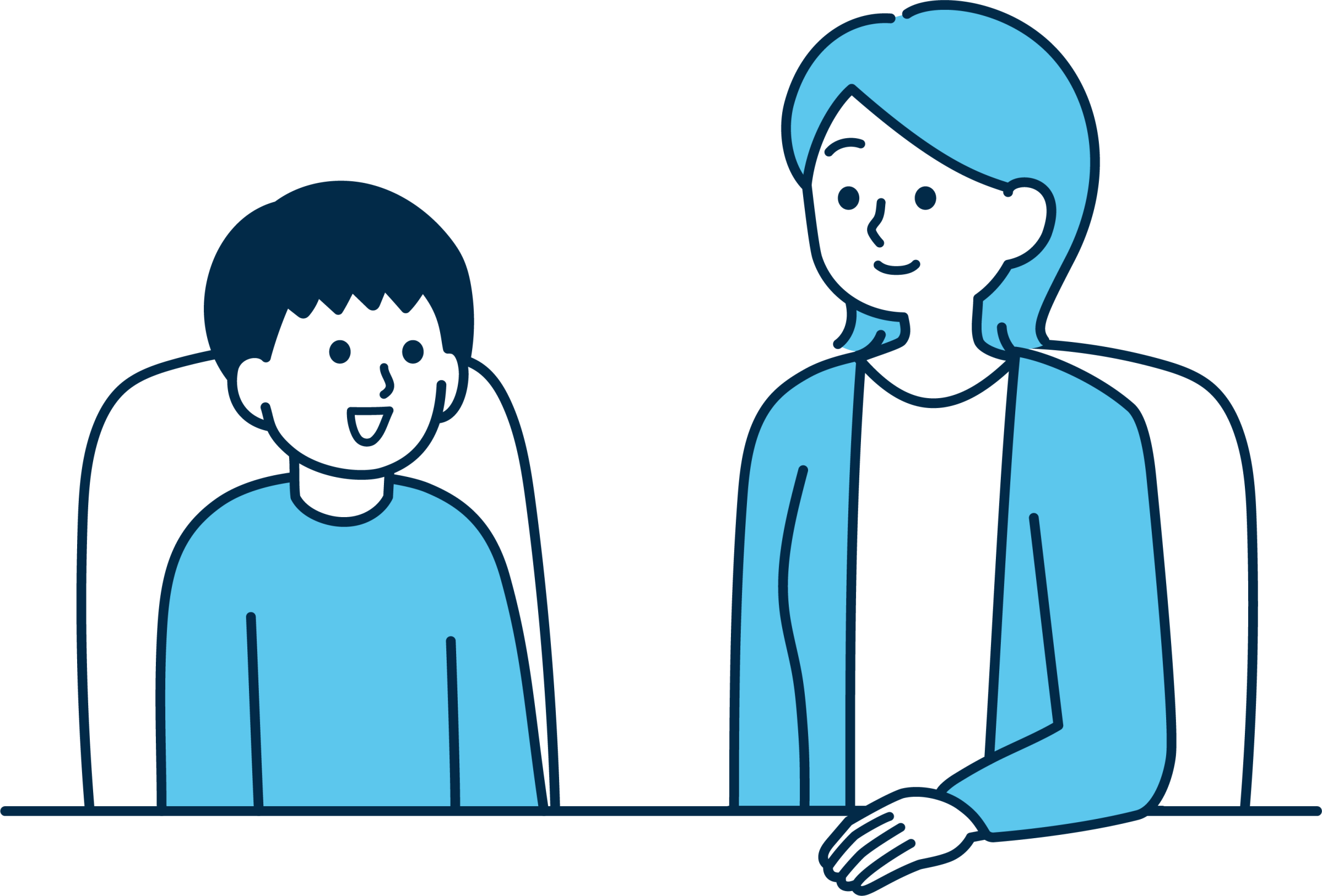
言葉を巡る問題
私が長年勤めていた同志社国際中学校・高等学校は、帰国生を受け入れることをおもな目的として京都に設立された学校です。40年前、帰国子女の数は今ほど多くはなかったものの、教育の現場では大問題になりつつありました。今でこそ海外に赴かれるご家庭は、帯同されるお子さんの将来についてある程度のビジョンを持たれていますが、当時は今ほど情報もなく、しかもある日突然帰国が決まったけれど、子どもは現地の学校にすっかり馴染んで、日本語が充分にできなくなってしまっているという方が多くいらっしゃいました。「地元の公立学校に通い始めたけれど教室での日本語がよくわからない」、「英語の授業で英語ネイティブスピーカー並みの発音で話すと、かえって教室で浮いてしまう」など、問題が山積していました。
そんな中、こともあろうに私は国語教師として、帰国生受け入れ校で授業を担当することになったのです。最初に行った「古典」の授業は忘れもしません。教材は「竹取物語」。誰もが知っていると高を括っていた私は、登場人物であるおじいさんが「なぜ竹などを山に取りに行くのか」と質問されたときに、どこから何を説明しなければならないのか、完全に思考の迷路に踏み込んでしまいました。「かごなんかをつくるんだ」と答えたものの、生徒は「かご」の意味が分からない様子でした。とっさに「バスケット」と説明したのですが、その時私がイメージしている「籠」と、生徒が思い描いたであろう「バスケット」は、全く違うものだと感覚的に気づきました。言葉が担う文化的な背景の問題です。
もう一つ言葉を習得する過程で興味深い話があります。
日本語を習得していく段階で、私たちはいかに複雑な過程を踏んでいるかを、広瀬友紀さんの『ちいさい言語学者の冒険』(岩波書店2017年)は教えてくれます。広瀬さんは5歳児が口にする「死む」「死まない」という間違った言葉づかいについて、「そもそも子どもはどうやってことばを覚えるのか」という問いに対し、「まわりの大人たちが使っていることばを聞いて覚えていく」のが、普通だとしながら、まわりの大人が使わない表現を子どもが用いるというのは「子どもは実際に聞いたことのある表現だけを身につけていくわけではないこと、実際に聞いたことのない表現も、その性質を類推し、その時点で身につけた規則を適用することによって、使える表現を自力で何倍にも増やしていく」のだと述べています。
言語を習得していくのはその元になる連綿と続く歴史を経た文化的な背景と、個人がおこなっている言語体系習得のための見えない努力があることを認識する必要があるでしょう。

終わりに
どれほど心がけていたとしても、現地校やインターナショナルスクールでは子供たちは日本語以外の言語で生活していることから、日本語の力が落ちていきます。やがて日本の教育課程などで学ぶはずの語彙や表現が身につかなくなるという現象が起こってきます。言葉の欠落は自己の中に確固たる文化を持てないということにつながりかねません。
例えば一人でいるときにふと感じる孤独で虚しい感覚は、「寂寥感」という言葉を学んで初めて、自分の中の感情として位置づけられると言えるでしょう。
習い事と補習授業校は同じ価値で選択できるものではありません。お子さんの将来を考えた、重要な決定になるということを認識しなくてはならないと思います。ただ、学齢が進んでおられるお子さんについては、ご自身の希望を大人が無下に否定することも得策だとは言えません。お子さん自身の将来を見据える視点を提示して、お子さんとしっかりと話し合われる必要があると考えます。
その際に忘れてはならないのが、お子さん自身がこれまで現地の学校でされてきた努力の評価です。海外で学ぶということがどれほど価値のあることか。それが将来どのように人生を決定していくか。お子さん自身が現在の経験の価値をしっかり認識し、自己に対する肯定感を持てた時、「補習授業校をやめてしまう」ではない選択肢が見えてくるのではないでしょうか。
<回答者> 海外子女教育振興財団 教育アドバイザー 戸田光宣(とだみつのぶ) 1980年に関西で唯一の帰国子女受け入れ専門校として設立された、同志社国際中学校・高等学校に、創立4年目より40 年間勤務。担当教科は国語。多くの帰国生に対し、日本語指導を含めた国語の授業を行ってきた。国内外で帰国子女に対する相談業務を担当し、教務主任、教頭、校長を歴任。 2024年4月より海外子女教育振興財団の教育アドバイザーを務める。
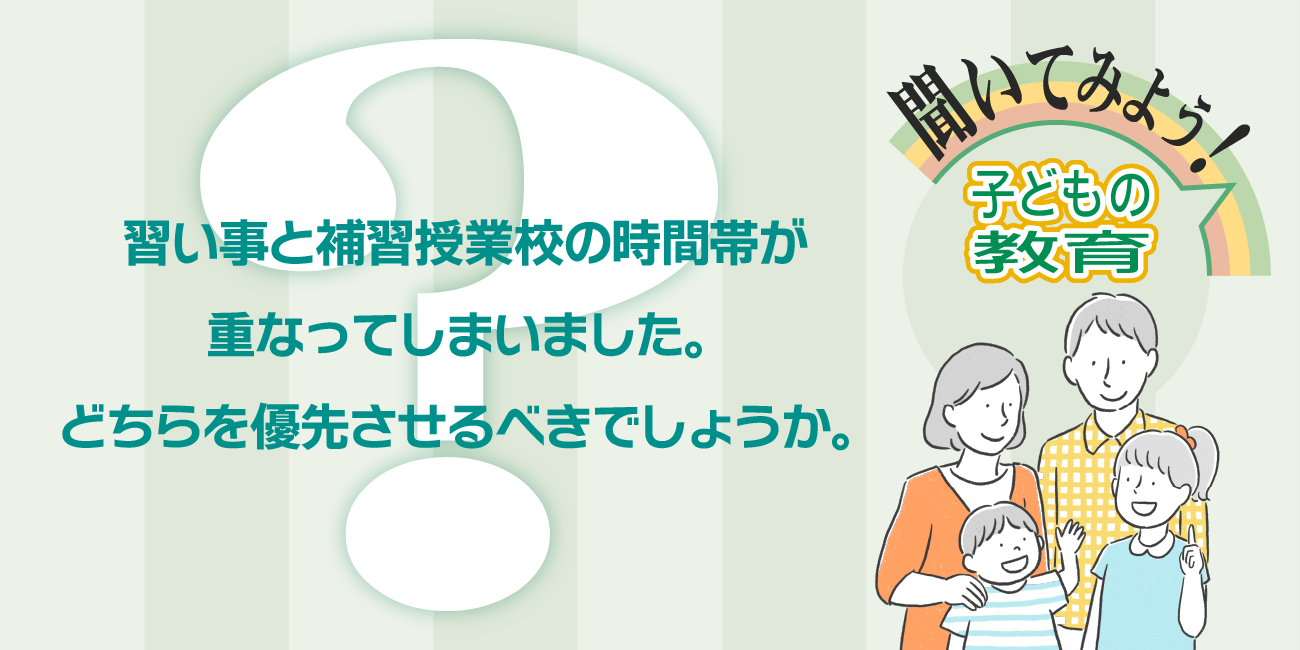
.jpg)