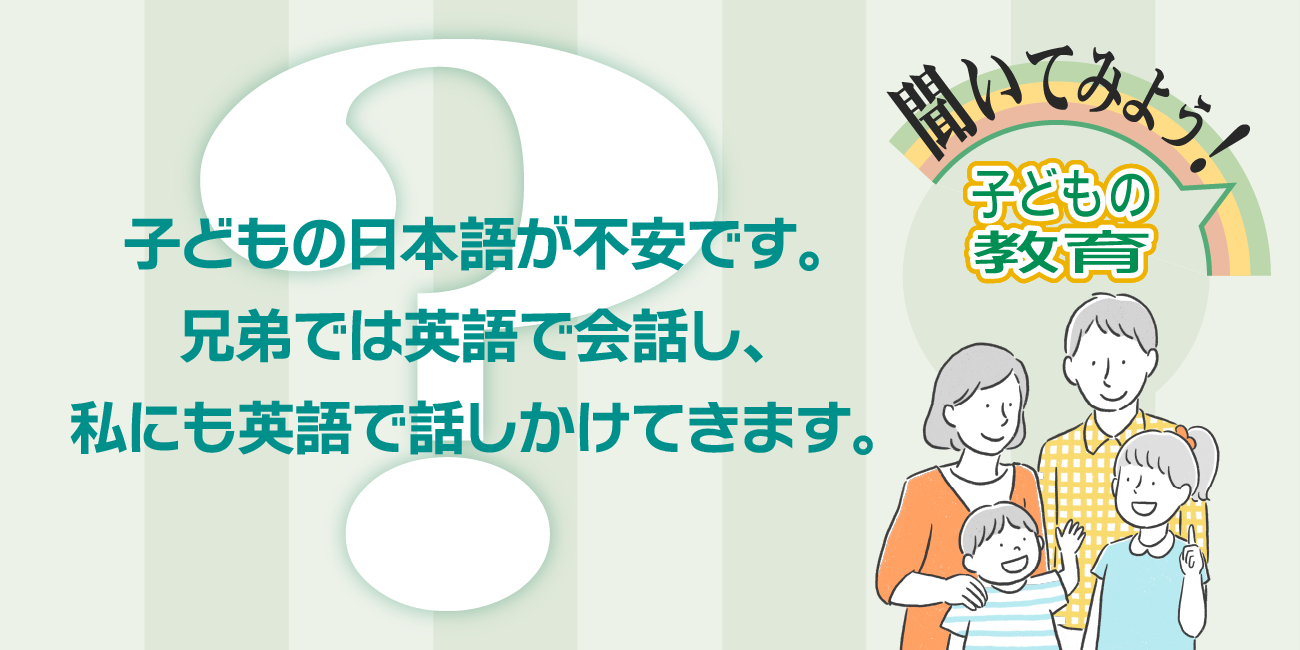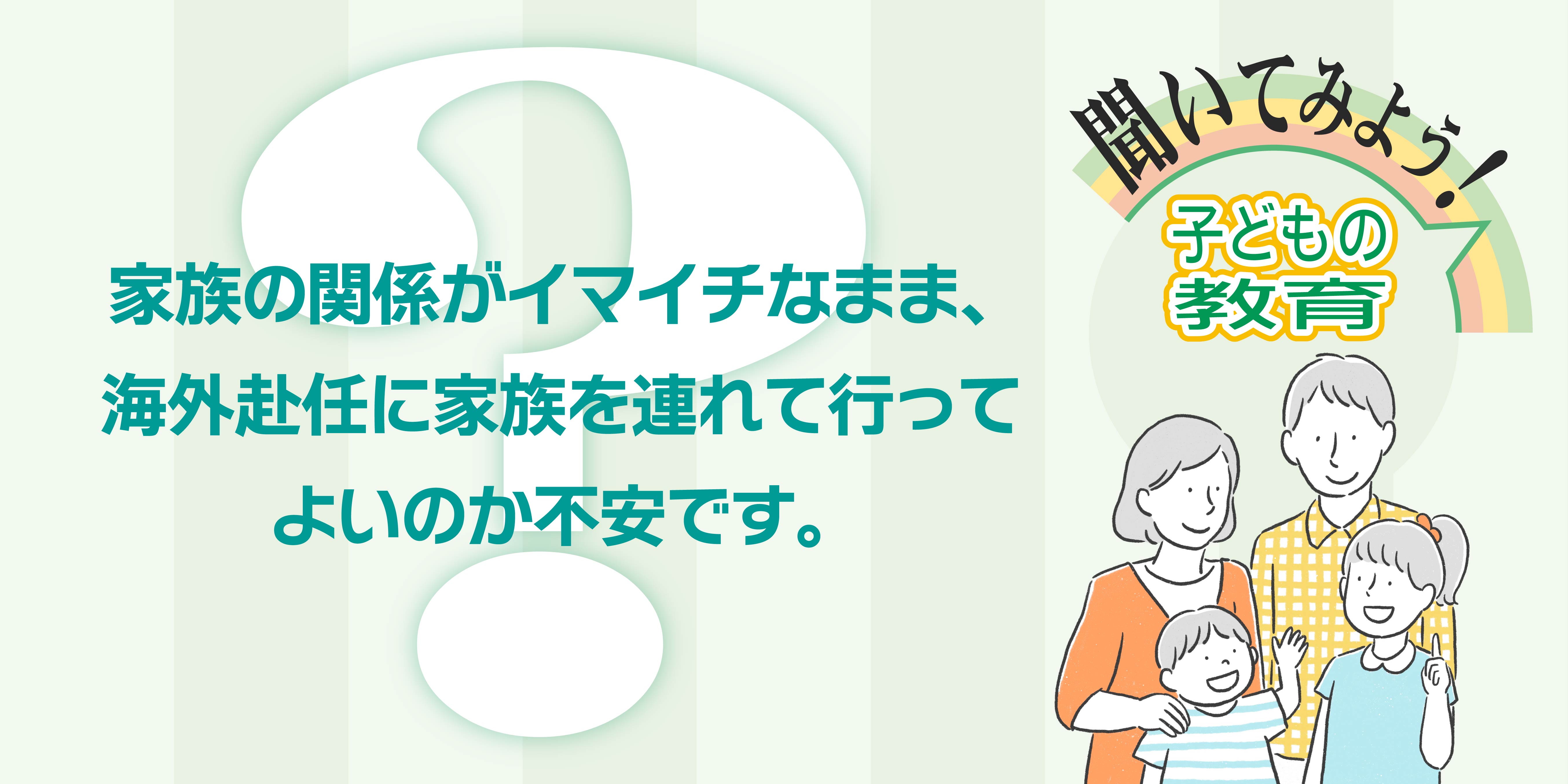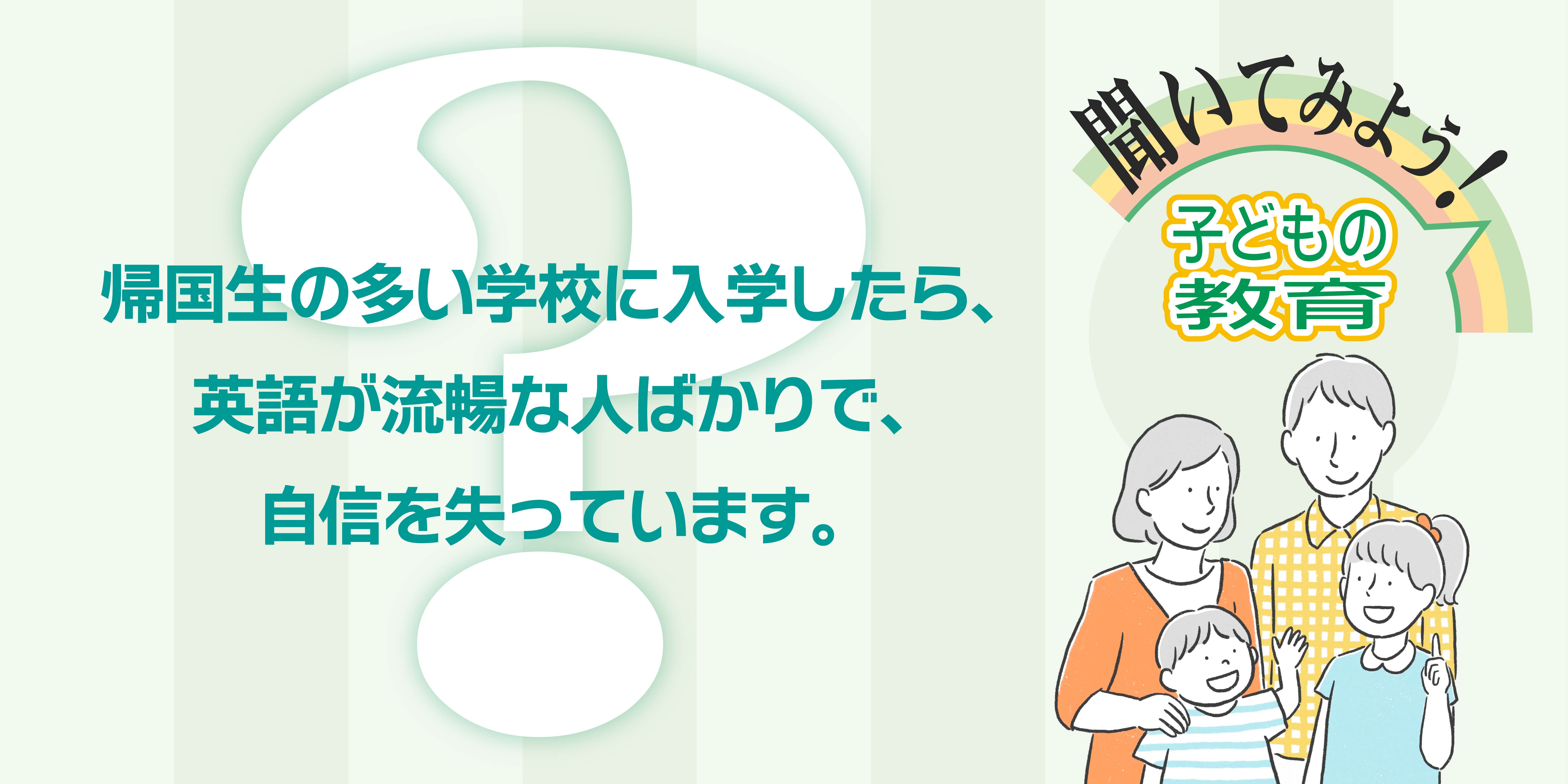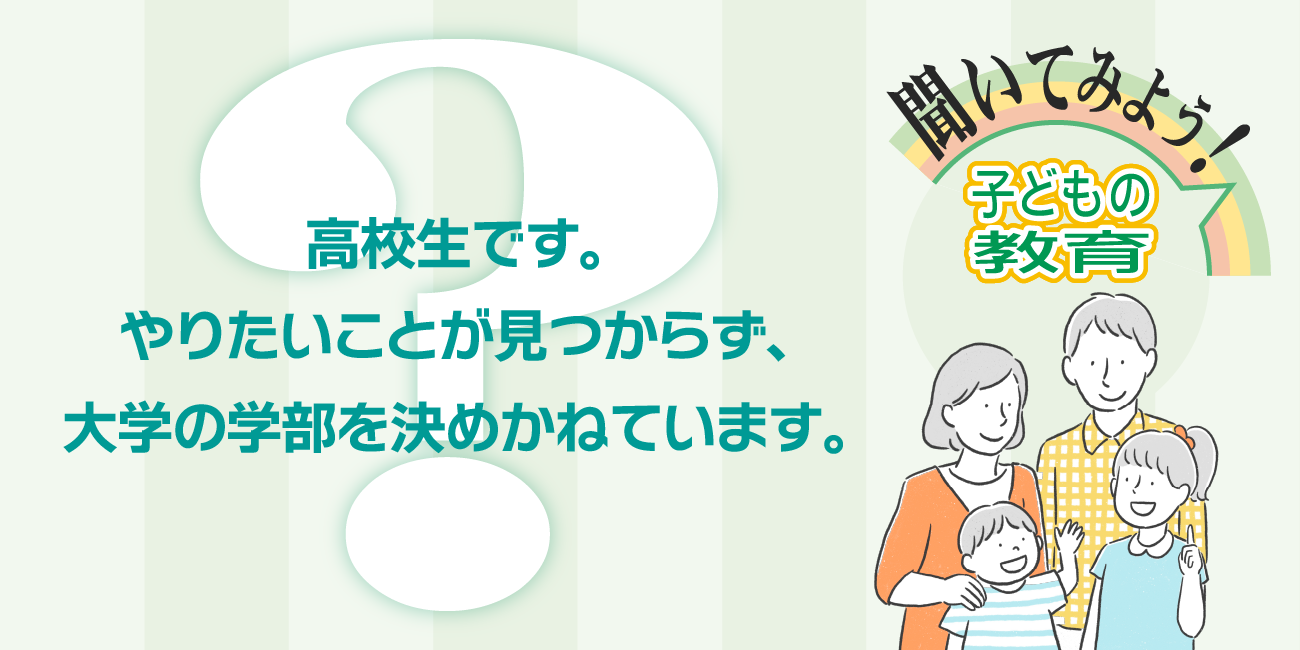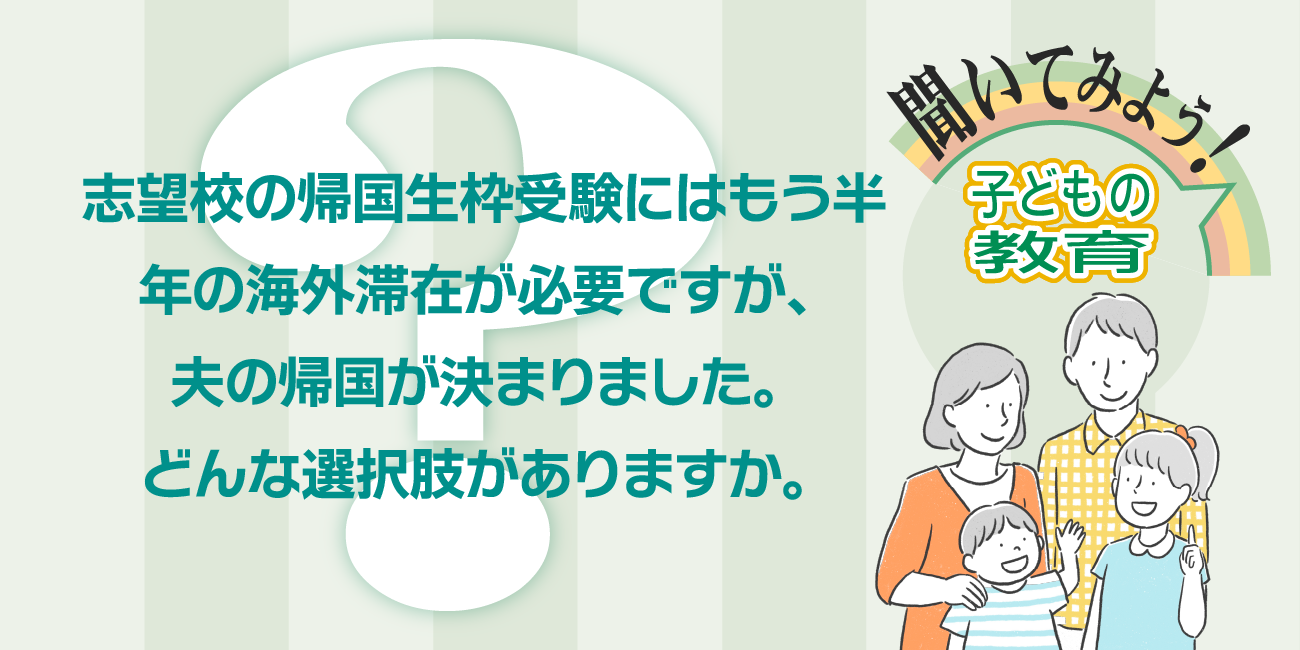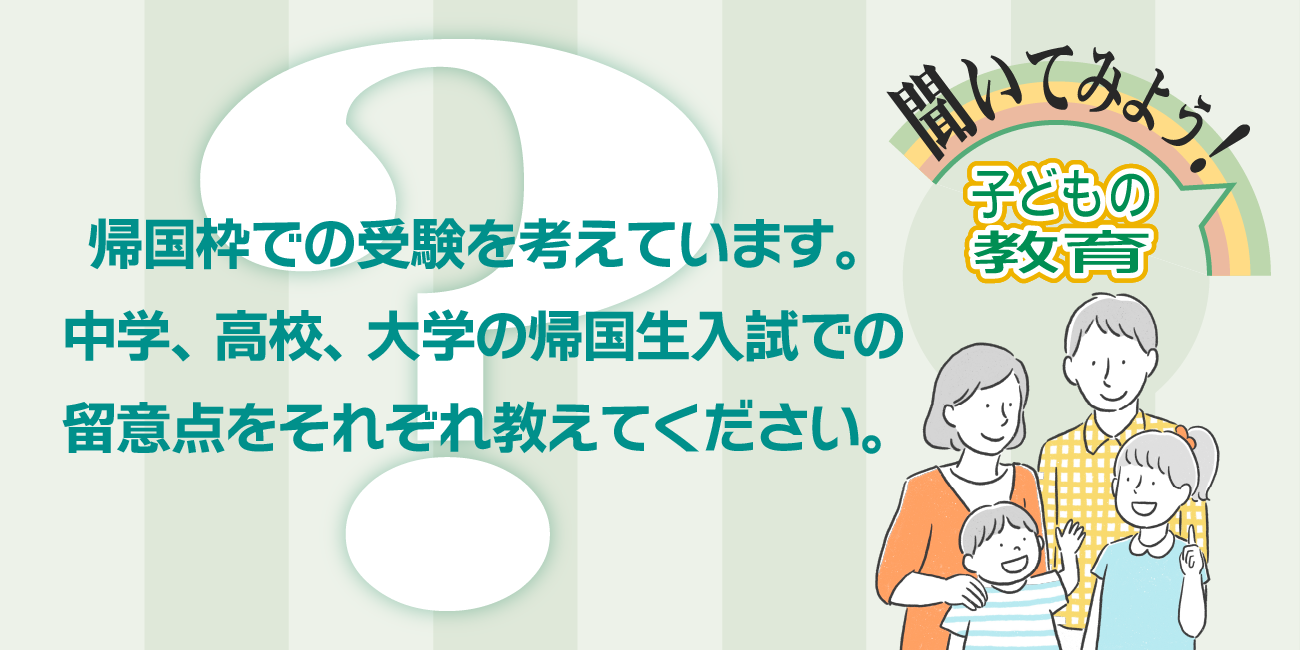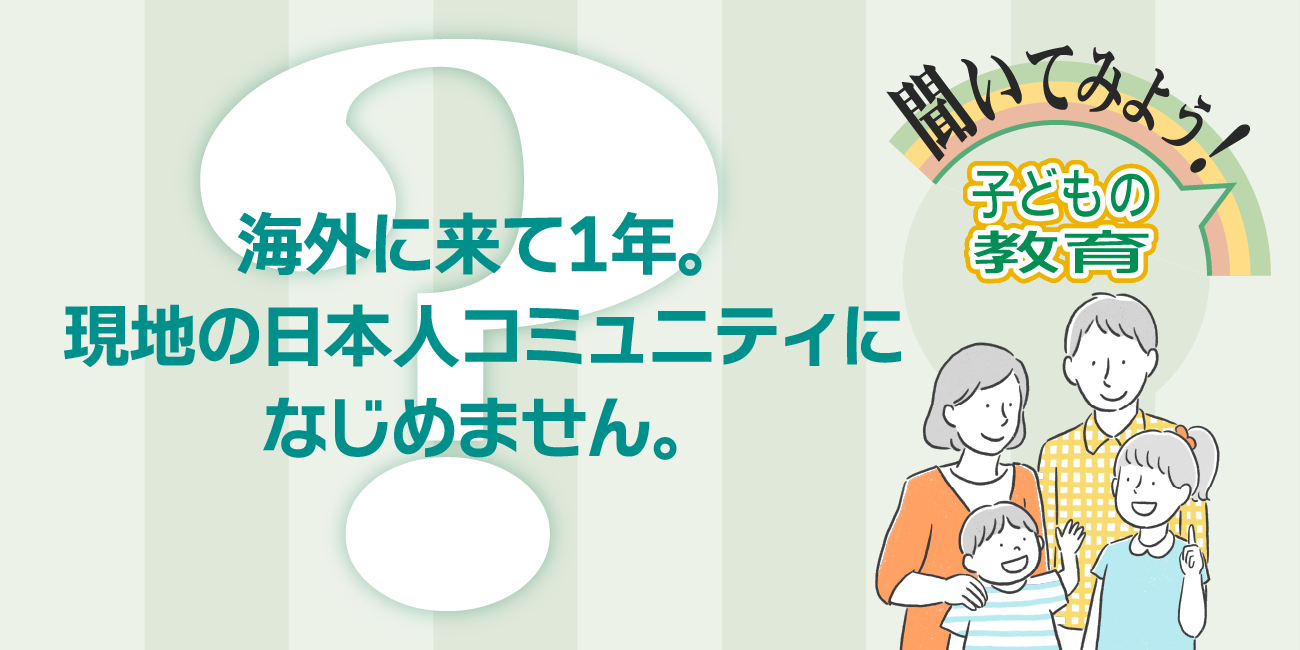<質問> 子どもの日本語が不安です。兄弟の会話では英語を使い、私にも英語で話しかけるようになっています。
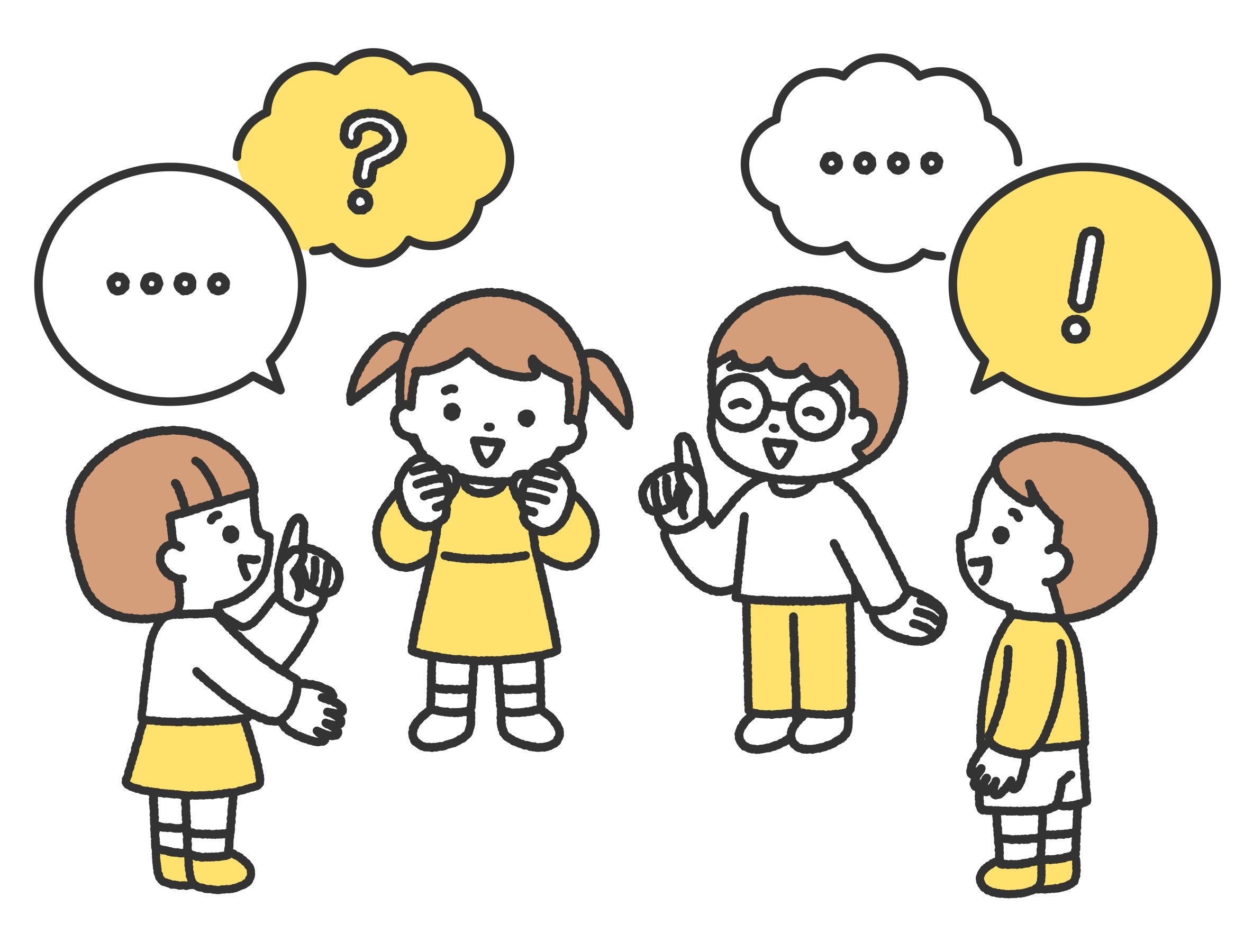
言葉の獲得
いったい人はどうやって「言葉」を獲得するのでしょうか。
言語獲得には大きく分けて、生得的な能力を重視する「言語獲得装置(LAD)」と、環境からの影響を重視する「言語獲得支援システム(LASS)」の2つの概念があります。言語獲得装置は言語学者ノーム・チョムスキーが提唱した概念で、人間は生まれつき言語を習得するための特定の脳の機能(言語獲得装置)を持っていて、そこから普遍文法、つまりすべての言語に共通する文法の基礎を抽出し個別の言語の文法を形成するというものです。また、言語獲得支援システムは、心理学者ジェローム・ブルーナーが提唱した概念で、子どもの言語発達には周囲の大人、特に親の言語的サポートが不可欠であると説き、大人は子どもの言語発達段階に合わせて適切な言葉かけやコミュニケーションを行うことで言語習得を支援するとした概念です。
この2つの考え方の違いは、言語獲得に関する「何か」が個人内にあるか、環境にあるかという視点ですが、いずれにしても生まれたばかりの赤ちゃんは周りの人が話しかける言葉を聞き、真似ることで徐々に言葉を覚えていきます。
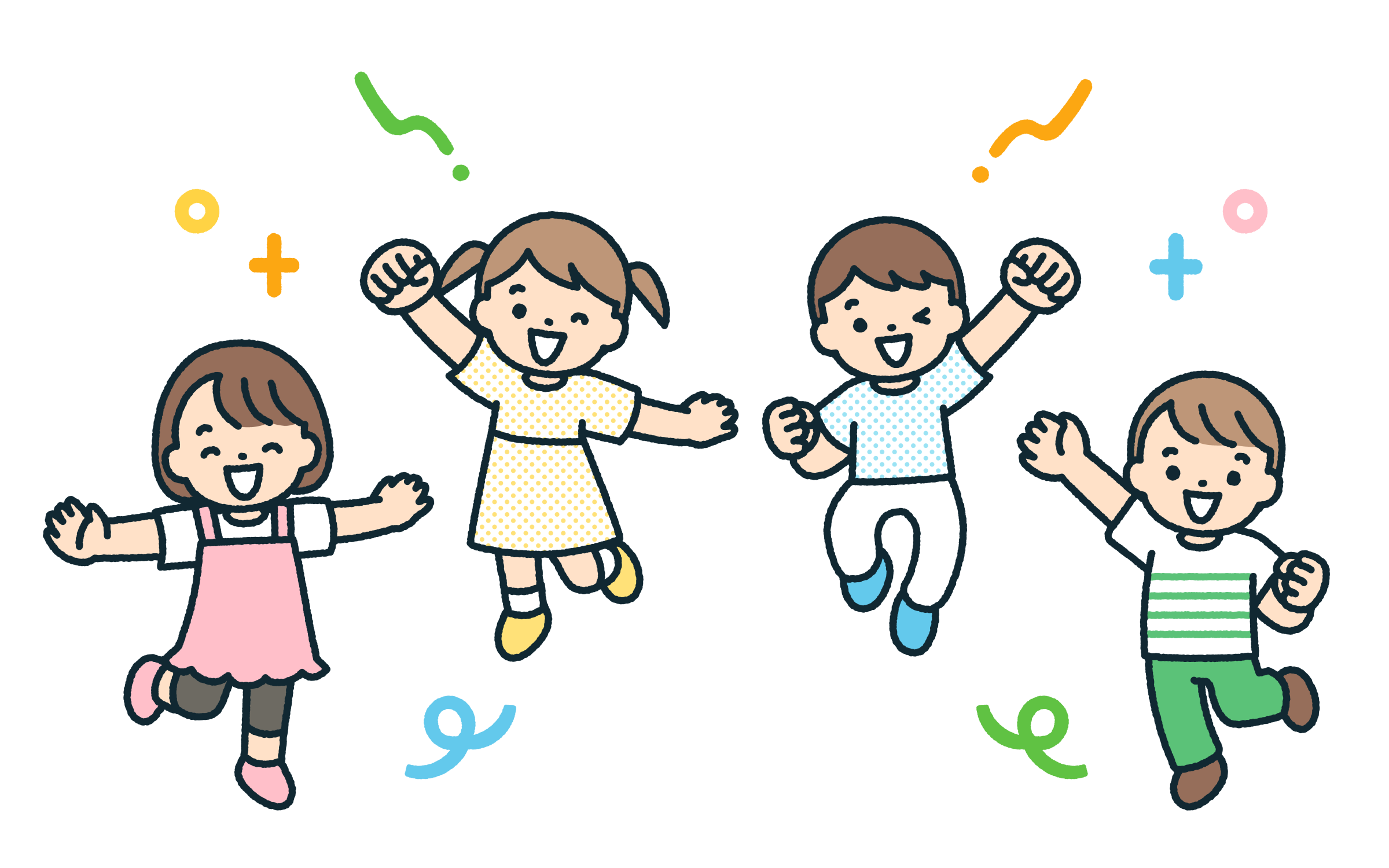
言葉の基本は母語で育つ
両親から最初に習得した言葉が「母語」です。母語は人間形成や感性といった人間の成長の基盤となる言葉のことで、第1言語とも言います。日本人であれば多くの場合「日本語」ということになります。母語は、学習の理解力や思考力、想像力、アイデンティティの形成などの基本となり、とても大切なものです。 母語がもっとも急激に発達するのは2歳から4歳ごろで、小学2年生くらいまでに深層面の中核となる「言葉の基礎力」を作っていきます。そして、母語で学習できる力(読む力・書く力)は、小学3年生から4年生頃までに完成するといわれています。
ですから、お子さんが小さい場合は、母語の獲得ということをぜひ大切に考えてください。
小さいお子さんの言葉は「学ぶもの」というよりは「生活そのもの」です。
日本語を使う環境が少なくなると日本語の力が弱まってきます。すると言葉の基礎となる力も弱まっていくことになります。言葉の力が弱くなるというのは単にその言葉が話せなくなるということではなく、理解力や思考力などその後の学習にも影響を及ぼすということになります。
したがって、現地校やインターナショナルスクールに通う場合は特に注意が必要です。理解力や思考力を高めるには母語が土台になりますので、小学2年生くらいまでは母語の獲得について、家庭での支援が欠かせません。
言語学者のカミンズは、2つの言葉の関係を「氷山のたとえ」で表しました。母語の発達が順調に進むと言葉の基礎力がしっかりつき、第1言語も第2言語もきちんと力を発揮します。
しかし母語が未発達な場合は、日常会話はできてもことばを使って考えたり学んだりすることがどちらの言葉でも難しくなり、言葉をうまく活用できない状態になります。
つまり「日本語ができなければ英語もできない」ということになります。小さいときに外国に行けば、英語も日本語も自然に同時に身につく、というのは誤った考え方で、かなり注意をしないと後々お子さんが苦労することになるのです。
物事を論理的に分析し、類推・比較し、まとめるといった抽象的思考力や、文章構造や文章の流れをつかむメタ言語能力といった「深層面の中核」となる言葉の基礎力を取り戻すには、相当の時間とエネルギーが必要となります。

母語があやしくなったサイン
日本語が母語であるはずのお子さんが、他の言語に徐々に移行していく現象のことをLanguage Shift(言語シフト)と言いますが、英語へのLanguage Shift が起きた場合の事例として、例えば「日本語に英語が混じる」「日本語に間違いが出てくる」「兄弟姉妹の会話が英語になる」「日本語で尋ねたのに英語で答える」などがあげられます。今回のお問い合わせの状況は、まさにLanguage Shiftが起こり、日本語を失いつつある状態といえます。
このように日本語に英語が混じったり、兄弟姉妹の会話が英語になったりするのは、子どもが日本語の必要性を感じなくなり楽な方の言語を使うからです。したがって、「家庭では日本語だけを使う」などのルール作りが大切になります。
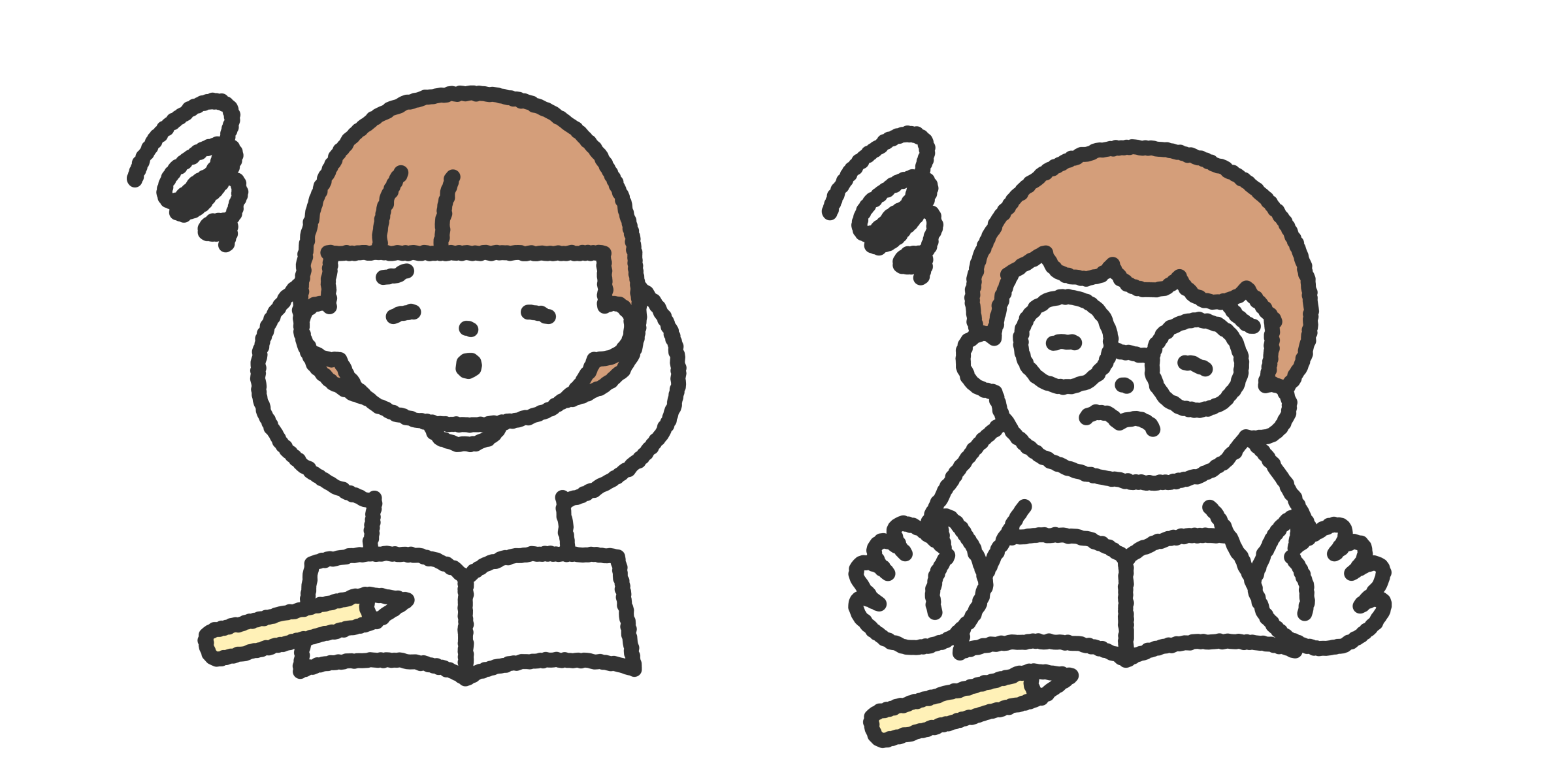
母語(日本語)を鍛える方法
日本では、ありとあらゆるところから日本語が聞こえてきます。しかし海外では、家族や在外教育施設・日系の幼児教育施設の先生や友達など、限られた環境からしか聞こえてきません。また会話をする場所が限定されるので、語彙の量が極端に減ります。ですから、海外では意識して日本語を聞く・話す機会を増やすことが重要となります。
幼稚園などに通って集団生活を始めれば、小さな子どもほどすぐに現地の言葉を覚える傾向にあります。
海外で日本語を育てるために気をつけていただきたいことは、家庭では正しい日本語での会話を徹底するなど「言葉のしつけ」を心がけてほしいということです。そして間違った日本語にはお手本を示してあげてください。
本の読み聞かせや、しりとり、かるたなど日本語に触れる機会を増やすことも大切です。その中でも読書は極めて大事ですので、お子さんの周りにたくさんの日本語の本がある環境を作ってあげてください。
一緒に絵本を読むときは膝の上など、なるべく近い距離で読んであげましょう。また、ゆっくりはっきりと、お父さんお母さんのやさしい声で読んであげるといいですね。うなずいたり相槌を打ったりしながら聞けるよう、たまには楽しい会話を交えたり、驚きの表情や楽しそうな表情、悲しそうな表情を駆使して読んだりすることも大事です。
ときには子どもが記憶した台詞を言わせて、参加型で読むのもいいと思います。「~は」「~が」など、助詞を強めに読むことも工夫の一つです。

ピンチはチャンス
英語に慣れることで日本語が「いらない言葉」にならないよう、日本語が必要な環境を意図的に作る必要があります。Language Shiftの兆候が表れたときこそチャンスととらえ、家では「日本語を使うのが当然」という雰囲気を作りましょう。
また、意識して「正しい日本語」を使うようにしてください。成長段階に応じた内容の会話をするように心がけることや、時間を決めて読み書きするなど「日本語を勉強する機会」を作ることも大切です。
日本語に英語が混じるのは、日本語の表現が出てこないとき英語を代用するためです。そんな時は正しい日本語を聞かせるチャンスです。
「ママ、help してあげようか?」
「あら、手伝ってくれるのね。ありがとう」
また、外国語の感覚で日本語を使う場合は、日本語の正しい使い方を教えましょう。
「このスイカ、さむくておいしい」
「ほんとにおいしいね。スイカは『つめたい』と言うんだよ。冬は『寒い』だね」
兄弟姉妹の会話が、英語になった場合、ある程度は仕方がないかもしれませんが、可能であれば、上の子には弟や妹のために日本語を使うように頼んでみましょう。
"Can I use your bike??"
"OK."
「自転車に乗るの。気をつけてね」
英語で話す方が楽に感じるようになったときは、家では「日本語」を意識させ、努力をほめましょう。
「ママ、Will you pick me up at the gym?」
「え? 日本語で言って」
「えっと、たいいくかんに、むかえにきて」
「はい、体育館に迎えに行きます。上手に言えたね」
日本語を育てるのは保護者の責任です。それぞれの家庭に合わせた対策を行ってください。漢字だけを学習させている家庭がありますが、漢字だけ覚えてもそれだけでは日本語の能力は伸びませんのでご注意ください。 また、生活言語と学習言語は別物です。日本語が話せることと、日本語を使って学ぶこととは異なりますので、お子さんの状況を正しく把握するようにしてください。
今のようにインターネットが発達していない時代、我が家は2歳の娘をオーストラリアに帯同し、現地の幼稚園にも通園させていました。
我が家では、日本の子ども番組や子どもが好みそうなアニメをビデオテープに録画して大量に持参し、日常的に日本語に触れる機会を徹底的に確保しました。
娘はジブリ映画の『トトロ』が大好きで、時間があれば繰り返し観ていました。帰国する頃には、台詞をすべて覚えるほどでした。その甲斐もあったのか、小学校に入学した時も何の障壁もなく学校生活を送ることができました。家庭により考え方は異なると思いますが、お子さんに合った対策をすることは必要です。

最後に
Language Shiftに陥らないためには、ご両親のかかわりが重要となります。
お子さんは現地の学校の宿題に追われたり、日々のスポーツ活動等に思いのほか時間を取られたりして、日本語力の伸びが遅れがちになることがあります。母語の発達に十分気を配っているつもりでも、特に敬語や日本語独特の単語・表現などの語彙の広がりは自然には期待できません。
2言語のバランスを考えながら、時間をかけて学年相応の学習言語を身につける努力をご家族で心がけてください。
第1言語を十分に入れてもらった子どもは、第2言語の習得もしやすくなります。お子さんをセミリンガルにしないためにも、ぜひ正しい日本語を与え続けることを忘れないでください。
<回答者> 海外子女教育振興財団 教育アドバイザー 渡辺 稔(わたなべ みのる) グローバル化が進む現代において、海外での生活は、お子さんにとってかけがえのない経験となり財産となります。言語や文化・習慣の全く違う国での生活は、苦労も多いかもしれませんが、その分、得るものも多くあります。お子さんにとって有意義な学びとなるよう、教育相談を通してお役に立ちたいと思います。 プロフィール ・元神奈川県公立学校校長 ・元シドニー日本人学校教諭、リオデジャネイロ日本人学校校長 ・2023年より現職