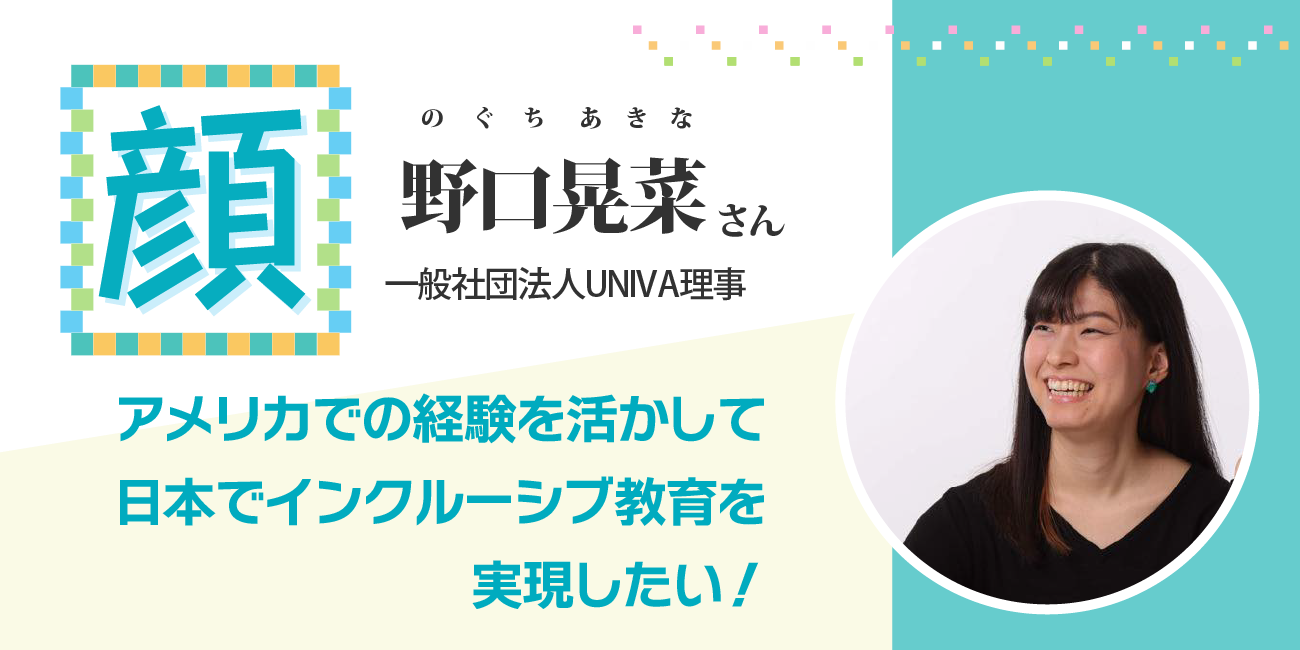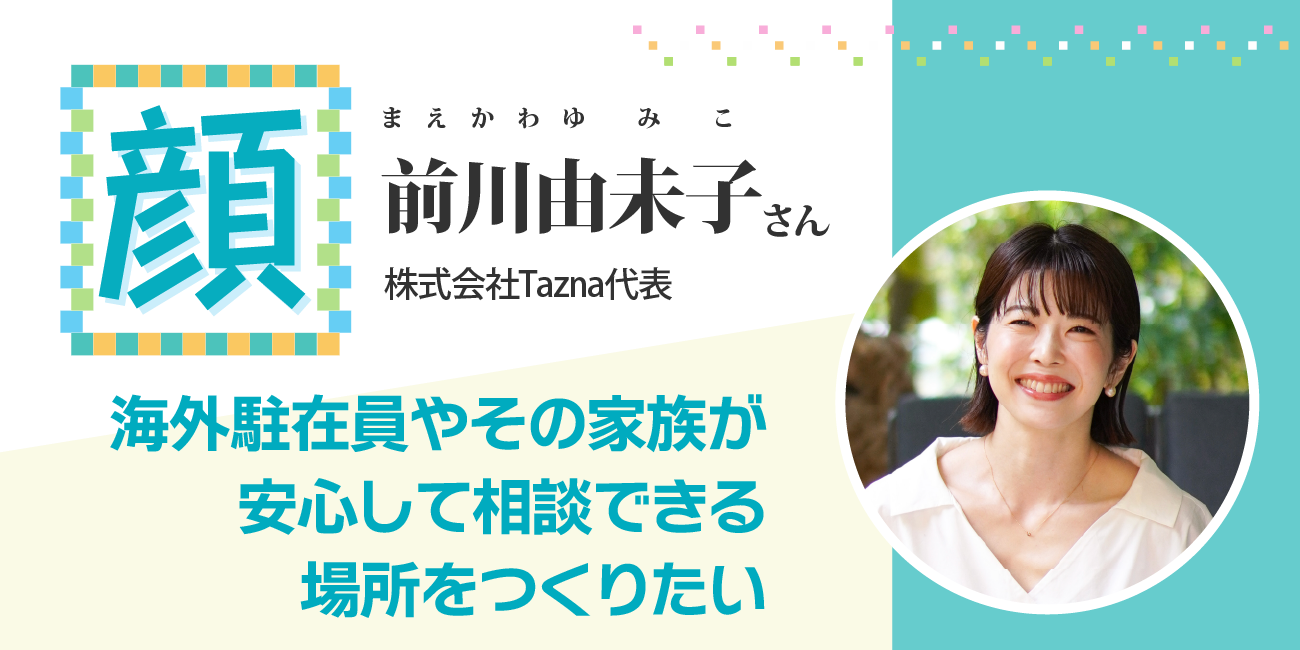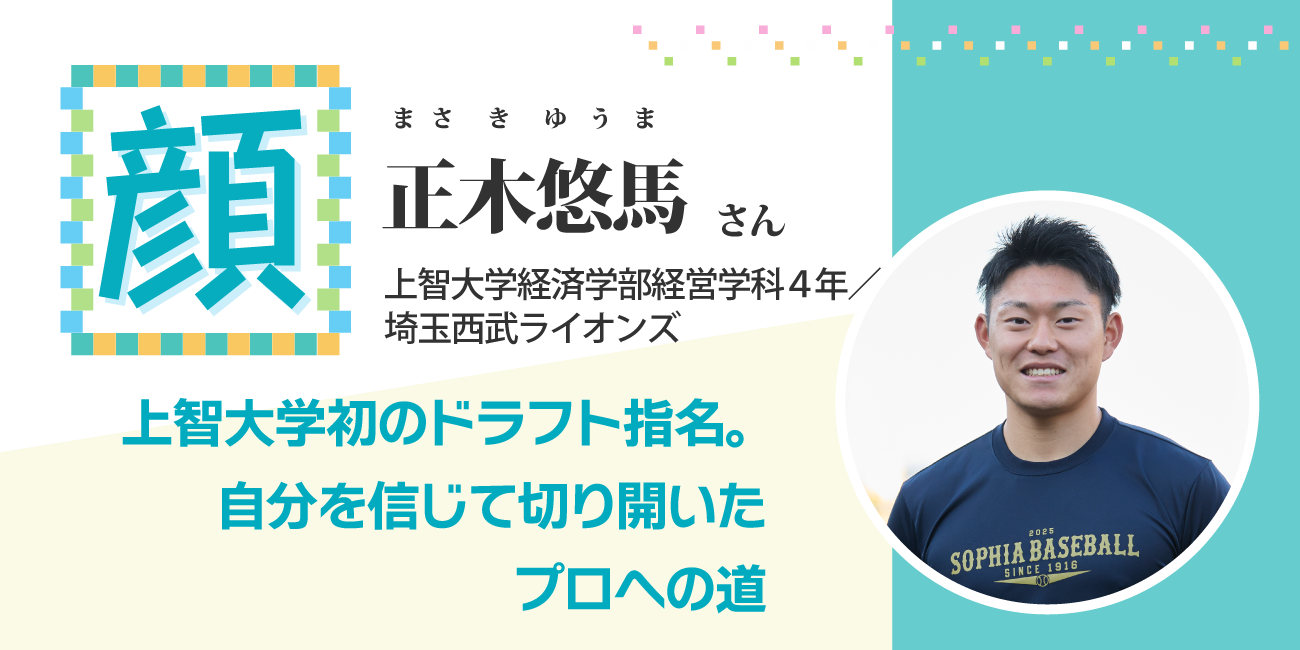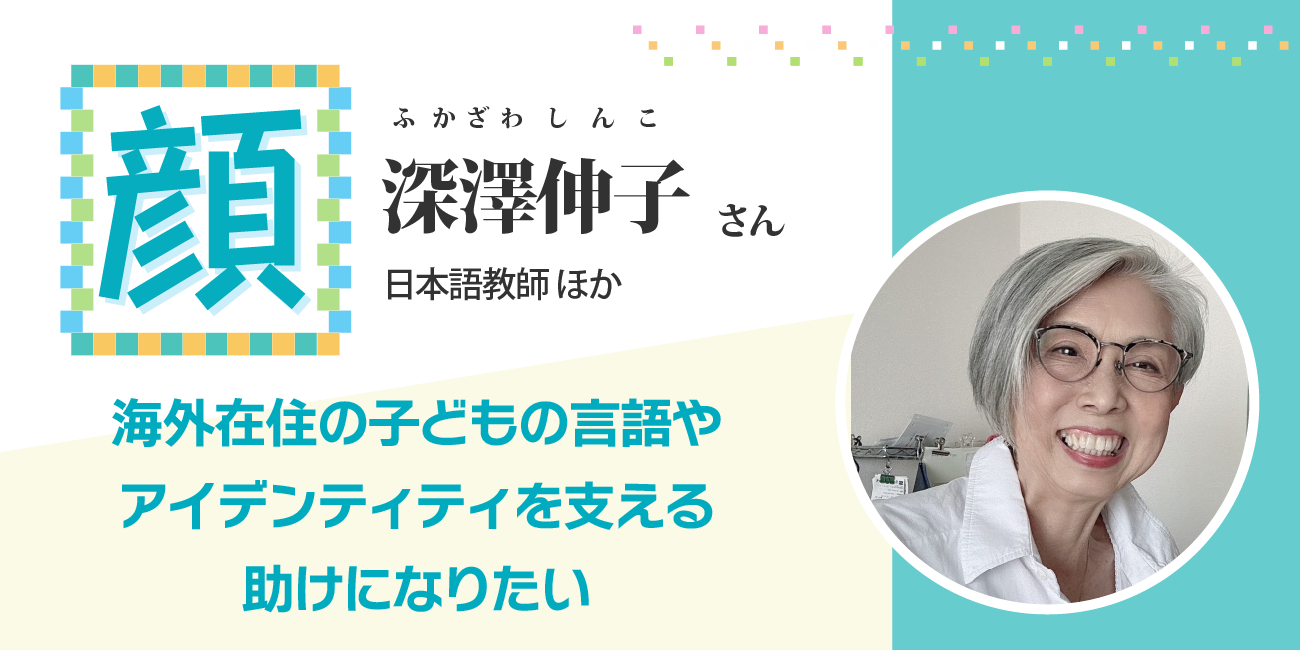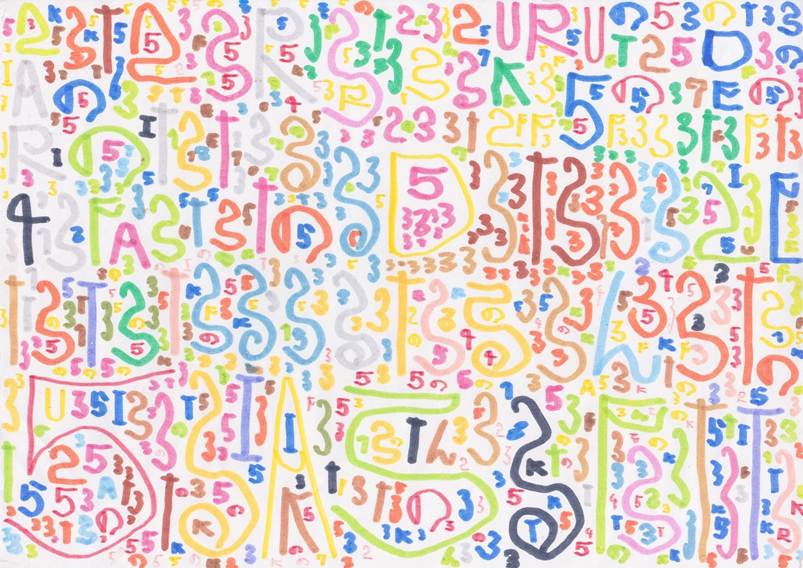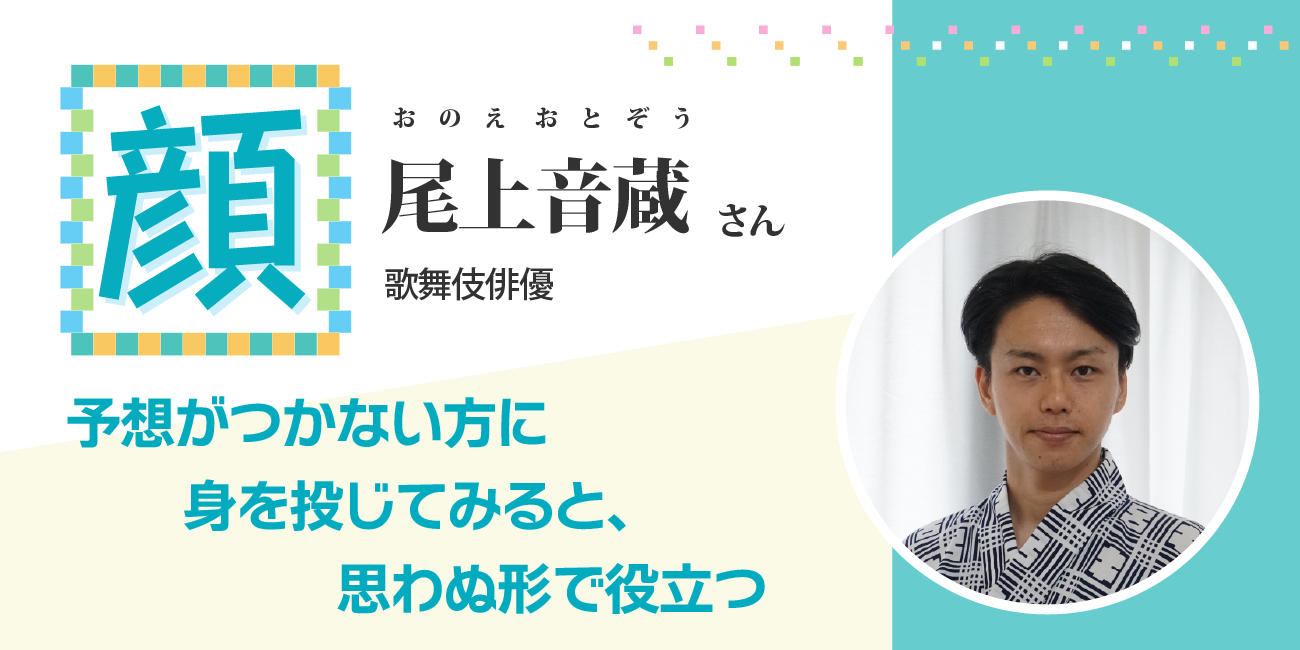インクルーシブ教育の研究者である野口晃菜さんは現在、一般社団法人UNIVA理事、中央教育審議会委員、戸田市インクルーシブ教育戦略官として、「多様な子どもたちが安心して過ごせる学校づくり」に取り組んでいる。この活動の原点は、小学校6年次に編入したアメリカの現地校で、車いすの子や脳性麻痺の子が当たり前にクラスで一緒に学ぶ姿を見た経験や、自身のはじめてマイノリティ経験があった。日本の学校をアップデートする野口さんの活動について詳しく聞いた。
(取材・執筆:丸茂健一)
「違い」が当たり前である中で共に学ぶ環境をどうつくるか
——野口さんの現在のお仕事について教えてください。
私は現在、一般社団法人UNIVAの理事や中教審の委員などを通して、学校や教育委員会と協力しながら「多様な子どもたちが安心して過ごせる学校づくり」に取り組んでいます。子どもたちが「違い」を当たり前のこととして捉えながら、異なる他者と共存する方法を学ぶ環境をどうつくるか——それは、私自身の原体験と深く結びついたテーマでもあります。
インクルーシブ教育の理念はすべての子どもが異なることを前提とした教育システムを目指すものです。障害のある子どもだけでなく、外国にルーツを持つ子ども、性的マイノリティ、貧困家庭の子どもなど、あらゆる「違い」を踏まえることが大切です。多様な子どもを既存の学校の枠に当てはめるのではなく、多様な子どもたちに合わせて学校側がアップデートしていくことがポイントです。
私の仕事は、学校でのインクルーシブな実践を先生方と共に考えたり、先生たちや学校を支える制度を整えたりすることです。実践と研究と政策をいったりきたりしながら、一歩ずつインクルーシブ教育を実現していく活動を続けています。

——障害児教育やインクルーシブ教育に関心を持つようになったきっかけは?
幼少期のアメリカ生活にあります。小学校6年生のとき、父の仕事の関係で、家族でアメリカのシカゴに移住することになりました。その前は埼玉県の公立小学校に通っていました。日本では一部の地域を除いて障害のある子どもたちと同じクラスで学ぶ機会は限られていたため、当時私の日常には障害のある人はいないと思っていました。
しかし、アメリカの公立学校に通い始めると、そこには車いすユーザーの子、脳性麻痺の子、言葉に障害がある子など、さまざまな子どもたちが同じ教室で学んでいました。日本の学校ではまったく出会わなかった光景が、そこでは“当たり前”として存在していたのです。最初は衝撃を受けましたが、次第に「なんで今まで一緒に学んで来なかったのか?出会う機会すらなかったのか?」とむしろ、日本の学校に疑問を感じるようになりました。
当時は私自身も、アメリカの現地校で英語がわからず、文化もわからず苦労していました。初日はランチのもらい方がわからず、助けの求め方もわからず、ただ泣くしかありませんでした。最初の数カ月は授業中も「何を言われているのかまったくわからない日々」でした。つまり、はじめて自分がマイノリティの側に立つ経験をしたのです。
私が通っていた小学校には、英語を話せない子どもが英語を学ぶESL(English as a Second Language)クラスがあって、そこでは私のような英語が第一言語ではない外国にルーツのあるの子がサポートを受けながら学んでいました。「必要な人が必要なサポートを受ける」——それが当たり前に制度として組み込まれていたことに救われました。

アメリカ同時多発テロで気づいた「無理に同化しなくていい」
——その状態からどうやって立ち直っていきましたか?
最初こそ苦労したものの、英語を覚えるのはかなり早かった方だと思います。渡米して1年も経たないうちに、英語で不自由なく会話できるようにはなっていました。その背景として、私は当初から「早くアメリカ人のようにならなければ」という気持ちを強く持っていました。アメリカ人のようにならなければ、友達ができない、見下されるかも、いじめられるかもと思い、クラスで目立っていた白人の子たちのように振る舞い、英語しかしゃべらない生活を自分に強いていました。日本語のテレビは見ないし、日本人の友達とも距離を取る。必死に現地に“同化”しようとしていました。
その考えは高校1年生のとき、2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロをきっかけに揺らいでいきました。9.11後、まだ犯人が特定されていないうちから、当時のブッシュ大統領は「責任者を追跡し罰する」と発言し、軍事措置を含めた報復を示唆し、街中が一気に戦争ムードに包まれました。人々は国旗を掲げ、「United We Stand(団結しよう)」というスローガンが広まりました。さらに、学校でも国旗に忠誠を誓う「Pledge of Allegiance(プレッジ・オブ・アレジアンス)」(「私はアメリカ国旗に忠誠を誓います」)を毎朝唱えるようになりました。
小学生の頃は意味もわからずに、「Pledge」を唱えていましたが、高校生になった私は、その意味を理解していましたこのような一連の出来事に強い違和感を覚えたのです。「戦争」を初めて身近に感じ、私はこの国に忠誠を誓いたいのだろうか? あれほど憧れていたアメリカという国に初めて距離を感じたのです。
それを機に、自分のアイデンティティを考えるようになり、これまでアメリカ人に同化したい、同化しなければ、と思っていた気持ちがなくなりました。
——アメリカでの高校時代は主にどのような分野を学んでいましたか?
高校では、「教育」に関する授業を選択していました。アメリカの高校には実践的なカリキュラムがあり、保育園のように子どもを実際に預かって子どもとの接し方を実践的に学ぶ授業があったり、地域の小学校でインターンシップをしたりすることもできました。私は午後の時間をまるごと使って、地域の小学校で「教育実習」のような活動をしていました。教員のスーパービジョンを受けながら、通常の学級に在籍する読み書きに困難を抱える子どもを支援する機会もありました。

驚いたのは、高校生の私が読み書き困難な子どもの支援に関わっても、しっかりと質が保証されるように教材や教員のスーパービジョンの仕組みが整っていました。「仕組みがあれば、多様性に応じた教育ができる」、そう実感すると同時に、「日本ではどうなっているんだろう?」という疑問が湧いてきました。障害のある子どもは地域の学校で学べているのか。もし学べていないとしたら、なぜなのか。この問いが、帰国後に日本の大学で「障害科学」と呼ばれる分野を学ぶきっかけにつながっていきました。
筑波大学大学院で「障害科学」の博士号を取得
——日本の大学での専攻について教えてください。
筑波大学に進学し、心身障害学(現在の障害科学)を専攻しました。筑波大学は附属の特別支援学校を複数持ち、学部段階から障害について学べる環境が整っていたことが進学の決め手になりました。日本における特別支援教育について学んだ上で、大学院の博士課程まで進み、アメリカのインクルーシブ教育をテーマに研究を行いました。
日本では、従来障害のある子どもは特別支援学校や特別支援学級で学ぶような制度になっています。現在、特別支援学校や特別支援学級の在籍者数が年々増加しており、その結果、日常生活において特別支援学校の通う障害のある子どもと、小中学校に通う子どもが出会う機会が限られています。それが結果的に、大人になってから「障害のある人とどう関わればいいのかわからない」という状況や、障害のある人を排除する社会を維持しています。多様な子ども同士が出会い、共存する方法を具体的に学べるインクルーシブ教育は、インクルーシブな社会をつくることにつながります。
アメリカで英語のわからない私が支援を受けたり、私が高校生の時にインターンシップとして読み書きに困難のある子を支援したりすることが制度に組み込まれていたアメリカのインクルーシブ教育制度を参考にしたいと思い、博士論文ではアメリカについて研究しました。
——日本の学校でインクルーシブ教育を実現したいというモチベーションにアメリカの学校に通った経験は欠かせないものですね。
そうですね。私がインクルーシブ教育に関心を持つようになったもう一つの理由は、アメリカでマイノリティとしての生活を経験したことにあります。上記の通りESLなどは整っていたものの、「(アジア人が)下に見られている」と感じることは常にありました。
先ほどお話したように、「アメリカ社会に同化しなければ認められない」というプレッシャーの中で、自分をすり減らしたこともあります。今、インクルーシブ教育を推進する立場になって、そのときの経験や焦っている気持ちをよく思い出します。だからこそ、学校という場が「どんな人でも安心していられる場所」であってほしい。
同化しなくても良い、と伝えたい
——野口さんの今後の目標をお聞かせください。また、海外で暮らす子どもたちやその保護者にメッセージを!
国や自治体の委員などを通して 現在、次期学習指導要領の改訂に関わる会議の委員を務めています。ちょうど先日出た論点整理においては、初めて次期学習指導要領の方針として「多様性の包摂」が掲げられました。日本でインクルーシブ教育を実現する上での、大きな一歩であり、ようやくスタートラインである、と思っています。これまで通り、学校現場におけるインクルーシブ教育を先生方と共に実践しながら、政策提言や研究を通して、一つひとつできることを積み重ねていきたいです。
最近は、海外在住の日本人家庭で、障害のある子どもを育てる保護者のコミュニティともやりとりをしています。自分の経験を活かして、海外にいる保護者や子どもたちにとっても有益な情報提供や取り組みをしていきたいです。
海外で暮らす子どもたちやその保護者の皆さんには、「無理に周囲に合わせようとしなくていい」ということをお伝えしたいです。異なる文化の中で生きることはとっても大変です。私が思ったように、周りに合わせなきゃ、と焦る時もあるかもしれませんが、自分の好きなこと、自分のペースを大切にしてほしいな、と思います
プロフィール 野口晃菜(のぐち あきな) 一般社団法人UNIVA理事、戸田市インクルーシブ教育戦略官。筑波大学大学院人間総合科学研究科障害科学専攻博士後期課程修了。博士(障害科学)。文部科学省「中央教育審議会教育課程企画特別部会」「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」委員など。専門は障害科学・インクルーシブ教育。学校、教育委員会、少年院などと共に、インクルージョン実現のために研究と実践と政策を結ぶのがライフワーク。著書に『発達障害のある子どもと周囲の関係性を支援する』(中央法規出版)、『差別のない社会をつくるインクルーシブ教育』(学事出版)、『教室の中の多様性図鑑』(Gakken)(監修)などがある。