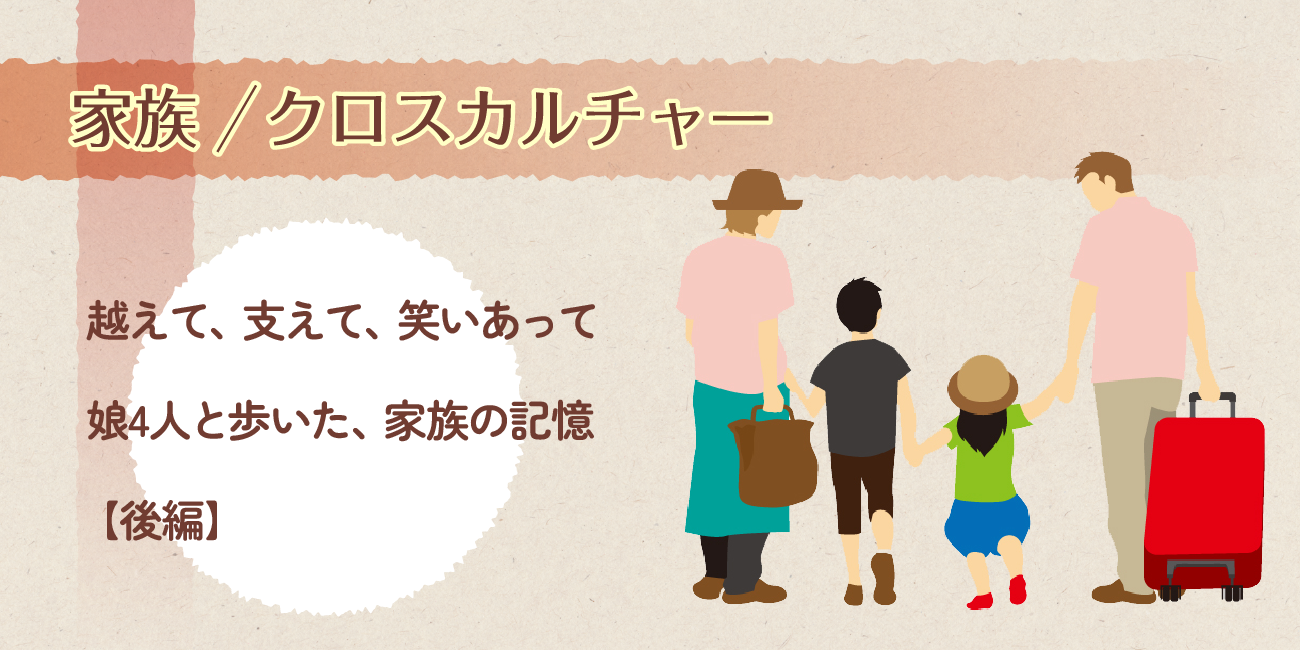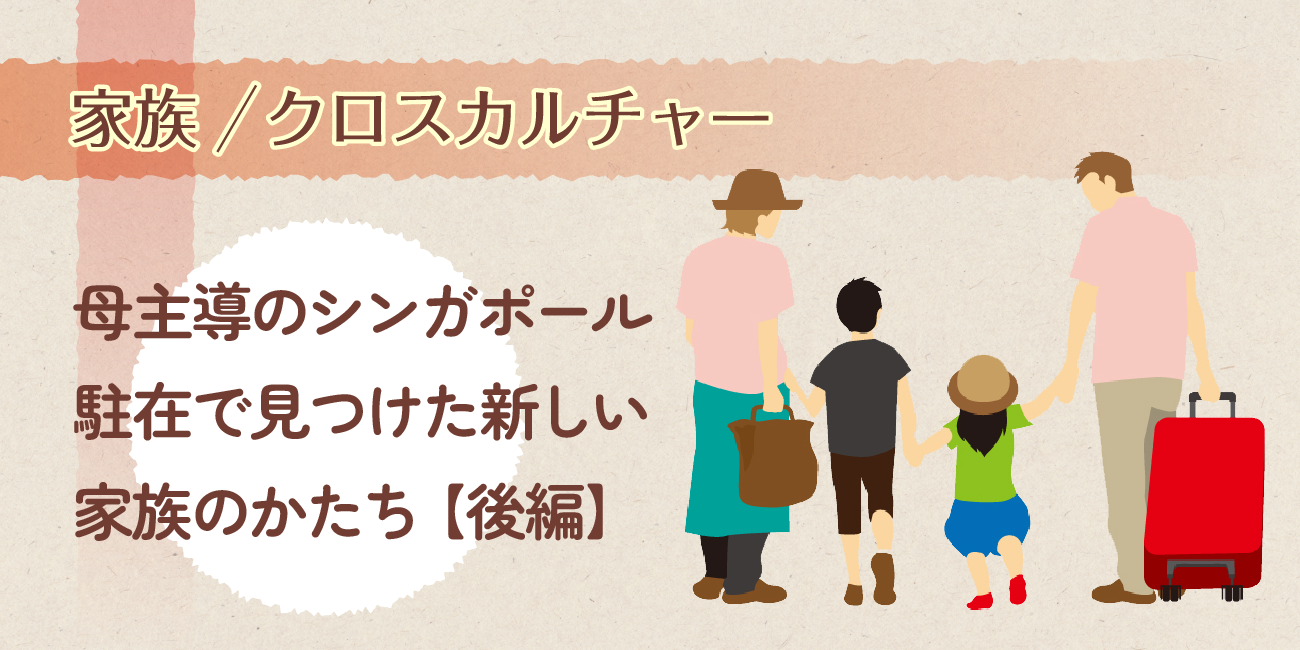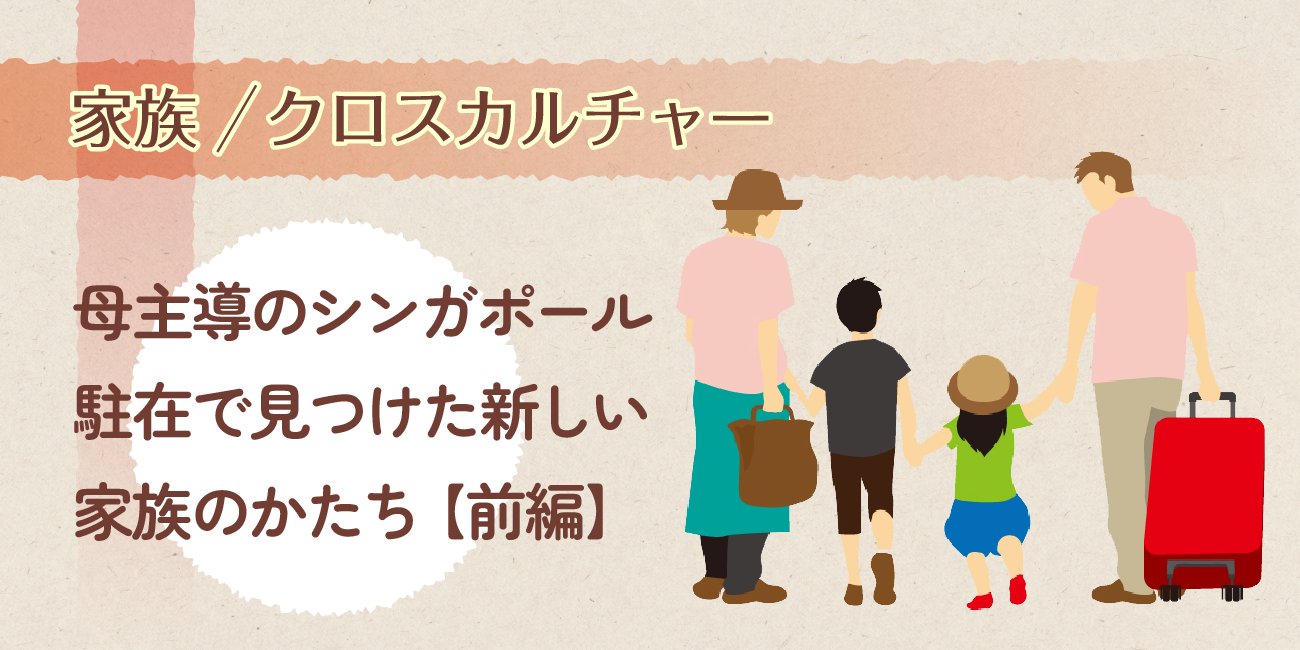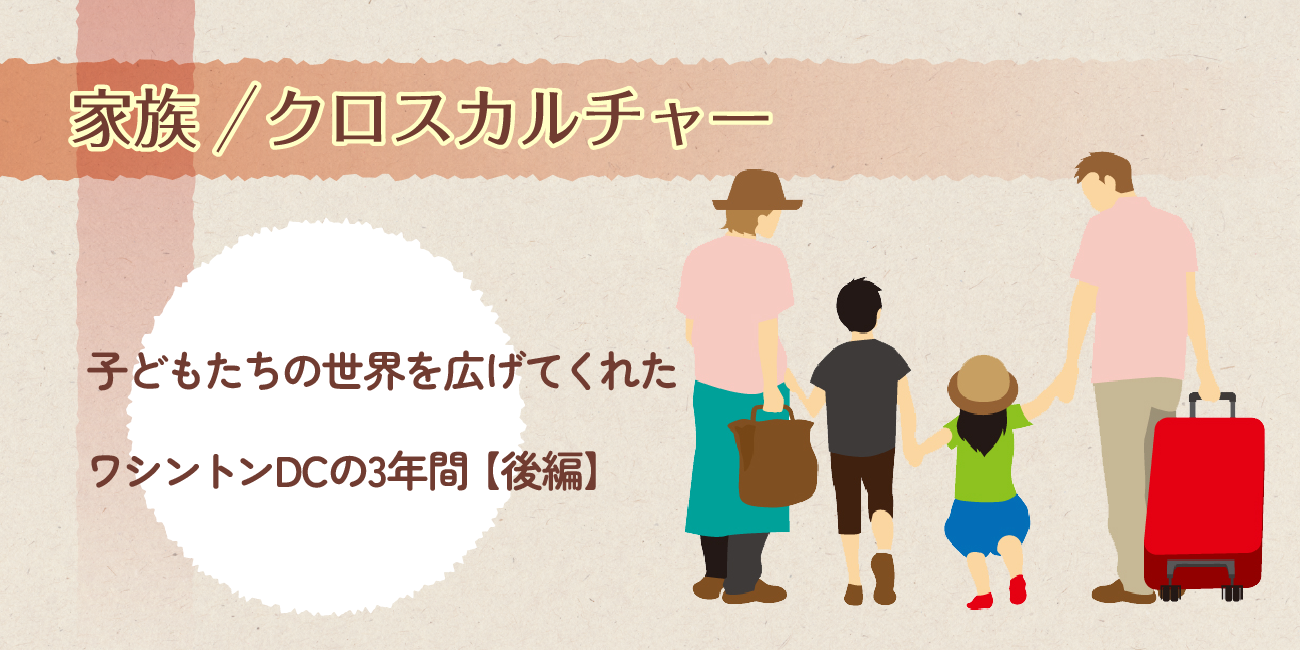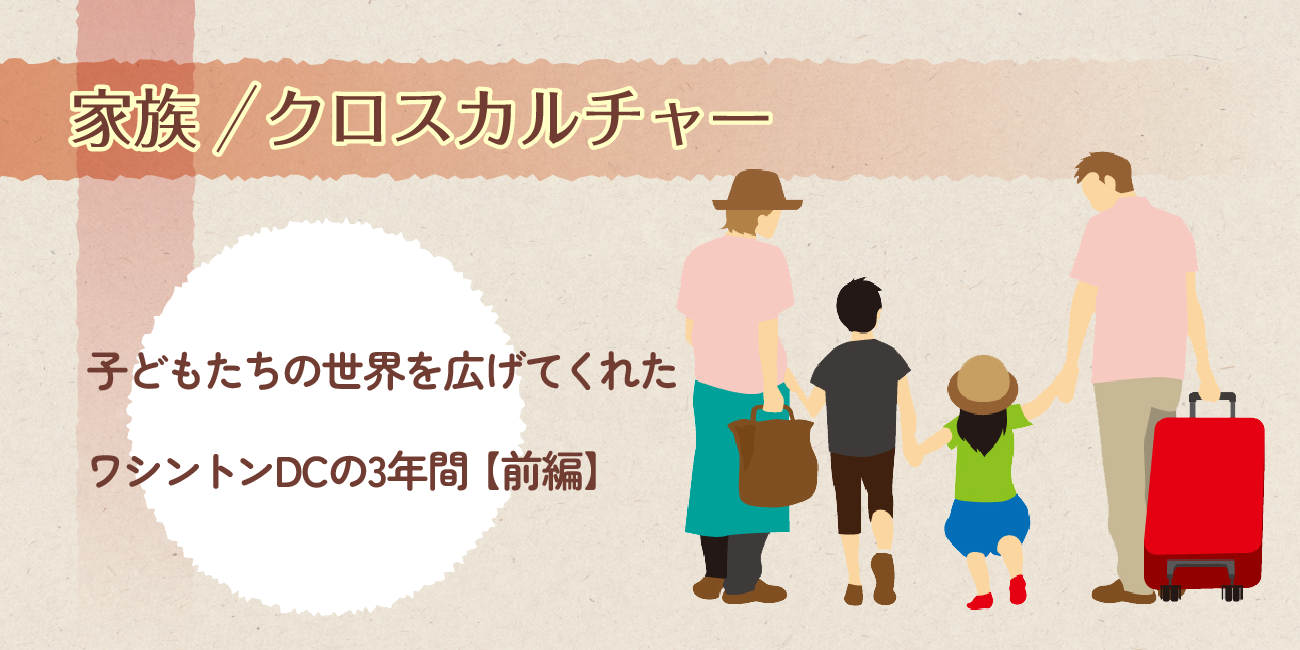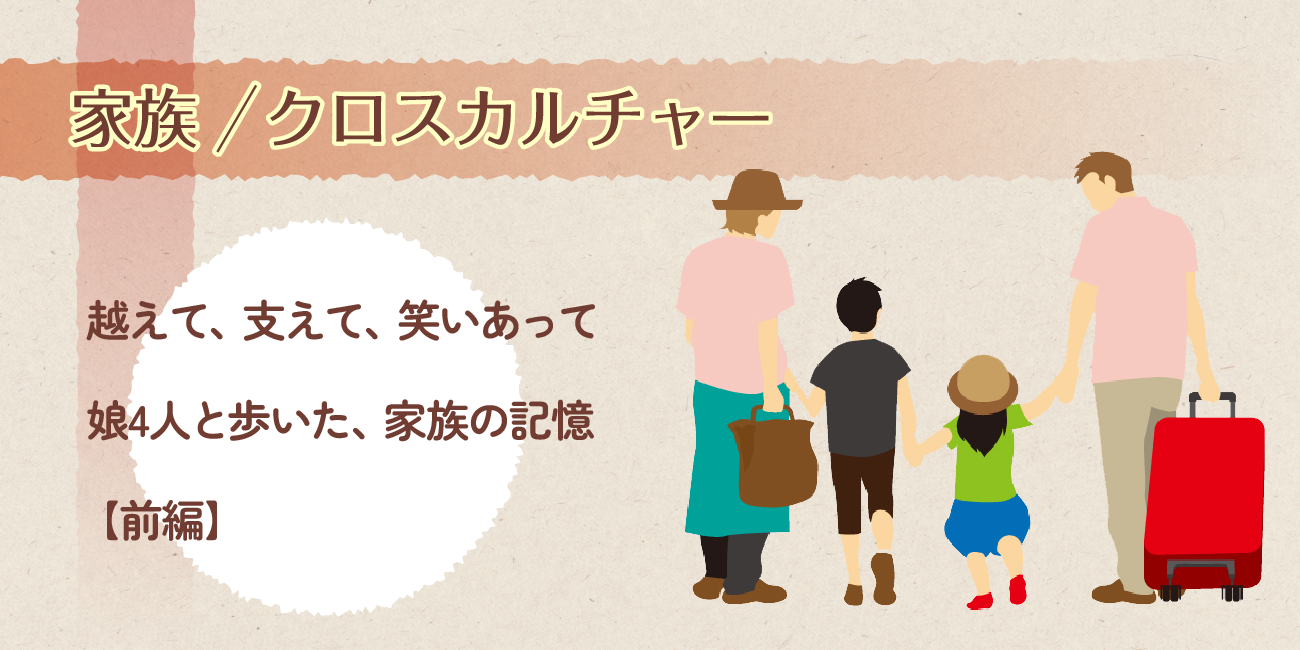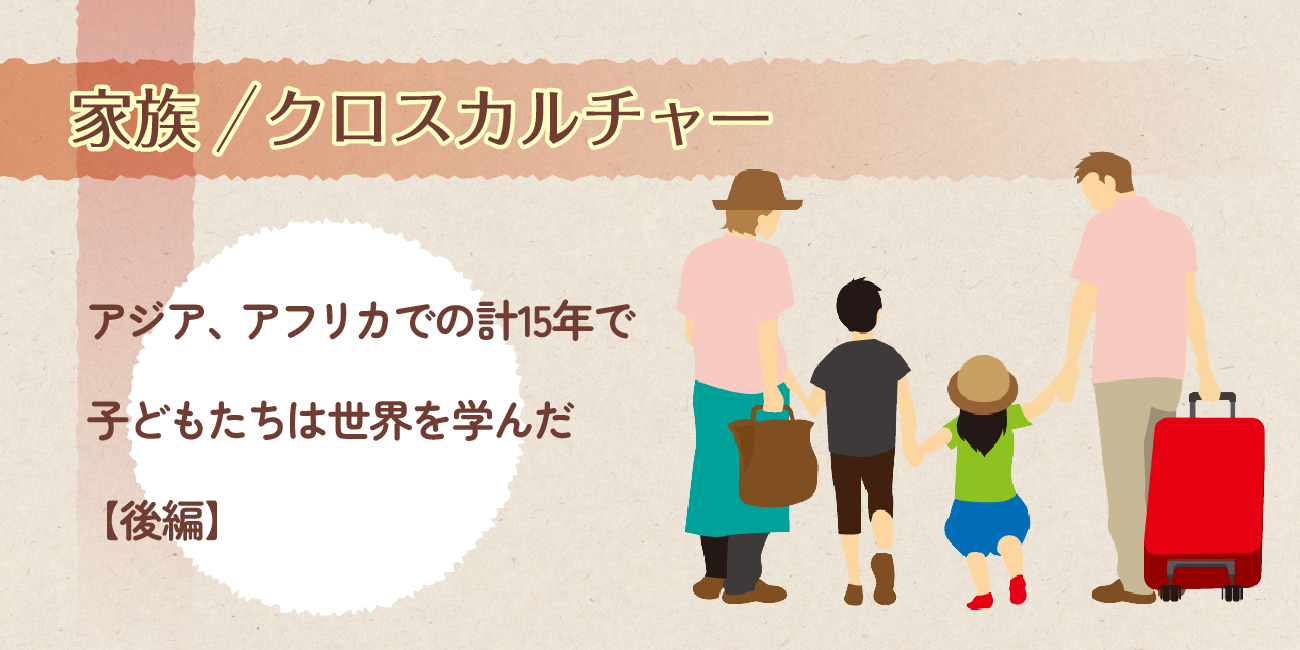韓国・ソウルでの6年間、ドイツ・フランクフルトでの3年間を経て、家族がたどり着いたのは第3の赴任先インドネシア・ジャカルタ。言語や文化の違いと向き合いながら成長した4姉妹は、それぞれが選んだ進路を歩んでいくこととなる。今回は、インタビューに同席してくれた三女アンズと四女ユズコにも、当時を振り返ってもらい、海外での生活について話を聞いた。(仮名)
(取材・執筆:武藤美稀)
楽しい日々が訪れたインドネシアでの生活
家族みんなで過ごしたドイツでの3年間を終え、2008年に日本に帰国したナオキ&イズミ夫妻とカエデ、モモコ、アンズ、ユズコの4人の姉妹。2015年からは、当時日本の大学に通っていたカエデを日本に残し、家族は3カ国目となる赴任先のインドネシア・ジャカルタへと渡った。
年間を通して気温が30度前後と高温多湿なインドネシア。街中の歩道は未整備だったり狭かったりする場所が多く、外を歩いて移動する人はほとんどいない。現地では、車やバイク、タクシーでの移動が主流で、事故を避ける意味でも、日本人家庭の多くに専属のドライバーがいた。ドイツでは、どこか義務感のような気持ちで続けていた運転も、インドネシアでは必要なかった。イズミにとっては、それは大きな負担軽減につながっていたようだ。
「当時、日本人が住んでいたマンションの敷地内には、プールやジム、テニスコートから、ショッピングモールといった施設まであり、快適な環境で暮らしていました。外出する際はどこへ行くにもドライバーが車を運転してくれたり、家のことはお手伝いさんに手伝ってもらったりと、周囲のサポートに恵まれ、毎日ゆとりを持って過ごすことができました。私自身の趣味の時間も充実させることができました。4人の子育てに奮闘したドイツと、インドネシアへの赴任の時期が逆だったら、どれほど楽だったかと思ってしまいます」
%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%A6%E3%82%99%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F(1).jpeg)
通学先の選択肢は、インターナショナルスクールと日本人学校。ドイツでは補習校があったが、当時のインドネシアにはなかった。日本人家庭の子どもの多くが、日本人学校かインターナショナルスクールに通いながら日本から進出した塾で日本語の勉強をした。
「モモコは、小学校低学年のときにドイツの現地校に通っていたこともあり、小さい頃から語学に長けていました。英語の習得も早かったので、インドネシアではインターナショナルスクールに入学し、早期卒業することができました。
アンズとユズコは日本人学校を選びました。アンズは、これまでの経験や言葉の壁への戸惑いによる負担も大きかったので、中学3年間は安心して学校生活を送れる日本人学校を選ぶのが自然な流れだったように思います。
ユズコも日本人学校に通っていましたが、本人の希望もあり、帰国前の半年間だけインターナショナルスクールに通いました」
当時住んでいたマンションには日本人の家族が多く、スクールバスが朝だけで5~6台来るほどの規模。バスはマンションのすぐ下まで迎えに来てくれて、そのまま学校に送ってくれる。朝は少し早かったが、子育て世代にとってはとてもありがたい環境だった。
異文化のリアルにふれて広がった子どもたちの視野
インドネシアでは、人口の約8割がイスラム教を信仰する国。これまで暮らしてきた国では、宗教的な出来事と関わることは少なかったが、ここでは日常の中で宗教が根づいていることを強く感じたという。断食月(ラマダン)になると、日中に食べ物や水を一切摂取することができない。ドライバーさんなど身近な人たちの前では、自分たちも飲食を避けるなどの配慮を忘れないようにしていたという。
「ジャカルタには貧富の差があり、厳しい暮らしをしている人たちも少なくありません。娘たちはそういった光景を目にして、自分たちの今ある生活が当たり前ではないということを実感したといいます。宗教や貧富の差、社会の格差を間近に感じられたことは、子どもたちにとっても貴重な経験でしたね」
.jpeg)
インドネシアでの生活では、テロや社会情勢に関する不安が身近な時期もあった。 知人が事件に巻き込まれかけたことがあったり、警察から「裏口から避難を」と指示されたりしたことも。外食中に「今、近くにテロリストが向かっているらしい」といった話が入り、急いで帰宅した経験もしたそうだ。
「マンションやショッピングモールの門や敷地内、学校の門に至るまで銃を持った警備員が常に立っていて、チェックを受けてからでないと中に入れない。それが“日常”でした。日本では考えられないような光景も、そこでは当たり前になっていたんです。ニュースでは“危ない国”と報じられるけれど、現地に住む私たちからすると、毎日怖がっているわけではない、というような距離感に近いと思います」
それでも常に、気を抜けない状況がどこかにあり、「のんきに見えて、無意識のうちに身を守る判断をしていたんだと思います」と振り返る。
韓国、ドイツ、インドネシアで見つけた姉妹それぞれの個性
いつか帰国する子どもたちの進路を考え、海外にいる間も、日本の教育についていけるようなサポートを惜しまなかった。本人たちの気持ちを聞きつつ、それぞれの個性や特性を見極めて、どこかで『区切り』をつけることを大事にしていたと話す。
「カエデはドイツで現地の小学校に通っていましたが、中学校に上がるタイミングで日本の教育に切り替えることにしました。ドイツでは、小学校5年生から大学進学コースか職業訓練コース、専門学校コースなどのはやくから進路を決めなければなりません。私たちはドイツに永住するわけでもなかったので、日本に戻ることを考えると、ここで切り替えておいたほうがよいと判断しました。そのため、当時バーデン=ヴュルテンベルク州にあったドイツ桐蔭学園に入学しました」

ドイツとインドネシアの2カ国での生活を経験したアンズとユズコにも、当時の生活について、楽しかったことや辛かったことなどの記憶に残っている思い出を聞いた。
「ドイツで過ごした幼稚園時代ははとても大変でした。ドイツ語の単語はいくつか覚えたものの、クラスメイトが何を言っているのか理解できず、会話ができませんでした。カルチャーショックを受けることも多くありました。特に印象に残っているのは、週に一度のピクニック。みんなで森に行ってお弁当を食べるのですが、雨の日でも決行されて、レインコートを着て、ミミズがいる濡れた地面や大木に座ってお弁当を食べるのが本当に苦手だったのを覚えています」(アンズ)
ドイツのお弁当は、パンやニンジンが丸ごと入っていたりするものが定番だが、アンズは、いつも母が握ったおにぎりを持って行った。クラスメイトからは変な顔をされたこともあるというが、大好きな白米を食べるために、ランチタイムのおにぎりだけは譲れなかったという。
ドイツでの経験もあり、インドネシアでは日本人学校を選んだ。「次は日本人学校に通いたい」というアンズ本人の希望だった。
「日本人学校には、私と同じようにさまざまな国で幼少期を過ごした子たちが集まり、みんな似たような価値観を持っていたので、居心地がよかったです。視野を広く持ち、精神的に自立しているような尊敬できる子が多くいました。今も変わらず、仲よくしています」(アンズ)
一方、ユズコは、小さい頃から言語に対する抵抗感は少なく、ドイツの幼稚園に通っていた当時からドイツ語を話していたという。インドネシアでは、アンズと同じく日本人学校に通っていたが、帰国前の半年間はインターナショナルスクールにも挑戦した。
「ずっと行ってみたいという思いがあったので、最後はインターナショナルスクールに通うことを決めました。クラスメイトたちと比べると英語は得意ではなかったのですが、文系の私なのに、意外なことに数学はクラスでも得意なほうで、みんなから“数学の天才”なんて言われていました」(ユズコ)
海外生活を通して強まった家族の結束力
イズミは当時のことを静かに思い返しながら、こんなふうに語ってくれた。
「どの国で暮らしていたときも、残念ながら必ずといっていいほど、駐在員のご家族やお友だちの中で、大切な方を亡くすという出来事に直面しました。楽しいこともたくさんある駐在生活ですが、実はいつもどこかで緊張感を抱えながら過ごしている。だからこそ、明るくふるまいながらも、内心では無意識に虚勢を張っていたり、気づかないうちにストレスを溜めていたりするのかもしれません。こうした経験を重ねてきたからこそ、『駐在生活は楽しいことばかりではない」と実感しています」
急な病気や突然死の知らせに、言葉を失うことも。どれも身近な出来事で、決して他人事ではなかった。
異国での暮らしのなかで、何より支えにしてきたのが家族の存在だった。どんなに大変な日々の中でも、いつも家族は頼れる存在だったと、イズミも、アンズも、ユズコも口をそろえる。今でも思い出話に花が咲き、家族の会話は途切れることはない。
海外での生活をともに乗り越えてきた時間が、家族のあいだに強い絆を育んでいった。そして、その結束を支えてきたのは、イズミの存在にほかならない。