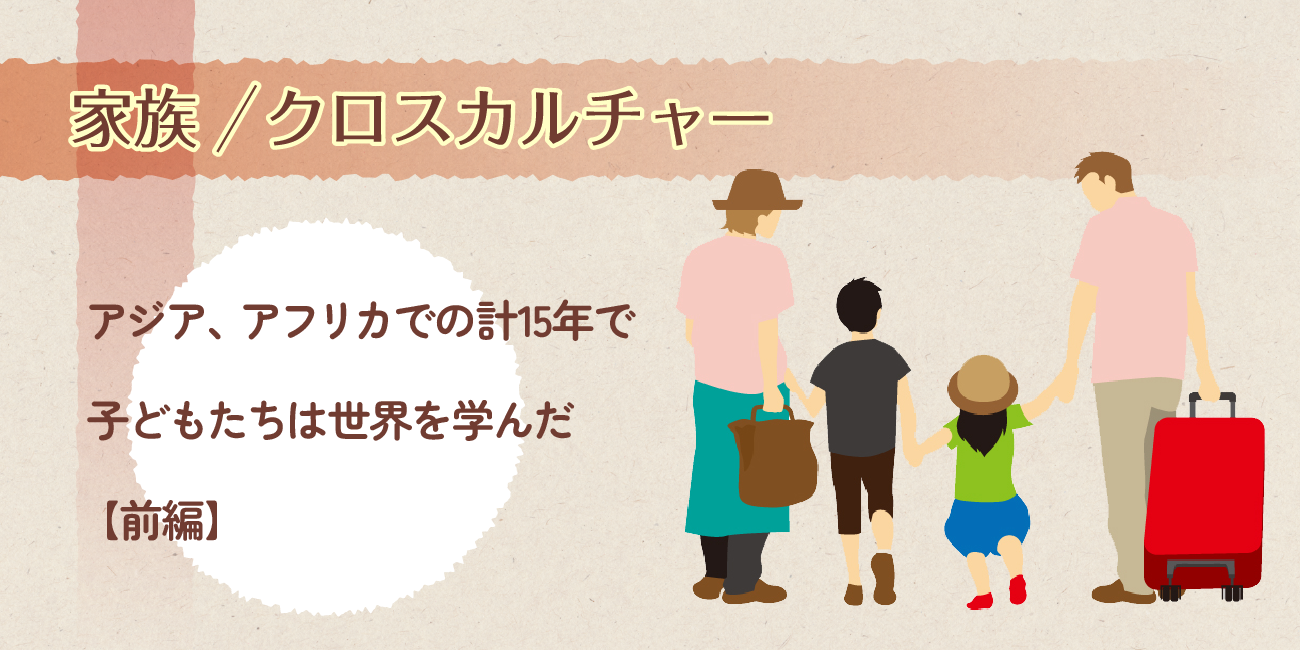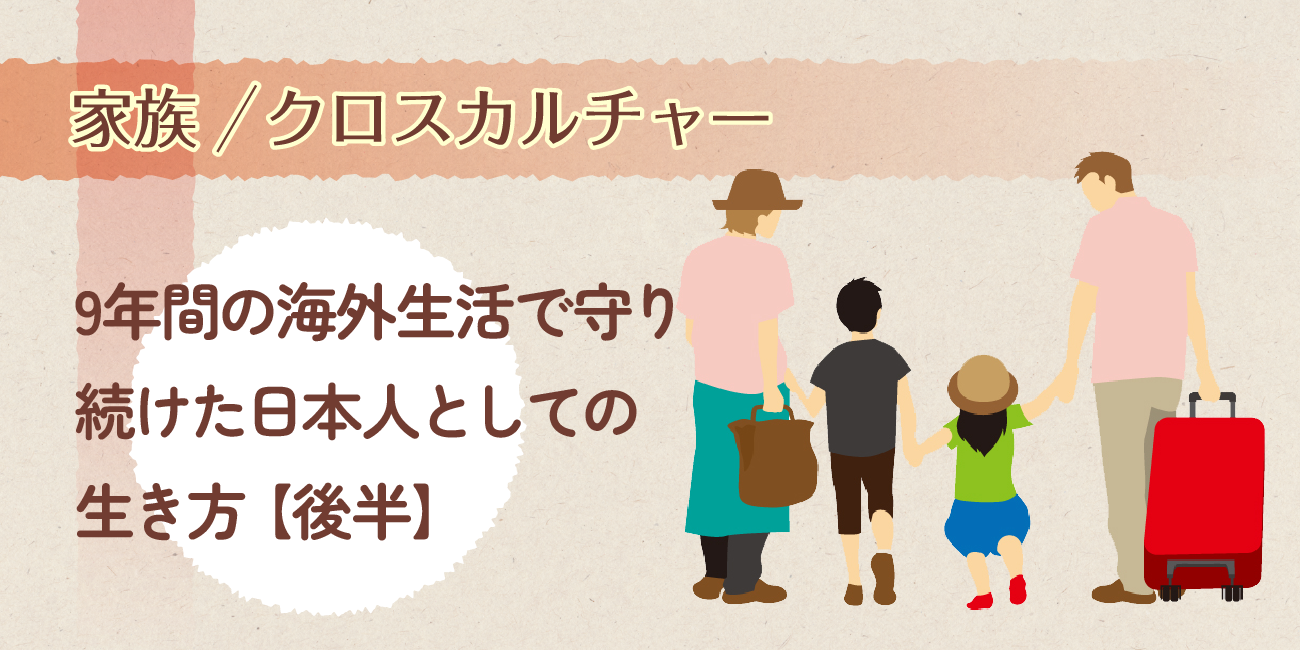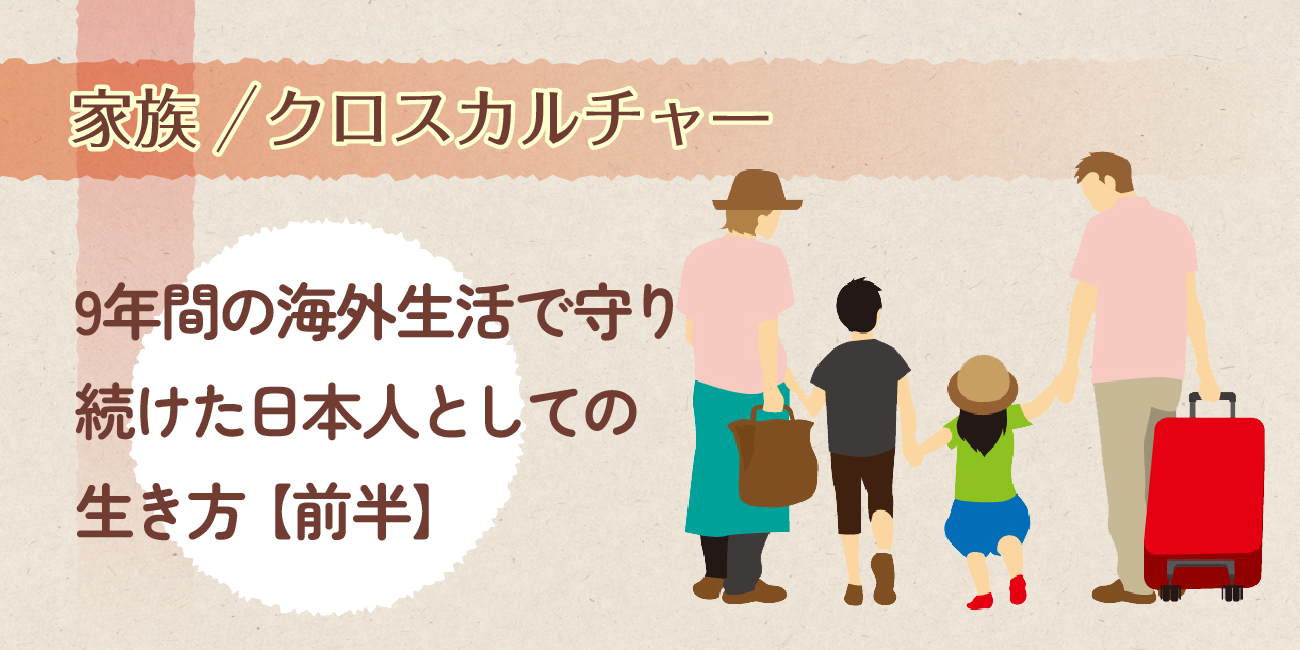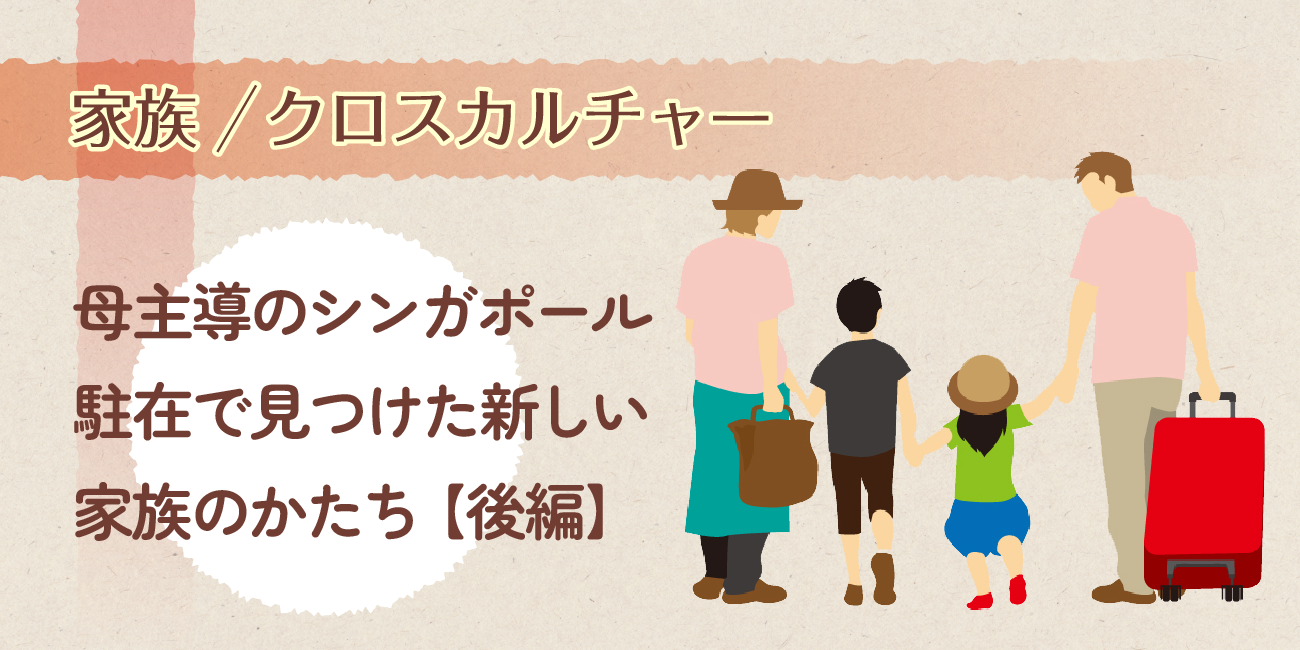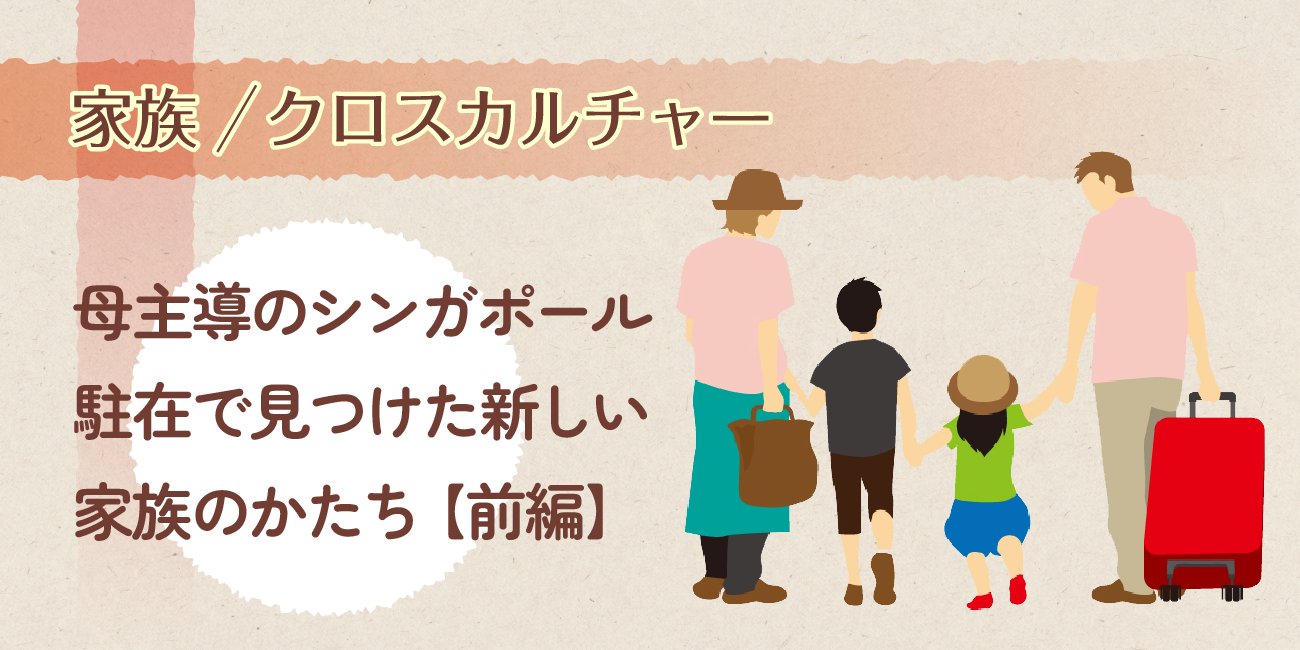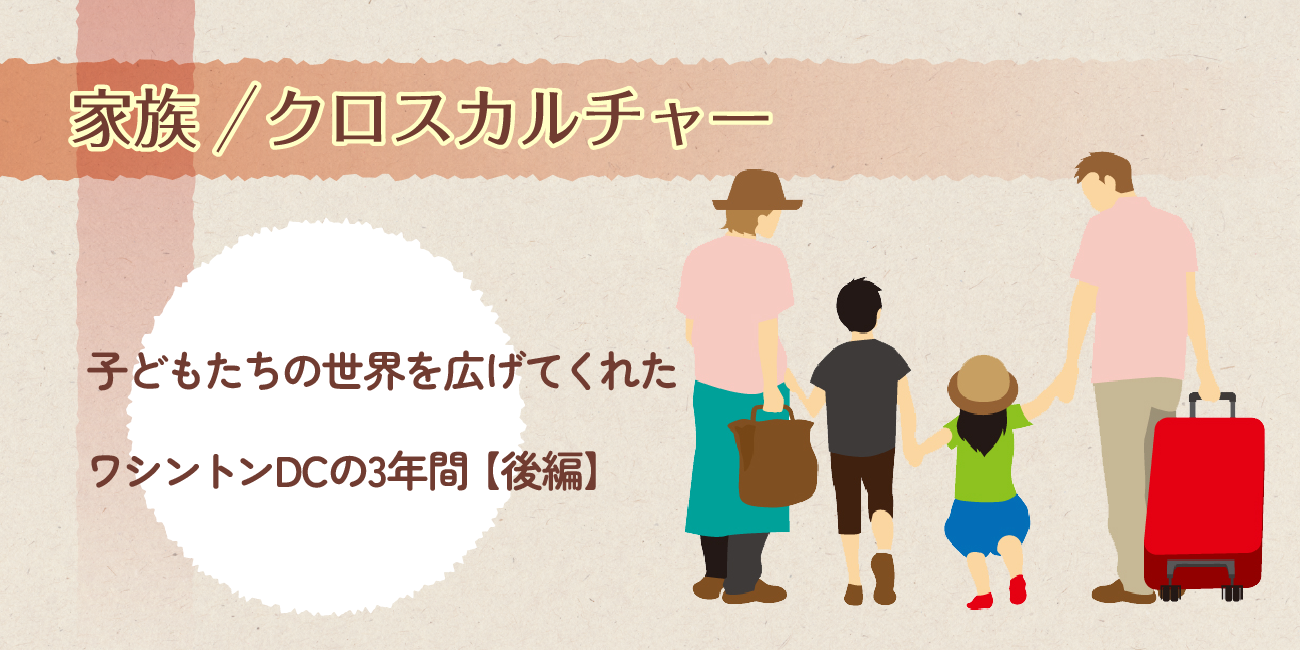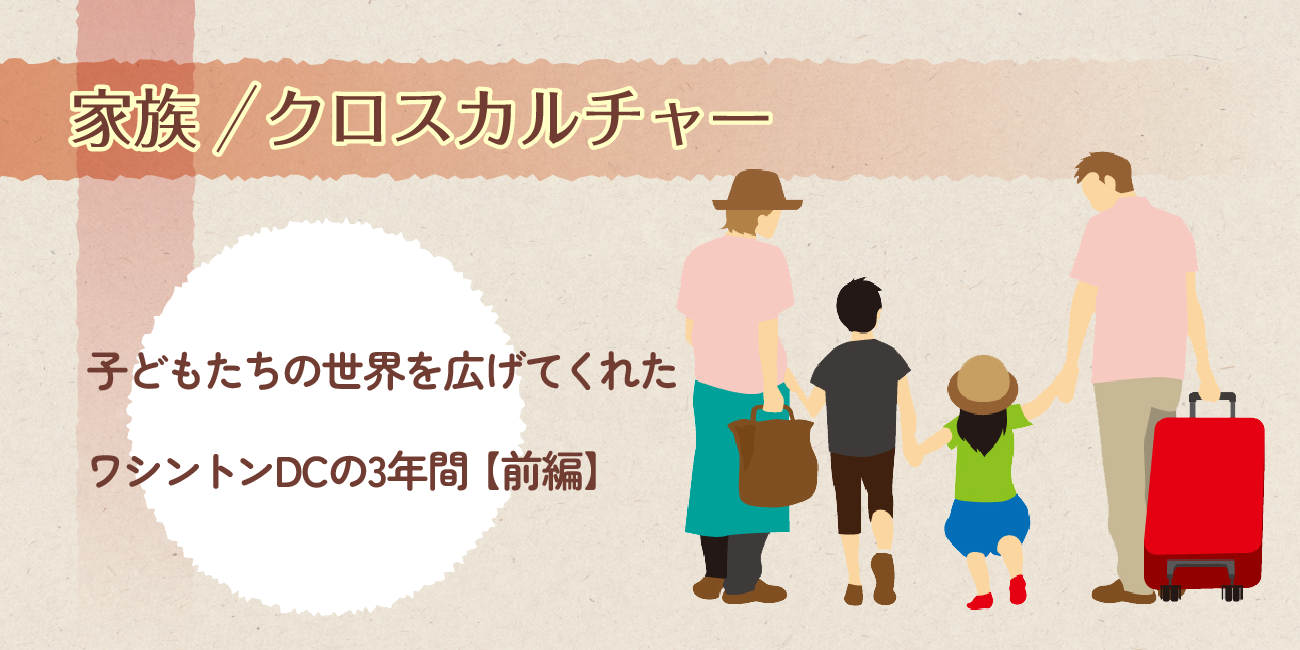国際開発の仕事に従事するかよ&けんじ夫妻は、長男ひかる、次男つばさ、長女かおると約15年に及ぶ海外生活を経験した。場所は、ケニア、ガーナ、ミャンマーなど。日系企業の駐在員が少ない地域だ。かよは、ケニアで長男と次男の出産を経験。夫婦共働きで子育てをしながら、所属する組織のリーダー職もこなしてきた。仕事との両立は大変だったが、開発途上国での子育ては、欧米圏での異文化体験とはまた違う面白さがあったという。家族5人の海外生活について聞いた。
(取材・執筆:丸茂健一)
長男を妊娠した状態でケニアに赴任
国際開発もしくは国際協力と呼ばれる領域の仕事がある。主に開発途上国・新興国の社会的、経済的な発展を支援し、勤務先は欧米諸国と異なり、日本人がほとんどいない場所であることも多い。
かよ&けんじ夫妻は、ともに国際開発を行う組織に所属し、お互いの仕事を尊重しながら、海外で子育てを続けてきた。ときには、かよが子ども3人を連れて西アフリカに単身赴任し、けんじがそこに定期的に通うというような時期もあったという。女性管理職が増え、海外赴任の辞令も当たり前に受ける時代になった今、かよのエピソードは、ワーキングママの海外子育て体験記としても参考になるだろう。
かよが国際開発の仕事に就いたのは、1995年のこと。ネパールにあるブータン人難民キャンプでUNHCR(国連難民高等弁護官事務所)の仕事をした。大学の経営学部を卒業後、大手銀行に就職したが、2年で退職し、もともと興味があった国際協力や難民支援の仕事に飛び込んだ。
「第2代国連事務総長だったダグ・ハマーショルドさんの伝記を読んで、難民支援などの仕事をしてみたいと考えていました。背景には、父親が転勤族で、小学生の頃、学校で居場所がない経験したことがあったからです。ちょっとした言葉のイントネーションの違いで仲間に入れてもらえず、そこから難民のような居場所を失った人々を助けたいという気持ちが芽生えたのだと思います」
ネパールでUNHCRの仕事を経験した後、かよは日本に帰国し、大阪大学大学院で国際公共政策を専門的に学んだ。そして、AMDAというNGOの職員として、1998年から2000年までバングラデシュとミャンマーで人道支援の職務にあたった。その仕事先で出会ったのが、当時JICA(国際協力機構)に勤めていたけんじだった。ふたりはミャンマーで結婚し、ひかるがお腹にいるタイミングで、ケニアに赴任となる。かよが当時を振り返った。
「2001年1月に、AMDAのアフリカ事務所長として、ケニアに赴任することが決まりました。妊娠している状態でケニアに行くということで、夫はJICA関係者のまま、ケニアの国連ボランティアの仕事を見つけて、同行してくれました。現地では、日本から助産師さんを呼んで出産する予定でしたが、その方が体調不良で渡航できなくなり、結局、マサイ族の助産師さんに頼んで、長男を出産しました。もともと現地のスラムで一緒に支援活動をしていた人だったので、信頼していました」
かよはケニアで大学院に通いながら仕事を継続
開発途上国での子育ては大変なことがある一方、日本よりヘルプを得やすい面もある。ケニアに赴任する外国人は、現地で家政婦や運転手を雇用する義務があり、かよは彼らに助けられながら、仕事を続けた。住んでいたのは、ナイロビ市街のマンション。治安の面で一定の注意は必要だが、住まいはセキュリティもしっかりしていて、安心感があった。
「男の子が生まれたと聞くと生きた鶏を持って来てくれて、その場でさばいて料理を振る舞ってくれたり、その後も家政婦さんの留守番中に子どもが泣くと、運転手さんが事務所まで連れて来てくれたり……子育てをする上で、途上国には途上国の温かいよさがありますね」
かよは、ナイロビのスラム街で保健医療のプロジェクトを実施していた。HIVの簡易検査を行い、陽性者には専門のカウンセリングも行った。また、低所得者層の職業訓練プロジェクトや当時内戦後の隣国ジブチの難民支援などにも携わった。
そんななかで、仕事上の必要性から現地のケニヤッタ大学の大学院に通い、パブリックヘルス(公衆衛生学と疫学)を専攻。子育てや仕事だけでなく、勉強もする日々を送った。そして、2002年には、つばさをケニアの自宅で出産。そのまま、2003年までケニアで男児2人を育てた。
家族一緒に南米のガイアナ協同共和国、そしてミャンマーへ
2004年、今度はけんじが、南米のガイアナ行きを命じられる。そこで、かよはケニアでの仕事に区切りをつけ、家族4人でガイアナでの生活をスタートする。南米ベネズエラの隣にあるガイアナは、旧イギリス領で、かつてはサトウキビプランテーションに、多くのアフリカ系、インド系労働者が奴隷として連れて来られた。そのため、国民の9割近くは移民で、もともと現地に住んでいた人は1割程度だった。同時、在留邦人は、当時たったの7人。中国系移民が多かったこともあり、日本人への風当たりはきつかったという。
「ガイアナで、子どもたちは現地の幼稚園に通っていました。サッカーが好きだったので、現地の子どもたちと馴染んでいましたね。当時の月刊『海外子女教育』にもガイアナの現地校情報は載っていなかったと思います」
かよ&けんじ夫妻の遊牧民のような海外生活は続く。ガイアナの次に、JICAに勤めていたけんじの赴任先となったのは、ミャンマーの首都ヤンゴン。かよは、2005年に日本でかおるを出産し、子ども3人を連れてのミャンマー生活となった。2006年といえば、ミャンマーは軍事独裁政権が続いていて、民主化デモが活発化していた。2007年には、民主化デモを取材していた日本人ジャーナリスト長井健司さんが銃撃され、亡くなるという事件も起きた。
.jpg)
そんな難しいタイミングではあったが、ミャンマーで子育てをすべく学校や幼稚園を探したかよ&けんじ夫妻。当時、ヤンゴンには日本人学校があり、65名ほどの子どもたちが通っていた。ひかる、つばさは、通学バスを使って日本人学校に通った。ミャンマーとは縁があり、後に2011年からまた家族でここに戻ってくることになる。
西アフリカのガーナに子ども3人を連れて単身赴任
東南アジアのミャンマーを経て、次にやってきたのが西アフリカのガーナ。このとき、ひかるが小学校1年生。ここから子どもたちの学校のことも真剣に考える必要が出てきた。当時は、かよもJICAに籍を置いており、けんじをミャンマーに置いたまま、子ども3人を連れて、ガーナの首都アクラで生活するという選択をした。つまり、母ひとりで、3人の子どもをアフリカで育てていたことになる。2008年のことだ。
「もちろん大変でしたが、むしろ家族で現地の生活を楽しんでいました。私がアフリカの隣国に出張する際は、日本からいとこや友人をアクラまで呼んで、留守番をしてもらっていました。子どもたちもそれが楽しかったようで、出張が決まると『次は誰が来るの?』と聞いてくるくらい。夫もJICAの仕事つながりで、定期的にガーナに来てくれていたので、それに合わせて出張の予定を組んだりしていました」
英語の勉強はインターで、母国語は家庭で
ガーナ時代、ひかるとつばさは、アクラにあるアメリカンスクールに通った。そこは、アメリカ大使館員の子どもたちなどが通う学校で、授業はアメリカのカリキュラムで、英語で行われていた。当時、現地に日本人学校はなく、毎週土曜になるとJICA職員であるが日本語補習校で子どもたちに日本語教育を提供していたという。通っていた子どもたちは30名程度。欧米圏の都市と比べれば、非常に小さな日本人コミュニティだった。
「インターの先生は、『英語の勉強は学校に任せてほしい。その代わり、母国語の勉強は家庭でしっかりやってほしい』と言われてました。なので、日本の文化を知る機会は意識的につくっていました。食事は自炊が基本でした。ここでも家政婦さんに日本食を教えて、うどんや茶椀蒸しをつくってもらっていました。次第にアフリカ風のアレンジが加わって、それはそれでおいしかったです。また、アクラには中国料理店や韓国料理店があったので、そこでも定期的に食事をしていましたね」
ガーナのアクラは、スリや引ったくりは出るものの、命を脅かすような犯罪に遭う危険性は低く、子どもたちは外でのびのびと遊んでいたという。(後編は、2025年5月12日公開予定)
.jpg)