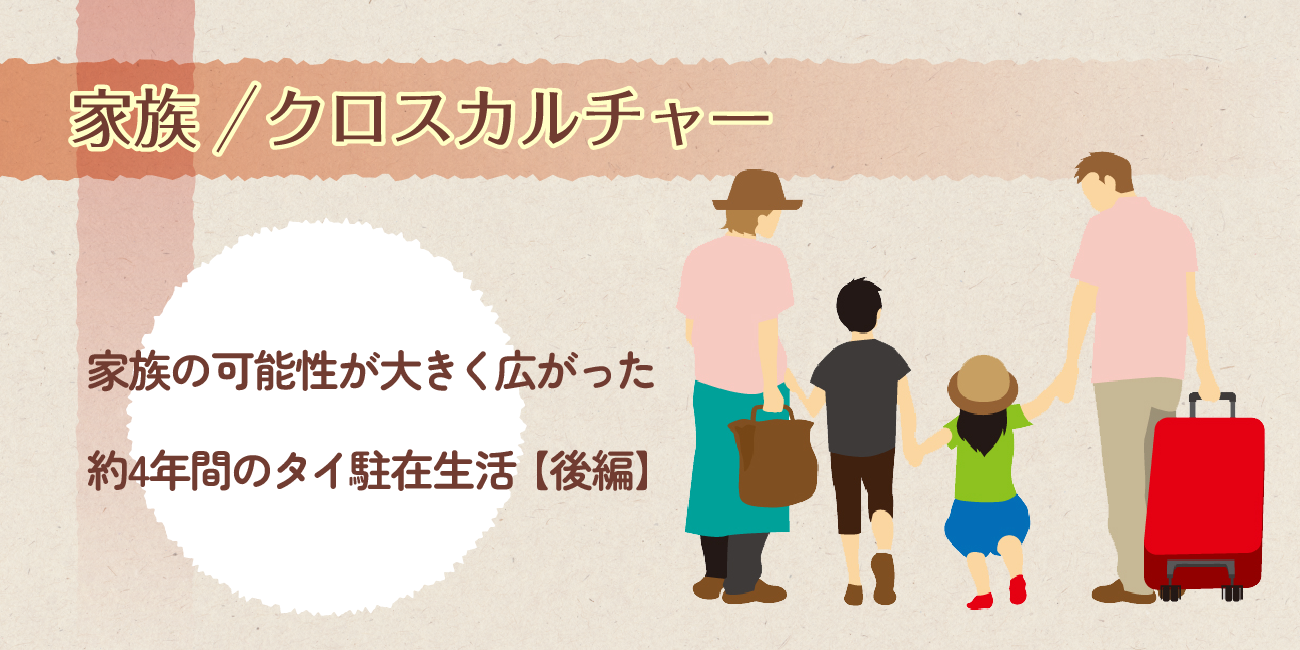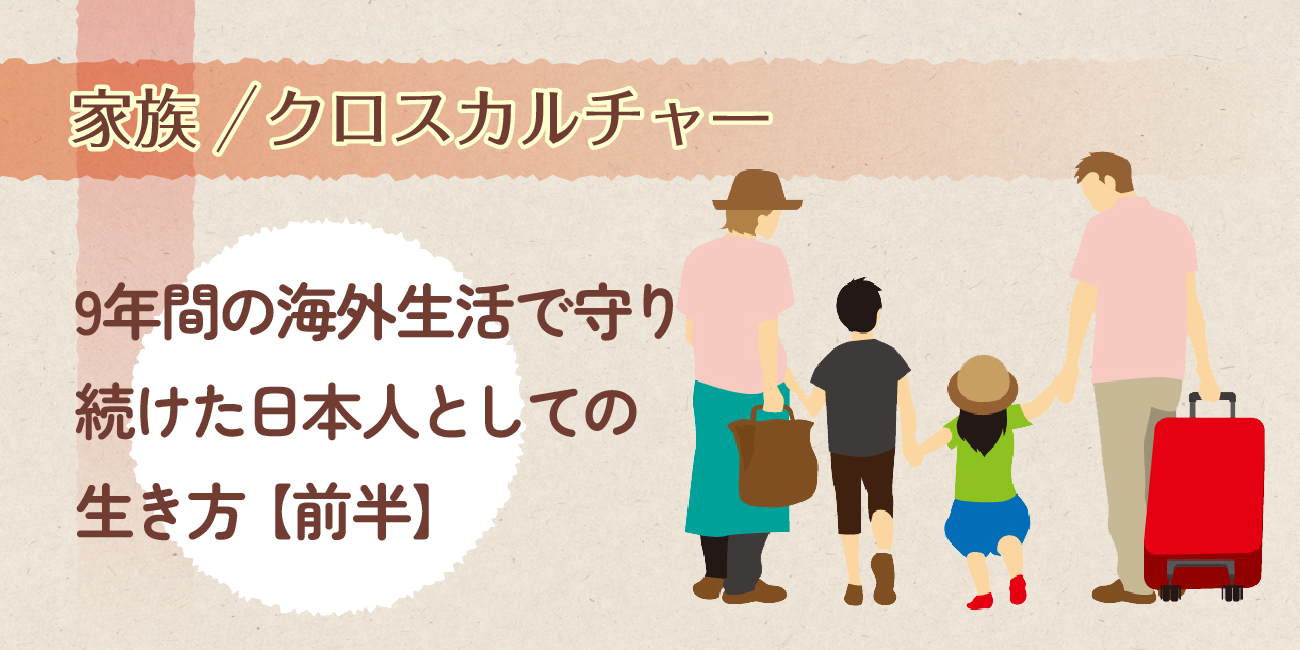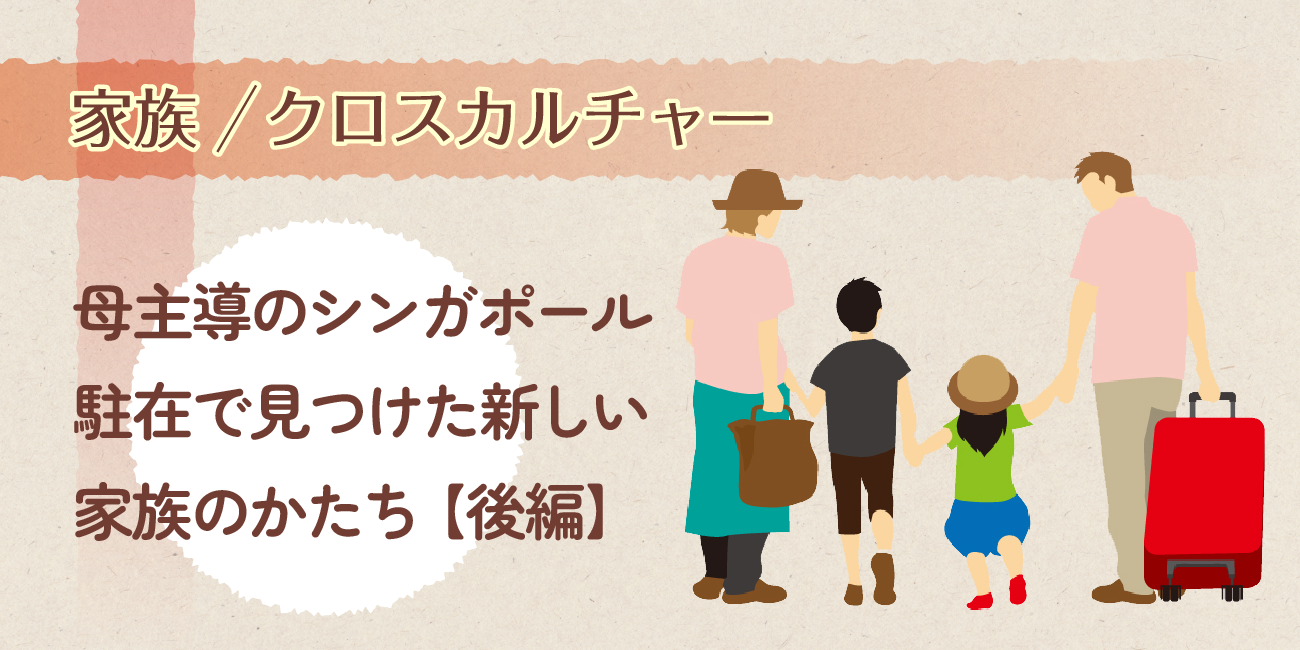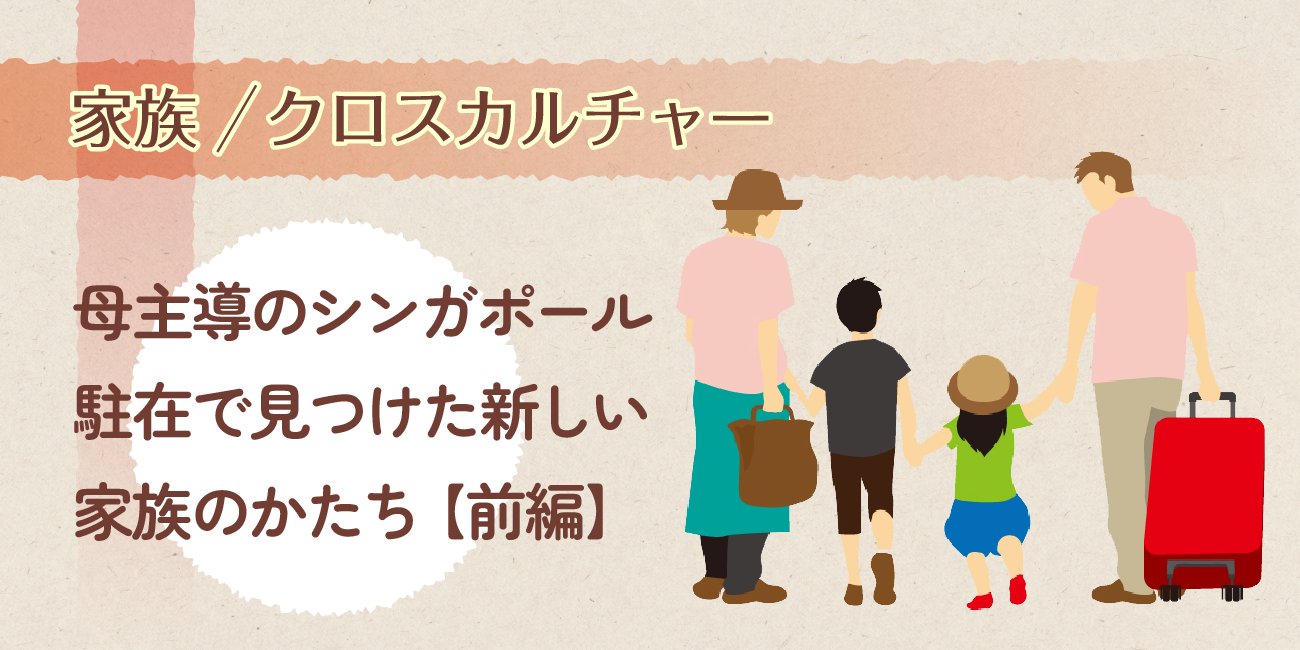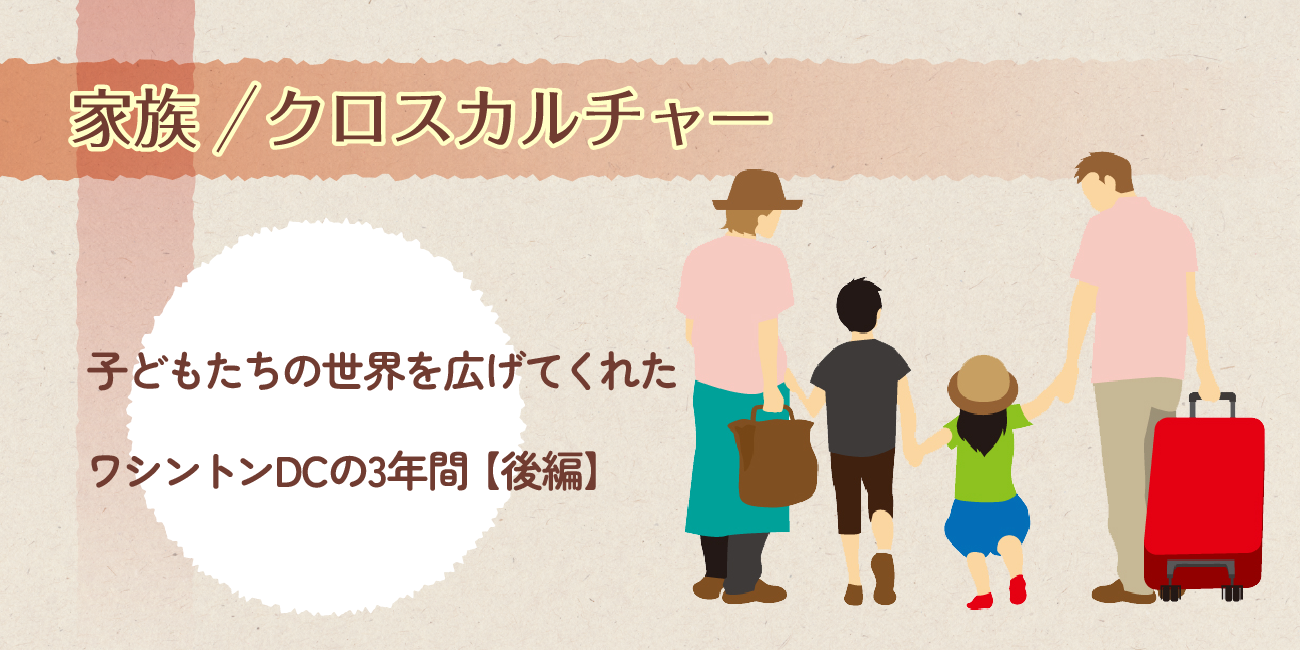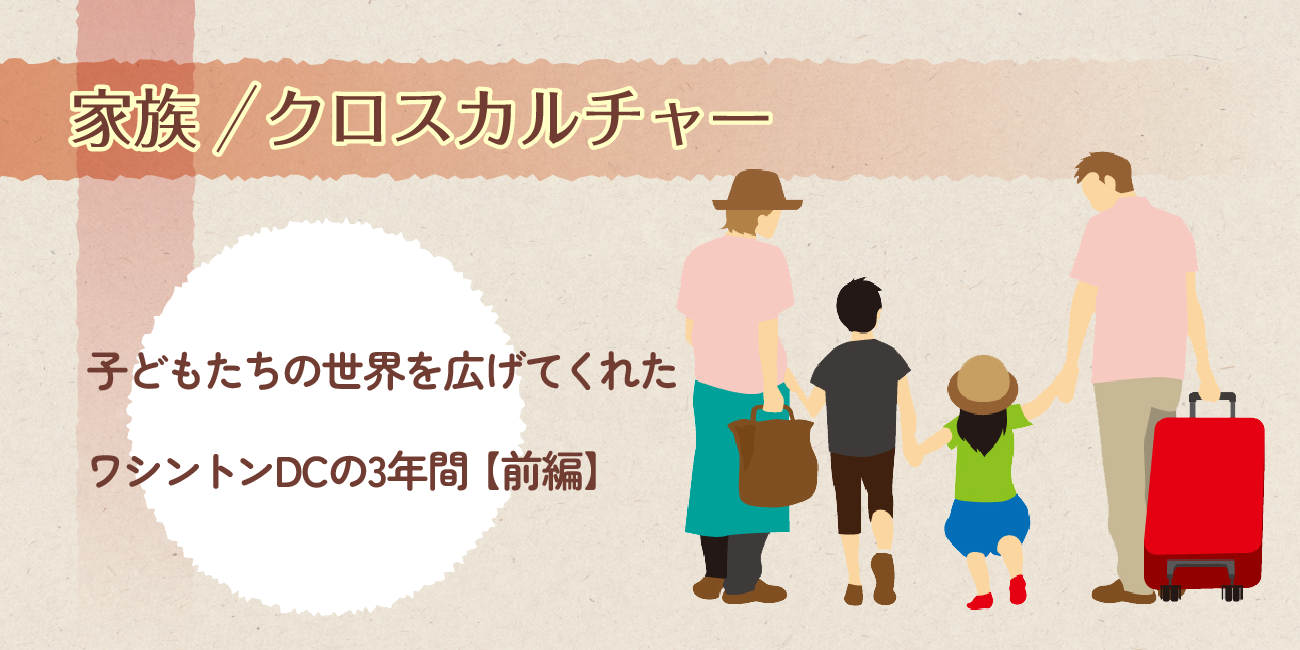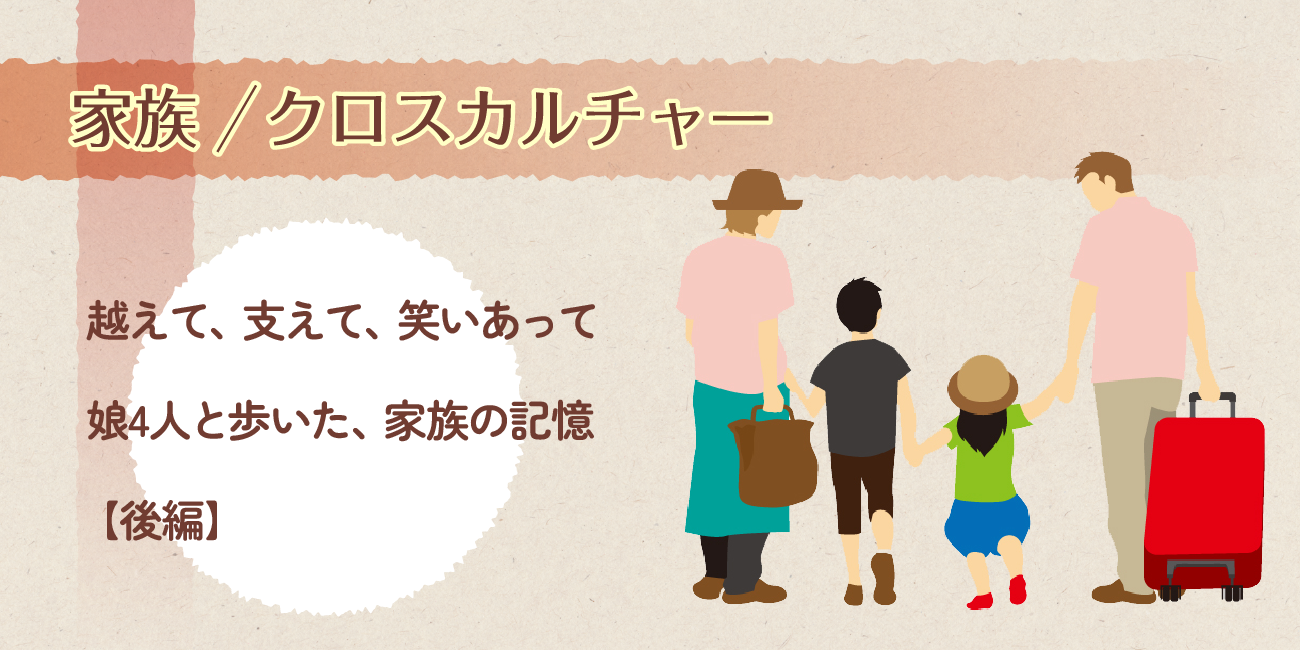自動車業界で働くハルオは、タイのバンコク近郊で約5年半の駐在生活を経験した。その間の約4年間は、妻ナツコ、長女ヒナも現地に呼び寄せて一緒に生活していた。バンコク近郊の街パタヤの特別支援学校に入学したヒナは、次第に学校生活に慣れていき、リラックスした日々が過ぎていく。出国前にヒナの主治医からタイ行きを止められたが、「家族一緒にいるのが正解だった」と振り返るナツコ。後編では、ヒナの学校生活や家族がタイ駐在で得たものなどを聞いた。(仮名)
(取材・執筆:ミニマル丸茂健一)
娘は英語環境で学び、世界各国の友達ができた
パタヤ滞在中にヒナが通っていたのは、イギリス系の私立インターナショナルスクールが運営する特別支援学校。そこは、郊外エリアに建つ一軒家で運営されたおり、3歳から18歳までの幅広い世代の児童・生徒が一緒に学んでいた。3クラスに分かれているものの、学年の区分などはなく、教室の中央に置いた大きなデスクで、子どもたちが自由に学んでいるような環境だった。

インターナショナルスクールだったので、授業は基本的に英語。タイ人の先生もいたので、タイ語でのやりとりもあったという。入学当初、ABCすらわからず、苦労したヒナだったが、次第に環境にも慣れていった。平日は毎日8時30分ごろ登校し、授業は15時まで。ランチの後は、お昼寝タイムもあったという。放課後は17時くらいまで、校庭で運動させてもらっていた。ヒナと一緒にナツコもバドミントンをしていたという。

イギリス式の学校らしく、週2回乗馬のレッスンがあった。これは、アニマルセラピー的な意味合いもあるのだという。さらに、パタヤビーチでSUP(Stand Up Paddleboard)に挑戦するなど、ビーチが近い学校ならではのアクティビティもあった。ほかにも運動会や音楽などの発表会、クリスマス会など、年中イベントも豊富にあり、ヒナは学校を「楽しかった」と振り返る。

「授業はタブレットを使って、動画などを見ながら行うスタイルで、当時の日本より進んでいたかもしれません。先生はカナダ人で、通っていたのは、イギリスのほか、中国、韓国、南アフリカ、スイス、タイなどのルーツを持つ多種多様な国籍の子どもたちでした。ヒナは、ここで英語やタイ語に触れて、特に英語はかなり上達しました。最終的には、英検3級を取得できたんですよ」(ナツコ)

学校との意思疎通のため、母も英会話教室に通う
現地の学校に通う上で、唯一、苦労したのが言葉の問題。インターナショナルスクールだけに保護者向けの連絡もすべて英語なのだ。入学当初、先生の説明がほとんど理解できなかったというナツコは、現地で英会話教室に通い、フィリピン人の先生からレッスンを受けた。もともと日常会話程度の英語はできたというナツコは、すぐに英語の環境にも慣れていく。住んでいたパタヤの街は、欧米系の観光客が多いことから、レストランやスーパーで働くタイ人もカタコトの英語を話すことが多く、生活面で困ることはほとんどなかったという。
一方、夫のハルオは、仕事で日常的にタイ人の社員とコミュニケーションを取る必要があり、滞在中にメキメキとタイ語を習得していった。
「仕事でタイに行き始めた2014年くらいからタイ語を独学で勉強しはじめて、日常会話ならかなり理解できるまでになりました。今では英語より、むしろタイ語のほうが得意ですね(笑)。現地でも店員さんとのやりとりは、家族の中で私が担当でした。コロナ禍の初めに帰国して、もう日本の生活が長いですが、せっかく覚えたタイ語を忘れないように勉強は続けています」(ハルオ)

タイの人々から学んだ「マイペンライ」精神
自動車業界に長く勤務するハルオだが、海外勤務はこれが初めて。留学経験もなく、異文化もわからないまま、駐在生活がスタートしたが、最終的にタイで約6年暮らして、「海外生活」の敷居はずいぶん下がったという。ヒナの教育や日常生活のことで心配を抱えていたナツコも駐在生活の後半では、すっかりタイの「のんびりペース」に慣れて、リラックスした日々を堪能することができた。
「タイ語に『マイペンライ(大丈夫、なんとかなる)』という決まり文句があって、タイ人は何かとこれを言うんです。確かに日本と比べれば、ものごとは時間通りに進まないし、サービスも大雑把なことが多い。それでも慣れてくるとむしろこれくらいがちょうどよくて、日本がきちんとし過ぎなんじゃないかと思えるようになるんですよね(笑)。タイの人々から学んだマイペンライ精神は、今でも心の支えになっています」(ナツコ)

家族の安心な生活には、会社からのサポートも大きかったとハルオは振り返る。通常、勤務先の場合は、駐在員の子どもの学費援助は日本人学校に通うことが前提となっている。しかし、ヒナが特別支援学校に通うことを理解し、サポートしてもらえたことで、家族は楽しくパタヤでの生活ができた。
家族が一緒なら世界中どこにいてもなんとかなる
実際に、アメリカやヨーロッパ、中国と比べ、タイは日本人にとって生活がしやすい。タイ人は親日的な上に、アジア圏なので食事も合う。さらに、バンコク近郊には日本人学校のほか、日本人が通うインターナショナルスクールも多数探せる。駐在先がタイだったのは、親子にとってラッキーだったともいえるだろう。最後に夫妻にこれから海外駐在を経験する家族へのアドバイスをもらった。

「自分の思い込みにとらわれないで、飛び出してみるといいかな。海外とはいえ、日本人のネットワークが必ずあります。私たちも支援が必要な子どもを連れての海外帯同に反対する声もありましたが、同じ境遇の仲間に会えました。タイに行って本当に正解だったと思います。海外で生活できたことで、娘の可能性が大きく広がったと感じています。家族が一緒なら世界中どこにいてもなんとかなるという自信がつきました。達成感は200%です。また海外赴任の機会があれば、迷わず行きます!」(ナツコ)
「なんとか無事に猫も含めた家族4人(3人+1匹)で4年間の現地生活ができて、ミッション達成だと思っています。今、私の勤務先のようなグローバル拠点を持つ企業でも海外赴任を打診すると多くの社員は、『あまり行きたくない』と言います。これは非常にもったいない。行ったら行ったで問題なく生活できるし、楽しいことも必ずあります。ぜひ海外赴任の機会があるなら、家族でトライしてほしいですね。必ず家族全員の視野が広がると思います」(ハルオ)

反対の声があっても「家族一緒にいること」を選んだハルオとナツコ。今回のタイ駐在生活で、「ヒナの将来の可能性が広がった」というナツコの言葉が印象的だった。ヒナの夢は、バンコクで会った世界各国の友達と日本で再会することだという。