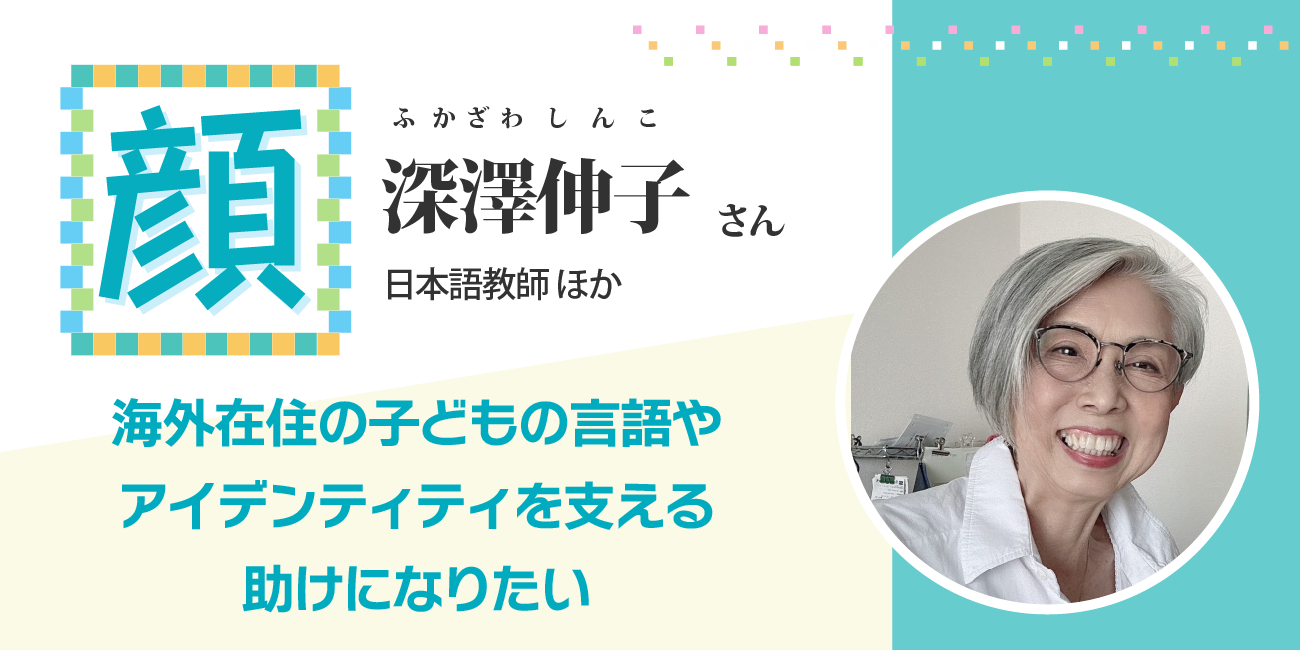上智大学硬式野球部に所属する正木悠馬(まさきゆうま)投手。コーチ不在の環境で独学による試行錯誤を重ね、投球は最速153キロに到達。2025年のプロ野球ドラフト会議で埼玉西武ライオンズから育成6位指名を受けた。幼少期や中高時代をアメリカで過ごし、さまざまなスポーツに親しみながら培った自主性と柔軟な発想が、プロへの扉を開いた。その歩みを、海外経験とともに振り返る。
(取材・執筆:仲里陽平)

チームメイトと見守った指名の瞬間
上智大学硬式野球部に所属する正木悠馬さんが、2025年10月23日(木)に行われたプロ野球ドラフト会議で、埼玉西武ライオンズから育成6位で指名を受けた。スポーツ推薦制度を持たない上智大学において、在学生がドラフト会議で指名を受けるのは、大学史上初の快挙。ドラフト会議当日、正木さんは大学に集まったチームメイトとともに、その行方を見守っていたという。
「チームメイトが先に集まってドラフト会議を見ていて、育成指名が始まるタイミングで自分も合流しました。待っている時間が長く、指名を終える球団も増えていくなかで、『自分の名前は呼ばれるのだろうか』という不安もありました。育成6位で名前が呼ばれた瞬間は、ホッとしたというのが一番の気持ちでした。周りのチームメイトが、自分以上に喜んでくれて。胴上げまでしてもらって、本当にうれしかったですね。待たせすぎたかな、という申し訳なさも少しありました(笑)」
家族もそれぞれの場所で指名の瞬間を待っていた。母親と姉は自宅でドラフト会議を見守り、涙ながらに電話をくれたという。一方、父親は飲み会に出かけていたが、「結局、一番喜んでくれているのは父なんだと思います」と正木さんは笑顔を見せる。幼少期や、中学・高校時代をアメリカで過ごした正木さんのもとには、海を越えて祝福の声も届いた。
「ドラフトの結果をInstagramに載せたら、アメリカの友人からダイレクトメッセージで『ドラフトで選ばれたの?』と連絡がきました。『頑張って』と言ってもらえて、素直にうれしかったです」

アラスカで育った幼少期。多彩なスポーツ経験が原点に
正木さんは神奈川県で生まれ、父親の仕事の関係で、1歳から小学1年生までをアメリカ・アラスカ州で過ごした。「両親が撮ったビデオを見て、なんとなく思い出す程度」と振り返るが、丘陵が広がり、冬には車が雪に埋もれるほどの厳しい自然環境は、今も印象として記憶に残っているという。
現地ではプリスクールやキンダーガーテンに通い、友達と遊ぶ日々を送った。幼い頃から体を動かすことが好きで、自然とスポーツにも親しんでいった。
「アラスカでは屋内競技が中心でしたが、水泳やフットサル、バスケットボールなどをやっていました。地元のマラソン大会に出たこともあります。両親が、いろいろなスポーツを経験させてくれたのだと思います」
プリスクールやキンダーガーテンなどでは英語が基本だった一方、家庭内では日本語を使うよう両親から促されていたという。いずれ日本へ帰国することを見据え、日本語の環境を意識的に保っていたのだ。ただ、2歳上の姉との会話は、慣れ親しんだ英語になることも多く、そのたびに注意されることもあったと正木さんは笑う。そんななか、小学2年生で日本に帰国。環境の変化に大きな戸惑いはなかったという。
.jpg)
「帰国してすぐに野球チームに入ったので、友達も自然とできました。アラスカでも家では日本語を使っていましたし、日本の通信教材で勉強もしていたので、ひらがなやカタカナ、漢字なども問題ありませんでした。まだ小学2年生で学習内容も基礎的だったこともあり、日本の生活には比較的スムーズに適応できました。小学4年生だった姉のほうが環境の変化は大きく、苦労も多かったのではないかと思います」
小学2年で野球を始め、中学2年に再渡米。異なる環境が育んだ競技観
正木さんが野球を始めたのは、小学2年生のときだった。父親が野球好きで、アラスカ滞在中も柔らかいゴムボールを使い、親子でキャッチボールのような遊びをしていたという。2009年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)を、アラスカで家族そろってテレビ観戦した記憶も残っている。野球を始めたのは特別な出来事ではなく、「ごく自然な流れだった」と振り返る。
小学生時代の主なポジションは内野手。所属していた東京・中央区のクラブチームは、地区大会で優勝する実力を持つなど、一定の競争環境にあった。中学進学後も野球を続けたが、野球部がなかったため、部活動ではなくクラブチームを選択した。学校では姉が所属していた陸上部で体を動かし、週末はクラブチームで野球に打ち込む日々を送っていた。
そして中学2年生のとき、父親の海外転勤に伴い、再びアメリカへ渡ることになる。行き先はワシントン州だった。幼少期とは異なり、戸惑いは大きかったという。
「日本に7年ほどいたので、英語はほとんど抜けていました。アメリカに行ってからの最初の3カ月は、本当にきつかったですね。英語の動画教材を繰り返し視聴するなど、地道な努力を続けました。母が夜遅くまで学校の課題に付き合ってくれたのもありがたかったです。9月に編入したのですが、10月には野球のクラブチームに加入。言葉が十分に通じなくても、スポーツを通して自然と友達の輪が広がり、友人関係とともに英語力も徐々に戻っていきました」
日本のクラブチームでは、大会に向けて厳しく練習する場面も多かった。一方、アメリカのクラブチームは「楽しむこと」を重視する雰囲気が強かったという。
「純粋に野球が好きだと思えたのは、この時期です。人生を通して野球を続けたいと思えた原点ですね」
高校時代は、春は学校の野球部、夏はクラブチームで野球を続け、秋はクロスカントリーランニング、冬は水泳と、季節ごとに競技を変えるアメリカ型のスポーツ環境を経験した。アメリカンフットボールへの興味もあったが、中学3年生の頃は身長が160センチに届くかどうかで、高校1年生になっても小柄だったことからそちらへの挑戦は見送った。身長が大きく伸びたのは高校3年生になってから。体重を含めたフィジカルが本格的に備わったのは、大学進学後だった。
.jpg)
帰国子女には心強かった上智大学の環境
アメリカの高校を卒業し、秋の帰国生入試で上智大学に合格し進学。帰国子女の学生が多いイメージがあったのも、進路を選ぶ上で決め手になった。
「英語は使わないとすぐに抜けてしまうので、上智大学は英語で行われる授業も多く、その点はとてもありがたかったです」
入学当初、大学でも野球を続けるかどうかについては、少なからず迷いがあった。オリエンテーション期間中にはアメリカンフットボール部から勧誘を受けたが、その場で「スポーツをやるなら野球部を考えている」と伝えた。その何気ない一言を、偶然すぐ後ろで耳にしていたのが、後に主将を務めることになる同学年の佐々木恵太朗さんだった。
「『野球やってたの? 野球部、一緒に入ろうよ!』と声をかけられました。それが入部のきっかけの一つになったのは間違いありません。ただ、最終的に背中を押したのは、“やっぱり野球が好きだ”という気持ちでした」
実は大学入学前に一時帰国し、野球部の体験入部にも参加していた。その際にともに練習した同学年の2人はいずれも日本の「高校野球」の部活動で鍛えられてきた選手。坊主から伸びかけた髪型、部活特有のハキハキとした太い返事。その姿に、「これが日本の野球部か」と強い印象を受けていたという。それでも、実際に入部して練習を重ねるなかで、自然とチームに溶け込んでいけた。
「部内には別の学年に帰国子女の選手もいて、そうした存在は心強かったです。学生主体で運営されている点も、アメリカの高校時代の部活動の雰囲気に近いと感じました」
高校時代には複数のポジションを経験し、そのなかで投手としてマウンドに立つ機会もあった。投げることへの手応えと楽しさは記憶に残っており、大学では本格的に投手に挑戦したいという思いを抱いていた。 「ほとんど経験はなかったのですが、『ピッチャーをやってました!』と言って入部しました(笑)」
.jpg)
独学で球速150キロへ
上智大学にはスポーツ推薦制度がない。野球部にも一般入試や帰国生入試などを経て入学した約50人の部員が在籍している。投手はそのうち13人ほど。所属する東都大学リーグ3部は下部リーグに位置づけられ、専任コーチもいない。練習の多くは、自主練習が中心になる。
大学1年次の最速は140キロ。もともと肩の強さには自信があり、高校3年間で身長が伸び、体重が増えたことも、球速向上の土台になっていた。投球フォームやトレーニング方法はすべて独学。InstagramやYouTubeを活用し、日本に限らず海外の動画にも目を向けた。「使える」と感じたものは積極的に取り入れていった。
「アメリカでは、トレーニング施設などで指導しているピッチングコーチが動画で発信していることも多いです。そうしたものも参考にしていました。フォームの見た目は良さそうでも、実際にやってみると自分には合わず、崩れてしまうこともある。最後に大切にしていたのは、自分の体の感覚に合っているかどうかでした」
練習では、チームメイトに投球姿を撮影してもらい、フォームを細かくチェック。試しては修正する作業を地道に繰り返し、自分にとって最適な形を探り続けた。高校時代の投手経験はほとんどなく、日本の部活動で体系的な指導を受けてきたわけでもない。ゼロに近い状態からの独学は、決して一般的とは言えない。それでも取り組めた背景には、アメリカで培った価値観がある。
「アメリカの高校では、与えられたメニュー以外は自分たちで考えるのが当たり前でした。調べて、試して、合わなければ変える。その感覚が、日本の大学野球でも自然に活きたと思います」
努力は数字となって表れ始める。大学4年次の春、最速153キロに到達。その投球がニュース記事として報じられ、プロ野球スカウトの目に留まった。春のリーグ戦以降、球場にはスカウトの姿が増え、夏のオープン戦では定期的に視察が入るようになった。独立リーグで野球を続けている先輩の存在も後押しとなり、3年次の終わり頃には、卒業後も野球を続ける決意が固まっていた。
「スカウトが来るようになってからは、もうやるしかないという気持ちでした。可能性はあるのかなと思いながらも、正直、どうなるかはわからなかった。プロ志望届を出して、あとは結果を待つしかありませんでした」
そして2025年10月23日(木)。プロ野球ドラフト会議で、正木さんは埼玉西武ライオンズから育成6位で指名を受けた。独学で練習を積み上げてきた日々が、プロへの扉を開いた。

自分を信じれば、道は開ける
2026年1月、正木さんは埼玉西武ライオンズの寮に入り、プロ野球選手としての生活をスタートさせる。求められる結果も野球への姿勢も、これまでとは比べものにならない。だからこそ、さらなる成長が必要になる。
「練習設備もコーチ陣も整った環境で野球ができる。すべてを吸収するつもりで取り組みたいです。将来的にはチームの勝利に貢献できる投手になることが目標ですが、まずは支配下選手登録を目指して、一日一日を大切にしたいと思っています」
育成選手として入団する正木さんにとって、支配下選手登録は最初の大きな目標だ。一軍公式戦に出場できるのは、各球団70人の枠に名を連ねた選手のみ。そこには厳しい競争が待っている。高校卒業時、野球を続けるかどうかさえ迷っていた。プロ野球選手としての現在の姿は、まったく想像していなかったという。
「日本とアメリカを行き来した学生時代でしたが、場所は関係ないと思っています。自分を信じて続けていけば、道は必ず開ける。それは野球に限りません。日本でしかできないこともあれば、海外だからこそ学べることもある。自分は強豪校にいたわけではありませんが、いろいろなスポーツに触れたり、自主性を持って取り組んだりした経験が、結果的に今につながっています。環境のせいで無理だと決めつける必要はない。どんな場所にいても、未来は自分で切り開けると思います」
.jpg)
プロフィール 正木悠馬(まさきゆうま)さん 2002年神奈川県生まれ。父の仕事の関係で1歳から小学1年までをアメリカ・アラスカ州で過ごす。小学2年で帰国し野球を始め、中学2年に再び渡米。高校卒業までアメリカ・ワシントン州で生活した。秋の帰国生入試で上智大学に進学し、投手経験がほとんどない状態から独学で研究。最速153キロを記録し、2025年のプロ野球ドラフト会議で埼玉西武ライオンズから育成6位指名を受けた。