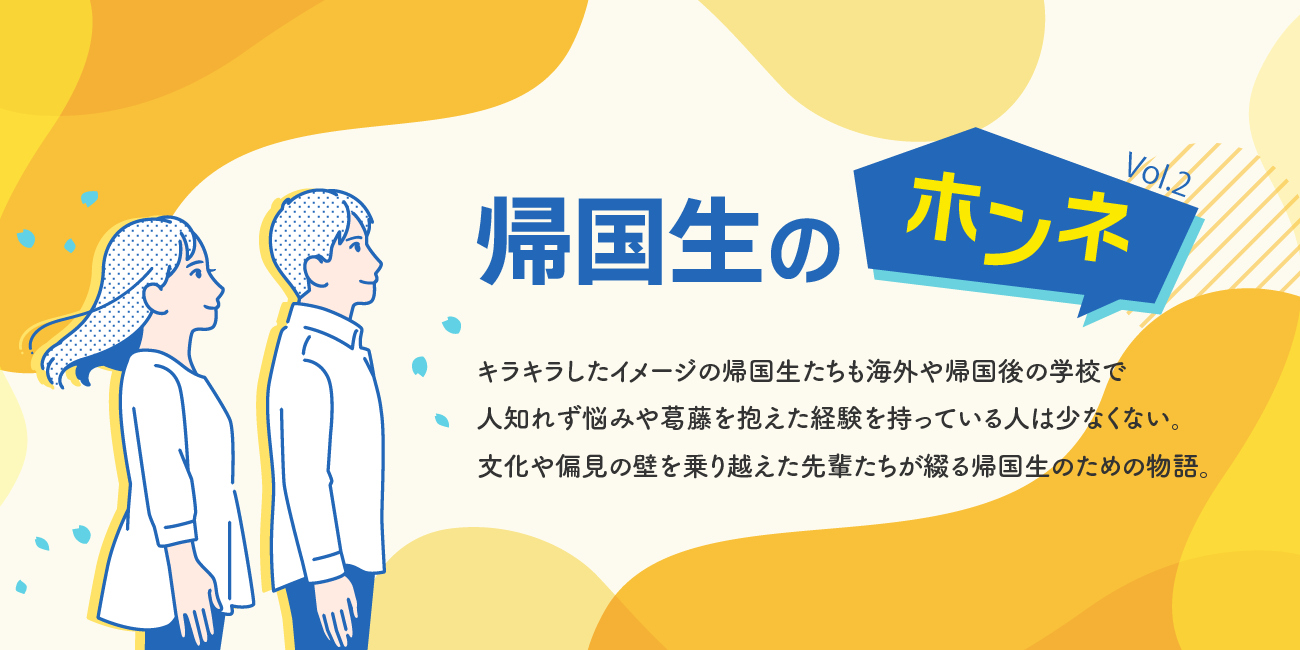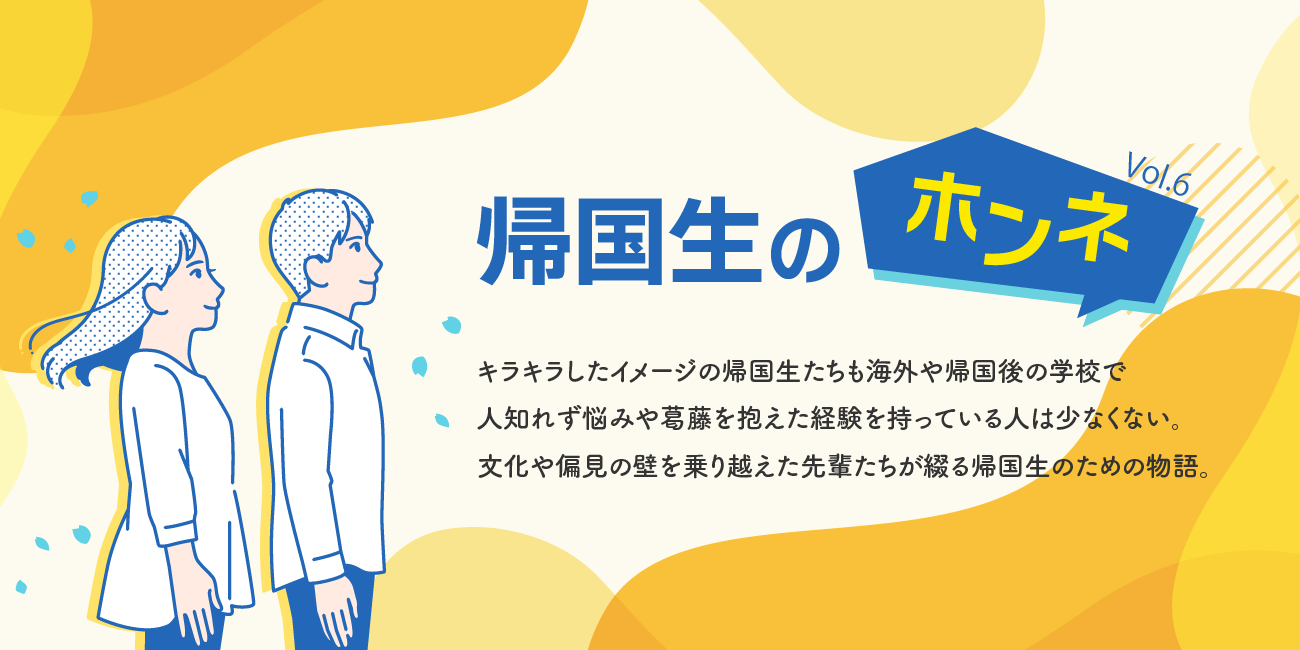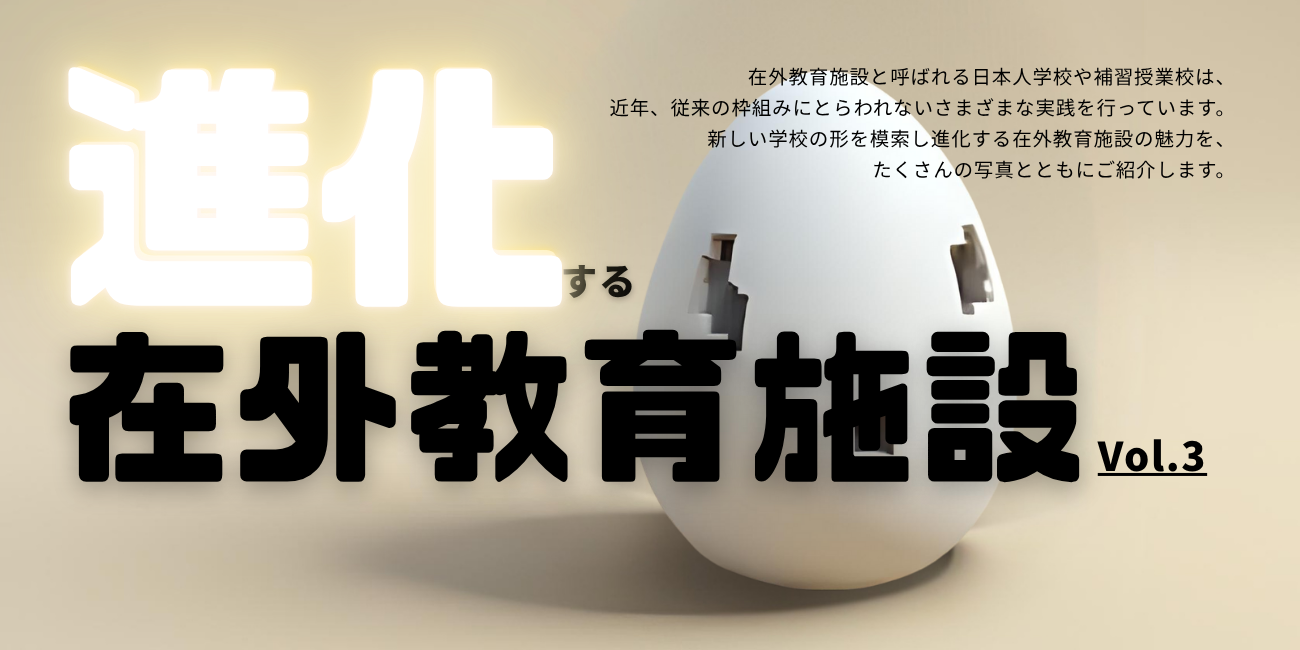小学校4年生から中学3年生までをアメリカ・ロサンゼルスで過ごした坂本鈴音さんは、現在、ドイツのケルンで暮らしている。多様な背景を持つ人々が暮らすドイツでの暮らしは、日本で暮らしていたときの閉塞感を忘れさせてくれるという。坂本さんは今、現地でドイツ語を学びながら、アメリカと日本の教育の違いについて考えている。アメリカの現地校で自分は何を身につけたのか、そして、この先のキャリアをどこで築いていくべきか——。その答えを新天地のドイツで見つけつつある。
(取材・執筆:ミニマル丸茂健一)
.jpeg)
「度胸あるねってよく言われるんです」
現在、ドイツのケルンで暮らす坂本鈴音さんは、小学校4年生から中学3年生までの多感な時期をアメリカ・ロサンゼルス(LA)で過ごした経験を持つ。帰国後は、公立高校から東京大学に進学。卒業後、2年半ほど務めた医療系コンサルティング会社を辞め、知らないドイツの街にやってきた。理由は、パートナーがドイツで仕事をすることになったから。社会人生活を経て、違うカルチャーの国で暮らしてみるのも面白そうだと思ったという。
「度胸あるねってよく言われるんです。でも、度胸というより、誰か助けてくれるし、どうにかなるさと思っているところがありますね。小学校時代にアメリカの現地校に飛び込んだ経験と比べたら、怖いものなんてありません」
坂本さんの家は、海外駐在ファミリーだった。まず、1歳から5歳までをトルコのイスタンブールで過ごした。現地では、日本人の子どももいたインターナショナルプリスクールに通い、英語の環境で自由に過ごした。その後、日本に帰国し、地元の小学校に通い始めたとき、ショックな経験をする。休み時間に自由帳に落書きをしていたら、友達に注意された。「自由帳にクレヨンで絵を描いちゃダメだよ」。トルコのインターナショナルスクールでは、「これはダメ」などと言われたことがなかった。悲しいと思ったが、その後、クレヨンは使わなかった。また同じように言われて悲しい思いをしたくなかったから。自分の母国であるはずのこの国は、ずいぶんとカルチャーが違うと幼心に思っていた。
LAトーランスの小学校で出会った多様性
それでも小学校4年生まで、日本の小学校でそれほど違和感なく過ごした。そして、4年生の終わりに父の仕事の都合でLAに行くことが決まった。場所はトーランス。日本人駐在員も多く住んでいる治安もいいエリアだ。そこで、坂本さんは、現地校に通うことになった。
「住んでいたのは、トーランスの海岸側で、公立校の教育水準が高いエリアでした。友達の家の庭にプールがあっても驚かないような感じで……。私が当時住んでいた集合住宅にもプールとペントハウスがありました。今思うとすごい生活をしていたと思いますね(笑)」
世界中からさまざまな人が集まるLAだけに、小学校の友達も肌の色やルーツは実にさまざまだった。ヨーロッパルーツのアメリカ人のほか、ヒスパニック系、アジア系、アフリカ系、中東系など、あらゆるカルチャーが学校内にあった。特に中国、韓国、インド・ネパールなどアジア系の子どもたちが多く、日本人も全校の約1割を占めていたという。 学校では、インターナショナルデイのような定番イベントがあり、子どもたちは、母国のルーツに準じた服装をして、慣れ親しんだ料理を振る舞う。坂本さんも学年に15人ほどいた日本人の同級生と一緒に「ソーラン節」を踊ったのを覚えているという。
「当時、英語はまったくできなかったのですが、親の意向もあって現地校に通い始めました。転校してすぐの小学校4年生のときは、クラスに日本人の女の子が3人いて、いろいろ教えてもらえました。そんなリラックスした環境で海外生活はスタートしました」
小学校5年生の最初の3カ月は「ホラー映画の世界」
英語のコミュニケーションに苦戦しながらもクラスの日本人の友達に助けられながら、楽しい日々を送っていた坂本さんに新たな試練が訪れる。5年生になると突然、4年生まで一緒だった日本人の友達とクラスがバラバラになり、「英語の中でひとりぼっち」という状態で放置されることになったのだ。
「小学校5年生の10月から12月まで、ネイティブイングリッシュの中で、ほぼ何もわからない状態のまま授業を受けていました。何が宿題で出されているかもわからない。教えてもらってもよくわからない。その当時、児童の名前が書いてあるクジを持っていて、先生が箱からそれを引いて、当たった子に回答させる授業があったんです。確か動画を見ながら、クイズに答えるような……。ちょっと厳しめの先生で、とにかく当たるのが怖くて、ビクビクしていました。まさにホラー映画の世界(笑)。あの不安な状況は誰にも相談できませんでしたね」
それでも不思議なもので、半年も経つと耳が英語に慣れてくる。親が頼んでくれた英語の家庭教師の助けもあり、宿題もなんとかこなせるようになっていく。アメリカの学校には、多様なコミュニティがあった。周りの人が言っていることがわかるようになりたい、みんなともっとしゃべりたい。そう思って、英語を頑張って学んだ。日本人コミュニティもあったが、その世界に閉じこもらず、バランスよく多様な友達と関わった。
さらに、アメリカ社会に馴染むきっかけになったのがスポーツだった。スポーツが盛んなアメリカでは、多少英語ができなくてもスポーツが上手であれば、友達ができた。坂本さんも女子サッカークラブに所属し、思い切り体を動かして楽しんだ。
「不安を吹き飛ばすために、夢中になれることを見つけて、飛び込んでいましたね。サッカーをやっていると『Shoot!』『Good job!』くらいで会話が成り立ちますよね。これがよかった。あとは、とにかく笑っていましたね。英語はよくわからないけど笑顔でいる、人と接するときは自分から笑いかける。そうすると次第にまわりが声をかけてくれるようになるんです。この成功体験は、後の人生にも影響を与えている気がします」
能動的に何かをする現地校の授業が好きだった
海外で現地校に通う子どもたちにとって、心の拠りどころとなるのが、日本語補習校だろう。しかし、坂本さんは日本語の授業はどこか退屈で苦手だった。日本語で友達と話せる場としては楽しかったが、宿題は正解を覚えて書き写すことの繰り返しに感じられ、面白みを感じられなかった。
一方で、ネイティブイングリッシュに苦労しながらも坂本さんは現地校の授業に面白さを感じていた。日本の受け身な授業と違い、能動的に何かをする授業が多く、それが自分に合っていた。例えば、モノをつくる、詩を書く、何かを調べて発表する。正解を出すことより、自分の意見をもって発信したり、工夫してクリエイティブなアウトプットをしたりすることが高く評価された。
中学校に入ると一人ひとり時間割が違い、自分のレベルと興味・関心に合わせた授業が用意されていた。アメリカでは成績優秀ならば、飛び級もできる。中学生時代に高校の授業を受けていた同級生もいたという。数学や歴史のほか、「陶芸」や「リーダーシップ」といった珍しい授業もあった。理科(サイエンス)の時間には、手づくりのロケットをつくって、ニュートン力学を確かめる実験なども経験した。社会の授業では、実際の大統領選をベースにした模擬選挙に挑戦。2009年に黒人初の大統領になったバラク・オバマの自伝などを読み、中学生ながら真剣にどの候補者を支持するかを検討した。
「いわゆる100点満点で評価するようなペーパーテストが主流ではないことに驚きました。どの授業もだいたいレポートで評価が決まり、ここでも正解を求めるより、自分の意見が求められます。例えば、英語のReadingのテストなら長めの文章を読んで、この人はなぜこんなことをしたのかを自分の言葉で考える。さらに、自分だったらどうするかを記入します。これは、帰国後に日本の中学校で受けた授業とはまったく違うものでしたね」
中学3年生になる頃には、すっかり英語もネイティブレベルになり、さまざまなルーツを持つ友達もできた。現地校では、日本人でかたまっている生徒たちもいたが、坂本さんは違った。LAのトーランス周辺は、日本人コミュニティやアジア人コミュニティが大きいこともあり、差別を受けるような場面もなく、どんどんネットワークを広げていった。
「中学校に入学したとき、校長が新入生に送ったメッセージは今でも忘れません。それは、『これから学校に通う君たちに、やってほしいことがあるんだ。毎朝起きて顔を洗って鏡を見るときにひと言、"You're hot!"(君は最高にかっこいいね!)と声に出して自分に語りかけてほしい。そして本当にそう思いながら、学校に通ってほしい』というもの。自己肯定感を自分で高めて、自分のことを大事にしようという発想は、日本の小学校にはなかったもので、新鮮な驚きを感じました。今思い返すと、アメリカの学校教育の根底にあるものがここに詰まっている気がします」

帰国時によぎった「いじめは絶対に避けたい」
そんな楽しい中学校生活にも終わりがやってくる。日本の中学3年生にあたるタイミングで、帰国することになった。
「丸4年もLAにいたので、そろそろかなとは思っていました。通っていた現地校でも 転勤族の日本人の子は、数年で帰国してしまうサイクルだったので、ちょっとさみしいけど、大きな驚きはありませんでした。ただ、日本で公立中学校に通うにあたり、漫画や小説で中学校でのいじめの話はよく見ていたので、絶対に避けたいと考えました。そこで、まずは形から溶け込もうと思い、ロングだった髪をショートにして、前髪もつくりました。あとは、英語の授業での発音もネイティブっぽくしないようにして、『出る杭』にならないためにやるべきことを一生懸命考えましたね」
帰国したのは、中学3年次の冬だった。すっかり生活に慣れたLAを離れて、日本の公立中学校に通うのは不安もあったが、卒業まで数カ月ならば、体験として楽しもうと考えた。
「日本の中学校の授業は、楽しい楽しくないというより、『受験』そのものでしたね。覚えること中心で、自分の意見を問われることはありません。日本とアメリカ、どちらが正しいということはありませんが、アメリカとの違いを実感しましたね」
英語力は国公立大学入試でもアドバンテージに
LA時代に補習校の勉強を頑張った甲斐もあり、高校受験では東京都立の進学校に推薦で入学することができた。そこは制服もなく、校則もほとんどないような自由な校風が有名な高校で、坂本さんも違和感なく馴染むことができた。文化祭を熱心にやることでも知られており、クラスごとにチーム一丸となって展示をする。そんな雰囲気を楽しみながら、自然と日本の学校生活に慣れていった。
「中学・高校時代は、それぞれの環境の中で、そこにいる人たちと楽しく過ごすにはどうしたらいいかを考えて振る舞っていました。帰国子女レッテルを貼られてしまい、距離を取られてしまいたくなかったので、私も『普通』で楽しい人間だと思ってもらえるよう振る舞っていたと思います。幸い受け入れてもらうことができ、そのように振る舞うこと、溶け込もうとすること自体も辛いと思うこともありませんでした」

そして、大学受験の季節がやってくる。坂本さんは奮起して、東京大学を志望。なんと現役で合格することに成功する。国公立大学の受験でもやはり英語力は大きなアドバンテージになったと坂本さんは当時を振り返る。
大学で出合った「身体教育学」
東京大学入学後は1、2年次で教養学部で幅広く学びを深めた。自身の経験から日本と欧米の教育の違いや、学校教育が子どもの精神や身体へ及ぼす影響に関心があったこともあり、3年次には教育学部へ進学した。
「高校はハンドボール部、大学はラクロス部の活動に熱中しました。そこは居心地がよく、人としても学びの多い場でした。お互いを尊重できるメンバーに恵まれ、意見の違いがあっても建設的に会話をして解決をしていくことができました。学年の違いで大きな溝があるわけでもなく、先輩たちも対等に接してくれました。海外から帰国した私にとって、スポーツチームは特別な場所でした。この経験からスポーツが人の健康や人格形成にどう影響があるのかを学びたいと思うようになり、3年次から『身体教育学』という分野を専門的に学びました」

身体教育学とは、健全な身体観・発達観・スポーツ観を育み、自分自身および社会において「身体と心を育む」ことに主体的に立ち向かい実践していく意識と行動力を育むことを目的とする学問分野(※)。LA時代にサッカークラブで居場所を見つけた経験も身体教育学に関心を持った背景にあるのかもしれない。
同じレールの上を進む同級生に違和感
「高校、大学と周囲に馴染んで過ごしてきましたが、就職活動を始めるにあたり、多くの人が同じレールの上を進んで行くのを見て、『この流れに乗るのは嫌だ、自分がどうしたいのかを考えたい』と思いました。周りには、国家公務員になりたい、“いい会社”に入りたいと先輩の成功モデルを追う人が多かったのですが、私は自分自身の考えと価値観に沿って将来を選択する視点を持てたのはよかったと思います。これは確実に、LAの中学校で自分の考えを常に問われ続けた経験が役立っていたと思います。面白く、ストレスフリーに働ける環境に身を置きたいと考え、小さくてもいいので、できるだけフラットな組織で働きたいと考えました」
新卒で選んだのは、医療系のコンサルティング会社。ベンチャー企業のような少人数の組織で、上下関係もあまりないような雰囲気に魅力を感じた。医療をよくしていくという事業内容にも魅力を感じた。結局、そこで2年半年ほど修業をして、ドイツに旅立つことになる。自由な職場ではあったが、どこか閉塞感を感じていた坂本さんは、将来のキャリアを見据え、「同調圧力」が根強く残る日本社会から外に飛び出した。
日本でキャリアをつくっていくイメージが湧かなくなった
会社で違和感を覚えた瞬間はいくつかあった。まず、社内のチャットでわからないことを「明確にしてほしい」と求めたところ、ストレートすぎるので、もう少しやわらかい表現にしたほうがいいと指摘を受ける。「日本的コミュニケーション」をうまくやるために、こんなにも気を使わなければいけないのかと驚いた。
さらに別のときに、先輩から「他人が自分に求める役割を理解して、周囲の期待に応える努力をすべき。自分の思う自分であり続けるのは自分の殻を破れず成長スピード遅くなると思う」というフィードバックを受けた。本来の自分と大きくずれる振る舞いをしてまでこの社会に溶け込むことが、本当に自分の目指す姿なのかわからなくなった。
「今思うとその先輩が言っていることも一理あると思います。新たな役割をもらうことで、成長するケースも多々あるでしょう。しかし、ストレートすぎず、柔らかい物言いを選び、年上を敬い、異議を唱える場合もやり方を考える必要がある環境、集団や周りの人を個人や自分より優先する社会で、自分がキャリアをつくっていくイメージが湧かなくなってしまったのです」
そんなタイミングで、坂本さんキャリアを考える半年間のワークショップに参加する。そこで、自分の会社以外で働く人たち、キャリアアドバイザーの人たち、会社だけでなくフリーランスなどさまざまな形態で仕事をしている人たちと知り合った。そこで、社会や会社が求めるストーリーが自分のストーリーでなくてもいいと思えるようになった。
オープンな目と耳と心で人に接することを大事にしたい
坂本さんは現在、ワーキングホリデービザでドイツに滞在し、パートタイムで働きながらドイツ語の語学学校に通っている。ケルンのトルコ系移民が多い地区に住み、まさに宗教も言語も異なる多様性の中で生きている。ドイツ国民の3割は、親もしくは祖父母が、外国ルーツを持っているという。
「日々感じるのは、ドイツは個人主義が強く、ルールに違反していなければ後は自由という考えが根付いている点です。語学学校では、授業中に寝転がっていたり、途中で教室を出て行ったりしてしまう学生がいるのですが、みんな自分の学びのために来ており、他の人が何をしているかはあまり気にしません。日本ではありえない風景に、文化の違いを強く感じることがあります」
誰かにとっての当たり前は他の誰かにとっての当たり前ではない……異国に来るだけで文化はこうも違うのかと再認識した。また、そんな多様な人々が暮らす環境だからこそ、一人ひとり異なる背景を持っている他者を断片的な情報でジャッジするのではなく、オープンな目と耳と心で人に接することを大事にしたいと改めて思ったという。
ドイツで暮らして気づいた「女性の強さ」
坂本さんは現在、ケルンのラクロスチームに所属している。チームメイトとの会話で、坂本さんがYESを無意識に期待して「こう思う」と話すと「NO、私はこう思う」と返事が戻ってくる。ここは日本のコミュニティではないことを思い出す瞬間だ。
「自分が同調を前提とした日本でのコミュニケーションを念頭に話していたと気づかされました。そのチームメイトに、『例えば、誰かが何かを嫌いと言っていたときに、自分が好きだったとしても日本ではそれは言わないようにしたりするんだ』と伝えたところ、『じゃあずっと俳優みたいに演じ続けるの?』と言われて確かにと思ってしまいました」
ドイツで暮らし始めて、「女性の強さ」にも勇気づけられている。ラクロスチームのメンバーをはじめとする周囲の女性たちは、どんなときも意見をしっかり言うし、交渉ごとでも負けない。頑張って勉強をして、いい仕事に就くという当たり前の自由が、男女平等に与えられているのを感じる。当然ながら日本社会も昔とは大きく変わっている。しかし、「男女平等と女性の生きやすさ」に関しては、ドイツのほうがはるかに進んでいるようだ。
平日午後3時の公園でパパと子どもが遊んでいるドイツの日常
ドイツをはじめとするヨーロッパ諸国は休暇の意識も強い。社員に年間30日の有給休暇を取らせなければ、企業の経営層が罰せられるのだという。当然ながら時短勤務なども積極的で、女性も子育てをしながら安心して働ける環境がある。男性の育休取得率も8割近く、平日午後3時の公園でパパと子どもが遊んでいる風景がケルンの日常だという。
「日本で感じた閉塞感の理由がドイツに来て少しわかった気がします。日本って、働いて給料を増やそう、高い評価をもらおうとすると、どうしても長時間労働をするしかない。これは私が日本で社会に出て、実感したことです。働くことが楽しければ、それは大きな喜びになるでしょう。しかし、誰もが『働くこと=人生』と考えているわけではありません。私は、日本人の働き過ぎの背景に、同じ学年は同じ歩幅でという学校生活の影響があると思います。人は一人ひとり違って当たり前なのに、日本人はどうしても決まった社会のモデルに自分を当てはめがちです。個人主義のドイツに来るとそれに気づかされます」
ドイツで暮らし始めて、これまで環境の変化があるたびに、目の前の世界に溶け込もうとしていた自分に気づいた。その中で身についた振る舞い方の中で、本当に自分がそうしたいと思っていることと、そうではないけれどしていることとがあると再認識した。坂本さんは今、外の環境から自分のありたい姿を新たに取り込んで、既存の自分と混ぜて、自分にしっくりいく自分のあり方を大事にしたいと思っている。
「どんな自分として、どんな社会で生きるのか、自分自身で決められる時代になってきていると思うんです。アイデンティティ形成の始まりの期間を文化が違う環境で過ごしていると、不安定で自分がどういう人間なのか自分でわからず、揺らぐこともあると思います。大切なのは、しっくりくる方向に動いていくこと、合いそうな環境に飛び込んでみること。しっくり来なかったらまた変えていくことを繰り返していいと思います。オープンに周囲を見渡すと、いい出会いがたくさんあると思います」
住む場所や使う言語によって表現できる自己も変わる
小学校4年生から中学3年生という多感な時期をLAで過ごし、言葉の壁やカルチャーギャップを乗り越えてきた。そんな貴重な経験を得た一方で、アメリカで鍛えたネイティブレベルの英語力を日本の中学・高校では隠し続けた。もちろん、そのままの自分を前面に出しても友だちとの関係は変わらなかったかもしれない。それでもネイティブの発音と日本人レベルの発音を使い分ける器用さで、坂本さんは日本社会で溶け込むことを優先し、安心な居場所を確実に見つけて行った。そして、大学卒業後、ドイツで生活を始めて、日本とアメリカで自分は何を学んできたのかを考えている。
「私がLAの現地校で学んだのは、『人は違って当たり前』ということを前提としたコミュニケーションの下地のようなものだったと思います。これを経て、日本の高校・大学で、多様性を尊重する意識が醸成されていった気がします。ドイツに来て、初めての土地や知らない文化、言語の中でも、時間をかけて学んでいけばなんとかやっていけるということを実感しています。私には知らない世界に飛び込んで、人の助けを得ながら、なんとかなってきた経験があります。そして、何より役立っているのが、全力で成果を求めて頑張って取り組むことと、楽しむことは相反するものではなく、両立できる、という考え方。何かに真面目に取り組む上で、遊び心を大事にすることは、むしろ成果を出す上で有効であるという考え方。実はこれがアメリカで得た最大の収穫かもしれません」
今後は、ドイツでキャリアをつくっていきたいという坂本さん。理学療法士を目指して、新たに勉強をする予定だという。生身の人対人で接して、一人ひとりとしっかり向き合って対話をしながら、身体を自由に動かす喜びを提供できる理学療法士になりたいと考えている。新天地での仕事は、ドイツ語ですることになるだろう。日本語の自分、英語の自分に加え、ドイツ語を話す自分も加わることになる。
「言語によって、表現できる自己も変わると思います。違う言語を使う際にどう自己表現の違いを出してどう統合するか、またどのような相手に対してどう工夫をしながら対話をするかなど、今後もっと探索していきたいですね」