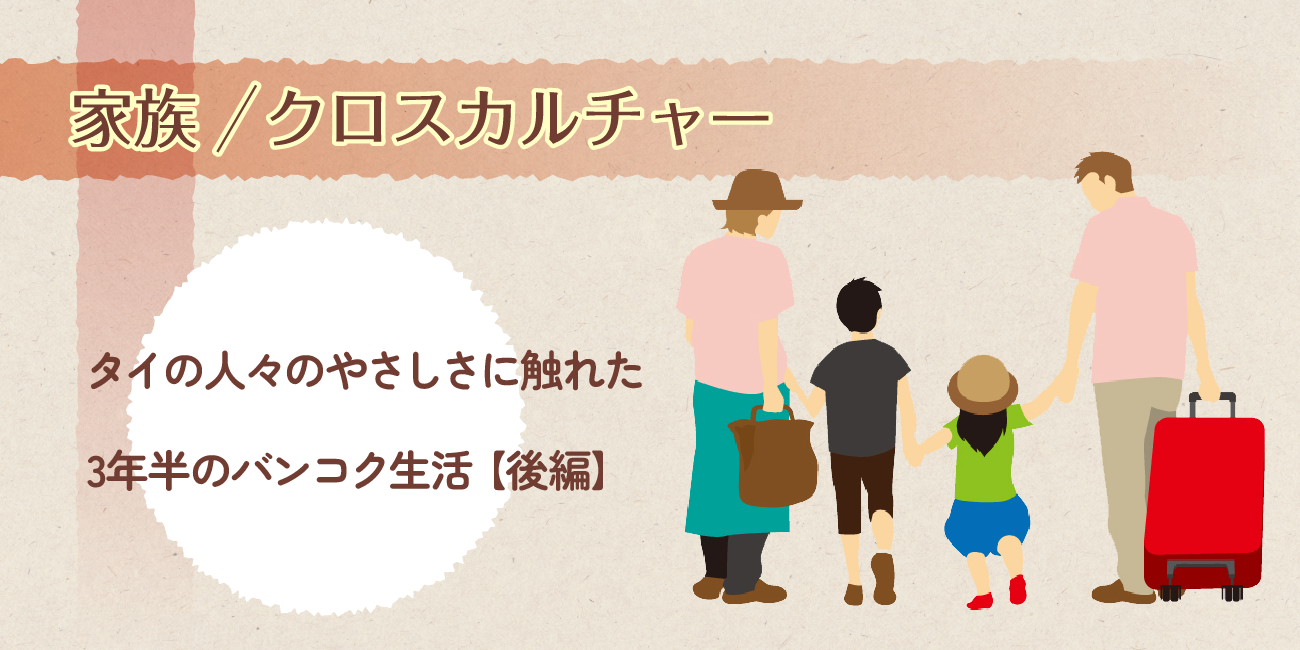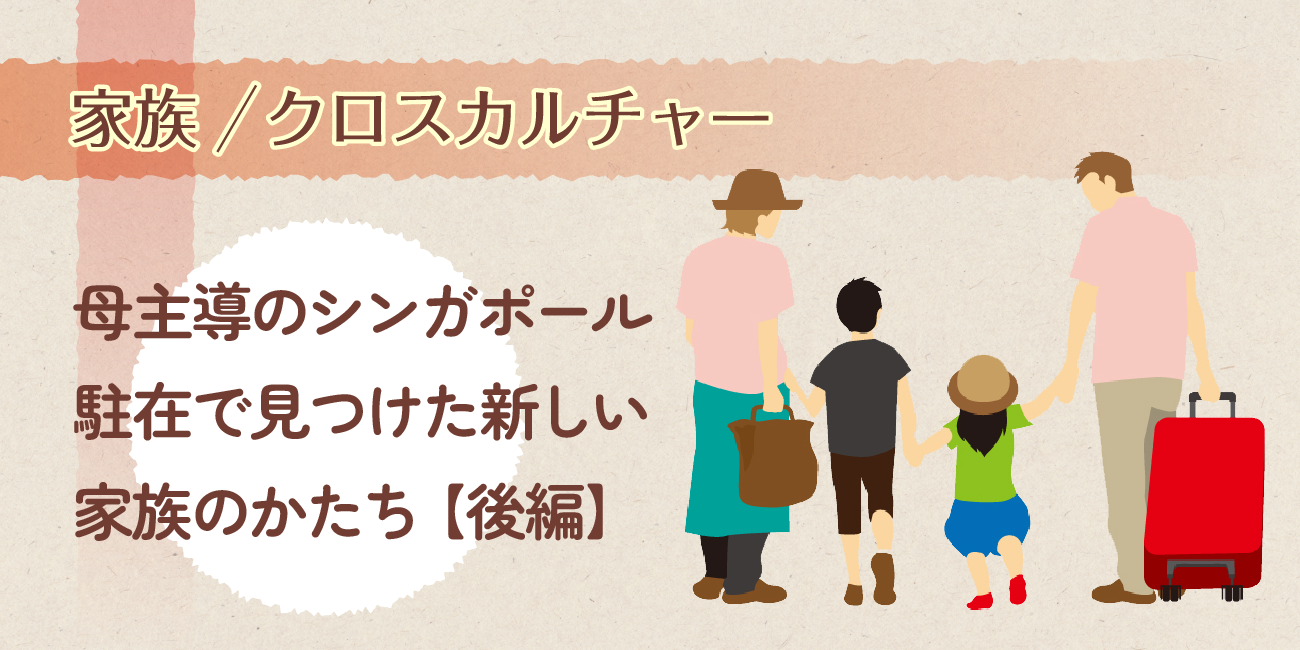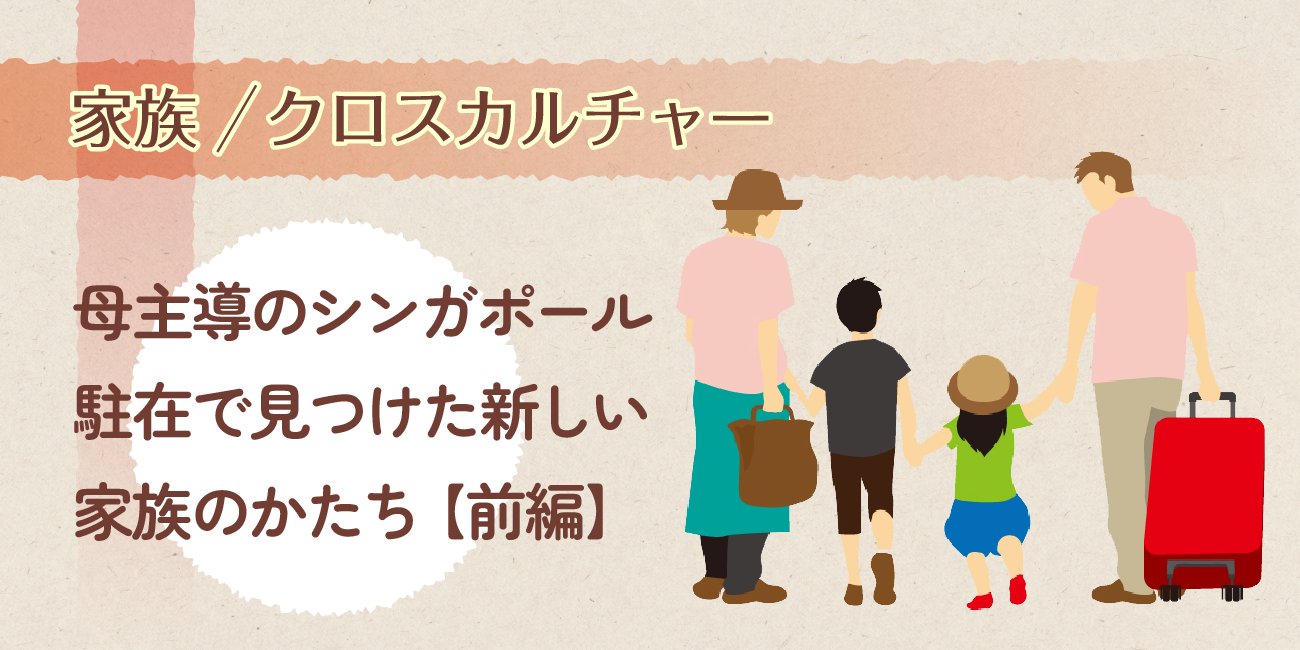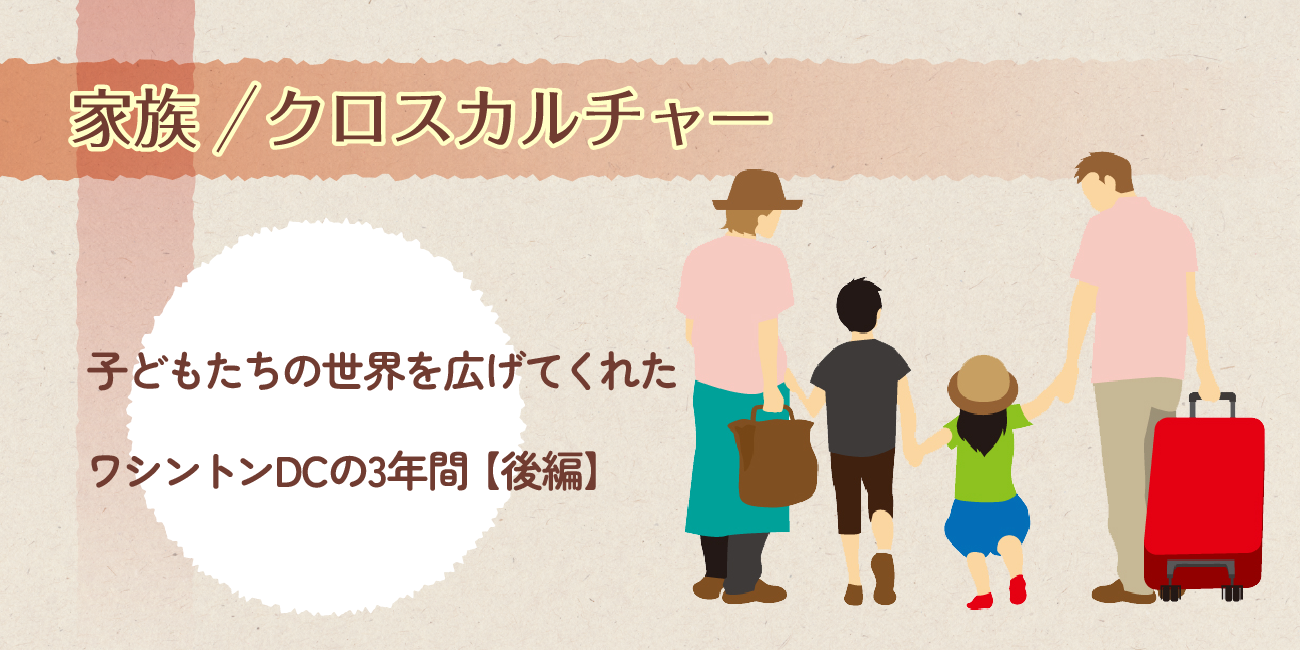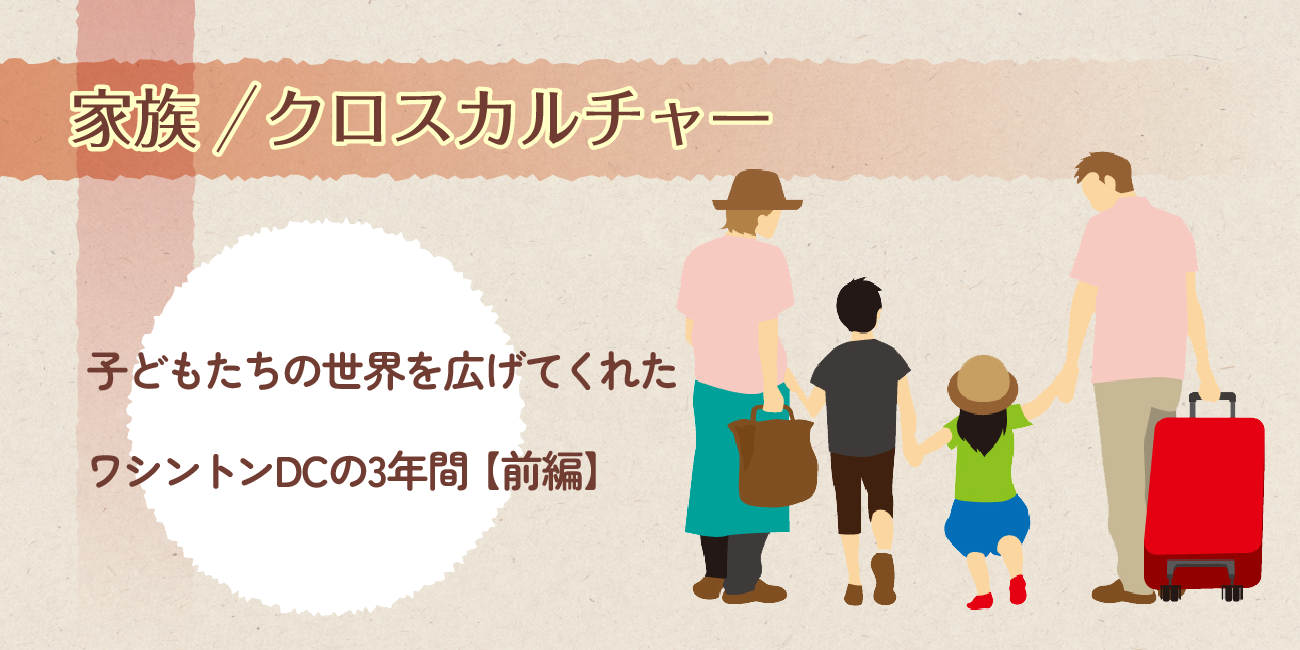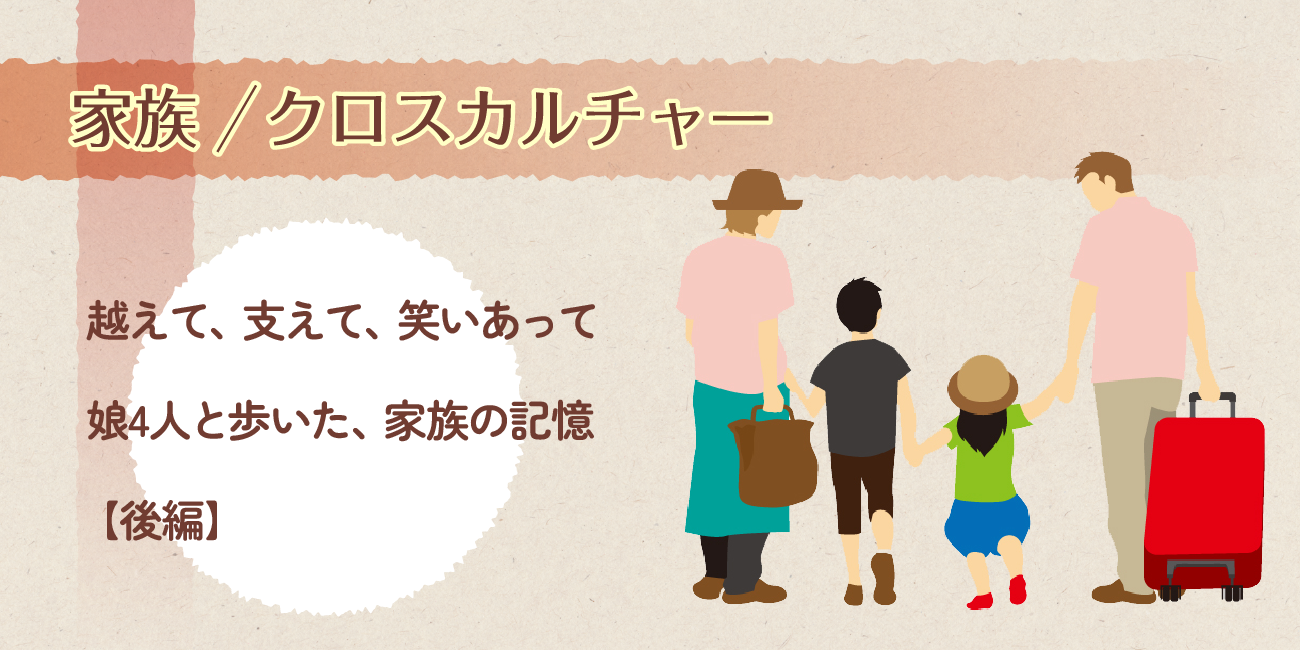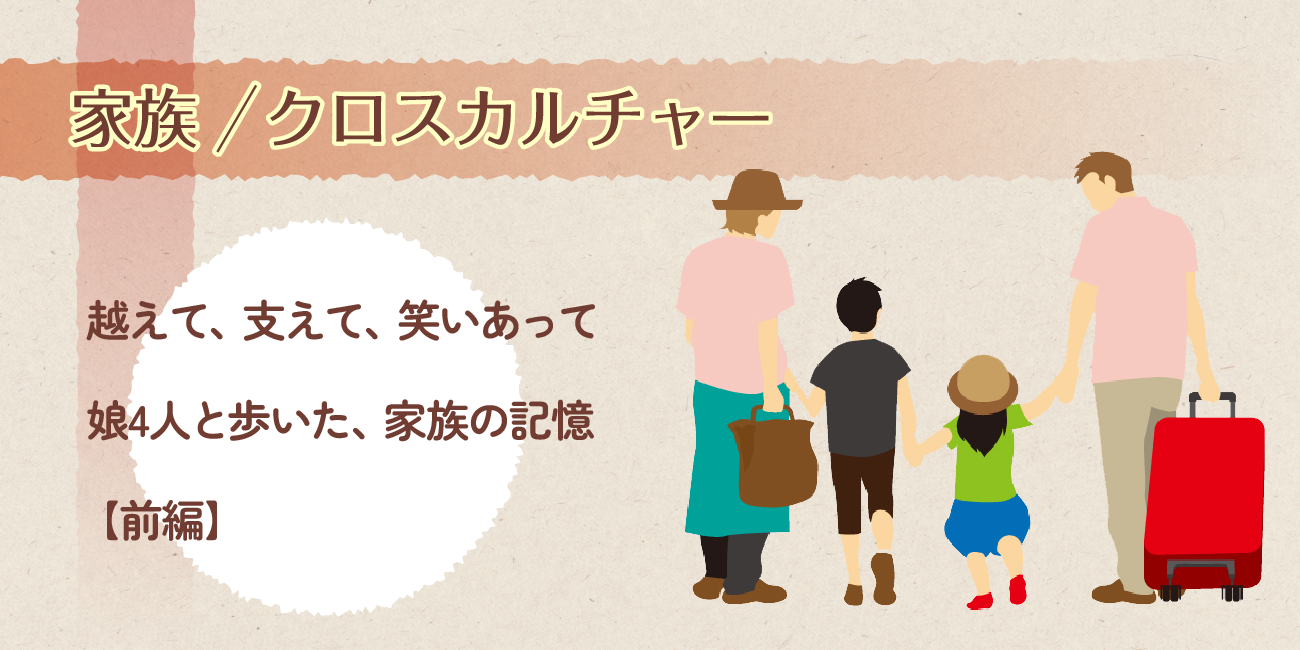医療系メーカーに勤務する父タケシと母ルイは、長女マキ、長男コウジ、次男ケンジと共にタイ・バンコクで3年5カ月に及ぶ駐在生活を経験した。渡航したのは、双子の長男・次男が生後8カ月、長女は2歳前のタイミング。現地の医療水準を心配しながらの駐在スタートとなった。その後、現地で次男が自閉症と診断され、受け入れ先の幼稚園を転々とすることに。そして、長男にも発達障害の症状が見られるようになる。その過程で、現地の日本人コミュニティに助けられながら、家族5人の生活スタイルを見つけて行った。マラソンが趣味のアクティブ夫婦が向き合ったバンコク駐在生活はいよいよ終盤へ。(仮名)
(取材・執筆:丸茂健一)
駐在中はほとんど日本食を自炊する生活
ケンジの幼稚園探しに東奔西走する日々も落ち着き、家族5人のバンコクでの生活スタイルも板に付いてきた。最初に住んだマンションの近くで大規模工事が始まり、滞在中に一度引っ越しを経験したが、転居先には子どもたちが遊べる広い庭のほか、1年中泳げるプールもあり、マキはすっかり泳げるようになった。
バンコク駐在中は、ほとんど日本食を自炊する生活だった。日系スーパーが近くにあり、食材調達に困ることはなかった。醤油、味噌などの調味料はもちろん、現地で育てた日本の野菜や卵も手に入った。料理をつくる時間がないときは、お弁当を配達してくれる日系のデリバリーサービスもあった。物価も安く、食生活に不満を感じることはなかったという。

タイといえば屋台のB級グルメが有名だが、屋台に挑戦するには子どもたちが小さすぎた。そのため、グリーンカレーさえもほとんど食べないバンコク生活だった。外食といえば、近くにあったラーメン屋や和食レストランへ。ごくたまにタイ料理も食べられるホテルのブッフェにも家族で出かけたという。
「子どもたちは、ラーメンも大好きになりましたし、ブッフェではタイのヌードルやマンゴーやパパイヤなどのフルーツなどをたくさん食べていました。私も色々な種類のパパイヤのサラダなど、現地のお料理をここぞとばかりに制覇しましたね。あとは、エビ釣りレストランにも3回ほど行きました。これは、手長エビの釣り堀が併設されたレストランで、釣ったエビをその場で料理してもらえます。子どもたちも大喜びでしたね」
チェンマイで「コムローイ」を体験
約3年半のタイ駐在の後半には、家族で旅行を楽しむチャンスもあった。バンコク近郊のパタヤでは、子どもたちが裸のゾウに乗る貴重な体験ができた。また、日本に帰国する直前にタイ北部チェンマイを訪れた際は、「ロイクラトン」というお祭りに参加することもできた。チェンマイではロウソクのついたコムローイ(ランタン)を大空に打ち上げる。夜空をオレンジに染めるランタンの幻想的な光景はルイにとって忘れられない思い出だ。

「かなりチャレンジングな環境でしたが、思い切って家族全員でタイに行ってよかったと思っています。当時のバンコクは3~4人乗りをしているバイクが歩いている人のすぐ近くを通ったり、バスや近場を移動する交通手段も独特でした。小学生や中学生が毎朝早くに大きなスクールバスに乗って登校する姿を何度も見送りにいきました。また、マンション近くで何度か洪水があったり、毎朝夕にタイの国歌が公共機関で流れたり*と、子どもたちは日本とは違う世界があることを体感として学べたのではないかと思います。また、私自身は、障がいのある子どもを支える保護者が集まるOZの会と出会えたことで、厳しい環境において、どうしたら前を向けるのか学べたと思っています。これはバンコクという小さい社会での出会いだったからこそ得られた財産だと思います」
*タイでは朝8時と夕方18時に公共の場で国家が流れる。歌が流れている間、皆、直立不動となり、歌が終わるまで動かない。
「みんなありがとう!」
ルイは、コウジ・ケンジの障がいと向き合いながらも子どもを連れてどんどん外に出るように心がけていた。子どもが幼稚園に通っている間にヨガ教室に通ったり、子どもと一緒にバンコクのマラソン大会に出場したりもした。常にどこか面白い場所がないかを探し、アクティブに過ごすことで、新しい世界を知って毎日を楽しく過ごすことができたという。
そのなかで、日本の生活では得られない“気づき”もあった。バンコクで住んでいたマンションには、住み込みのハウスキーパーさんたちが働いていた。酷暑のバンコクで、クーラーのない部屋で暮らしながら、笑顔を絶やさず朝から元気に挨拶してくれた。子どもたちがマンションの庭で遊んでいるときもいつも声をかけてくれた。レストランでは大人がなかなか食べられないときに子供を見ていてくれたり、自然な優しさにたくさん触れることができた。幼稚園ママやマンションの友達は、どこかに行くときに誘ってくれたり、お宅にお邪魔させてくれたりした。さまざまな境遇の人々と接するなかで、「みんな助けてくれてありがとう」と自然に感謝しながら暮らすことができた。

「障がいのあるお子さんがいる場合、海外生活を躊躇するご家庭もあると思います。ただ、機会があれば、怖れずに飛び込んでほしいと思います。現地に行ってみれば、必ず誰かが助けてくれます。なかには、自分以上に子どものことを親身に考えてくれているのではと思うような先輩ママもいます。我が家は、子どもたちが小さすぎて、移動するのも大変だったので、旅行もなかなか行けませんでした。それでもタイ人の笑顔、日本人コミュニティのやさしさに触れることができたいい駐在生活だったと思います」
帰国後の地域とのつながりも子どもたちのおかげ
2013年に帰国後、マキは、地元の小学校に入学し、持ち前の明るさでどんどん友達をつくっていった。人種や価値観の違いを超えて、誰とでも仲よくなれる性格は、バンコクで身についたものだとルイは考えている。コウジ・ケンジも今では高校生になった。障がいがあるため自然と学校との関係が深くなり、タケシは小学校でPTA会長を務めたこともある。また夫婦の趣味であるマラソンという強みを活かして、地域の子どもたちの陸上コーチも務めているという。
「子どもたちのおかげで、自分では想像もしなかった地域とのつながりができています。私自身もバンコクの日本人コミュニティに大いに助けられました。子育てで困ったことがあったときは、SOSを出せば誰かが助けてくれる……。それを教えてくれたのがバンコク駐在生活でした。いま陸上競技などで地域の子どもたちのサポートをしているのは、当時の恩返しの意味もあると思っています」